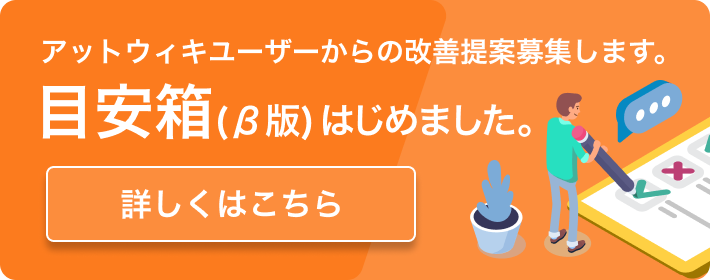身売りされた貴族のお話 08
酒場の扉をくぐると、やかましい声に加えて熱気と酒気が出迎えてくれた。どこにでもある、酒場の日常である。もはや、こうした光景には慣れきってしまった。
俺は片腕に抱えた紙袋を落とさないように気を配りながら、静かに客たちの間を通り、店のカウンターのほうに姿を見せにいく。そこにいた給仕――店主の娘は、ようやく俺の存在に気づいたのか、
俺は片腕に抱えた紙袋を落とさないように気を配りながら、静かに客たちの間を通り、店のカウンターのほうに姿を見せにいく。そこにいた給仕――店主の娘は、ようやく俺の存在に気づいたのか、
「あら、アシュリー! いつもありがとう。こっちに来てもらえる?」
その言葉に頷き、俺は彼女に従って店の奥へ進んでいった。
厨房を抜けて小さな個室に着くと、俺は紙袋を娘に渡した。彼女はその中身――数個の瓶を取り出すと、机の上に並べた。それぞれの瓶の中には、魔力の込められた液体が入っている。
俺は端から一つ一つを指差して、それぞれの効能を説明しはじめる。外傷に効くものから、内部から生命力を回復させるもの、睡眠を催すものなど、魔法薬 の種類はさまざまだ。それらはすべて、俺自身が拵えたものだった。
形式的な商品説明を終えると、娘は満足したように頷いた。
厨房を抜けて小さな個室に着くと、俺は紙袋を娘に渡した。彼女はその中身――数個の瓶を取り出すと、机の上に並べた。それぞれの瓶の中には、魔力の込められた液体が入っている。
俺は端から一つ一つを指差して、それぞれの効能を説明しはじめる。外傷に効くものから、内部から生命力を回復させるもの、睡眠を催すものなど、
形式的な商品説明を終えると、娘は満足したように頷いた。
「うん、だいたい前回のと同じ感じね。それじゃ、お代は……」
商品と引き換えの金銭を受け取った俺は、なくさぬようにしっかりと懐にしまった。平均的な相場よりも安価で取引をしているので、硬貨の枚数はそれほどでもなく、重みも歩くのに邪魔にならない程度だ。
「それでは、私はこれで」
社交辞令として軽い笑みを浮かべながら、会釈をする。そして退室しようと背を向けた時、
「あ……」
ぽつりと漏らした娘の声に、俺は振り返った。商品や説明に何か不備があったのだろうか。若干の不安を抱きながら、「どうしましたか?」と尋ねる。
「えっと、何か悪いことでもしちゃったかな? って思って……ううん、気にしないで!」
彼女は慌てたように、そう答えた。
悪いこと? 発言の意味が掴めない。……いや、もしかしたら俺の言動のせいか。こうも堅苦しく事務的な対応を、外見不相応にしてしまったのでは、相手としてもやりづらいのかもしれない。
今度からは、もう少し自然に愛嬌を振り撒くべきだろうか。そんな性に合わないことを考えながらも、今回はもう終わってしまったことなので、俺は苦笑でごまかしながら部屋を出た。
そして店の邪魔にならぬよう、早々に厨房を抜けて、酒場を出ようとして――
悪いこと? 発言の意味が掴めない。……いや、もしかしたら俺の言動のせいか。こうも堅苦しく事務的な対応を、外見不相応にしてしまったのでは、相手としてもやりづらいのかもしれない。
今度からは、もう少し自然に愛嬌を振り撒くべきだろうか。そんな性に合わないことを考えながらも、今回はもう終わってしまったことなので、俺は苦笑でごまかしながら部屋を出た。
そして店の邪魔にならぬよう、早々に厨房を抜けて、酒場を出ようとして――
「アシュリー?」
あまり聞きたくない声を耳にしてしまった。
俺は苦い感情を抱きながらも、後ろを振り返った。すると、予想どおり、そこには喜気を浮かべた少年の顔があった。
……この店の主人の子供だ。俺よりも二、三くらい年上だったと記憶している。
俺は苦い感情を抱きながらも、後ろを振り返った。すると、予想どおり、そこには喜気を浮かべた少年の顔があった。
……この店の主人の子供だ。俺よりも二、三くらい年上だったと記憶している。
「薬を届けにきてくれたの?」
「ええ。前に来た時から、ふた月ほど経っているので、新しいものをと」
「いつもありがとう! アシュリーの薬のおかげで、この間もすぐに怪我を治せたし……」
「ええ。前に来た時から、ふた月ほど経っているので、新しいものをと」
「いつもありがとう! アシュリーの薬のおかげで、この間もすぐに怪我を治せたし……」
好意をあらわにして語る彼とは正反対に、俺は沈んだ心持ちになっていた。
この少年がこうして話しかけてくるのは、おそらく俺が初めてこの酒場に来たとき、たまたま怪我をしていた彼に水魔法を使ってしまったからだろう。同年代のメイジ――それも貴族身分ではない者に、そんなお節介を受けてしまったのであれば、親近感を抱いて接するようになるのは道理である。
だが、俺にはできるだけ近づかないでほしかった。それはべつに、彼に嫌悪感を持っているというわけではない。……むしろ、俺が嫌悪しているのは、俺自身なのだろう。
この少年がこうして話しかけてくるのは、おそらく俺が初めてこの酒場に来たとき、たまたま怪我をしていた彼に水魔法を使ってしまったからだろう。同年代のメイジ――それも貴族身分ではない者に、そんなお節介を受けてしまったのであれば、親近感を抱いて接するようになるのは道理である。
だが、俺にはできるだけ近づかないでほしかった。それはべつに、彼に嫌悪感を持っているというわけではない。……むしろ、俺が嫌悪しているのは、俺自身なのだろう。
「……すみませんが、私は急いでいるので」
俺はわざと不快そうな表情を顔に浮かべて、冷たく言い放った。
だというのに、
だというのに、
「あ、ごめん。忙しいところを引き留めちゃって……。それじゃ、また今度!」
彼はにっこりと笑って、手を振った。こっちの意図が伝わっていない様子の言動に、俺は内心で大きな溜息をついた。
「……失礼します」
軽く頭を下げた俺は、逃げだすように酒場を出た。そして重苦しい胸のうちを振り払うように、早足で通りを歩みだす。
――馬鹿らしい悩みだ。自分でも、それはよくわかっている。
それでも、俺は極力、他人との親密な関わりを避けたかった。そうしなければ、己の不安を抑えきれないからだ。……もう、あんなことは、二度と御免なのだ。
それでも、俺は極力、他人との親密な関わりを避けたかった。そうしなければ、己の不安を抑えきれないからだ。……もう、あんなことは、二度と御免なのだ。
日の沈みかける道をしばらく進みつづけると、ようやく寝泊まりしている宿に辿り着く。客らしき男たちの後ろに続いて、俺も店の中に入った。
酒の臭いと、香水の匂いが鼻をつく。男の蛮声と、女の嬌声が耳に響く。
俺は一階の騒がしい酒場を通り抜けて、客室の並ぶ二階に上った。そしていちばん奥まで進むと、ほかの客室よりも少し広めの、オーナー用の私室が現れる。俺はそのドアをノックした。
酒の臭いと、香水の匂いが鼻をつく。男の蛮声と、女の嬌声が耳に響く。
俺は一階の騒がしい酒場を通り抜けて、客室の並ぶ二階に上った。そしていちばん奥まで進むと、ほかの客室よりも少し広めの、オーナー用の私室が現れる。俺はそのドアをノックした。
「入ってきなさい」
その声を聞いて、ドアを開ける。
そんな俺を出迎えたのは、執務机に座って記帳している四十路前後の女性だった。痩身で、長い金髪にやや釣り気味の目が特徴である。
そんな俺を出迎えたのは、執務机に座って記帳している四十路前後の女性だった。痩身で、長い金髪にやや釣り気味の目が特徴である。
「アシュリーか。おかえり」
「ただいま、戻りました」
「ただいま、戻りました」
お決まりの挨拶とともに、俺は懐にあった金銭を女性――エリザベスに手渡した。彼女は硬貨の枚数を数えて、その金額をべつの帳簿に記載すると、それらを机下の金庫にしまった。
俺の稼いだ金は、こうしてこの宿の女主人であるエリザベスに管理してもらっていた。そこから月に一度、下宿分の賃金を差し引いてもらっている。金銭管理は意外と面倒なだけに、こうして計算してくれるのは楽でよいものだ。まあ、相手が金を預けても心配のない人間であることが前提のやり方だが。
俺の稼いだ金は、こうしてこの宿の女主人であるエリザベスに管理してもらっていた。そこから月に一度、下宿分の賃金を差し引いてもらっている。金銭管理は意外と面倒なだけに、こうして計算してくれるのは楽でよいものだ。まあ、相手が金を預けても心配のない人間であることが前提のやり方だが。
「ああ、それと今日届いた秘薬や薬草の類は、そこに置いてあるよ。確認しておきな」
そう言ってエリザベスが顎で示した先は、部屋の隅に置いてある木製の箱だった。その中には、秘薬やそれの素となる草花などが、いくつかの袋に分けられて入っている。俺が魔法薬 を作るために、秘薬屋から取り寄せていたものだった。
といっても、名目上の購入者はエリザベスになっている。当たり前の話だが、俺が自分で取引しようにも、見た目が障害となってしまうのだ。十歳に満たないガキが秘薬を買い求めるというのは不自然だし、素性も知れないため信用されにくい。
だから結局、情けない話であるが、俺はこのエリザベスに大きく頼っていた。魔法薬 の商売にしても、外面的にはエリザベスが販売主で、俺は品物を客に届けているだけということで通している。
つまるところ、こうして現状が成り立っているのは、すべてエリザベスが俺を信用してくれているからだ。だが、そもそも、彼女がなぜ俺のことを怪しまないのかということは疑問だった。俺は年齢を二つ上、つまり九歳と詐称しているのだが、その歳を差し引いても異常性は有り余るはずだ。だというのに、当時この街――ロンディニウムに着いて宿を探していた俺の話を聞いて、迷うことなく間借りの契約を交わしたというのは、今でも釈然としないところがある。
……とはいえ、こっちが疑いの目を持ってしまっては本末転倒だ。それに、この半年間の生活で、エリザベスが俺に害意など持ち合わせていないことは、十分に理解している。だから俺にできることは、せめて目立たぬように細々と生活し、そして万が一、俺のせいでエリザベスやその周囲の人間に不利益が及びそうであるのならば――即刻、ここから立ち去るだけである。
といっても、名目上の購入者はエリザベスになっている。当たり前の話だが、俺が自分で取引しようにも、見た目が障害となってしまうのだ。十歳に満たないガキが秘薬を買い求めるというのは不自然だし、素性も知れないため信用されにくい。
だから結局、情けない話であるが、俺はこのエリザベスに大きく頼っていた。
つまるところ、こうして現状が成り立っているのは、すべてエリザベスが俺を信用してくれているからだ。だが、そもそも、彼女がなぜ俺のことを怪しまないのかということは疑問だった。俺は年齢を二つ上、つまり九歳と詐称しているのだが、その歳を差し引いても異常性は有り余るはずだ。だというのに、当時この街――ロンディニウムに着いて宿を探していた俺の話を聞いて、迷うことなく間借りの契約を交わしたというのは、今でも釈然としないところがある。
……とはいえ、こっちが疑いの目を持ってしまっては本末転倒だ。それに、この半年間の生活で、エリザベスが俺に害意など持ち合わせていないことは、十分に理解している。だから俺にできることは、せめて目立たぬように細々と生活し、そして万が一、俺のせいでエリザベスやその周囲の人間に不利益が及びそうであるのならば――即刻、ここから立ち去るだけである。
「……たしかに、注文分はすべて揃っています。ありがとうございます、エリザベスさん」
余計な思考をしつつ、品物を確認しおえた俺は、彼女に礼を述べた。
「どういたしまして。代金はいつもどおり、お前の金から払っておいたよ」
俺は頷いた。実験や魔法薬 の作製に必要な道具・秘薬代は高くつくものの、それでも半年間の商売を通じて、コストを上回る金は稼げている。金はいくらあっても、困ることはない。そのことは、ロンディニウムに辿り着くまでの旅路で身に染みていた。
「では、私は“部屋”に戻りますね」
そう言って、俺は杖を取り出した。
そして上を向き、“念力”の魔法を使う。振るわれた杖に応じて、天井の裏へ通ずる開き戸が開いた。
部屋、というのは屋根裏部屋だった。手に入れた素材や道具などは、すべてこの中に保管しており、商品の作製や実験などもここで行なっている。なぜ普通の客室を使わないのか、というと、薬品の臭気や日照による品質管理などの問題があるからだ。
そして上を向き、“念力”の魔法を使う。振るわれた杖に応じて、天井の裏へ通ずる開き戸が開いた。
部屋、というのは屋根裏部屋だった。手に入れた素材や道具などは、すべてこの中に保管しており、商品の作製や実験などもここで行なっている。なぜ普通の客室を使わないのか、というと、薬品の臭気や日照による品質管理などの問題があるからだ。
「フル・ソル・ウィンデ……」
ついでレビテーションの魔法を唱え、先程の木箱を屋根裏に上げたのち、自らの体も浮かせて部屋の中に入りこむ。魔法が使えるおかげで、屋根裏に出入りするのに踏み台や梯子が必要ないということも、利点の一つだった。
「夕食の時間になったら、また下ります」
「ああ、またその時に」
「ああ、またその時に」
最後に下の部屋のエリザベスとそんな会話をして、俺は戸を閉じた。
それと同時に、周囲は極端に暗くなった。もともとは物置として作られていた空間なので、採光窓が小さく、わずかな月光しか入ってこない。もちろん、このままでは何もできないので、照明を点けなければならない。
パチン、と俺は指を軽く鳴らす。すると、上部に取り付けられたランプが反応し、魔法の光で部屋を照らしだした。光度はそれほどでもないが、作業するには十分な程度である。
それと同時に、周囲は極端に暗くなった。もともとは物置として作られていた空間なので、採光窓が小さく、わずかな月光しか入ってこない。もちろん、このままでは何もできないので、照明を点けなければならない。
パチン、と俺は指を軽く鳴らす。すると、上部に取り付けられたランプが反応し、魔法の光で部屋を照らしだした。光度はそれほどでもないが、作業するには十分な程度である。
よし、と小さく声に出してから、俺は仕事に取りかかった。
まずは注文した素材や物品を仕分けし、必要のないものは小棚にしまう。それから在庫のなくなってきた薬の補充のため、調合と魔法の付与を行なう。
作るものは高度な秘薬ではなく、一般大衆向けの薬なので、作製自体はそれほど難しくはない。とはいえ、ある程度の量を用意しなくてはならないため、相応の労力がかかるのは確かだった。
まずは注文した素材や物品を仕分けし、必要のないものは小棚にしまう。それから在庫のなくなってきた薬の補充のため、調合と魔法の付与を行なう。
作るものは高度な秘薬ではなく、一般大衆向けの薬なので、作製自体はそれほど難しくはない。とはいえ、ある程度の量を用意しなくてはならないため、相応の労力がかかるのは確かだった。
――そして、気づけば時間が経ち。
それまで休憩を挟まず作業を続けていたのだが、ようやく一段落ついたこともあり、俺は少し手を休めることにした。
長らく同じ姿勢だった体をほぐすために、伸びをしようとして、
それまで休憩を挟まず作業を続けていたのだが、ようやく一段落ついたこともあり、俺は少し手を休めることにした。
長らく同じ姿勢だった体をほぐすために、伸びをしようとして、
「……っ」
一瞬、目眩に襲われて倒れそうになる。
俺は右手で目頭を抑えながら、近くに広げていた毛布の上に仰向けになった。
大きく、嘆息のような深呼吸をする。天井に吊るされている魔法照明の光でさえ、軽い羞明を覚えた。
俺は右手で目頭を抑えながら、近くに広げていた毛布の上に仰向けになった。
大きく、嘆息のような深呼吸をする。天井に吊るされている魔法照明の光でさえ、軽い羞明を覚えた。
「イル・ウォータル・デル……」
自分に癒しの魔法をかけると、なんとか症状が治まった。だが、気怠さは変わらないままである。身を起こそうとしても、まるで俺の体ではないかのように動かない。
最近、こうした目眩や頭痛が多くなった。その都度、水魔法でごまかしてきたが――これは本格的にまずいかもしれない。
薬売りの水メイジがこの有り様とは、とんだ皮肉である。苦い笑みが込み上がってきた。
明確な病気ではない。だが、おそらく、これが何であるかを俺は知っていた。
最近、こうした目眩や頭痛が多くなった。その都度、水魔法でごまかしてきたが――これは本格的にまずいかもしれない。
薬売りの水メイジがこの有り様とは、とんだ皮肉である。苦い笑みが込み上がってきた。
明確な病気ではない。だが、おそらく、これが何であるかを俺は知っていた。
――心身症だ。
「アシュリー」
下の部屋から、俺を呼ぶ声が聞こえた。
無視するわけにはいかない。気力を絞り出して、立ち上がる。
無視するわけにはいかない。気力を絞り出して、立ち上がる。
「……どうしました?」
出入り戸を開けて、俺はエリザベスに尋ねた。
彼女は俺の顔を見上げて、
彼女は俺の顔を見上げて、
「いや、いつもの食事の時間になっても下りてこなかったからね。忙しいところを邪魔してしまったかい?」
慌てて、懐中時計を確認する。……本当だ、もうこんなに経っていたのか。
ダメだ、時間感覚も狂ってきている。俺は唇を軽く噛んだ。思いのほか、疲れが溜まっているのだろうか。
ダメだ、時間感覚も狂ってきている。俺は唇を軽く噛んだ。思いのほか、疲れが溜まっているのだろうか。
「すみません。いま、行きます」
大ざっぱな片づけをしてから、俺は急いでエリザベスの部屋に下りた。
そして「食事をしてきます」と言い、すぐに室外に出ようとして――
そして「食事をしてきます」と言い、すぐに室外に出ようとして――
「アシュリー」
呼び止められた。
後ろを振り向く。そこには、めずらしく心配げな表情をしたエリザベスがいた。
彼女は小さな溜息をつくと、俺のそばにまで歩み寄ってきた。
後ろを振り向く。そこには、めずらしく心配げな表情をしたエリザベスがいた。
彼女は小さな溜息をつくと、俺のそばにまで歩み寄ってきた。
「顔色が悪いぞ。体を壊してしまったら、元も子もないじゃないか」
目線を合わせるように屈んだエリザベスが、手のひらを俺の頬に当てる。
まるで、聞き分けのない子供に言い聞かせるかのようだった。
まるで、聞き分けのない子供に言い聞かせるかのようだった。
……俺は子供じゃないんだ。
だから、お願いだ。そんなに気にかけないでくれよ、エリザベス。
だから、お願いだ。そんなに気にかけないでくれよ、エリザベス。
「大丈夫ですよ」
できるかぎり安心させるために、意識して柔和な笑みを浮かべる。
「作業も、ほとんど終わりました。今日は早めに、体を休めますから」
「……アシュリー」
「……アシュリー」
一瞬、何をされたのかわからなかった。
自分が抱き締められるなんて、予想だにしていなかったからだ。
自分が抱き締められるなんて、予想だにしていなかったからだ。
「約束だよ。食事をした後は、きちんと休みなさい」
それは、本心から労わる言葉だった。
そのぬくもりに、俺は情を揺り動かされそうになるのを堪えて、
そのぬくもりに、俺は情を揺り動かされそうになるのを堪えて、
「わかりました」
と、静かに答えた。
「もう、行きますね」
「……ああ」
「……ああ」
抱擁が解かれると、俺はすぐに部屋を出た。まるでエリザベスから逃げだすように。……いいや、まさに逃げているのだ。俺は臆病者だった。
沈んだ気分になりながら、一階に下り、酒場を通り抜けて厨房に赴く。そこで、俺はいつものように賄いを貰うと、給仕の控え室で料理を淡々と口に運びはじめた。
そうして、食事を八分ほどまで進めたところで――誰かが部屋に入ってきた。
沈んだ気分になりながら、一階に下り、酒場を通り抜けて厨房に赴く。そこで、俺はいつものように賄いを貰うと、給仕の控え室で料理を淡々と口に運びはじめた。
そうして、食事を八分ほどまで進めたところで――誰かが部屋に入ってきた。
「あら、お食事中? 邪魔しちゃってゴメンね、アシュリー」
「構いませんよ」
「構いませんよ」
店で働いている女性の一人だった。
そんな彼女の姿をちらりと見て、俺はすぐに異変に気づいた。
そんな彼女の姿をちらりと見て、俺はすぐに異変に気づいた。
「……怪我、ですか?」
「ええ、そうよ。バカな男にいきなり腕を掴まれて、転んじゃったの。その時に手をついて……これよ」
「ええ、そうよ。バカな男にいきなり腕を掴まれて、転んじゃったの。その時に手をついて……これよ」
彼女は左手を軽く振ってみせた。そのひらには擦り剥いた傷が見える。
「まったく、いやになっちゃう。そういう乱暴な男はダメダメよ! アシュリーも覚えておくといいわ」
憤慨の声を上げる彼女に対して、俺は食器をいったん置くと、杖を取り出しながら椅子から降りた。
「傷、見せてください」
「あ……いいの?」
「エリザベスさんと、約束をしていますから」
「あ……いいの?」
「エリザベスさんと、約束をしていますから」
もともと下宿させてもらう条件として、この店の従業員の健康管理なども含まれていた。というのも、ここは売春も商売の一つとしている宿であるので、そういった傷病にはとりわけ注意する必要があるのだろう。まあ、健康管理といっても、怪我や病気になっていたら癒しの魔法をかけるという簡単なものなので、俺にとってはそれほど負担があるわけではない。
「私の前に、手を出していただけますか?」
俺には左腕がないので、彼女の手を取ることはできない。はっと気づいた様子の彼女は、慌てたように怪我をした手を差し出した。
俺はその傷に意識を集中させながら、ルーンを唱えた。傷を治すのに十分な魔力が体を巡った瞬間、杖を振り下ろす。
俺はその傷に意識を集中させながら、ルーンを唱えた。傷を治すのに十分な魔力が体を巡った瞬間、杖を振り下ろす。
「――これで、大丈夫です」
水の魔法によって皮膚は再生し、傷は跡形もなく消え去っていた。
彼女は治った手を確認すると、満面の笑みを浮かべて「ありがとう!」と感謝の言葉を述べた。
彼女は治った手を確認すると、満面の笑みを浮かべて「ありがとう!」と感謝の言葉を述べた。
「アシュリーは本当にすごいわ。その歳で、こんな魔法を使えちゃうんだから」
「……それほどでは、ありません」
「んもう、謙遜しちゃってー。みんな、あなたの話を聞くと驚いちゃうくらいなのよ?」
「……それほどでは、ありません」
「んもう、謙遜しちゃってー。みんな、あなたの話を聞くと驚いちゃうくらいなのよ?」
そう言って、彼女は俺の頭を優しく撫でた。純粋な子供ならともかく、俺にとっては素直に喜びがたい褒められ方だったのだが――少なくとも、今はそんな動作が気にならないほどに、俺は衝撃を受けていた。
……彼女は、なんと言った?
聞き間違いであってほしい。そう思いながら、震える声で、俺は尋ねた。
「……私の話を聞いて驚く、とは?」
「ん、お客さんにアシュリーのことを話した時の反応よ。『ウチのお店には、こんな小さなメイジがいる』って言うと、みんな驚いてくれるの。……もしかして、嫌だった?」
「ん、お客さんにアシュリーのことを話した時の反応よ。『ウチのお店には、こんな小さなメイジがいる』って言うと、みんな驚いてくれるの。……もしかして、嫌だった?」
彼女は俺の顔を心配そうに覗きこんだ。おそらく、今の俺はそうとう、ひどい顔色をしているはずだ。
「ア、アシュリー? どこか具合、悪いの?」
「…………いえ」
「…………いえ」
大丈夫です、と言いきる気力も残っていなかった。
胸が締めつけられるように痛い。立っているのもやっとな状態だった。
胸が締めつけられるように痛い。立っているのもやっとな状態だった。
「――――」
「――――」
「――――」
もはや、相手が何を言っているのかもわからなかった。
それどころか、自分がどんな言動をしているのかも理解できない。もしかしたら、頭のおかしなことを口走っていたのかもしれない。だが、それを知る術はなかった。
それどころか、自分がどんな言動をしているのかも理解できない。もしかしたら、頭のおかしなことを口走っていたのかもしれない。だが、それを知る術はなかった。
結局、俺の意識がまともに戻ったのは――次の日の朝だった。
◇
悪夢を見た。
あの男に四肢をもがれ、心臓を抉り出されて殺されるという、胸糞悪い夢だ。なぜ、そんな夢を見たのか、俺はよくわかっている。
認めよう。俺は心底、恐怖しているのだ。
ダッシュウッド男爵に目を付けられた件のように、この街で俺に関する話が広まってしまえば、また誰かに狙われるのではないかと。また、そのせいで周囲の善良な人間に危害が及ぶのではないかと。
あの男に四肢をもがれ、心臓を抉り出されて殺されるという、胸糞悪い夢だ。なぜ、そんな夢を見たのか、俺はよくわかっている。
認めよう。俺は心底、恐怖しているのだ。
ダッシュウッド男爵に目を付けられた件のように、この街で俺に関する話が広まってしまえば、また誰かに狙われるのではないかと。また、そのせいで周囲の善良な人間に危害が及ぶのではないかと。
重い溜息をつきながら、俺は上半身を起こした。
ここは――エリザベスの部屋か。昨夜、おそらくあの場で気を失ったのであろう俺は、ここに運ばれて寝かされたのだろう。
俺は自分の体に目を向けた。上着は脱がされ、下着だけになっている。それでも汗だらけになっているところを見ると、とんでもなくあの悪夢にうなされていたようだ。
……ひとまず、エリザベスに会いに行くべきか。そう考えて、ベッドから下りた時だった。
ここは――エリザベスの部屋か。昨夜、おそらくあの場で気を失ったのであろう俺は、ここに運ばれて寝かされたのだろう。
俺は自分の体に目を向けた。上着は脱がされ、下着だけになっている。それでも汗だらけになっているところを見ると、とんでもなくあの悪夢にうなされていたようだ。
……ひとまず、エリザベスに会いに行くべきか。そう考えて、ベッドから下りた時だった。
「――起きたかい」
ちょうど、彼女が部屋に入ってきた。その脇には、水の入った桶とタオルが抱えられている。俺の汗を拭きとるために、わざわざ持ってきてくれたのだろう。
「……エリザベスさん。昨夜は、ご迷惑をおかけしました」
「そう気にする必要はないさ。今日は、ゆっくりと休みなよ」
「……はい。ありがとう、ございます」
「そう気にする必要はないさ。今日は、ゆっくりと休みなよ」
「……はい。ありがとう、ございます」
エリザベスは、水桶を俺の足元に置いた。
俺は彼女からタオルを貰うと、それで体を拭きはじめた。だが、その途中、あることに気づく。
俺は彼女からタオルを貰うと、それで体を拭きはじめた。だが、その途中、あることに気づく。
「そういえば……私が、ここで寝ていたとなると、エリザベスさんは?」
ぶっ倒れた俺がこのベッドを占領していたとなると、彼女はどこで寝ていたのだろうか。申し訳ない気分で疑問を口にすると、エリザベスは「ああ、それか」と微笑で答えた。
「ちょうど、昔から馴染みの客が泊まっていてね。この歳ながら、その男と寝床を共にしたってわけさ。ま、だから心配はいらないよ」
なるほど、夜伽か。彼女も、以前はこの店でよく男性客の相手をしていたらしいから、その縁で親しい人間は多いのだろう。
納得した……が、なんと反応すればよいか困っていると、エリザベスはそれを察したのか、「さて」と話を変えてくれた。
納得した……が、なんと反応すればよいか困っていると、エリザベスはそれを察したのか、「さて」と話を変えてくれた。
「アシュリー。ずいぶん前に、お前から頼まれていたことなんだが」
頼み事?
なんのことか、すぐにわからない。慌てて記憶を辿ってみるが、それらしいものは思い出せなかった。
俺の脳味噌はこんなに劣化してきているのか、と本気で不安になりかけたところで、エリザベスは“頼み事”について補足をした。
なんのことか、すぐにわからない。慌てて記憶を辿ってみるが、それらしいものは思い出せなかった。
俺の脳味噌はこんなに劣化してきているのか、と本気で不安になりかけたところで、エリザベスは“頼み事”について補足をした。
「あー、お前が最初の頃、私に聞いてきたことだよ。『探している人物がいる』というね」
「……ああ」
「……ああ」
あのことか。「もし何か知っていれば、教えてくれ」といった程度の会話だったので、俺としては頼み事というほどの認識はなかったのだが。
しかし、エリザベスが今になって、この話を持ち出してくるということは……。
しかし、エリザベスが今になって、この話を持ち出してくるということは……。
「宿屋を経営している知人たちに、前から頼んでおいたのさ。お前の言うような人物が客として来たのなら、私に伝えてくれとね」
「それは……」
「ああ。まさか、今になって連絡が来るとは思わなかったよ」
「それは……」
「ああ。まさか、今になって連絡が来るとは思わなかったよ」
もはや、予想はついている。
少しの間を置いたのち、ついにエリザベスはそのことを言いきった。
少しの間を置いたのち、ついにエリザベスはそのことを言いきった。
「――チャーリーという傭兵のメイジが見つかった」
それはまさしく、思いがけぬ好機であった。