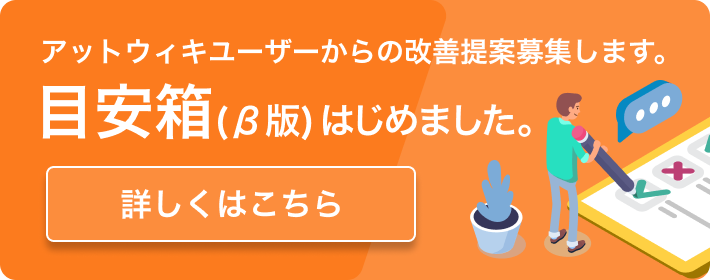身売りされた貴族のお話 07
ダッシュウッド男爵が殺害された事件は、一時は市井を大きく騒がせた。彼は多数の貴族と交流を持っており、かなり名声のある貴族だったらしい。実際に、弔問にはサンドウィッチ伯爵といった名門貴族も名を連ねていたようだ。それほどの大物貴族の死となれば、市民の話の種にならないはずがない。
とはいえ……その話題も、月日に従って流されていった。これが詳細不明の謎の変死といったものであれば、市民の興味も長続きしたのかもしれないが、下手人は傭兵のメイジで相討ちの結末だったと最初から判明していただけに、飽きられるのも早かったようだ。
当然ながら、ダッシュウッド男爵が地下牢に何者かを監禁していたという噂も、いっさい耳にしなかった。さらにその後も、アシュリーという子供をサウスゴータの街で捜索しているような人物は出てこなかった。やはり彼は、俺の存在を完全に秘密にしていたということである。
とはいえ……その話題も、月日に従って流されていった。これが詳細不明の謎の変死といったものであれば、市民の興味も長続きしたのかもしれないが、下手人は傭兵のメイジで相討ちの結末だったと最初から判明していただけに、飽きられるのも早かったようだ。
当然ながら、ダッシュウッド男爵が地下牢に何者かを監禁していたという噂も、いっさい耳にしなかった。さらにその後も、アシュリーという子供をサウスゴータの街で捜索しているような人物は出てこなかった。やはり彼は、俺の存在を完全に秘密にしていたということである。
そうして、ひとまず身辺の危険が去ったことを理解した俺は、これからどうすればよいのか迷った。
最初に頭に浮かんだ案は、すでにサウスゴータの街から去っていた傭兵団――チャーリーたちに、ヘレンが死んだ事実を伝えるということだった。ヘレンの覚悟を考えると、チャーリーたちも彼女がどうなるかをわかっていて別れたのかもしれないが、それでも事の仔細と謝罪を述べ伝えることは必要だ。……そんな思いから、傭兵団を追うためにサウスゴータの街から出るということも考えた。
だが、
「知識も技量もないガキが、そう簡単に生きていけると思うな」
その愚案は一蹴されてしまった。俺を拾い上げてくれた人物――エドワードの、冷厳な言葉によって。
あの時、俺が倒れていたのは、かつてヘレンと一緒に来た魔法屋の目の前だった。エドワードは、くたばり損なっていた俺を助けて、さらに今後の生活の保障までしてくれると言ったのだ。
無論、俺は最初、その申し出を断ろうとした。
転生に関することは伏せたが、自分がダッシュウッド男爵に捕えられていたことは、隠さずに伝えた。ふたたび何者かに狙われるかもしれない。だから、すぐに出ていく。――俺はそのように主張したものの、エドワードは一歩も引かなかった。
結局、折れたのは俺のほうだった。「お前一人で、どうやって生きていくのだ」というエドワードの言葉に、まともな回答を出せなかったからだ。杖の再契約をしておらず、肉体も弱っていた状態では、野垂れ死ぬのが容易に想像できてしまっていた。
無論、俺は最初、その申し出を断ろうとした。
転生に関することは伏せたが、自分がダッシュウッド男爵に捕えられていたことは、隠さずに伝えた。ふたたび何者かに狙われるかもしれない。だから、すぐに出ていく。――俺はそのように主張したものの、エドワードは一歩も引かなかった。
結局、折れたのは俺のほうだった。「お前一人で、どうやって生きていくのだ」というエドワードの言葉に、まともな回答を出せなかったからだ。杖の再契約をしておらず、肉体も弱っていた状態では、野垂れ死ぬのが容易に想像できてしまっていた。
それから、俺はエドワードのもとで暮らすことになった。俺ができる範囲の雑事をこなす代わりに、エドワードは都市生活の常識や魔法に関する技術を教えてくれた。
やはりエドワードは引退した士官貴族だったらしく、実力もさることながら知識も膨大だった。そして皮肉なことに、彼もダッシュウッド男爵と同じ“水”を得意とする優秀なメイジだった。だが……そのおかげで、得るところも大きかったと言えるが。
やはりエドワードは引退した士官貴族だったらしく、実力もさることながら知識も膨大だった。そして皮肉なことに、彼もダッシュウッド男爵と同じ“水”を得意とする優秀なメイジだった。だが……そのおかげで、得るところも大きかったと言えるが。
幸いなことに、とくに大きな問題も起きず、時間は経過していった。その中で、俺は確かに知識を蓄え、技量を磨いていった。
そして次第に、己がなすべきことも明瞭になった。一つは以前から決めていた、チャーリーたちに出会うこと。だが、これは手がかりがまったくないだけに、後回しにせざるを得なかった。
だから、俺はもう一つのほうを優先することに決めた。それはエドワードから“ある魔法”を学んだことで、実現可能になった目標だった。
そして次第に、己がなすべきことも明瞭になった。一つは以前から決めていた、チャーリーたちに出会うこと。だが、これは手がかりがまったくないだけに、後回しにせざるを得なかった。
だから、俺はもう一つのほうを優先することに決めた。それはエドワードから“ある魔法”を学んだことで、実現可能になった目標だった。
そう、それは。
――復讐だ。
◇
俺がサウスゴータの街を出ることにしたのは、エドワードに拾われてから半年ほど経った頃だった。性急という自覚はあったが、それでもできるだけ早く、目標を果たしたかったのだ。
街を発つということを伝えると、エドワードは「そうか」とだけ言った。そして別れの際も、「またいつか、戻ってこい」という簡素な言葉を送っただけだった。彼の顔に心配の色が皆無だったのは、俺が生きていくのに十分な力を得たのだと判断してくれたからだろう。ハルケギニア全般の常識から、ポーションの作り方などの専門的な知識まで、俺がエドワードから学んだことは計り知れないほど大きかった。
そして俺は、サウスゴータを離れ――
「……ようやく、か」
魔法で一時的に強化した視力は、鮮明な映像を脳にもたらしていた。そこに映っているのは、もっとも自分がよく知る屋敷だった。
そう、俺はあそこで生まれ、あそこで育ったのだ。我が家……だったところだ。今はもう、たんなる敵地に過ぎないが。
そう、俺はあそこで生まれ、あそこで育ったのだ。我が家……だったところだ。今はもう、たんなる敵地に過ぎないが。
丘の草原に腰を下ろし、屋敷を眺めながら、精神を落ち着かせるよう深呼吸する。
昨日の雨のおかげで湿度は高く、水魔法を使うのに適した天気である。ただし、時刻は正午過ぎ。曇り気味とはいえ真っ昼間なわけだから、発見される可能性については、つねに気を配っておかなければならない。
昨日の雨のおかげで湿度は高く、水魔法を使うのに適した天気である。ただし、時刻は正午過ぎ。曇り気味とはいえ真っ昼間なわけだから、発見される可能性については、つねに気を配っておかなければならない。
なぜ深夜に紛れないかというと、屋敷やポートランド伯爵の様子について、面倒なことが判明していたからだ。それは、就寝時間になると屋敷の廊下などに魔法人形 が配置されるということだった。
一週間前に一度、下見で侵入を試みたところ、俺はアレの厄介さを身をもって思い知った。どうやらあの人形は、侵入者を発見すると警告音を発するようにできているらしい。つまり夜半に忍び込むなら、あの見張りをどうにかしなければならないわけである。
俺が屋敷にいた時は、あんなものを見たこともなかったが、おそらくダッシュウッド男爵が殺されたことを知ってから用意したのだろう。ポートランド伯爵が半年前から屋敷の私室に籠りがちになったのも、俺の報復を恐れてのことかもしれない。
一週間前に一度、下見で侵入を試みたところ、俺はアレの厄介さを身をもって思い知った。どうやらあの人形は、侵入者を発見すると警告音を発するようにできているらしい。つまり夜半に忍び込むなら、あの見張りをどうにかしなければならないわけである。
俺が屋敷にいた時は、あんなものを見たこともなかったが、おそらくダッシュウッド男爵が殺されたことを知ってから用意したのだろう。ポートランド伯爵が半年前から屋敷の私室に籠りがちになったのも、俺の報復を恐れてのことかもしれない。
そうしたこともあって、俺は決行時刻を昼間に変更していた。夜より、むしろ昼のほうが警戒も少ないように見えたからだ。一週間ほど観察を続けた結果、使用人や衛士の行動パターンも、大体を把握できていた。
まあ最悪、見つかっても“眠りの雲”で眠らせればよい。あれからさらに鍛えた俺の魔法ならば、叫ばれる前に意識を奪うことができるはずだ。何人もの敵を同時に相手にするという最悪の状況でなければ、まずしくじることはなかろう。
まあ最悪、見つかっても“眠りの雲”で眠らせればよい。あれからさらに鍛えた俺の魔法ならば、叫ばれる前に意識を奪うことができるはずだ。何人もの敵を同時に相手にするという最悪の状況でなければ、まずしくじることはなかろう。
「……さて」
行くか。
俺はタクト型の杖を振るい、フライの魔法を発動した。できるだけ速度を緩めて、地面すれすれを静かに移動する。
広大な屋敷の庭には、庭師や衛士が数人いるだけなので、気づかれずに近づくのは簡単だった。塀を越えて裏庭に侵入すると、すぐに草木の陰に身を隠す。体が小さいと、こういうところだけは役に立つものである。
広大な屋敷の庭には、庭師や衛士が数人いるだけなので、気づかれずに近づくのは簡単だった。塀を越えて裏庭に侵入すると、すぐに草木の陰に身を隠す。体が小さいと、こういうところだけは役に立つものである。
さあ、問題はこれからだ。
俺はわずかに顔を上げて、屋敷のほうを確認した。すぐ向こうに、厨房につながっている裏口のドアが見える。そこから屋敷内に入ることを、俺は計画していた。
深呼吸してから、緊急時に迅速な対応ができるように、事前に“眠りの雲”のルーンを唱える。そして周りに人影がないのを目視してから、俺は素早く裏口に向かった。
昼食の後片づけも終わり、夕食の準備にはまだ遠い時間――とはいえ、中に人がいないとは限らない。緊張を保ちながら、俺はドアを開けて厨房に侵入した。
深呼吸してから、緊急時に迅速な対応ができるように、事前に“眠りの雲”のルーンを唱える。そして周りに人影がないのを目視してから、俺は素早く裏口に向かった。
昼食の後片づけも終わり、夕食の準備にはまだ遠い時間――とはいえ、中に人がいないとは限らない。緊張を保ちながら、俺はドアを開けて厨房に侵入した。
「……っ」
誰もいないことに安堵の息を吐こうとした自分を、内心で叱咤する。気を抜いてはならないのだ。つねに警戒せよ。
裏口のドアを閉め、厨房内に人がいないことを再確認。……よし。
同じように、厨房から食堂へと移動する。こちらも人はいない。後ろ手でドアを閉めつつ――
裏口のドアを閉め、厨房内に人がいないことを再確認。……よし。
同じように、厨房から食堂へと移動する。こちらも人はいない。後ろ手でドアを閉めつつ――
がちゃり、と廊下から食堂へとつながるドアが開いた。
俺は姿勢を低くして、杖を構えた。ドアを開けた人物が完全に室内へ入ったところで、“眠りの雲”を浴びせる算段だった。
中に入ってきたのは、一人だけだった。その小さい人影が、自分の入ってきたドアを閉めたところで、ようやく俺の存在に気づいたようだ。
中に入ってきたのは、一人だけだった。その小さい人影が、自分の入ってきたドアを閉めたところで、ようやく俺の存在に気づいたようだ。
不覚にも、俺は杖を振り下ろすことをためらってしまった。
なぜなら、そこにいた人物は――
なぜなら、そこにいた人物は――
「……だ、だれ?」
相手がその言葉を発した瞬間、俺は無意識に魔法を放っていた。睡魔の雲に包まれて、少年は即座に眠りに落ちた。
……半年間、削ぎ落ちた左耳を覆い隠すために、ろくに髪を切らずに伸ばしていた。おまけに衣服も、貧相で薄汚れたローブを着ている。そして極めつけは、腕が一本しかないという有様である。こんな見てくれでは、俺と気づかないのも無理からぬことである。
そう自分に言い聞かせて、俺は眠っている少年――コリーをレビテーションで浮かせて移動し、厨房の物陰に隠した。彼がなんの用事で食堂に来たのかは不明だが、少なくとも俺がポートランド伯爵の私室に到達するまでに見つからないでくれれば、どうにかなるだろう。
そう自分に言い聞かせて、俺は眠っている少年――コリーをレビテーションで浮かせて移動し、厨房の物陰に隠した。彼がなんの用事で食堂に来たのかは不明だが、少なくとも俺がポートランド伯爵の私室に到達するまでに見つからないでくれれば、どうにかなるだろう。
再度、食堂に戻り、廊下側の様子を確かめる。そして人の気配はないと判断した俺は、静かにドアを開けて廊下に出た。
ルーンの詠唱は新たに済ませておいたので、あとは杖を振り下ろすだけで“眠りの雲”を使える状態だ。いざという場合を頭に入れておきながら、廊下を渡りはじめる。
目的地は二階だが、玄関ホールを通るのは無謀なので、目指すのはホールとは反対側の廊下突き当たりにある狭い階段。こちらは主に使用人が上り下りするものだから、人に出くわしたとしても対処しやすい平民のほうで済むはずだ。
ルーンの詠唱は新たに済ませておいたので、あとは杖を振り下ろすだけで“眠りの雲”を使える状態だ。いざという場合を頭に入れておきながら、廊下を渡りはじめる。
目的地は二階だが、玄関ホールを通るのは無謀なので、目指すのはホールとは反対側の廊下突き当たりにある狭い階段。こちらは主に使用人が上り下りするものだから、人に出くわしたとしても対処しやすい平民のほうで済むはずだ。
「…………」
……意外なほど、あっさりと階段までたどり着くことができた。前回に出くわしたような魔法人形 がいないだけで、こうも容易になるとは。やはり、この時間帯に侵入して正解だったようだ。
声のない安堵の息をつきながら、俺は階段を上りつめた。運もよいのか、やはり人に発見されることはなかった。ここまでくれば、あとは問題あるまい。
廊下が無人であることを確認した俺は、すぐさま早足で移動した。ポートランド伯爵の私室はそれほど離れておらず、十秒とかからずドアの前に到着する。
声のない安堵の息をつきながら、俺は階段を上りつめた。運もよいのか、やはり人に発見されることはなかった。ここまでくれば、あとは問題あるまい。
廊下が無人であることを確認した俺は、すぐさま早足で移動した。ポートランド伯爵の私室はそれほど離れておらず、十秒とかからずドアの前に到着する。
「……開けッ」
強く念じ、ドアノブに向けて杖を振るう。多少の抵抗はあったが、すぐに俺の精神力に負けて、ドアは“アンロック”される。
そして素早く次の魔法を唱えながら、俺はポートランド伯爵の私室へと侵入した。
そして素早く次の魔法を唱えながら、俺はポートランド伯爵の私室へと侵入した。
ドアを開き、我が身を室内に躍りこませ、すぐさま“サイレント”の魔法を発動させる。それと同時に、後ろ足で乱雑にドアを閉め、執務机に座っている眼前の人物に杖を突きつける。
「ポートランド伯爵」
俺がその名を口にした直後、ようやくポートランド伯爵も事態を把握したようだ。彼は慌てて立ち上がり、「誰かっ!」と叫んだ。
「無駄だ。“サイレント”で、声は届かん」
その言葉どおり、俺は先程のサイレントの魔法を、室内の外周だけに沿って展開していた。そのため、俺とポートランド伯爵の声は、ここにいる二人にしか聞こえない。ただし、こんな器用な芸当を長時間続けていれば、俺の精神力はすぐに枯渇してしまうだろう。
「不用意に叫べば、私はすぐに、貴様を殺す。死にたくなければ、叫ぶな」
そう言ってから、俺は“サイレント”を解除した。ポートランド伯爵は、俺の脅しが偽りないものであると理解したのか、苦い顔で口を閉ざした。
「……久しいな、ポートランド伯爵。我が子に再開した気分は、どうだ?」
「戯れ言を、悪魔の子め……!」
「戯れ言を、悪魔の子め……!」
悪魔の子。
懐かしいその言葉に、俺は笑みを浮かべた。その反応が意外だったのか、ポートランド伯爵は一瞬ながら面食らったような顔をする。
懐かしいその言葉に、俺は笑みを浮かべた。その反応が意外だったのか、ポートランド伯爵は一瞬ながら面食らったような顔をする。
「ポートランド伯爵。私がここに来た理由、それが何かわかるか?」
「……殺す、つもりか」
「……殺す、つもりか」
憎悪と諦観が入り混じったような声で、ポートランド伯爵はそう答えた。たしかに、これまでの経緯を考えれば、そのために俺が来たのだと考えるのが普通だろう。
だが、
だが、
「いいや、殺さん」
そうだ。
たとえ、この男を殺したとしても、それで満足するのは俺だけだ。むしろ領主が殺されたとなれば、領地が混乱することにより、結果として領民が苦しむハメになるかもしれない。
ならば――もっと別の方法が必要だ。そして、そのための魔法を、俺は会得していた。
たとえ、この男を殺したとしても、それで満足するのは俺だけだ。むしろ領主が殺されたとなれば、領地が混乱することにより、結果として領民が苦しむハメになるかもしれない。
ならば――もっと別の方法が必要だ。そして、そのための魔法を、俺は会得していた。
「ポートランド伯爵。貴様には、私の命令に従ってもらう」
「命令、だと……?」
「命令、だと……?」
険しい表情で聞き返すポートランド伯爵。そんな彼に、俺はある物を渡すために、ローブの内ポケットからそれを取り出した。
と、その瞬間――
こんこん、と控えめなノック音が響いた。
……使用人だろうか。いずれにしても、今は闖入されるとまずい状況である。
俺はポートランド伯爵に目配せをして、ドアの前の人物を追い返すように促した。
俺はポートランド伯爵に目配せをして、ドアの前の人物を追い返すように促した。
だが、ポートランド伯爵が口を開く前に、ドアの向こうから幼い声が伝わってきた。
「おとうさま。おはなし、したいことあるの」
心臓が、高鳴った。
この声を、忘れているわけがない。かつてこの屋敷で、彼女はコリー以上に無垢な態度で俺に接してくれた、数少ない人物なのだから。
この声を、忘れているわけがない。かつてこの屋敷で、彼女はコリー以上に無垢な態度で俺に接してくれた、数少ない人物なのだから。
――シンシア。
俺の妹だった子。あれから半年経って、彼女も誕生日を迎えたはずだから、今は五歳のはずだ。
俺の妹だった子。あれから半年経って、彼女も誕生日を迎えたはずだから、今は五歳のはずだ。
「……ポートランド伯爵」
一つのことを確認したい衝動を抑えきれず、俺はその言葉を発していた。
「シンシアを、室内に入れろ」
「ま、待てッ。娘には――」
「危害は加えん。私に従え」
「ま、待てッ。娘には――」
「危害は加えん。私に従え」
杖を見せつけて強く言うと、ポートランド伯爵は押し黙った。それからわずかな逡巡を経て、彼は苦渋の表情でドアの向こうへ声をかけた。
「シンシア。そこにいるのは、お前だけかい?」
「うん。……おへやに、おきゃくさん、いるの?」
「……構わないよ。ドアは開いているから、入ってきなさい」
「はい」
「うん。……おへやに、おきゃくさん、いるの?」
「……構わないよ。ドアは開いているから、入ってきなさい」
「はい」
そして、ドアはゆっくりと開かれた。
その小さな姿は、見覚えがあると同時に成長もはっきりと現れていた。背は伸びたし、佇まいも以前よりしっかりとしている。やはり、半年という月日を実感してしまう。
だが……。
もっとも様変わりしたのは、おそらく、この俺だろう。あるいは、交流の少なかった人物であれば、別人と見間違えられることにも頷けた。
だが……。
もっとも様変わりしたのは、おそらく、この俺だろう。あるいは、交流の少なかった人物であれば、別人と見間違えられることにも頷けた。
そうだ。
交流の少なかった――つまり、親しくなかった人物であれば、だ。
交流の少なかった――つまり、親しくなかった人物であれば、だ。
シンシアは、無言で立ち尽くす異様な俺の姿を見て、怯えと戸惑いの混ざった表情で呟いた。
「……だぁれ?」
俺は笑った。
見事なまでに、予想が的中したからだ。
見事なまでに、予想が的中したからだ。
そりゃあ、そうだよなぁ?
事を面倒にしない一番の方法は、俺の存在を“なかったこと”にすることなのだから。
おまけに、ダッシュウッド男爵が関わっていたとなれば、どういう手段を講じたのか一目瞭然だ。
事を面倒にしない一番の方法は、俺の存在を“なかったこと”にすることなのだから。
おまけに、ダッシュウッド男爵が関わっていたとなれば、どういう手段を講じたのか一目瞭然だ。
「イル・ウォータル・スレイプ・クラウディ……」
スリープ・クラウドのルーンを唱えて、シンシアを“眠りの雲”で包む。幼く耐性のない彼女は、すぐに眠りに落ちた。
俺は静かに、薄笑いを浮かべながら、ポートランド伯爵のほうへ振り返った。
「……どうやら、よっぽど、私を消したかったようだな」
言葉を詰まらせるポートランド伯爵に、俺は念のための確認をする。
「ダッシュウッド男爵の、入れ知恵か?」
「……そうだ。彼の提案で、シンシアの記憶の一部を消した。それと、お前と親しかったメイド長の息子も、だ」
「……そうだ。彼の提案で、シンシアの記憶の一部を消した。それと、お前と親しかったメイド長の息子も、だ」
やはり、か。
いくら外見が変わったとはいえ、コリーとシンシアがことごとく俺に気づかないのは、道理に合わぬことだ。ならば疑うべきは、記憶の操作である。対象となる人物の年齢が低く、精神が未熟であることに加えて、高度な知識と技量を持つダッシュウッド男爵が手を貸したとなれば、二人から俺の記憶を抜き去ることは不可能ではなかったのだろう。
いくら外見が変わったとはいえ、コリーとシンシアがことごとく俺に気づかないのは、道理に合わぬことだ。ならば疑うべきは、記憶の操作である。対象となる人物の年齢が低く、精神が未熟であることに加えて、高度な知識と技量を持つダッシュウッド男爵が手を貸したとなれば、二人から俺の記憶を抜き去ることは不可能ではなかったのだろう。
どこか胸の内で、濁った感情が蠢く。失望なのか、悲嘆なのか、憤怒なのか、それとも憎悪なのか。……いや、どれでも構わないか。いずれにせよ、その情動は俺の魔法の効果を強めてくれるに違いない。ならば――十分だ。
俺は、ポケットから小瓶を取り出した。床から転がして、それをポートランド伯爵の足元に送る。
「命令だ。それを飲め」
ポートランド伯爵は、小瓶を床から取り上げた。そして、その中に入っている液体に気づいて、警戒の顔色を浮かべた。
「これを飲ませて……どうするつもりだ」
「シンシアやコリーにしたことと、同じようなことをするだけだ。わかるだろう?」
「…………」
「シンシアやコリーにしたことと、同じようなことをするだけだ。わかるだろう?」
「…………」
顔を歪め、小瓶を手にしたまま、ポートランド伯爵は動かない。
ああ。
その気持ちは、よくわかるさ。
――俺も“同じこと”を経験したのだから。
その気持ちは、よくわかるさ。
――俺も“同じこと”を経験したのだから。
だからこそ、どうすれば相手を従わせられるのか、俺は知っている。
「飲め。もし、命令を聞けないのであれば――」
俺は己の顔に、できるかぎりの残虐と憎悪を混ぜ込んだ笑いを浮かべた。
「――シンシアを殺すことだって、厭わない」
もはや、この家に未練はない。だからこそ、どんなに下劣な手段であっても忌避しない。
そんなふうに信じ込みながら、俺はブレイドで魔力の刃を纏わせた杖を、床上で気を失っているシンシアの首に近づけた。
そんなふうに信じ込みながら、俺はブレイドで魔力の刃を纏わせた杖を、床上で気を失っているシンシアの首に近づけた。
それでようやく理解したのか、ポートランド伯爵は慌てて小瓶の蓋を開けた。
「……わかったっ! お前の言うとおりにする。だから……シンシアに危害は加えるな」
「ならば、その薬を飲め」
「ならば、その薬を飲め」
俺は冷たい言葉で命令した。もはや逃れる術はないと判断したのか、ポートランド伯爵は意を決して、小瓶の中身の液体を一気に嚥下した。
その薬は、人の心に作用する魔法薬 だ。とりわけ、恐怖や悲哀といった負の感情を増長させる効果がある。それを飲んだポートランド伯爵にとって、もはや俺は逆らうことのできない存在となるだろう。
俺は一歩、ポートランド伯爵のほうへ踏み出した。それに反応して、彼は怯えの表情を浮かべながら後ずさる。だが、その後ろは窓で行き止まりだ。
「動くな」
俺がそう声に出すと、ポートランド伯爵は床にへたり込んで動かなくなった。……いいや、移動しなくなっただけだ。彼の体は、俺への恐怖によって震えていた。
――悪魔の子。もともと、そう言って忌諱していたほどだ。薬を飲んだ今は、いったいどれほど苦痛な感情を抱いているのだろうか。
――悪魔の子。もともと、そう言って忌諱していたほどだ。薬を飲んだ今は、いったいどれほど苦痛な感情を抱いているのだろうか。
だが、それは俺にとって、まさしく都合のよいものに違いない。
復讐を果たすために必要なルーンを唱えおわった俺は、さらにポートランド伯爵のもとへ近寄った。
「私は、貴様に命令する。もしそれを破ったならば、私は貴様とその周囲の人間を、殺しつくしてやる」
瞋恚を滾らせた顔を作りだす。
そう、俺は――悪魔だ。断じて、神の血などはこの身にない。
そう、俺は――悪魔だ。断じて、神の血などはこの身にない。
俺は、ゆっくりと、その命令を切りだした。
「ポートランド伯爵」
怯え、震えつづける彼の横に立ち、その無様な姿を見下ろす。
俺は杖を掲げた。あとは、命令を伝え、魔法を解放するだけだ。
俺は杖を掲げた。あとは、命令を伝え、魔法を解放するだけだ。
そう、これで、ようやく、復讐が完成するのだ。
俺は、ついに最後の口を開いた。
「――領民に尽くせ」
そして俺は、杖を振り下ろした。
◇
風がそよいだ。
無造作に伸びた髪が、うっとうしく靡く。耳が隠れるようにしつつ、邪魔な部分は短くしたいものだ。自分で切るなら、鏡が必要だろうか。いや、都市に行って散髪屋を探したほうがいいかもしれない。
そんなことを考えながら、遠い向こうの屋敷を見やる。今頃は、きっと騒動になっているだろう。なんせ、侵入者が領主とその娘を昏倒させていたのだから。
そしてポートランド伯爵が回復したら、おそらく使用人たちはもっと驚くに違いない。最近、自室に籠ってばかりだった主人が、まるで人が変わったかのように仕事をしだすのだから。
そんなことを考えながら、遠い向こうの屋敷を見やる。今頃は、きっと騒動になっているだろう。なんせ、侵入者が領主とその娘を昏倒させていたのだから。
そしてポートランド伯爵が回復したら、おそらく使用人たちはもっと驚くに違いない。最近、自室に籠ってばかりだった主人が、まるで人が変わったかのように仕事をしだすのだから。
……俺にできることは、これまでだ。
ダッシュウッド男爵やエドワードと違って、俺の魔法はまだまだ未熟。もしかしたら、年月が経てば“制約”が消えてしまうかもしれない。あるいは、領主の異常に気づいた医者が、何かしらの術で制約を除去してしまうかもしれない。
だが、それでも今回の一件は大きな意義を持つ。俺の死を明確に認知しないかぎり、ポートランド伯爵は領民に尽くさざるを得ないからだ。彼がもっとも恐れているのは、条理に適わぬ“悪魔の子”からの復讐なのだから。
ダッシュウッド男爵やエドワードと違って、俺の魔法はまだまだ未熟。もしかしたら、年月が経てば“制約”が消えてしまうかもしれない。あるいは、領主の異常に気づいた医者が、何かしらの術で制約を除去してしまうかもしれない。
だが、それでも今回の一件は大きな意義を持つ。俺の死を明確に認知しないかぎり、ポートランド伯爵は領民に尽くさざるを得ないからだ。彼がもっとも恐れているのは、条理に適わぬ“悪魔の子”からの復讐なのだから。
――だからこそ、俺はこの郷里を去らなければならない。
そして残りの目標、チャーリーたちと出会うことを果たさなければ。それが終われば、俺がすべきことは……せいぜい“生きる”ことくらいだ。
そして残りの目標、チャーリーたちと出会うことを果たさなければ。それが終われば、俺がすべきことは……せいぜい“生きる”ことくらいだ。
長年過ごしたかつての家に、背を向ける。
涼しい風を浴びながら、小さな歩みを進めながら。
涼しい風を浴びながら、小さな歩みを進めながら。
俺は最後に、風音に紛れて呟いた。
「――さようなら、父さま」