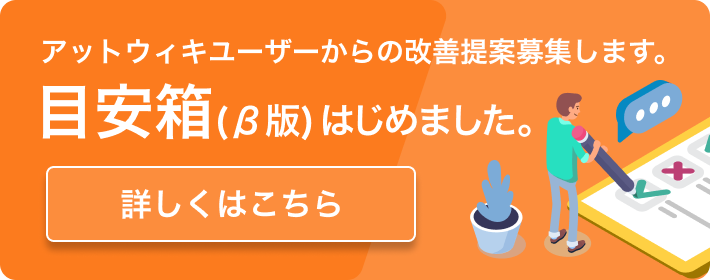身売りされた貴族のお話 06
目を覚まして感じたのは、そこにあるはずのものがないという、明確な違和だった。
恐る恐る、己の左腕に視線を向ける。寝ている間にローブを着せられたようだが、左肩から先の部分の布は切り取られている。そして当然ながら、左腕のあったところには虚空が存在しているだけだった。上腕の切断部は、すでに新しい皮肉に覆われており、痛みすらない。つい先刻まで、そこには確かに俺の腕が存在していたというのに。
恐る恐る、己の左腕に視線を向ける。寝ている間にローブを着せられたようだが、左肩から先の部分の布は切り取られている。そして当然ながら、左腕のあったところには虚空が存在しているだけだった。上腕の切断部は、すでに新しい皮肉に覆われており、痛みすらない。つい先刻まで、そこには確かに俺の腕が存在していたというのに。
くふ、と口から笑い声が漏れた。
すでに片腕をもぎ取ったように、ダッシュウッド男爵は本気で奥義書 どおりに事を進めるつもりなのだろう。となると、近いうちに残りの手足も解体され、肉達磨となったところで心臓を抜かれて死すという未来は、ほぼ確定と言えよう。……なんと、滑稽で醜悪な死に様なことか。
だが存外、俺にとってはお似合いな末路なのかもしれない。愚者への報い。そう捉えることもできなくはないだろう。あるいは、“痛み”を与えられないだけマシなのだろうか。
だが存外、俺にとってはお似合いな末路なのかもしれない。愚者への報い。そう捉えることもできなくはないだろう。あるいは、“痛み”を与えられないだけマシなのだろうか。
もはや俺の精根は一切が尽き、諦観だけが全身に巣食っていた。
自嘲の笑みを顔に張り付かせて仰向けになっていると、階段を下りてくる音が響く。案の定、鉄格子の前に現れたのはダッシュウッド男爵だった。
自嘲の笑みを顔に張り付かせて仰向けになっていると、階段を下りてくる音が響く。案の定、鉄格子の前に現れたのはダッシュウッド男爵だった。
「やあ、気分はどうだい?」
どの口が、そんな言葉を吐くのやら。悪気がないのであれば真性の気違いであり、故意でしているのであれば最低の人でなしである。
俺は気怠さに口を開くこともできず、彼を無視するように押し黙った。
俺は気怠さに口を開くこともできず、彼を無視するように押し黙った。
「……ふむ。どうやら、状態には問題がないようだね。その様子であれば、明日にはまた秘術の続きを実行できるだろう」
左腕の切断部が完治しているのはもちろんのこと、相当量の出血をしただろうに、俺は貧血にすらなっていなかった。もしかしたら、水の秘薬でも使って人為的に増血させているのかもしれない。であるならば、この頭のいかれた儀式が完遂されるのも、そう遠くはなかろう。
「さて、秘術の中止以外で要望があるのなら、最大限まで聞いてあげることはできるけど……何かあるかい?」
「…………私の、視界から、消えてくれ」
「…………私の、視界から、消えてくれ」
俺は心からの願いを吐いた。もうこいつの顔を見るのは、必要最低限にしたかった。
ダッシュウッド男爵はにこりと笑うと、
ダッシュウッド男爵はにこりと笑うと、
「では、きみが夕食を取ったら戻ろう」
そう言って、彼は鉄格子の扉を開けて、食事を乗せたトレーを俺の横に置いた。
俺は煩わしさを感じながら、口を開いた。
俺は煩わしさを感じながら、口を開いた。
「……いらん」
「そういうわけにもいかない。栄養状態が悪いと、水魔法の効果も弱まってしまうからね。――食べろ」
「そういうわけにもいかない。栄養状態が悪いと、水魔法の効果も弱まってしまうからね。――食べろ」
その言葉に、びくりと俺の体が反応する。これは命令だ。彼の命令には……逆らえない。
起き上がった俺は、意志に関係なく食事を取りはじめた。貴族用の高級な料理ばかりであるが、望まない食事は死ぬほど不味かった。
必要な分の量を胃に収めたところで、俺はようやく拷問まがいの食事から解放された。必要なことは済んだからか、その後、ダッシュウッド男爵は俺の要望どおり、さっさと上に帰っていった。
起き上がった俺は、意志に関係なく食事を取りはじめた。貴族用の高級な料理ばかりであるが、望まない食事は死ぬほど不味かった。
必要な分の量を胃に収めたところで、俺はようやく拷問まがいの食事から解放された。必要なことは済んだからか、その後、ダッシュウッド男爵は俺の要望どおり、さっさと上に帰っていった。
独りになった俺は、食事後にすぐ寝転がるわけにもいかず、冷たい石壁に背を預けた。
明日に、また一本。
次は右腕か、それとも両足のうちのどちらかか。いずれにせよ、すぐに命の消えることがわかっているのだから、どれから切り取られようが、さほど違いはなかろうが。
明日に、また一本。
次は右腕か、それとも両足のうちのどちらかか。いずれにせよ、すぐに命の消えることがわかっているのだから、どれから切り取られようが、さほど違いはなかろうが。
腕をなくした左肩を右手で握り、歯噛みをする。
負の感情が混ざり合い、言葉に表せないものとなる。込み上げたそれらは、俺の精神を着実に蝕んでいく。何も考えたくなかったのだが、先刻までずっと気絶していたせいで、眠気もなく目が冴えてしまっている。
負の感情が混ざり合い、言葉に表せないものとなる。込み上げたそれらは、俺の精神を着実に蝕んでいく。何も考えたくなかったのだが、先刻までずっと気絶していたせいで、眠気もなく目が冴えてしまっている。
俺はじっと、天井を見つめつづけた。何分、何十分とそうしていたのか、わからない。もしかしたら、何時間も経っていたかもしれない。
時間感覚が完全に狂った時、小さな足音がかすかに聞こえた。おそらく、ダッシュウッド男爵だろう。また、何か用があるのだろうか。こちらとしては声も聞きたくないというのに。
時間感覚が完全に狂った時、小さな足音がかすかに聞こえた。おそらく、ダッシュウッド男爵だろう。また、何か用があるのだろうか。こちらとしては声も聞きたくないというのに。
「アシュリー」
「え?」
間抜けな声を、俺は上げた。
おそらく、顔も間抜け面だったに違いない。それほどまでに、俺は驚き、そして混乱していたのだから。
おそらく、顔も間抜け面だったに違いない。それほどまでに、俺は驚き、そして混乱していたのだから。
震えを抑えられないまま、視線を天井から下ろす。
鉄格子の向こう側に、その人物は気配もなく立っていた。
幻聴と幻視か、と最初は思った。けれども、彼女はもう一度、今度ははっきりと存在を主張するように、明確に言葉を投げかけてきた。
鉄格子の向こう側に、その人物は気配もなく立っていた。
幻聴と幻視か、と最初は思った。けれども、彼女はもう一度、今度ははっきりと存在を主張するように、明確に言葉を投げかけてきた。
「遅れてすまない。……動くことは、できるか?」
答えようとして、声が出なかった。緊張を抑えこめるために、一度呼吸を直して、唾を飲みこむ。それでようやく、なんとか口が利けるようになった。
「……なん、で……ここに……」
そうだ。
なぜ、ここに来た。
あなたには、そんな理由も義理もないはずだ。
なぜ、ここに来た。
あなたには、そんな理由も義理もないはずだ。
――ヘレン。
「お前を助けに来た」
まるで当たり前だと言わんばかりに、ヘレンは答えた。
ばかな。
あまりに都合がよすぎる。
これは、俺の妄想ではないのか。
あまりに都合がよすぎる。
これは、俺の妄想ではないのか。
そう惚ける俺の前で、ヘレンは杖を振るう。すると、鉄格子の扉が嘘のようにたやすく開いた。彼女はそこから獄中に入り、俺の前で視線を合わせるように屈みこむ。
「アシュリー」
そう名前を呼ぶヘレンは、たしかに実在していた。これは……俺の妄想などではない。本当に、彼女は、俺を助けに来たのだ。
なぜ、という言葉を呑みこむ。
ここで、あれこれと問答している暇はない。混乱から復帰してきた頭が、そう判断を下す。ここは敵陣であり、危険を冒しながら、ヘレンはやってきたのだ。いますべきことは、いかにして素早くここを脱出するかであろう。
ここで、あれこれと問答している暇はない。混乱から復帰してきた頭が、そう判断を下す。ここは敵陣であり、危険を冒しながら、ヘレンはやってきたのだ。いますべきことは、いかにして素早くここを脱出するかであろう。
「動けるか?」
ふたたび尋ねるヘレンに、俺は強く頷いた。あれほど萎えていた生気が、いつの間にか湧き出ていた。これは死地から脱出する、最後のチャンスだ。ここまで来てくれた彼女のためにも、無駄にするわけにはいかない。
「ありがとう……ヘレン」
感謝を口にしながら、ゆっくりと立ちあがる。
「詳しいことは、あとで話す。今は逃げることを優先しよう」
ヘレンの提案に賛成し、牢獄を出る彼女の後ろに続く。
開けられた鉄格子の扉をくぐろうとして――俺の脚が止まった。
開けられた鉄格子の扉をくぐろうとして――俺の脚が止まった。
体が震えて動かない。くそ、動けッ!
己を叱咤しても、やはり結果は変わらない。その原因を、俺はよく理解していた。脱出の機会を前にしてなおも、ダッシュウッド男爵の仕掛けた制約は俺を縛りつけていた。
脱獄するということは、彼に対して明確な抵抗となる。
己を叱咤しても、やはり結果は変わらない。その原因を、俺はよく理解していた。脱出の機会を前にしてなおも、ダッシュウッド男爵の仕掛けた制約は俺を縛りつけていた。
脱獄するということは、彼に対して明確な抵抗となる。
その場で尻餅をついた俺は、苦々しい顔でヘレンに制約の内容を伝えた。
それを聞いた彼女は、少しだけ考えこむと、すぐにルーンを唱えはじめた。
それを聞いた彼女は、少しだけ考えこむと、すぐにルーンを唱えはじめた。
「ユビキタス・デル・ウィンデ……」
詠唱を終えて、杖を振る。次の瞬間には、“もう一人のヘレン”が現れていた。
分身、と言って差し支えないだろう。まったく同一の姿かたちをした人間が並んでいるのは、じつに奇妙な光景だった。
――遍在。スクウェアクラスの風魔法である。実際に目にするのは、当然ながらこれが初めてだった。
分身、と言って差し支えないだろう。まったく同一の姿かたちをした人間が並んでいるのは、じつに奇妙な光景だった。
――遍在。スクウェアクラスの風魔法である。実際に目にするのは、当然ながらこれが初めてだった。
分身のほうであるヘレンが、座りこんだままの俺を抱きかかえる。その状態で、彼女は鉄格子の外へ出た。
「自力でなければ、問題はないか」
どうやら、ヘレンの言うとおりのようだ。俺の意志では一歩も動けないものの、他人の力で運んでもらえば、ここから離れることも可能だろう。……なんとも情けない体裁だが。
相も変わらず無力な己に自虐感を募らせていると、ヘレンが言いにくそうに口を開く。
相も変わらず無力な己に自虐感を募らせていると、ヘレンが言いにくそうに口を開く。
「その左腕は――」
「大丈夫……です。傷口は、治っています」
「……すまない。モリグに調べさせていたのだが、時間をかけすぎたな。もっと早く侵入していれば……」
「大丈夫……です。傷口は、治っています」
「……すまない。モリグに調べさせていたのだが、時間をかけすぎたな。もっと早く侵入していれば……」
モリグ――そうか、思い出した。ヘレンの使い魔か。主人と使い魔は、感覚の共有をすることもできる。ならば、たしかにあの小鳥を使えば、屋敷の内外などを気づかれずに調べられるだろう。
とはいえ、屋敷に存在する人間の行動などを正確に把握しておくためには、相応の時間はかかってしかるべきである。それを怠って侵入を試みれば、予想外のミスが生まれるかもしれないのだ。それを考慮すれば、ヘレンの行動はまったく正しかったと言えよう。それに現時点で犠牲になったのは、“たかが”俺の片腕一本だけなのだから。
とはいえ、屋敷に存在する人間の行動などを正確に把握しておくためには、相応の時間はかかってしかるべきである。それを怠って侵入を試みれば、予想外のミスが生まれるかもしれないのだ。それを考慮すれば、ヘレンの行動はまったく正しかったと言えよう。それに現時点で犠牲になったのは、“たかが”俺の片腕一本だけなのだから。
「……行くぞ」
ヘレンは雑念を払うように首を振り、静かにそう言った。俺も余計なことは口にしまいと、「はい」とだけ短く答えた。
先頭をヘレン。後ろに、俺を抱えた遍在が続く。
狭い階段を上へと歩いていくと、前方が行き止まりになった。どうやら、出入り口は棚のようなもので塞ぎ隠されているようだ。ヘレンが杖を振るうと、念力の魔法によって、棚がゆっくりと横にスライドしていった。
その出入り口から出たところは、思いがけない場所だった。それは――書庫だった。整然と書架が並べられ、ほとんどの棚が本で埋まっている。奥義書 などというものにまで手を出しているということは、ダッシュウッド男爵はそれ以外の一般書も膨大な量を読了しているのだろう。もし彼がこれらの書物をすべて読んでいるのだとしたら、末恐ろしい執心である。
狭い階段を上へと歩いていくと、前方が行き止まりになった。どうやら、出入り口は棚のようなもので塞ぎ隠されているようだ。ヘレンが杖を振るうと、念力の魔法によって、棚がゆっくりと横にスライドしていった。
その出入り口から出たところは、思いがけない場所だった。それは――書庫だった。整然と書架が並べられ、ほとんどの棚が本で埋まっている。
「この上が、屋敷の一階につながっている」
ヘレンが声を潜めて言った。
ということは、俺がいた牢獄は地下のさらに下にあったようだ。なるほど、それならいくら大声で騒ごうとも、屋敷の人間には気づかれないだろう。おまけに、貴重な書物が収められている書庫となると、普通の使用人が立ち入ることさえ滅多にないはずだ。牢獄の存在を隠匿するのはたやすかろう。
ということは、俺がいた牢獄は地下のさらに下にあったようだ。なるほど、それならいくら大声で騒ごうとも、屋敷の人間には気づかれないだろう。おまけに、貴重な書物が収められている書庫となると、普通の使用人が立ち入ることさえ滅多にないはずだ。牢獄の存在を隠匿するのはたやすかろう。
「タイミングを見計らって、書庫から一階へ、そして屋敷の窓から外に出る。声は出さんように、注意しろ」
ヘレンの指示に、俺は頷いた。
それからは口を閉ざし、書庫から一階に続くドアの前で待機する。遍在ではない、本体のほうのヘレンは両目を閉じていた。おそらく、モリグの視界を共有して外の様子を確認しているのだろう。
それからは口を閉ざし、書庫から一階に続くドアの前で待機する。遍在ではない、本体のほうのヘレンは両目を閉じていた。おそらく、モリグの視界を共有して外の様子を確認しているのだろう。
「――出るぞ」
ふいに、ヘレンが声を上げた。すぐに彼女はアンロックの魔法で開錠して、ドアを開く。
そこからは素早く、されど足音をいっさい漏らさずに移動する。ヘレンのその身のこなしは、さすが気配に鋭敏な風メイジといえよう。
廊下を渡り、突き当たりのところで、目的と思われる窓があった。先にヘレンがそこを通り、遍在と抱えられた俺があとに続く。
外は月明かりで照らされていた。深夜とはいえ、これだと目を凝らせば遠くからでも姿が見えてしまう。途中で発見されるのではないかと緊張したが、俺たちはなんとか屋敷から離れることができた。
そこからは素早く、されど足音をいっさい漏らさずに移動する。ヘレンのその身のこなしは、さすが気配に鋭敏な風メイジといえよう。
廊下を渡り、突き当たりのところで、目的と思われる窓があった。先にヘレンがそこを通り、遍在と抱えられた俺があとに続く。
外は月明かりで照らされていた。深夜とはいえ、これだと目を凝らせば遠くからでも姿が見えてしまう。途中で発見されるのではないかと緊張したが、俺たちはなんとか屋敷から離れることができた。
――逃げだせた。
そのことを、ようやく実感した時だった。
寒気が走った。
それが強烈な殺気だと俺が気づくより早く、ヘレンは行動していた。背後を振り返り、風魔法を放ったのだ。烈風が唸り声を上げて、こちらを射殺さんと飛んできた氷の矢を弾き飛ばした。
「…………」
ヘレンは、魔法が飛来してきた方向を無言で睨んでいた。俺もゆっくりと、震えながら、そちらへと視線を移す。
その姿を見て、俺は危うく小さな悲鳴を上げかけた。
……彼がいたのだ。ここからでもわかるほどの、見る者すべてを畏怖させうる熾烈な魔力を滾らせて。
「ダッシュウッド男爵……」
俺は苦々しく、その名を呟いた。
遠目だが、ダッシュウッド男爵の服装は寝衣のままだとわかる。もしかしたら偶然、俺たちの脱走に気づいて、駆けつけたのかもしれない。だとしたら、なんとも運の悪い話である。
遠目だが、ダッシュウッド男爵の服装は寝衣のままだとわかる。もしかしたら偶然、俺たちの脱走に気づいて、駆けつけたのかもしれない。だとしたら、なんとも運の悪い話である。
「アシュリー」
ヘレンは声に緊張を含みながらも、決意したように言い放った。
「私は、ここでやつと戦う」
「え?」
「え?」
予想だにしていなかった言葉に、俺は面食らってしまった。
「やつは単身だ。お前の今後の安全を確保する好機は、今しかない」
ダッシュウッド男爵を、殺そうと言うのか。
それは……ダメだ。危険すぎる。
それは……ダメだ。危険すぎる。
たしかに、ヘレンは強いかもしれない。傭兵として渡り歩いているのだから、戦いのスキルは豊富なのだろう。
しかし相手――ダッシュウッド男爵も、スクウェアの力を持つメイジなのだ。楽にあしらえるような甘い敵ではないと断言できる。
おまけに今、俺という足手まといがいることも考えると、戦況は不利といっても過言ではない。
しかし相手――ダッシュウッド男爵も、スクウェアの力を持つメイジなのだ。楽にあしらえるような甘い敵ではないと断言できる。
おまけに今、俺という足手まといがいることも考えると、戦況は不利といっても過言ではない。
そして、もう一つ――相手はきちんとした爵位を持つ貴族なのだ。
それを殺すなどということは、世間的に見れば途轍もない大罪である。背負うリスクの大きさは計り知れないだろう。
そう……俺のために、ヘレンがそこまでする必要はない。こうして逃してくれただけでも、十分すぎるほどの恩義があるのだから。
それを殺すなどということは、世間的に見れば途轍もない大罪である。背負うリスクの大きさは計り知れないだろう。
そう……俺のために、ヘレンがそこまでする必要はない。こうして逃してくれただけでも、十分すぎるほどの恩義があるのだから。
「ヘレン! ダメだ!」
俺は思わず叫んでいた。そして、抑えきれない心情をぶちまける。子供らしい口調も忘れて、彼女の行動をやめさせようと、ダッシュウッド男爵の危険性を説いた。
なのに。
それでも。
それでも。
「ならば、なおさら放っておけん」
まったく退く気配も持たず、ヘレンは言いきった。
なぜだ!
どうして、そんなにこだわるんだ……!
どうして、そんなにこだわるんだ……!
わからない。理解できなかった。迷惑しかかけていない俺のために、どうして……。
「アシュリーッ!」
その鬼気迫る声に、俺はぞくりとした。
ダッシュウッド男爵は、すでに声の届く位置にまで来ていた。そして、これまでの様子からは信じられないような怒気を湛えて叫んだ。
ダッシュウッド男爵は、すでに声の届く位置にまで来ていた。そして、これまでの様子からは信じられないような怒気を湛えて叫んだ。
「命令だ! ――ぼくのところへ戻れ!」
命令、と聞こえたところで、ダッシュウッド男爵の声が不自然に消えた。これは――サイレントの魔法だ。ギアスの効果が発現されないように、途中でヘレンが阻害したのだろう。
「もう時間がない。……ここから、立ち去るぞ」
俺を抱えている、遍在のほうのヘレンがそうささやき、飛行 の魔法のルーンを唱えはじめた。お荷物でしかない俺を連れて、ここから離脱させるつもりなのだろう。
……ヘレン、本当に俺のために、ここで彼と対決するというのか。
……ヘレン、本当に俺のために、ここで彼と対決するというのか。
「……逃げる気か、アシュリー。だが……無駄なことだ。ぼくの取り込んだ、きみの血 は、きみの気配の在り処を教えてくれるのだから」
俺から目を離さず、ダッシュウッド男爵が口を開いた。サイレントの魔法のせいで、彼がどういう言葉を上げたのかわからない。だが――俺の存在を諦めない意志と執念が、その所作から感じとれた。
遍在のほうのヘレンが、俺をしっかりと抱きしめて、フライで上空に飛び上がる。
地上に残った二人――本体のヘレンとダッシュウッド男爵は、お互いに杖を構えて対峙した。……もはや、戦闘は避けられまい。どちらかが死ぬことになるのだろう。
先に杖を振るったダッシュウッド男爵の上方に、三十はゆうに超える数の氷の矢が出現した。彼はそのうちの半分を放ったが、ヘレンは風魔法と俊敏な身動きでそれらを防ぎいなした。
先に杖を振るったダッシュウッド男爵の上方に、三十はゆうに超える数の氷の矢が出現した。彼はそのうちの半分を放ったが、ヘレンは風魔法と俊敏な身動きでそれらを防ぎいなした。
俺が認識できた光景は、それで最後だった。フライの高速な移動で、もはやあの二人の姿が見えないところまで来てしまったのだ。
「アシュリー。私が死んで、あの男が生き残ったら、できるだけサウスゴータから離れろ」
遍在とはいえ、俺を抱えている彼女も、紛れもなくヘレンと同一の記憶や思惟を持っている。すなわち、その言葉はヘレンの述べるものに相違ない。
だからこそ。
だからこそ。
――死ぬなんて、言わないでくれ。
震え声で、俺がそう言うと、
「私は、もういいんだ」
なぜ彼女がそんなことを言うのか、まったくわからなかった。俺のために命を危険にさらすことにも、まるで納得できなかった。
かける言葉を見つけられずにいると、すぐにサウスゴータの街に着いてしまう。ヘレンはそのまま降下して、人気がない建物間の細い路地に着地した。
「……思いどおりに、いかないことばかりだな、この世は」
ぽつりと呟いたヘレンは、俺の肩に手をかけてしゃがんだ。
そして、ゆっくりと、語りかける。
そして、ゆっくりと、語りかける。
「あの男との決着がついた」
その言葉に、俺は顔を強張らせた。
決着がついた。
そして眼前の遍在である彼女は――消失していない。
そして眼前の遍在である彼女は――消失していない。
ならば――
「やつの息の根は止めた」
安堵が漏れ、次いで不安が湧き出る。
ダッシュウッド男爵が死んだということは、ヘレンは無事だということだ。しかし、彼を殺したということは、今後はその罪から彼女は追われるに違いない。
そんなヘレンに対して、俺はどう感謝して、どう謝罪すればよいのか。
言葉を探し出そうとして――
ダッシュウッド男爵が死んだということは、ヘレンは無事だということだ。しかし、彼を殺したということは、今後はその罪から彼女は追われるに違いない。
そんなヘレンに対して、俺はどう感謝して、どう謝罪すればよいのか。
言葉を探し出そうとして――
異変に気づいた。
「……ヘレンっ!」
眼前の彼女の姿が、揺らいでいた。
……遍在が、消えかかっている?
……遍在が、消えかかっている?
まさか。
もしかしたら。
もしかしたら。
いやな予感が膨れ上がる。
それが間違いであってほしかった。
それが間違いであってほしかった。
けれども、ヘレンは、躊躇なく言い放った。
「致命傷だ。私も助かるまい」
足の力が抜けて、倒れそうになる。
だが、その体を支えるように、ヘレンは力強く俺の肩を抱きしめた。
だが、その体を支えるように、ヘレンは力強く俺の肩を抱きしめた。
「……私からのお願いがある」
胸が破裂しそうなほど高鳴り、乱れた息は過呼吸に近いほどになっていた。
何度かうめき声を上げたのち、ようやく俺は「……な、に」とだけ言葉を返すことができた。
何度かうめき声を上げたのち、ようやく俺は「……な、に」とだけ言葉を返すことができた。
ヘレンが最期に託す願い。
傭兵団のメンバーへの遺言か、それとも別のことか。いずれにせよ、何がなんでも、俺の命に換えようが、実現させなければならないだろう。それは最低限必要な、彼女に対する感謝と謝罪となる。
傭兵団のメンバーへの遺言か、それとも別のことか。いずれにせよ、何がなんでも、俺の命に換えようが、実現させなければならないだろう。それは最低限必要な、彼女に対する感謝と謝罪となる。
「アシュリー」
固唾を呑んで次の言葉を待つ俺に、ヘレンは初めて大きな笑みを浮かべて、
「――生きろ」
そして彼女は、風のように立ち消えた。
俺は、崩れ落ちるように膝をついた。
◇
気づけば、日の出の時刻になっていた。
いつの間に、それほどの時間が経ったのだろうか。あのことが、つい数分前のことのように思えるのに。
膝をついたままの俺の頭には、ずっとヘレンの言葉が離れなかった。
いつの間に、それほどの時間が経ったのだろうか。あのことが、つい数分前のことのように思えるのに。
膝をついたままの俺の頭には、ずっとヘレンの言葉が離れなかった。
――生きろ。
とんだ皮肉だ。ダッシュウッド男爵の命令と同じだなんて。
それでも、それは、ヘレンの願いなのだ。ならば、俺は、“命に換えても”生きなければならないのだろう。
それでも、それは、ヘレンの願いなのだ。ならば、俺は、“命に換えても”生きなければならないのだろう。
右腕に力を込めて、こぶしを握る。
大丈夫。動ける。動かなければならないのだ。
おもむろに、着実に、立ち上がる。
大丈夫。動ける。動かなければならないのだ。
おもむろに、着実に、立ち上がる。
行こう。
そう思ったが、どこへ、と自問する。
そう思ったが、どこへ、と自問する。
ダッシュウッド男爵が死亡した以上、俺への明確な脅威はなくなったはずだ。彼は俺の存在を秘匿していたのだから、彼のあとを継いで俺を狙うような輩もすぐには現れまい。つまりは、何も今すぐ、着の身着のままでサウスゴータから離れるような必要はないわけだ。とはいえ彼が死亡した事件について、今後起こるであろう騒動の推移には注目しておくべきだろうが。
ならば差し当たり、この街に留まるとして、どうすればよいのだろうか。
ヘレンの傭兵団のメンバー――チャーリーたちに会ってみる? だが、おそらく、もはや彼らはサウスゴータにはいないだろう。ヘレンのあの行動は、明らかに単独で計ったものだった。そしてチャーリーたちについて、ヘレンが何も言及していなかったことを考えると、やはり彼女は傭兵団と袂を分かったのだと推測できる。それはきっと――危険に巻き込みたくなかったからだろう。
今後、少なくともヘレンの死については、傭兵団に言い伝えなければならない。彼らがヘレンに対してどう思っているのであれ、だ。しかしながら、彼らがこの街にいないとなると、現状では保留するしかないが。
今後、少なくともヘレンの死については、傭兵団に言い伝えなければならない。彼らがヘレンに対してどう思っているのであれ、だ。しかしながら、彼らがこの街にいないとなると、現状では保留するしかないが。
……ひとまず、生き延びることを優先すべきか。我が身が滅びてしまっては、元も子もないのだから。
とにかく、新しい杖と契約して魔法が使えるようになれば、最低限どうにかして生存はできるだろう。しかし、その契約を交わすまでの間は、何かしらの方法で食事と住居を確保しなければならない。
とにかく、新しい杖と契約して魔法が使えるようになれば、最低限どうにかして生存はできるだろう。しかし、その契約を交わすまでの間は、何かしらの方法で食事と住居を確保しなければならない。
そこまで考えて、頭に浮かんだのは、この街で俺がもっとも知っている宿屋だった。
「……モーリス」
そして、彼のことが頭に浮かぶ。命に別状はなかったとはいえ、俺のせいで怪我をさせてしまったのだということは確かだ。
寝床を貸してくれ、などと厚かましいお願いをするわけではないが、迷惑をかけたことについては、宿の主人やモーリス自身に詫びなければなるまい。
そうした考えもあって、俺が行き先をあの宿と決めるのに時間はかからなかった。
寝床を貸してくれ、などと厚かましいお願いをするわけではないが、迷惑をかけたことについては、宿の主人やモーリス自身に詫びなければなるまい。
そうした考えもあって、俺が行き先をあの宿と決めるのに時間はかからなかった。
獄中生活のせいでなまった足の筋肉を動かし、細い路地から通りに出る。
まだ日が出て間もない時刻なので、人影はほとんど見えない。
フライの魔法で降り立った位置から方角を判断して、俺は街の大通りへ向けて歩きだした。
まだ日が出て間もない時刻なので、人影はほとんど見えない。
フライの魔法で降り立った位置から方角を判断して、俺は街の大通りへ向けて歩きだした。
澄んだ空気と、拘束のない開放感。あの昏く濁った牢獄を経験してからだと、こんな普通のことがすこぶる大切なのだと実感する。
いつだってそうだ。本当はこよなく大事なものなのに、なくさなければそれに気づけない。
いつだってそうだ。本当はこよなく大事なものなのに、なくさなければそれに気づけない。
のろのろと歩みを進めて、ようやく見覚えのある道に出る。ここまでくれば、なんとかあの宿屋のところまでは行けるだろう。
時間が経ったこともあって、徐々に人の姿も増えはじめていた。通行人は俺とすれ違うたびに、顔をしかめたり、奇異の目を向けたりする。
だが、それも当たり前の反応だろう。今の俺の外見が、まともな子供のものではないのは自覚していた。そして、そうなってしまった元凶が、誰なのかもよくわかっていた。
時間が経ったこともあって、徐々に人の姿も増えはじめていた。通行人は俺とすれ違うたびに、顔をしかめたり、奇異の目を向けたりする。
だが、それも当たり前の反応だろう。今の俺の外見が、まともな子供のものではないのは自覚していた。そして、そうなってしまった元凶が、誰なのかもよくわかっていた。
周囲の目線を甘受しながら、健常な大人なら半分以下で済むような時間をかけて――俺はようやく、目的地にたどり着くことができた。
すでに店は開いている。しばらく深呼吸を繰り返して、覚悟を決めてから、俺は中に足を踏み入れた。
すでに店は開いている。しばらく深呼吸を繰り返して、覚悟を決めてから、俺は中に足を踏み入れた。
まだ朝の時間であるからか、酒場には人影がほとんどない。それだけに、給仕が俺の来店に気づくのにも時間はかからなかった。
店の主人を呼んでくれるように俺が頼むと、給仕は不審な顔をしながらも奥へ戻っていった。
店の主人を呼んでくれるように俺が頼むと、給仕は不審な顔をしながらも奥へ戻っていった。
そして間もなく、モーリスの父親である主人がやってきた。彼は一瞬、俺の風体を見てたじろいだようだったが、すぐに無愛想な表情に戻して、
「なんの用だ」
疲れと怒りが入り混じったような声だった。……それも当然か。俺のせいで、店で傭兵たちに暴れられたのだ。主人からすれば、もういっさい関わりたくない人間なのだろう。
主人の反応から、これを最後にもう二度と顔を見せないことを、俺は心中で決めた。それが今の俺にできる、最大の詫びだろう。
俺は謝罪の言葉を述べ、頭を下げた。
主人はそんな俺の様子を、つまらなそうな顔で見ていた。
主人の反応から、これを最後にもう二度と顔を見せないことを、俺は心中で決めた。それが今の俺にできる、最大の詫びだろう。
俺は謝罪の言葉を述べ、頭を下げた。
主人はそんな俺の様子を、つまらなそうな顔で見ていた。
「あの」
謝罪のあと、俺はおずおずと口を開いた。わがままかもしれないが、最後に一つだけ聞いておきたいことがあったのだ。
モーリス。彼が元気になったのかどうかを確認したかった。俺にはもう合わせる顔がないのだが、それでも気になって仕方がなかったのだ。
モーリス。彼が元気になったのかどうかを確認したかった。俺にはもう合わせる顔がないのだが、それでも気になって仕方がなかったのだ。
「モーリスは」
どうしているのか。
そう聞こうとしたところで、遮るように主人は言い放った。
「死んだよ」
体が倒れないようにするのが精いっぱいだった。
絶句している俺に、主人はいらついた様子で言葉を続けた。
絶句している俺に、主人はいらついた様子で言葉を続けた。
「……打ちどころが悪かったようだ。悔しいが……済んでしまったことだ。だから――」
――もう出て行ってくれ。
疲労のにじみでたその声に、俺は機械的に「はい」と呟いて、踵を返した。
店から出た俺は、ふらふらと歩きだした。行く当てはないが、とにかくどこかへ逃げたかった。
馬鹿な話だよ。少し考えれば、予想できたことだろう。
ダッシュウッド男爵からすれば、俺は獄中で食われ死ぬ存在だった。つまり、俺が外の事実を確認する術はなかったのだ。ならば、事の真偽はどうでもよい。俺を操作しやすい情報を与えられれば、それだけでよかった。
それなのに、のうのうとダッシュウッド男爵の話を信じていたとは、俺はなんと愚かで惨めなのか。
ダッシュウッド男爵からすれば、俺は獄中で食われ死ぬ存在だった。つまり、俺が外の事実を確認する術はなかったのだ。ならば、事の真偽はどうでもよい。俺を操作しやすい情報を与えられれば、それだけでよかった。
それなのに、のうのうとダッシュウッド男爵の話を信じていたとは、俺はなんと愚かで惨めなのか。
くつくつと笑いが漏れる。後悔と羞恥で、もはや俺は自身を消し去りたかった。
それでも――生きなければならない。生きてこの苦痛を味わうことこそが、俺の犯した罪への罰なのだろう。
それでも――生きなければならない。生きてこの苦痛を味わうことこそが、俺の犯した罪への罰なのだろう。
乾いた笑いを浮かべて歩む俺に、道行く人々が目線を向ける。それは愚者を憐れむ目か、それとも狂人を蔑む目か。いずれにせよ、俺に近づくまいと道を避けてくれることはありがたかった。
頭が痛い。あまりにも考えることが多すぎた。これから何をするのか。どうすればよいのか。しかし道を決めたとしても、また悪いほうへ転がるだけではないのか。他人を巻き込むのではないか。
胸が痛い。みな、死んでしまった。だが、それを悲しめる資格があるというのか? 誰のせいでそうなったのか、一目瞭然ではないか。
足が痛い。こんな衰えた足では、運動に限界があった。歩くことすらままならないとは、なんという欠陥品なのだろうか。
胸が痛い。みな、死んでしまった。だが、それを悲しめる資格があるというのか? 誰のせいでそうなったのか、一目瞭然ではないか。
足が痛い。こんな衰えた足では、運動に限界があった。歩くことすらままならないとは、なんという欠陥品なのだろうか。
どこに来たのかもわからなくなってきた頃、ふいに俺は地面につまずいて転んだ。
起き上がろうとしても、右手だけでは体が持ち上がらない。
気力もない。体力もない。そして、せめてもの頭すらない。ないない尽くしだ。このどうしようもない俺という存在を、どう扱えばよいのやら。
起き上がろうとしても、右手だけでは体が持ち上がらない。
気力もない。体力もない。そして、せめてもの頭すらない。ないない尽くしだ。このどうしようもない俺という存在を、どう扱えばよいのやら。
諦めて、ぼんやりと地面を眺めていると、頭上からどこかで聞いたことのある声が降ってきた。
「……私の店の前で、何をしている」