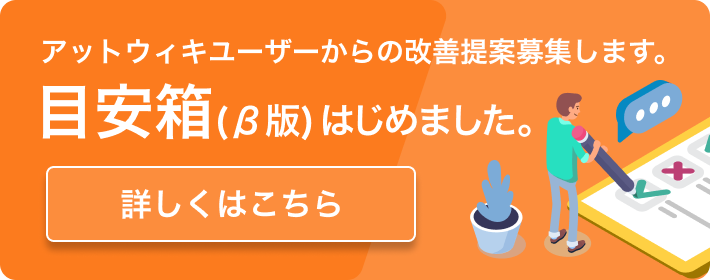身売りされた貴族のお話 05
「おはよう、アシュリー」
気分が悪くなるくらいに爽やかな声で、俺は起こされた。
ゆっくりと上半身を持ち上げると、すぐ近くにダッシュウッド男爵が立っていた。そばには着替えと思われる衣類と、朝食のトレーがある。朝っぱらから、ご苦労なことである。
ゆっくりと上半身を持ち上げると、すぐ近くにダッシュウッド男爵が立っていた。そばには着替えと思われる衣類と、朝食のトレーがある。朝っぱらから、ご苦労なことである。
「朝食の前に、まずは排泄と洗面と着替えを」
「……後ろを、向いていて、もらえるかな?」
「残念だが、そういうわけにもいかないな。きみが何をしでかすかわからないし、我慢してもらうよ」
「……後ろを、向いていて、もらえるかな?」
「残念だが、そういうわけにもいかないな。きみが何をしでかすかわからないし、我慢してもらうよ」
はあ、とため息をついて、俺はローブと下着を脱いだ。こんな状況だ。いまさら羞恥心を持っていたって、なんの役にも立たないだろう。
さっさと小便を終えると、ダッシュウッド男爵は杖を振って宙に大きめの水玉を作り出していた。……魔法の無駄遣いだな。そう呆れながら、水玉に腕を突っ込んで手と顔を洗う。
それから、新しい衣服――といっても、形状はまったく同じ下着とローブをまとい、身支度を完了させる。
さっさと小便を終えると、ダッシュウッド男爵は杖を振って宙に大きめの水玉を作り出していた。……魔法の無駄遣いだな。そう呆れながら、水玉に腕を突っ込んで手と顔を洗う。
それから、新しい衣服――といっても、形状はまったく同じ下着とローブをまとい、身支度を完了させる。
その後、ダッシュウッド男爵は脱いだ衣服や排泄容器を回収して、上へ帰っていった。またすぐにこちらへ戻ってくると言っていたので、その間に朝食を食べられる分だけ口にする。
しばらくすると、ダッシュウッド男爵がふたたび姿を現した。その右手には、何かが握られているようだが、物の判別はできない。
彼は牢獄の中に入ってきて、口を開いた。
彼は牢獄の中に入ってきて、口を開いた。
「きみが昨日言っていた人物に関することだが」
俺は息を呑んだ。間違いなく、モーリスのことだろう。はたして、彼は無事なのか。緊張と不安で体が震えそうになる。
そんな俺を見据えながら、ダッシュウッド男爵はにっこりと笑顔を浮かべた。
そんな俺を見据えながら、ダッシュウッド男爵はにっこりと笑顔を浮かべた。
「今日未明から傭兵に調べさせていたが、ついさっき報告があった。モーリス少年は、あのあと通りすがりのメイジから治療を受けたらしい。後遺症もない様子だったとのこと」
その言葉を聞いて、俺はほっとした。あの時は怪我の程度がはっきりとわからなかったが、どうやら大事にならずに済んだようだ。不幸中の幸い、といったところか。
「さて」
そう切り替えて、ダッシュウッド男爵は右手に持っている物を、俺に見せた。
「きみのお願いは聞いてあげたよ。今度は――こっちの頼みを聞いてもらおうか」
それは小瓶だった。中には白濁した液体が入っている。その成分は、一見しただけでは判別できない。だが……強い魔力が宿っているのを感じる。尋常の効果をもたらす秘薬ではないのは、確かだろう。
「口を開けるんだ」
小瓶の蓋を開けながら、ダッシュウッド男爵は静かに命令した。彼は無感情の瞳で俺を見据えながら、ゆっくりと詰め寄ってくる。
ひどい怖気に襲われて、俺は無意識に後ずさった。しかし逃げ場などない。すぐに石壁に背がついてしまう。足の震えもとめられず、俺はその場にへたり込んでしまった。
諦めろと理性が冷ややかに囁き、やめてくれと本能が見苦しく叫ぶ。なすがままにされるしかない、それはわかっている。だが、いざ我が身に危害が加えられるという時になって、冷静にそれを受け入れられるほど屈強な精神など、俺は持ち合わせていなかった。
ひどい怖気に襲われて、俺は無意識に後ずさった。しかし逃げ場などない。すぐに石壁に背がついてしまう。足の震えもとめられず、俺はその場にへたり込んでしまった。
諦めろと理性が冷ややかに囁き、やめてくれと本能が見苦しく叫ぶ。なすがままにされるしかない、それはわかっている。だが、いざ我が身に危害が加えられるという時になって、冷静にそれを受け入れられるほど屈強な精神など、俺は持ち合わせていなかった。
俺は恐怖に顔を醜く歪ませた。すると、ダッシュウッド男爵は足をとめ、困惑と怪訝の混ざり合った色を顔に浮かべる。
「きみは――なかなか面白い子だね。それとも、頭がおかしくなったのかな?」
頭がおかしいだと? ふざけるなよ、腐れ外道。
たとえ一度死んで生まれ変わろうが、怖いものは怖いんだ。お前の言う“神の子”とやらも、結局は“人の子”でしかない。全てを超克し、全てを超越するような、完全で無欠の存在ではないのだ。それは……俺が、いちばんよくわかっているさ……。
たとえ一度死んで生まれ変わろうが、怖いものは怖いんだ。お前の言う“神の子”とやらも、結局は“人の子”でしかない。全てを超克し、全てを超越するような、完全で無欠の存在ではないのだ。それは……俺が、いちばんよくわかっているさ……。
「……仕方がない」
やれやれといった様子で、ダッシュウッド男爵は左手を伸ばした。その手は俺の顎を掴み、無理やり口を開かせる。そして小瓶を突っ込み、中身の液体を流し込んでくる。
どろりとしたものが、喉を通る。味はしなかったが、最低の気持ち悪さだった。
俺が薬を嚥下したのを確認して、ダッシュウッド男爵は満足げな顔で一歩下がった。
どろりとしたものが、喉を通る。味はしなかったが、最低の気持ち悪さだった。
俺が薬を嚥下したのを確認して、ダッシュウッド男爵は満足げな顔で一歩下がった。
「きみには感謝をしなくちゃいけない」
言葉の意味がわからない。俺が、お前に、何をしたっていうんだ?
――それを理解するのは、ダッシュウッド男爵の次の言葉を聞いた直後だった。
「なぜなら、きみは自分の弱点を教えてくれたのだから」
もはや迂闊を通り越して、救いようのない愚鈍であった。
そうだ……なぜ、俺はそのことをダッシュウッド男爵に教えてしまったのだろうか。
どうせ、獄中で死にゆく身なのだ。そうとわかっているのなら、大人しく他者のことなど気にかけないでおくべきだったのだ。
そうだ……なぜ、俺はそのことをダッシュウッド男爵に教えてしまったのだろうか。
どうせ、獄中で死にゆく身なのだ。そうとわかっているのなら、大人しく他者のことなど気にかけないでおくべきだったのだ。
「モーリスという少年は、きみにとって大切な子供のようだね」
にっこりと笑顔を浮かべて言うその姿は、まるで慈悲深い聖職者のようだ。だが、その内心にどれだけのおぞましい企みが渦巻いているのか、知りたくもなかった。
「……彼は、関係ない! 私、以外は……巻き込まないで、くれ……。頼む……」
「それは、きみの返答次第だよ。アシュリー」
「それは、きみの返答次第だよ。アシュリー」
冷徹に言い放ったダッシュウッド男爵は、杖を取り出した。
「もしも、きみが言うことを聞かないのであれば――」
彼の言葉の途中で、視界の色彩が異常なほど鮮明になったように感じて、くらりと目眩がした。
どくん、どくん、と心臓が暴れている。気づけば、呼吸も荒くなっていた。なんだ、これは。
どくん、どくん、と心臓が暴れている。気づけば、呼吸も荒くなっていた。なんだ、これは。
「――モーリスという少年を殺すことだって厭わない」
それを聞いた瞬間、俺は発狂しそうなほどに感情が迸った。経験したことのないほどの恐怖と自責が沸き上がり、頭を掻きむしりたくなる。
自分でもわかる。この反応はあまりにも過剰だ。おそらく、さっき飲まされた薬のせいだろう。だが……そうとわかっていても、この激情を抑えることはできなかった。
自分でもわかる。この反応はあまりにも過剰だ。おそらく、さっき飲まされた薬のせいだろう。だが……そうとわかっていても、この激情を抑えることはできなかった。
「アシュリー」
ダッシュウッド男爵が俺の顎を掴み、無理やり視線を合わせる。
彼の瞳は、どこまでも冷たく、どこまでも暗かった。そこに宿る感情があるとすれば――狂気以外の、何物でもなかった。
体が震える。冷や汗がとまらない。
彼の瞳は、どこまでも冷たく、どこまでも暗かった。そこに宿る感情があるとすれば――狂気以外の、何物でもなかった。
体が震える。冷や汗がとまらない。
「――ぼくの言うことに従え」
その瞬間、彼は杖を振った。
同時に、俺の頭を底冷えするような魔力が駆け巡る。そこでようやく、俺は気づいた。
同時に、俺の頭を底冷えするような魔力が駆け巡る。そこでようやく、俺は気づいた。
――制約 か!
対象に制約をかけ、一定の行動や心理を操作、あるいは制御する魔法。もちろん、いくら優秀なメイジといえども、健常の相手にはそこまで強い制約を課すことはできない。
だが……薬と脅迫によって精神を乱されている、今の俺のような相手には、恐ろしいほど強い効果を得ることができるだろう。それも行使者が、天才的な魔法の技量を持つダッシュウッド男爵であれば、なおさらのことだ。
だが……薬と脅迫によって精神を乱されている、今の俺のような相手には、恐ろしいほど強い効果を得ることができるだろう。それも行使者が、天才的な魔法の技量を持つダッシュウッド男爵であれば、なおさらのことだ。
――ぼくの言うことに従え。
隷属をもたらすその制約は、寸分の狂いもなく俺に課されたに違いない。さすれば、これから自分がどうなるかも、考えるまでもなく想像できてしまう。
そう、俺はダッシュウッド男爵に言われるがままに、向こうの世界について話すことだろう。だが、それだけで済むかもわからない。もし制約がずっと続くのであれば、俺は彼の操り人形に成り下がる可能性まである。……考えるだけで、身の毛がよだつ。最悪だ。
そう、俺はダッシュウッド男爵に言われるがままに、向こうの世界について話すことだろう。だが、それだけで済むかもわからない。もし制約がずっと続くのであれば、俺は彼の操り人形に成り下がる可能性まである。……考えるだけで、身の毛がよだつ。最悪だ。
言葉をなくし、顔面蒼白となった俺に、ダッシュウッド男爵はにこりと笑う。
「アシュリー、ぼくからの命令だ。――生きろ」
ぞくりと寒気がした。彼の言葉が、深く俺の脳に刻まれる。
「きみに自殺でもされたら困るからね。警戒するに越したことはない」
どうしようもないくらいに、完敗だった。もはや、俺がダッシュウッド男爵を出し抜く要素は一つもない。
「そして、もう一つ」
ダッシュウッド男爵は俺の頭を掴み、さらに目を近づけさせた。その瞳は、先程よりもさらに狂気が増しているように感じられた。
やめてくれ。
許してくれ。
もう……いいだろ……。
許してくれ。
もう……いいだろ……。
だが、彼は慈悲など無縁とばかりに、ゆっくりと開口した。
「――ぼくに抵抗するな」
その言葉で、俺の希望は砕け散った。
◇
「魔法のない世界、か。なかなか興味深いものだね」
鉄格子を挟んだ向こう側で、ダッシュウッド男爵は椅子に座りメモを取っている。
「なあ、知っているかい? たまにハルケギニアでも、魔法が使われていないにもかかわらず、マジックアイテムのように不可思議な道具が見つかることがある。ボタンを押すと、鮮やかな色が映ったり、耳慣れない音が鳴ったりするようなものとかね。どの文献で詳細を見たかは忘れたが、その形状はきみが少し前に言ったやつと似ているね。なんて名前だったかな……。ケータイ……」
「ケータイデンワ」
「そうそれ。きみの世界からの落とし物、ってところかな? もしかしたら、この世界ときみの世界はどこかでつながっているのかもしれない」
「ケータイデンワ」
「そうそれ。きみの世界からの落とし物、ってところかな? もしかしたら、この世界ときみの世界はどこかでつながっているのかもしれない」
俺が“向こう”から“こちら”に転生したように、二つの世界にはなんらかのつながりが確かに存在するはずだ。とはいっても、双方を生身の人間が簡単に行き来できるような方法は、まずありえまい。そんなことが可能なら、かつて俺のいた地球において、異世界の発見が多少なりともニュースになっていてしかるべきなのだから。
そんなふうに考えを抱けども、言葉にすることはなかった。今までずっと話しつづけていたせいで、もう口を開くのも億劫になっていたからだ。
……考えていることを話せ、と命令されたら、俺の意思に反して開口せざるを得ないのだろうが。
そんなふうに考えを抱けども、言葉にすることはなかった。今までずっと話しつづけていたせいで、もう口を開くのも億劫になっていたからだ。
……考えていることを話せ、と命令されたら、俺の意思に反して開口せざるを得ないのだろうが。
しかし幸いながら、今回はこれで解放されるらしい。ダッシュウッド男爵は懐中時計をちらりと確認して、至極わざとらしい口振りで言った。
「おや、もうこんな時間か。夢中になると、どうも時が経つのは早いね」
俺にとっては死ぬほど長く感じたがな。お前との会話は苦痛で仕方がない。
……などと罵倒する気力も残っていなかった。これから何日も同じようなことを続けるのだと思うと、ただひたすらにぞっとしなかった。
……などと罵倒する気力も残っていなかった。これから何日も同じようなことを続けるのだと思うと、ただひたすらにぞっとしなかった。
「しばらくしたら、夕食を持ってくるよ」
そう言って地下を去るダッシュウッド男爵を、俺は無言で見送った。
毛布に倒れ込む。
彼がいない間に、一度自殺をできないか試してみた。だが、やはり無駄だった。いざ死のうと思うと、強烈な忌避感が込み上げて、まったく動けなくなるのだ。それが制約によるものだとわかっていても、無理やり打ち破れるほどの意志の強さは、俺には存在しなかった。
彼がいない間に、一度自殺をできないか試してみた。だが、やはり無駄だった。いざ死のうと思うと、強烈な忌避感が込み上げて、まったく動けなくなるのだ。それが制約によるものだとわかっていても、無理やり打ち破れるほどの意志の強さは、俺には存在しなかった。
……制約 。その魔法が禁忌とされている理由を、俺は身をもって痛感した。
命令されても、意識は保ったままで会話も多少の自由が利くのは、まだマシと言えるのだろうか。……あるいは、その分、行動の強制のみに特化して魔法をかけられているのかもしれないが。ダッシュウッド男爵が並外れた水魔法の操作と応用を可能としているのは、ポートランドの屋敷で受けた何回かの指導だけでも十分に理解している。制約 という禁忌の魔法が存在するということも、そうした指導のついでに教えてもらったのだ。
あの時、魔法の存在と効果だけではなく、制約を解除する方法も聞いておくべきだったか。いや、もし聞いていたとしても、ダッシュウッド男爵は俺を手中に収めた場合を考慮して、答えをはぐらかしていたかもしれない。俺と違って、あの男は狡猾に先を見据えられる頭脳を持っているのだから。
あの時、魔法の存在と効果だけではなく、制約を解除する方法も聞いておくべきだったか。いや、もし聞いていたとしても、ダッシュウッド男爵は俺を手中に収めた場合を考慮して、答えをはぐらかしていたかもしれない。俺と違って、あの男は狡猾に先を見据えられる頭脳を持っているのだから。
ふっ、と俺は笑う。
結局のところ、二回目の生というアドバンテージを持っていようが、凡人は凡人にすぎないのだ。そのことは、俺の現状が何よりもの証拠となっている。ダッシュウッド男爵が先日に挙げたような、華々しい活躍を遂げた転生者たちは、きっと俺などと違ってもともと頭の良い人間だったのだろう。
彼らのように表舞台に立ちたかった、とは言わない。けれども、最低限、少しぐらい不自由でも、静穏な生を送りたかった。――その願望は、もはや実現できまいが。
結局のところ、二回目の生というアドバンテージを持っていようが、凡人は凡人にすぎないのだ。そのことは、俺の現状が何よりもの証拠となっている。ダッシュウッド男爵が先日に挙げたような、華々しい活躍を遂げた転生者たちは、きっと俺などと違ってもともと頭の良い人間だったのだろう。
彼らのように表舞台に立ちたかった、とは言わない。けれども、最低限、少しぐらい不自由でも、静穏な生を送りたかった。――その願望は、もはや実現できまいが。
どこから間違ったのか。
どうして間違ったのか。
どうして間違ったのか。
わずかばかり考えただけでも、数々の浅慮と愚行が思い浮かぶ。もはや己に怒りを感じるどころか、愛想が尽きるレベルだった。
……後悔したって仕方がないし、卑下したって意味はない。
それもわかっているが、気を紛らわすモノもないこの牢獄の中では、どうしても沈思から逃れることができなかった。
それもわかっているが、気を紛らわすモノもないこの牢獄の中では、どうしても沈思から逃れることができなかった。
――これを、あと何日続ければよいのか。
その考えに及んだ時、全身に震えが込み上げた。
無理だ。
耐えられない。
耐えられない。
頭をからっぽにするなどということは、もはや俺には不可能としか言えない。これがさらに続けば、いずれ発狂してしまう。そういう確信があった。
そうなれば、何も考えられなくなった俺は、本当にダッシュウッド男爵の傀儡になるかもしれない。脆い精神であればあるほど、水魔法で人を操ることは容易になる。まして彼ほどの腕前であれば、赤子の手を捻るのと同じようなものだろう。
そうなれば、何も考えられなくなった俺は、本当にダッシュウッド男爵の傀儡になるかもしれない。脆い精神であればあるほど、水魔法で人を操ることは容易になる。まして彼ほどの腕前であれば、赤子の手を捻るのと同じようなものだろう。
そう理解した俺は、今までよりさらに強い感情を抱いた。
それは――死の願望。もう楽になりたい、という想い。
だが同時に、それを否定する声が頭に響いていた。
だが同時に、それを否定する声が頭に響いていた。
――生きろ。
それはダッシュウッド男爵の施した、制約による命令だったのか。
それとも自分自身の抱いた、生を渇望する叫び声だったのか。
それとも自分自身の抱いた、生を渇望する叫び声だったのか。
かつり、かつりと、階段を下りる音が聞こえる。
彼が牢獄の前に姿を現すのと同時に、俺は口を開いた。
彼が牢獄の前に姿を現すのと同時に、俺は口を開いた。
「ダッシュウッド男爵」
「うん? どうしたんだい?」
「うん? どうしたんだい?」
夕食の乗ったトレーを魔法で浮かべながら、彼は首を傾げた。
早く私を殺せ――そう言ってみようとしたのだが、声が出なかった。自殺を試みた時と、まったく同じだった。制約が、死を求めることを拒絶している。
ならば、考え方を変えてみよう。直接的な行動や言葉がダメなら、もっと婉曲すればよい。制約を騙せばよいのだ。
ならば、考え方を変えてみよう。直接的な行動や言葉がダメなら、もっと婉曲すればよい。制約を騙せばよいのだ。
「私の、処分は、どうする?」
これは単なる疑問である。不明なことを尋ねるのは、命令で禁止されていない。
俺の質問に、ダッシュウッド男爵は少し困ったような顔をした。
俺の質問に、ダッシュウッド男爵は少し困ったような顔をした。
「……きみからは、まだ聞きたいことがある。今すぐに、どうこうするつもりはないよ」
「聞き出した、そのあとは?」
「聞き出した、そのあとは?」
ダッシュウッド男爵は微笑を浮かべた。
「――約束しよう。ぼくは、きみを殺すつもりだ」
信じてはならないはずの彼の言葉なのに。
どうしてなのだろうか。
どうしてなのだろうか。
俺は、それが嘘ではないと直感してしまった。
◇
死にたくない。
そう思いながらも、俺の心持ちはどこか楽になっていた。それはきっと、奥底で死という名の希望が生まれたからだろう。
生きろ、という制約はたしかに強大だが、俺のすべてを支配するほどのものではない。だからこそ、事を済ませば俺は死ねる、と思う――思い込むことによって、俺は精神が自壊するのをなんとか免れていた。
生きろ、という制約はたしかに強大だが、俺のすべてを支配するほどのものではない。だからこそ、事を済ませば俺は死ねる、と思う――思い込むことによって、俺は精神が自壊するのをなんとか免れていた。
ダッシュウッド男爵に命令された俺は、機械のように口を開いた。
向こうの世界でのことを、覚えているかぎり吐き出した。
家族のこと、友人のこと、自分のこと。世界のこと、自国のこと、地域のこと。歴史、宗教、政治、哲学といった学術的な知識から、小説、ゲーム、映画、テレビ番組といった娯楽や文化まで。
向こうの世界でのことを、覚えているかぎり吐き出した。
家族のこと、友人のこと、自分のこと。世界のこと、自国のこと、地域のこと。歴史、宗教、政治、哲学といった学術的な知識から、小説、ゲーム、映画、テレビ番組といった娯楽や文化まで。
俺はすべてを口述し、奴はすべてを記録した。
そうして、何日経ったかもわからなくなってきた頃。
「――満足したよ。いろいろな話が聞けて、面白かった」
ダッシュウッド男爵は、そう言った。
欲しい情報は聞き出した、ということなのだろう。
そして用済みになった、ということでもある。
欲しい情報は聞き出した、ということなのだろう。
そして用済みになった、ということでもある。
これで、俺は……。
彼は、いつものように微笑を浮かべた。
「あと少しだけ、きみには用がある。それが終わると同時に、きみは死ぬことになる」
魔法の実験体にでもして、殺すのだろうか。
死ぬのはいい。だが苦しむのは、勘弁したいものである。
死ぬのはいい。だが苦しむのは、勘弁したいものである。
楽に殺してくれ、と言おうとして、声が出なかった。面倒な制約のせいだ。舌打ちして、俺は別の言葉を伝えた。
痛いのは嫌いだ、と。
ダッシュウッド男爵は、ほほえみを深めた。
「“痛み”を与えたりはしないつもりだ、と最初に言ったはずだよ?」
そうか。そういえば、そんなことを言っていたな。
すっかり忘れていた。ずいぶんと昔のことのように感じる。
すっかり忘れていた。ずいぶんと昔のことのように感じる。
痛みがないのなら、十分だ。
俺は満足して、笑みを浮かべた。
俺は満足して、笑みを浮かべた。
「……そんな顔をされても、反応に困るものだね」
やれやれ、とダッシュウッド男爵は肩をすくめた。
いつも嘘くさい笑顔のお前に言われるとは。心外だな。
……まあ、どうでもいいことか。どうせ、俺はすぐに死ぬのだから。
……まあ、どうでもいいことか。どうせ、俺はすぐに死ぬのだから。
「具体的にどうするかは、明日に教えてあげよう。今日は、もう寝るといい」
明日のお楽しみ、というわけか。せいぜい、期待でもしておこう。
「おやすみ、アシュリー」
おやすみ、ダッシュウッド男爵。
◇
夢を見た。
幸せそうな家族が、団欒としている様子だった。
それを俯瞰している俺は、笑いたくて仕方がなかった。
それは、万に一の可能性もない光景だったからだ。
馬鹿げた妄想だ。なぜ、こんなものを夢見たのか。
俺は否定したくて、仕方がなかった。
だって、そこにいる女性の面影は――
◇
目を覚ます。
背に冷たい汗が流れていた。気分もひどく悪い。
俺は呼吸を整えて、頭を振った。
あれは腐った脳味噌が見せた幻想だ。気にすることはない。
俺は呼吸を整えて、頭を振った。
あれは腐った脳味噌が見せた幻想だ。気にすることはない。
そう言い聞かせながら、立ち上がる。
「悪い夢でも見ていたのかい?」
その言葉で、俺は初めてダッシュウッド男爵の存在に気づいた。彼は鉄格子の向こうで、椅子に座って分厚い書物を手にしていた。
「体調がよくないのなら、水魔法をかけてあげるけど」
「いらん」
「いらん」
俺は吐き捨てるように即答した。この男から善意を受けるなど、気分が悪化するだけである。
ダッシュウッド男爵は微苦笑を浮かべながら、肩をすくめた。
ダッシュウッド男爵は微苦笑を浮かべながら、肩をすくめた。
「その返答なら、大丈夫そうだね。さて――身支度を済ませてもらおうか」
「…………」
「…………」
俺は黙って、命令どおりに排泄と着替えを済ませた。食欲が湧かなかったので、朝食はほんのわずかしか取れなかったが。
その後、ダッシュウッド男爵は上に戻っていった。昼前にまた下りてくるらしい。つまりは、それまで俺には何もすることがないというわけである。
その後、ダッシュウッド男爵は上に戻っていった。昼前にまた下りてくるらしい。つまりは、それまで俺には何もすることがないというわけである。
毛布の上に仰向けになり、瞑目する。
俺の処分は今日に教えると言っていたが、いったいどうなることやら。俺の頭では、あの男が何をしでかすか想像もつかない。特殊な魔法薬を俺の体で試用する、程度であったのならよいのだが……妙な期待をすべきではないか。
俺の処分は今日に教えると言っていたが、いったいどうなることやら。俺の頭では、あの男が何をしでかすか想像もつかない。特殊な魔法薬を俺の体で試用する、程度であったのならよいのだが……妙な期待をすべきではないか。
気づけば、体が震えていた。
死を目前にして、肉体が恐怖している。黙らせてやりたかったが、どうにもならなかった。煩わしいものである。
諦めて我が身を無視し、俺は瞑想に耽ることにした。思索の題目は、「死後どうなるのか」。これでまた転生しようものなら、俺は絶望するしかないだろう。願わくは、天国でも地獄でもなく、すべてが無に帰すことである。
諦めて我が身を無視し、俺は瞑想に耽ることにした。思索の題目は、「死後どうなるのか」。これでまた転生しようものなら、俺は絶望するしかないだろう。願わくは、天国でも地獄でもなく、すべてが無に帰すことである。
そんなことをあれこれ考えていたら、いつの間にか時間が経っていた。ふと足音が聞こえ、俺はまぶたを持ち上げる。そして、ゆっくりと上半身を起こすと、ちょうど鉄格子の前にダッシュウッド男爵が来たところだった。
彼がレビテーションで浮かべているものを見て、俺は一瞬ながらもうろたえてしまった。
彼がレビテーションで浮かべているものを見て、俺は一瞬ながらもうろたえてしまった。
「……料理でも、するつもりか?」
「おや、鋭いね」
「おや、鋭いね」
ふふ、とダッシュウッド男爵は不気味に笑った。
そんな彼が持ってきたものは、大きな鍋だった。本気で料理を? もはや、こいつの考えることは理解不能だ。
そんな彼が持ってきたものは、大きな鍋だった。本気で料理を? もはや、こいつの考えることは理解不能だ。
呆れている俺を尻目に、ダッシュウッド男爵は鍋を床に置くと、今朝に読んでいた本を取り出した。
彼はその表紙を俺に見せると、ゆっくりと口を開いた。
彼はその表紙を俺に見せると、ゆっくりと口を開いた。
「今から百年ちょっと前、ゲルマニアの貴族であるイストファン・バートリ・フォン・エセット伯爵の著した、奥義書 の原本だ」
……グリモワールだと? 異端の書物に、俺は驚きつつも眉をひそめた。そうしたものの大半は、一般的な系統魔法の理論や法則に則らない、でたらめで荒唐無稽なものばかりのはず。そんなものを、優秀なメイジであるダッシュウッド男爵が取り上げるとは、予想外も甚だしかった。
彼は俺の反応を確かめると、くすりと笑って言葉を続けた。
「おかしいと思うのかい? だが、その考えは改めるべきだろう。なぜなら――これには、神の国と神の子についても記されているのだから」
俺は息を呑んだ。
そうか……まさに俺のような存在は、通常の魔法からでは説明しきれない。であるならば、異端の書物のほうが核心に触れている可能性は、十分に高いだろう。
そうか……まさに俺のような存在は、通常の魔法からでは説明しきれない。であるならば、異端の書物のほうが核心に触れている可能性は、十分に高いだろう。
ダッシュウッド男爵は書物を椅子に置くと、今度は杖を手に持った。そしてアンロックを使い、鉄格子の扉を開錠する。
「エセット伯爵自身は転生者ではない。だが、彼もきみのような転生者の存在に気づき、異なる世界や神的な力の存在を知った」
話しながら、彼は先程の鍋を手にして牢獄内に入ってくる。……何を、する気だ。
「だが知ってしまえば、それが欲しくなるのは人の道理だと思わないかな? それも転生という神秘であれば、魅力は抗いがたいほど大きなものだ」
彼はポケットから、液体の入った小瓶を取り出した。中身は無色透明だが、やはり強い魔力を感じる。これは……なんの秘薬だ。
「飲め」
短く命令して、ダッシュウッド男爵は小瓶を差し出した。その言葉が脳髄を刺激して、俺の体が勝手に動く。……ちくしょう。悔しいが、どうにもならない。震える手がそれを掴み、小瓶の蓋を開けた。そして、かすかな刺激臭がするその液体を、俺の手は容赦なく喉の奥に流し込む。
味はしなかったが、やはり気分が悪かった。
味はしなかったが、やはり気分が悪かった。
「次は、服を脱げ」
言われるがままにするしかない。俺はローブと下着を脱いで、全裸になった。
「それでいい。さて、話を戻そうか。――神秘を手に入れるには、どうしたらいいと思う?」
……俺が知るわけない。自分がなぜこんなオカルトな現象に巻き込まれたのか、これっぽっちも理解していないのだから。少なくとも、神様に毎日お祈りをしているかどうかが無関係であるのは、間違いないだろうが。
「答えは簡単だ。――神秘を自身に取り込むこと。そうすることで、対象に宿る力を手に入れられるという思想は、古くから随所にも見られる。とくに今でも、一部の種族の亜人などには、その風習が残っているようだね」
神秘を取り込む?
その言葉に、いやな予感がとまらなかった。
その言葉に、いやな予感がとまらなかった。
その意味を知りたくない。耳を塞いでいたい。
「エセット伯爵は、神の子から力を得る秘術を書物に記した。それは――」
やめろ!
言うな!
言うな!
……お願いだよ。
やめてくれ。
言わないでくれ。
言わないでくれ。
「神の子の血肉を食らい、その神秘の力を我が物とすること」
すべてが崩れ落ちるような感覚に陥った。
それを言葉で表すなら、絶望、といったところだろうか。
それを言葉で表すなら、絶望、といったところだろうか。
ダッシュウッド男爵は無表情で、けれども途轍もない狂気を宿して言葉を並べる。
「まず四肢を順に、のちに心の臓を食らうこと。さすれば神の子に宿る祝福を得られん。――シンプルでわかりやすいだろう?」
馬鹿な。
あまりにも、理不尽で不合理すぎる。
お前は、本気でそれを信じているのか。
あまりにも、理不尽で不合理すぎる。
お前は、本気でそれを信じているのか。
「人知を超えた存在には、尋常の方法をなしても無意味だ。であるならば――試してみる価値は、十分にある。ぼくがそう確信するほど、転生という神秘は魅力的なのさ」
ふざけるな。
そう言おうとしても、声が出なかった。それどころか、体の一切が動かない。俺は今、情けなく震えているはずなのに、その感覚さえなかった。
薬の効果だ――麻痺してきた頭で、その答えに行き着く。
そう言おうとしても、声が出なかった。それどころか、体の一切が動かない。俺は今、情けなく震えているはずなのに、その感覚さえなかった。
薬の効果だ――麻痺してきた頭で、その答えに行き着く。
「最初に言ったはずだよ。“今すぐ”は食わないと。だが、興味のあることは粗方を聞いた。かわいそうだが、ぼくが神の力を得るための犠牲になってもらおう」
ダッシュウッド男爵が俺の左腕を掴んだ。そして、蓋を外した鍋に上に、俺の腕を配置する。
なるほど、そうかい。
これから料理を作るための食材を得るというわけか。
……笑えない冗談だぜ。なあ、おい。冗談だと言ってくれよ。
これから料理を作るための食材を得るというわけか。
……笑えない冗談だぜ。なあ、おい。冗談だと言ってくれよ。
「水の秘薬は持ってきている。切断しても、すぐに傷口は治せるから安心するといい。“痛み”はいっさい与えない」
ダッシュウッド男爵は、ブレイドの魔法で杖に水の刃をまとわせた。その鋭利な凶刃には、膨大な魔力が凝縮されている。これなら硬い金属ですら、造作もなく断ち切れるレベルだろう。ましてや、子供の細腕ならば――
「では、まずは左腕から」
やめろッ!
そう叫ぶこともできず、杖が振り下ろされる。
そう叫ぶこともできず、杖が振り下ろされる。
薬で痛覚はなかった。
だが、骨肉を切り裂く感触が生々しく脳に伝えられる。
だが、骨肉を切り裂く感触が生々しく脳に伝えられる。
俺は心中で絶叫を上げて――失神した。