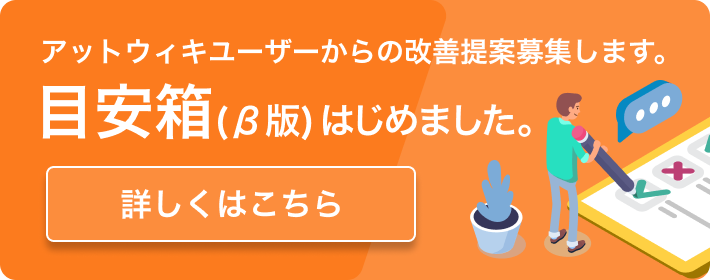身売りされた貴族のお話 01
目を覚ますと、天幕の張られた荷馬車の中だった。
俺の視界には、雑多な積み荷に紛れて座っている、二人の少女が映っていた。左のほうにいるのは、ブルネットの長髪に、そばかすの少しある、八か九歳くらいの娘。右のほうにいるのは、肩口で切り揃えられた金髪で、気の強そうな印象を受ける、十歳くらいの娘。どちらも服装からして、農村の娘――平民であると思われた。
だが、もっとも注目すべきなのは、二人の少女の腕に存在しているものだろう。
だが、もっとも注目すべきなのは、二人の少女の腕に存在しているものだろう。
……どちらも、片腕に拘束具がつけられている。
俺は己の左腕を見た。ご多分に漏れず、手首に革製の手錠がかけられている。それが馬車の一部分に固定されているので、これでは移動することができない。また、手錠のバックルには錠がかけられているので、手錠を外すということもむずかしい。
なんとなく、現状を理解しつつも、俺は懐を探った。だが、いつもそこにあるはずの杖はない。当然と言えば、当然と言えよう。魔法が使えれば、こんな手錠の鍵なんて一発で“アンロック”されるのだから。
心中で舌打ちしていると、ブルネットの少女が話しかけてきた。
なんとなく、現状を理解しつつも、俺は懐を探った。だが、いつもそこにあるはずの杖はない。当然と言えば、当然と言えよう。魔法が使えれば、こんな手錠の鍵なんて一発で“アンロック”されるのだから。
心中で舌打ちしていると、ブルネットの少女が話しかけてきた。
「あ……起きたの?」
俺は返答しなかった。考えることが多すぎて、口を開く気力が湧かなかったのだ。
しかし、少女はそんな俺を見て、不安そうに口をつぐんでしまった。……このままでは、情報は得られまい。仕方なく、俺は小さく言葉を発した。
しかし、少女はそんな俺を見て、不安そうに口をつぐんでしまった。……このままでは、情報は得られまい。仕方なく、俺は小さく言葉を発した。
「ここは、どこ?」
俺が話したことに安堵した様子を、少女は見せた。だが、すぐに暗い顔になって答える。
「……わからない。外、自由に見れないから」
「では、私たちは、なぜ、ここに?」
「では、私たちは、なぜ、ここに?」
急に相手は押し黙る。俺は小さく鼻を鳴らした。この様子では、俺の予想は悪いほうに当たっているのだろう。
それを裏付けるように、もう一人の、金髪の少女が重い口を開いた。
それを裏付けるように、もう一人の、金髪の少女が重い口を開いた。
「売られたのよ」
俺は小さく笑った。二人の少女が、驚きのような表情を浮かべたのち、不審な目を向ける。気でも狂ったのか、と思っているのだろうか。あるいは、「売られた」という意味が理解できていないのではないか、と思っているのかもしれない。
だが、どれも違う。俺は嗤ったのだ。このような状況に至った、これまでの人生を。そして、自嘲だけではない。“やつら”の存在も嘲笑していた。俺というイレギュラーを産み、一度はその魔法の才に歓喜しておきながら、やがて「悪魔の子」と恐れ疎んでいた、我が両親を。
いずれ、この借りは返してやる。そう思ったのは、怒りと憎しみによる復讐心なのだろうか。だが、今はこの感情を抑えなければならない。なすべきことは、現状をいかにして打破するかということのみ。
だが、どれも違う。俺は嗤ったのだ。このような状況に至った、これまでの人生を。そして、自嘲だけではない。“やつら”の存在も嘲笑していた。俺というイレギュラーを産み、一度はその魔法の才に歓喜しておきながら、やがて「悪魔の子」と恐れ疎んでいた、我が両親を。
いずれ、この借りは返してやる。そう思ったのは、怒りと憎しみによる復讐心なのだろうか。だが、今はこの感情を抑えなければならない。なすべきことは、現状をいかにして打破するかということのみ。
「私の名前は、アシュリー。あなたたちの、名前は?」
この二人の娘からは情報を得る必要性があったが、まずはそれを円滑にするために、自己紹介をしておかなければならない。俺の問いに、二人は名前と簡単な事情を述べてくれた。
ブルネットの少女は、シェリー。農家の娘だったが、体が弱くて農作業の手伝いもあまりできなかったらしい。売られたのは、そのためだろう。
金髪の少女は、ベル。こちらも農家の娘だったようだが、とくに家族との折り合いが悪かったらしい。何かしらのいざこざがあったのだろうが、この場でいちいち聞き出す意味はないだろう。
ブルネットの少女は、シェリー。農家の娘だったが、体が弱くて農作業の手伝いもあまりできなかったらしい。売られたのは、そのためだろう。
金髪の少女は、ベル。こちらも農家の娘だったようだが、とくに家族との折り合いが悪かったらしい。何かしらのいざこざがあったのだろうが、この場でいちいち聞き出す意味はないだろう。
「私が、ここに連れてこられたのは、どれくらい前?」
「……六時間前、ってところかしら」
「……六時間前、ってところかしら」
ベルが答えた。
六時間前か。馬車に備え付けられた小窓から外を見るかぎり、今は正午あたり。この時間帯になるまで目を覚まさなかったということは、おそらく魔法か薬のようなもので、ずっと眠らされていたのだろう。
さて、となると、馬車はどこへ向かっているのだろうか。この移動速度からすると、まだそれほど離れたところまで来てはいまい。俺の家の領地から出るか出ないか、といった地点だろうか。
どこへ連れていかれるのは知らないが、脱出を狙うなら急いだほうがよいだろう。だが、杖もない状況で、どうすればよいのだろうか。
あれこれ考えていると、シェリーが聞いてくる。
六時間前か。馬車に備え付けられた小窓から外を見るかぎり、今は正午あたり。この時間帯になるまで目を覚まさなかったということは、おそらく魔法か薬のようなもので、ずっと眠らされていたのだろう。
さて、となると、馬車はどこへ向かっているのだろうか。この移動速度からすると、まだそれほど離れたところまで来てはいまい。俺の家の領地から出るか出ないか、といった地点だろうか。
どこへ連れていかれるのは知らないが、脱出を狙うなら急いだほうがよいだろう。だが、杖もない状況で、どうすればよいのだろうか。
あれこれ考えていると、シェリーが聞いてくる。
「アシュリーは……貴族の子?」
「…………そう、だけど」
「…………そう、だけど」
頭の中で計画を立てながら、俺は頷いた。おそらく、身なりや服飾から判断したのだろう。
「じゃあ、もしかして――ポートランド伯爵の?」
その名に、反吐が出そうになった。俺を売った張本人だ。気分がいいはずがない。
だが、この娘に八つ当たりするべきではない。彼女も、親から見捨てられた哀れな子供なのだから。
だが、この娘に八つ当たりするべきではない。彼女も、親から見捨てられた哀れな子供なのだから。
「そう。でも、どうして、わかったの?」
「えっと、わたしの村の近くに棲みついていたオーク鬼を退治したのが、伯爵家のアシュリーっていう子だと聞いたから……。それで、あなたのことかなって」
「オーク鬼?」
「えっと、わたしの村の近くに棲みついていたオーク鬼を退治したのが、伯爵家のアシュリーっていう子だと聞いたから……。それで、あなたのことかなって」
「オーク鬼?」
ベルが胡乱な顔つきをした。
「この子、五歳か六歳くらいでしょ? オーク鬼なんて倒せるわけないじゃない!」
それは正しい考えだ。普通ならば、いくらメイジの血を持っていても、この程度の歳のガキが凶暴な亜人を倒せるはずがない。――普通ならば。
だが、異常な存在の俺は、それができた。ある農村近くで、平民がオーク鬼に襲われたと聞いて、それを解決しに向かったのだ。
むろん、それには危険性も伴っていた。身体は小さな子供なのである。一歩間違えれば、オーク鬼の棍棒によって脳漿を撒き散らしていたかもしれない。
だが、そうせざるを得なかった。領主である伯爵が動かなかったからだ。伯爵――俺の父は、平民のことなど何も考えておらず、ただ面倒事は御免だと無視をしていた。だから、俺はあの碌でなしに代わって、オーク鬼を殺しつくしたのだ。
そして、家に帰って父が俺に向けたのは――罵声と気味悪がる顔色だった。母は「悪魔の子よ」と言って、絶望したような表情を浮かべた。貴様の産んだ人間だ、と言ってやりたかったが、すべてを諦めていた俺は何も言わなかった。
結局のところ、こういう状況になったのも、あれが一番の契機だったのかもしれない。だとしたら、俺はあの両親に媚を売っておくべきだったのか? ……ふざけるな。そんなことをしたら、俺もクズの仲間入りだった。俺は、あの選択を間違ったものだとは思っていない。
だが、異常な存在の俺は、それができた。ある農村近くで、平民がオーク鬼に襲われたと聞いて、それを解決しに向かったのだ。
むろん、それには危険性も伴っていた。身体は小さな子供なのである。一歩間違えれば、オーク鬼の棍棒によって脳漿を撒き散らしていたかもしれない。
だが、そうせざるを得なかった。領主である伯爵が動かなかったからだ。伯爵――俺の父は、平民のことなど何も考えておらず、ただ面倒事は御免だと無視をしていた。だから、俺はあの碌でなしに代わって、オーク鬼を殺しつくしたのだ。
そして、家に帰って父が俺に向けたのは――罵声と気味悪がる顔色だった。母は「悪魔の子よ」と言って、絶望したような表情を浮かべた。貴様の産んだ人間だ、と言ってやりたかったが、すべてを諦めていた俺は何も言わなかった。
結局のところ、こういう状況になったのも、あれが一番の契機だったのかもしれない。だとしたら、俺はあの両親に媚を売っておくべきだったのか? ……ふざけるな。そんなことをしたら、俺もクズの仲間入りだった。俺は、あの選択を間違ったものだとは思っていない。
湧きあがるどす黒い感情を抑えながら、俺は二人に問いかけた。
「ねえ、この中に、細い棒か何か、ない?」
「棒? ……ううん、ないと思う」
「棒? ……ううん、ないと思う」
ベルも首を振っていた。いちおう、俺もざっと積み荷を見渡すが、それらしいものは見つからない。
では、どうしようか。次の策を考えていると、馬車の揺れが止まった。しばらくすると、馬車後方の垂れ幕が開いて、男が姿を現した。
では、どうしようか。次の策を考えていると、馬車の揺れが止まった。しばらくすると、馬車後方の垂れ幕が開いて、男が姿を現した。
「起きたようだな。体調はどうだ?」
男の目はモノを見るような色だった。間違いではない。俺たちは商品なのだ。
少し考えて、俺は排泄を訴えた。馬車で漏らすわけにもいかないだろう。男も了承し、拘束を解いて、俺を外に連れ出した。
草原の広がる街道だ。場所がどこら辺かはわからない。
俺は後ろを振り向いた。さっきまで乗っていた馬車と、そしてその前方にもう一つ別の馬車がある。この男のほかにも、仲間が複数人いるのだろう。余裕があれば、人数と特徴を掌握しておきたいところだが……。
少し考えて、俺は排泄を訴えた。馬車で漏らすわけにもいかないだろう。男も了承し、拘束を解いて、俺を外に連れ出した。
草原の広がる街道だ。場所がどこら辺かはわからない。
俺は後ろを振り向いた。さっきまで乗っていた馬車と、そしてその前方にもう一つ別の馬車がある。この男のほかにも、仲間が複数人いるのだろう。余裕があれば、人数と特徴を掌握しておきたいところだが……。
「おい、ついてこい」
男は強い語調で言った。これ以上は、仕方ないか。
俺は男に従い、街道から少し外れて、大きな木の陰に向かった。到着すると、さっさと用を足せと言われる。
俺は男に従い、街道から少し外れて、大きな木の陰に向かった。到着すると、さっさと用を足せと言われる。
「…………」
「どうした。早くしろ」
「後ろ、向いていて」
「どうした。早くしろ」
「後ろ、向いていて」
男は舌打ちして、背後を向けた。所詮、六歳児である。杖も持っていないので、警戒していないのだろう。だが、その愚かさに感謝しつつ、俺は所用を済ませた。
その日の夜、左手を繋がれた馬車の中、俺は小窓から夜空を眺めていた。シェリーとベルの寝息が、かすかに聞こえる。こんな不自由な身で寝起きして、何もせず過ごさなければならないとは、不憫なものだ。
なんとかできれば、よいものだが。そんなことを思いながら、俺は“右手にある物”を擦りつづけた。
なんとかできれば、よいものだが。そんなことを思いながら、俺は“右手にある物”を擦りつづけた。
◇
それから二日経って、俺はある程度の状況を把握することができた。
この馬車は、どうやらサウスゴータの街へ向けて動いているようだ。あの古都は、俺も一度だけ訪れたことがある。美しい街だった。だが、その中にも汚れた部分はあるのだろう。その汚れへと、俺たちは送られるのだ。
まあ、素直にそうなる気は毛頭ない。右手の物を弄くりつつ、今日もシェリーとベルの会話を暇潰しに聞く。
この馬車は、どうやらサウスゴータの街へ向けて動いているようだ。あの古都は、俺も一度だけ訪れたことがある。美しい街だった。だが、その中にも汚れた部分はあるのだろう。その汚れへと、俺たちは送られるのだ。
まあ、素直にそうなる気は毛頭ない。右手の物を弄くりつつ、今日もシェリーとベルの会話を暇潰しに聞く。
「わたしたち、これからどうなるのかな? 毎日、ごはんは食べられるのかな?」
「ふん。食べられることは、食べられるんじゃないの? ……何をされるか、知らないけどね」
「ふん。食べられることは、食べられるんじゃないの? ……何をされるか、知らないけどね」
これまでの言動を見てみると、シェリーはあまり自分の状況を理解していないように思える。逆に、ベルは我が身がどんなことになるかを予想できているようだ。それだけに、ベルのほうが悲観的だ。
「ねえ、アシュリーはどう思う?」
シェリーが俺に言葉を求めた。俺はみずから言葉を発することはないが、聞かれたときだけは答えることにしていた。
「貴族か、お金持ちの平民に、買われる、のかもね」
相変わらず、たどたどしいガリア語だ。ここ数年、屋敷の人間とはごく一部を除いて、ほとんどまともに会話をしていなかった。それだけに、この世界――ハルケギニアの言語にはいまだ慣れきっておらず、俺は言葉を口に出すのが苦手なままだった。
「それから、ご奉仕することに、なるのかも」
「ご奉仕?」
「ご奉仕?」
シェリーが首を傾げるが、俺は口を閉ざした。そもそも、俺の言語力では表現する言葉が見つからない。
まあ、内容は言うまでもなかろう。特殊な技能もなく、労働力にならない女子供を買う意味は、ほとんどその肉体を性欲の捌け口にするために決まっている。それ以外の目的があるとすれば……人体実験か? 俺のような異常なメイジならば、魔法研究を目的として手に入れる意義は大きいのかもしれない。
まあ、有用なことなど何一つ解明されないだろうが。そもそも、俺自身が自分のことをほとんど理解していないのだ。なぜ、この世界に転生したのか。わかるやつがいたら、ぜひとも教えてほしいものだ。
まあ、内容は言うまでもなかろう。特殊な技能もなく、労働力にならない女子供を買う意味は、ほとんどその肉体を性欲の捌け口にするために決まっている。それ以外の目的があるとすれば……人体実験か? 俺のような異常なメイジならば、魔法研究を目的として手に入れる意義は大きいのかもしれない。
まあ、有用なことなど何一つ解明されないだろうが。そもそも、俺自身が自分のことをほとんど理解していないのだ。なぜ、この世界に転生したのか。わかるやつがいたら、ぜひとも教えてほしいものだ。
「ねえ、アシュリー」
ふと、ベルが俺に話しかけてきた。
「あなた、貴族――メイジなんでしょう? 魔法は……使えないの?」
「……杖が、ない」
「でも……」
「……杖が、ない」
「でも……」
ベルが目線を移動させた。その先には、俺の右手がある。もっと正確に言えば、俺の弄くりつづけている物へ向けているのだろう。
頭のよい子だ。俺は称賛の笑みを送った。だが、今は下手に話に出さないほうがいいだろう。
頭のよい子だ。俺は称賛の笑みを送った。だが、今は下手に話に出さないほうがいいだろう。
「気に、しないで」
俺は右手の人差し指を口元に当てて、目線を馬車の御者台があるほうへ向けた。それで理解したのだろう。ベルは口を閉ざして押し黙った。シェリーは、相変わらずわけがわからないといった様子で、首を傾げていたが。
その日の夜。シェリーとベルが眠ったのを確認すると、俺は右手の物を愛撫しながら、彼女らの寝息に紛れて小さく小さく呟く。今まで覚えてきた魔法のスペルを、それぞれ何度も何度も繰り返しつづける。最初の頃と比べたら、魔力の流れも感じられるようになってきた。この調子でいけば、近いうちに……。
気づいたら、朝になっていた。焦って、右手を確認する。大丈夫だ、なくなっていない。男に見つからぬように、俺はすぐにそれをポケットに隠した。
しばらくして、男から食事が出された。今日も、パンと水だけだった。ケチな野郎どもだ、と声に出さず愚痴りながら、それらを消化した。
馬車が走りだしてからは、また昨日と同じように、右手で例の物を触りつづける。この触覚を頭に刻みつけて、体に馴染ませなければならない。
しばらくして、男から食事が出された。今日も、パンと水だけだった。ケチな野郎どもだ、と声に出さず愚痴りながら、それらを消化した。
馬車が走りだしてからは、また昨日と同じように、右手で例の物を触りつづける。この触覚を頭に刻みつけて、体に馴染ませなければならない。
「……お外で遊びたいなぁ」
ぼんやりとシェリーが呟いた。その様子からは疲労感がはっきりと伝わってくる。こんな狭い箱に閉じ込められたままでは、それも当然だろう。
ベルは昨日よりもさらに無口になっていた。だが、その目は希望を失っていない。たびたび、俺のほうを見つめている。それは期待の視線だった。
わかっているさ。失敗するつもりはない。俺だって、さっさとここから逃げ出したいのだから。
その意志を代弁させるように、俺は右手に意識を集中させつづけた。
ベルは昨日よりもさらに無口になっていた。だが、その目は希望を失っていない。たびたび、俺のほうを見つめている。それは期待の視線だった。
わかっているさ。失敗するつもりはない。俺だって、さっさとここから逃げ出したいのだから。
その意志を代弁させるように、俺は右手に意識を集中させつづけた。
夜。
研ぎ澄ませた意識とイメージを、「開け」という小さな声に乗せる。一瞬間して、かちゃりと錠から音が鳴った。俺は口を笑みに歪ませた。
だが、まだだ。この程度の契約では、高等な魔法の行使に堪えられるかどうか、まだ自信がない。サウスゴータに着くまで、あと一日間ある。明日中に、できるだけ契約を強めなくては。
開錠したものを、ふたたびロックで施錠してから、俺は眠りに就いた。
研ぎ澄ませた意識とイメージを、「開け」という小さな声に乗せる。一瞬間して、かちゃりと錠から音が鳴った。俺は口を笑みに歪ませた。
だが、まだだ。この程度の契約では、高等な魔法の行使に堪えられるかどうか、まだ自信がない。サウスゴータに着くまで、あと一日間ある。明日中に、できるだけ契約を強めなくては。
開錠したものを、ふたたびロックで施錠してから、俺は眠りに就いた。
「アシュリー……!」
緊迫したベルの声に、俺は意識を覚醒させた。
「なに?」
想定外の事態か。俺は目を擦りながら問うた。
「予定より早くなって、今日中に街に着くって、あいつらが……」
くそったれ! 俺は顔をしかめた。
だとしたら、今日の深夜に脱出するということはむずかしくなる。昨夜のうちに逃げ出しておくべきだったか? いや、それもそれで危険も大きかっただろう。……いまさら考えても詮なきことか。
俺は小窓から外の様子を見た。この明るさからすると、もう少ししたら男が朝食を持ってくるだろう。狙うなら、そのタイミングか。
だとしたら、今日の深夜に脱出するということはむずかしくなる。昨夜のうちに逃げ出しておくべきだったか? いや、それもそれで危険も大きかっただろう。……いまさら考えても詮なきことか。
俺は小窓から外の様子を見た。この明るさからすると、もう少ししたら男が朝食を持ってくるだろう。狙うなら、そのタイミングか。
これまでの道中で、敵の詳細はある程度知ることができていた。数は三人だ。この馬車に乗っている平民の男。先頭の馬車に乗っているメイジの男。もう一人の男は、メイジか平民かは不明。だが、メイジだと考えて動いたほうが危険は少ないだろう。
食事を持ってくるのは、平民の男。これを処理することはたやすい。騒がせずに始末できれば、先頭にいるメイジ二人にも奇襲を加えることができる。勝機は十分にあるだろう。
食事を持ってくるのは、平民の男。これを処理することはたやすい。騒がせずに始末できれば、先頭にいるメイジ二人にも奇襲を加えることができる。勝機は十分にあるだろう。
「シェリー。これから、私たちは逃げる。だから、落ち着いて、目を閉じながら、待っていて」
「え……ほんと? わ、わかった」
「え……ほんと? わ、わかった」
俺はポケットから、杖を取り出した。数日前まで使っていた、正規の杖ではない。馬車に乗せられた初日、排泄の隙に拾った、十サント程度の木の小枝だ。あまりにも頼りないが、これを信じて乗りきるしかない。
アンロックでそれぞれの鍵を外して、手錠を外す。そして、硬化の魔法で杖自体を補強したのち、“ブレイド”で杖に魔力を纏わせる。その状態で、俺は荷台の後方で立って待機した。
これで、男が外から垂れ幕を開けた時、ちょうど目の前に男の顔が来る位置関係になる。つまり、必殺が可能というわけである。
アンロックでそれぞれの鍵を外して、手錠を外す。そして、硬化の魔法で杖自体を補強したのち、“ブレイド”で杖に魔力を纏わせる。その状態で、俺は荷台の後方で立って待機した。
これで、男が外から垂れ幕を開けた時、ちょうど目の前に男の顔が来る位置関係になる。つまり、必殺が可能というわけである。
息を飲む音。誰のものだったのだろうか? わからないし、どうでもいい。重要なのは、男が垂れ幕を開けて顔を出したという事実だけだった。
俺は男の頭を掴んで、その首に杖を突き刺した。ブレイド――水の魔力の刃が、ケーキにナイフを入れたような滑らかさで、男の頚部の肉を貫く。それから、喉を千切るようにして、杖を引き抜いた。
鮮血が降り注ぐ。初めての殺人だったが、それほど動じはしなかった。オーク鬼を殺した時の、油のような血と劣悪な臭いに比べたら、はるかにマシである。
これならば、いける。そう確信した時だった。
俺は男の頭を掴んで、その首に杖を突き刺した。ブレイド――水の魔力の刃が、ケーキにナイフを入れたような滑らかさで、男の頚部の肉を貫く。それから、喉を千切るようにして、杖を引き抜いた。
鮮血が降り注ぐ。初めての殺人だったが、それほど動じはしなかった。オーク鬼を殺した時の、油のような血と劣悪な臭いに比べたら、はるかにマシである。
これならば、いける。そう確信した時だった。
「い、いやああああぁぁぁっ!」
……あまりにも、迂闊だった。おそらく、好奇心か何かで目を開けてしまったのだろう。どうして、この可能性を考慮しなかったのだろうか。これまでのシェリーの人間性を観察していれば、こうした事態も予測できたではないか。事前に魔法で眠らせるなどしておけば、無問題であっただろうに。……アシュリー、貴様は愚か者だ。
なれど、後悔して状況が好転するわけではない。動かなければならないのだ、俺は。
シェリーの叫び声に反応して、すぐに先頭にいるメイジがやってくるだろう。あまり時間はなさそうだ。
俺はルーンを唱えながら、荷台から飛び降りた。馬車の前方を見ると、男が御者台から降りるところだった。そこへ狙いをつけて、俺は氷の矢を放った。
だが、男はこちらの攻撃にいち早く気づいたようだ。飛来する三本の矢を前にして――迷わず体を伏せた。男の肩を、一本だけ矢がかする。……それだけ、だった。
素晴らしい判断力だ。俺は敵を恨んだ。これで俺は、先手のアドバンテージを失ったわけだ。あとは……実力勝負のみだ。
俺はルーンを唱えながら、荷台から飛び降りた。馬車の前方を見ると、男が御者台から降りるところだった。そこへ狙いをつけて、俺は氷の矢を放った。
だが、男はこちらの攻撃にいち早く気づいたようだ。飛来する三本の矢を前にして――迷わず体を伏せた。男の肩を、一本だけ矢がかする。……それだけ、だった。
素晴らしい判断力だ。俺は敵を恨んだ。これで俺は、先手のアドバンテージを失ったわけだ。あとは……実力勝負のみだ。
いいだろう。殺してやる。
身体能力差が絶望的とはいえ、腐っても俺はトライアングルのメイジだ。やれないことは、ない。
身体能力差が絶望的とはいえ、腐っても俺はトライアングルのメイジだ。やれないことは、ない。
ルーンを唱えて、杖を振る。俺の目前に、水が集まっていく。それらは剣となり、そして盾となるのだ。
メイジの男は杖を振った。風の刃がこちらへと向かう。俺は水を前方に広げて、風を受け止めた。その衝撃にいくらか水が吹き飛ばされたが、貫通には遠く及ばない。
やれる。にい、と笑みを浮かべた俺は、溜まった水を鞭に変えて、男へと振り払った。だが――敵に到達する前に、水の鞭は消失した。いや、消失させられたのだ。横から放たれた、灼熱の炎によって。
やはり、もう片方もメイジだったか。形勢逆転。不利なのは、明らかに俺のほうになった。
メイジの男は杖を振った。風の刃がこちらへと向かう。俺は水を前方に広げて、風を受け止めた。その衝撃にいくらか水が吹き飛ばされたが、貫通には遠く及ばない。
やれる。にい、と笑みを浮かべた俺は、溜まった水を鞭に変えて、男へと振り払った。だが――敵に到達する前に、水の鞭は消失した。いや、消失させられたのだ。横から放たれた、灼熱の炎によって。
やはり、もう片方もメイジだったか。形勢逆転。不利なのは、明らかに俺のほうになった。
だからって、命乞いでもするのか? それもバカな話だ。すでに俺は一人殺しているんだ。やつらだって、許しちゃあくれないだろう。
いまさら、恐怖が込みあげてきた。少しでもミスをすれば、一瞬で殺されることだろう。一度死んだ身ではあるが、それでも命を失うことは怖い。いや、経験したからこそ、死が怖いとわかるのだ。
いまさら、恐怖が込みあげてきた。少しでもミスをすれば、一瞬で殺されることだろう。一度死んだ身ではあるが、それでも命を失うことは怖い。いや、経験したからこそ、死が怖いとわかるのだ。
死にたくねぇ。
だから……やるしかないんだ。やつらの息の根を止めろ。躊躇をするな。――悪魔になってみせろ、アシュリー。
「ガキだと思ったら……なんてやつだ」
「用心しろ。あれでもトライアングルらしいからな」
「用心しろ。あれでもトライアングルらしいからな」
杖を振り、水を集める。
持久戦になったら、不利なのはこちらだ。だとしたら、早期決着を狙うしかない。
持久戦になったら、不利なのはこちらだ。だとしたら、早期決着を狙うしかない。
片方のメイジが、火球を放ってくる。俺はそれを、最小限の水を操作して払い除けた。
真正面からの撃ち合いでは、水の壁を突破できないと判断したのだろう。メイジたちは、俺を挟み込むように回りはじめた。
俺は舌打ちした。前後反対に回られたら、それぞれに水の壁を割り当てなければならない。単純計算で、防御力が半分になるのだ。かといって、俺の身体能力では動き回りながらの戦闘は不可能だ。ほぼ固定砲台になるしかないのが、俺の明確な弱点だった。
真正面からの撃ち合いでは、水の壁を突破できないと判断したのだろう。メイジたちは、俺を挟み込むように回りはじめた。
俺は舌打ちした。前後反対に回られたら、それぞれに水の壁を割り当てなければならない。単純計算で、防御力が半分になるのだ。かといって、俺の身体能力では動き回りながらの戦闘は不可能だ。ほぼ固定砲台になるしかないのが、俺の明確な弱点だった。
後手に回っては負ける。俺は火メイジへ向けて、水弾を放った。その弾速は緩やかなもので、男は難なく横に移動して避けた――つもりだったのだろう。だが、俺の目的は別にあった。男が避けた水弾は、その場で破裂した。周囲に水が飛び散り、当然ながら男にも水がかかる。
まずは、一手完了。濡れた服は重みになり、ある程度の動きを封じることができる。
まずは、一手完了。濡れた服は重みになり、ある程度の動きを封じることができる。
背後で、風がうなった。俺を護っていた水が、弾け飛ぶ。と同時に、俺はルーンを唱えて、即座に水を呼び戻した。
水を蒸発させる炎と違って、たんなる風の射撃魔法では有効打がない。それに気づいたのか、風メイジの男は俺に接近してきた。
水を蒸発させる炎と違って、たんなる風の射撃魔法では有効打がない。それに気づいたのか、風メイジの男は俺に接近してきた。
そうだ。その調子だ。かかってこいよ。
俺は水の壁を鞭に変えて、近づく男へと振るった。男はそれを、ブレイドをまとわせた軍杖で斬り払う。壁を失った俺は、隙を見せる形となった。それを見逃さず、男は杖を振りかぶる。
俺はそれを、横に跳んで避けた。
杖をからぶった男の顔には、動揺が浮かんでいた。それもそのはず。俺は、今まで一歩も足を動かしていなかったからだ。だが実際のところは、わざとそうしていただけである。子供の身体とはいっても、ちょっとくらいの運動は可能だ。今まで微動だにしていなかったのは、“動かないもの”と認識させて意表を突くためだった。
たたらを踏んだ男へ、俺は杖を振った。水の塊が敵にぶつかり、遠くへ吹き飛ばす。本来ならば、これに追撃を加えて勝利を得られるのだが……。
たたらを踏んだ男へ、俺は杖を振った。水の塊が敵にぶつかり、遠くへ吹き飛ばす。本来ならば、これに追撃を加えて勝利を得られるのだが……。
俺は水を操り、横から飛来してきた火球を防いだ。だが、火球の爆発を相殺しきれずに、衝撃で地面を数メイル転がる。くそ、体がいてぇ。
それでも、弱音を吐いている暇はない。たった数秒でも命取りになるのだから。
ルーンを唱えながら立ち上がり、火メイジの男を見据える。相手は次の攻撃魔法を唱えているところだった。
やらせるかよ。俺は杖を振って、水を操作した。
それでも、弱音を吐いている暇はない。たった数秒でも命取りになるのだから。
ルーンを唱えながら立ち上がり、火メイジの男を見据える。相手は次の攻撃魔法を唱えているところだった。
やらせるかよ。俺は杖を振って、水を操作した。
操ったのは――男の服に染みこんでいた水だ。それらの水を、男の口元に集めて息をできなくさせる。突然のことに男は混乱した様子で、慌てて“念力”の魔法を使って水を払った。しかし……その隙は致命的だった。
すでに別の魔法を唱えていた俺は、杖を振った。その動きに合わせて、鞭となった水が唸り声を上げる。
火メイジの男の顔が凍った。だが、それも一瞬。鞭の一撃を受けた男の首が遠くへ跳んでいった。――あっけないものだ。
すでに別の魔法を唱えていた俺は、杖を振った。その動きに合わせて、鞭となった水が唸り声を上げる。
火メイジの男の顔が凍った。だが、それも一瞬。鞭の一撃を受けた男の首が遠くへ跳んでいった。――あっけないものだ。
残りは一人。
俺は風メイジの男のほうを向いた。やつは悪夢を見ているかのような表情を、顔に貼りつかせていた。それを見て、俺はぞくりと嗜虐的な快感を抱いた。この時の自分は、血の臭いに浮かされて気を狂わせていたのかもしれない。
男は大量の氷の矢を作り出し、撃ち放ってきた。恐怖心と焦燥感からか、何本かは的外れな方向へ飛んでいる。我が身へ迫る矢を、俺は水の壁で難なく防ぎ――
俺は風メイジの男のほうを向いた。やつは悪夢を見ているかのような表情を、顔に貼りつかせていた。それを見て、俺はぞくりと嗜虐的な快感を抱いた。この時の自分は、血の臭いに浮かされて気を狂わせていたのかもしれない。
男は大量の氷の矢を作り出し、撃ち放ってきた。恐怖心と焦燥感からか、何本かは的外れな方向へ飛んでいる。我が身へ迫る矢を、俺は水の壁で難なく防ぎ――
小さな悲鳴が後方から鳴った。
「あ?」
今の声はなんだと間抜けな顔をして、ふと可能性に思い当たる。途端に全身に沸いた震えを抑えて、後ろを振り向く。そこにはベルがいた。彼女は倒れていた。胸元に、氷の矢を突き立てて。
なんてことはない。おそらく、ベルはそこから俺の様子を覗いていたのだろう。だが、そこへ……たまたまさっきの矢が飛んでいき、彼女の息の根を止めたのだ。
不幸な少女だ。そう、あまりにも。
皮肉としか言いようのない現実に、俺は乾いた笑みを漏らした。と、その時、背後から殺気を感じた。反射的に、俺は横に跳んだ。
ひゅんと音が間近で鳴る。
危なかった。一歩遅ければ、俺も今の氷の矢の餌食に――
なんてことはない。おそらく、ベルはそこから俺の様子を覗いていたのだろう。だが、そこへ……たまたまさっきの矢が飛んでいき、彼女の息の根を止めたのだ。
不幸な少女だ。そう、あまりにも。
皮肉としか言いようのない現実に、俺は乾いた笑みを漏らした。と、その時、背後から殺気を感じた。反射的に、俺は横に跳んだ。
ひゅんと音が間近で鳴る。
危なかった。一歩遅ければ、俺も今の氷の矢の餌食に――
「ぐああああぁぁぁぁッ!」
俺は激痛に叫んだ。避けられてなどいなかったのだ。この阿呆が、と己を罵りたくなった。
目前に、ブロンドの髪の毛と肉片が散っていた。俺の左耳は完全に削がれていた。吐き気を堪えつつ、癒しの魔法でなんとか処置をする。
すぐに、三度目の氷の矢が飛んできた。そう何度もやられてたまるかってんだよ! 俺は怒りと痛みを魔力に変えて、水の鞭で矢を払った。そして、そのまま水を氷へと変えて、鋭利な氷の槍を投擲する。男は風でそれを吹き飛ばそうとするが、あまりに微力すぎた。男は絶望の表情を浮かべ、そして腹を巨大な穂先に貫かれて、即死した。
目前に、ブロンドの髪の毛と肉片が散っていた。俺の左耳は完全に削がれていた。吐き気を堪えつつ、癒しの魔法でなんとか処置をする。
すぐに、三度目の氷の矢が飛んできた。そう何度もやられてたまるかってんだよ! 俺は怒りと痛みを魔力に変えて、水の鞭で矢を払った。そして、そのまま水を氷へと変えて、鋭利な氷の槍を投擲する。男は風でそれを吹き飛ばそうとするが、あまりに微力すぎた。男は絶望の表情を浮かべ、そして腹を巨大な穂先に貫かれて、即死した。
……終わった。
「ああ、くそ、痛い」
呟き、ふたたび癒しの魔法を左耳があった部分にかけるが、じんじんと熱く痛みつづける。応急処置でなんとかなる傷ではなさそうだ。あとで、しっかり水魔法の治療を試みなければなるまい。
苦痛と疲労に耐えながら、俺はふらふらと荷馬車へ向かった。そして、垂れ幕を開けると、隅っこで積み荷に紛れて、シェリーがぶるぶると震えていた。
苦痛と疲労に耐えながら、俺はふらふらと荷馬車へ向かった。そして、垂れ幕を開けると、隅っこで積み荷に紛れて、シェリーがぶるぶると震えていた。
「シェリー」
レビテーションで荷台に上がりながら、俺は彼女に呼びかけた。そこで初めて気づいたかのように、びくりと、シェリーは俺に顔を向ける。そして――表情が恐怖の色に染まった。
「シェリー」
もう一度呼びかけて、そばに近寄って――
「いや、来ないで!」
俺は突き飛ばされた。荷台の壁に頭を打ち付ける。その衝撃で、左耳部分の傷から血が流れ出す。ちくしょう、いてぇなぁ。早く治さないとやばそうだ。
そんなことをぼんやりと思いながら、シェリーのほうを見やる。馬車を出た彼女は、ベルの死体に気づいたようで、また悲鳴を上げた。そして、全てから逃げ出すように、街道を走って去っていく。
どうしようか。俺は迷った。連れ戻して、俺に同行させるべきなのだろうか。でも、きっと、こんな血塗れの殺人鬼と一緒に居たくないのだろう。
そんなことをぼんやりと思いながら、シェリーのほうを見やる。馬車を出た彼女は、ベルの死体に気づいたようで、また悲鳴を上げた。そして、全てから逃げ出すように、街道を走って去っていく。
どうしようか。俺は迷った。連れ戻して、俺に同行させるべきなのだろうか。でも、きっと、こんな血塗れの殺人鬼と一緒に居たくないのだろう。
結局、俺はシェリーを追わなかった。というか、追う気力と体力が残っていなかった。魔法で精神力を消費したうえ、傷もひどい。休息と治療をしなければ、自分の命が危なかった。
その後、二台の馬車の積み荷を漁って、俺は柔らかい布を手に入れた。それを傷口に巻き、慎重に癒しの魔法を使い、なんとか止血する。そこで眠りに落ちそうになったが、なんとか睡魔に耐えて、馬車の外に出る。
その後、二台の馬車の積み荷を漁って、俺は柔らかい布を手に入れた。それを傷口に巻き、慎重に癒しの魔法を使い、なんとか止血する。そこで眠りに落ちそうになったが、なんとか睡魔に耐えて、馬車の外に出る。
「……ベル」
死んだベルを見下ろして、俺は彼女の名前を呟いた。馬車の外に出てきてしまったのは、俺が心配だったからなのだろうか。……俺が注意していれば、彼女の危機に気づけたかもしれないのに。
ベルの胸元には、大きな穴が開いていた。氷の矢は、すでに融けて水になっている。俺は彼女についた水を払うと、その遺体をレビテーションで持ち上げた。そのまま、街道から少し外れて、大きな木の下へ持っていく。
ベルの胸元には、大きな穴が開いていた。氷の矢は、すでに融けて水になっている。俺は彼女についた水を払うと、その遺体をレビテーションで持ち上げた。そのまま、街道から少し外れて、大きな木の下へ持っていく。
「よし、やるか」
休息を訴える体に鞭を打ち、念力の魔法で地面の土を掘る。それほど土質は硬くないが、今の状態ではひどくつらい作業だ。だが、せめてこれだけは、済ませなくてはならない。
ひたすら土を掘り起こし、そしてやっと満足のいく穴の大きさになったのは、小一時間経ってからだった。
ひたすら土を掘り起こし、そしてやっと満足のいく穴の大きさになったのは、小一時間経ってからだった。
「……ベル、ごめん」
謝って、何になるのだろうか。自嘲しながら、彼女をレビテーションで動かして、穴の中へ置く。それから、ふたたび土を穴へ戻す。その作業は十分くらいで終わった。これで埋葬はできた。本当に、簡易なもので申し訳ないけれども。
『きみの来世が幸福でありますように』
俺の本当の母国語である、日本語で呟く。
だが、来世なんて本当に存在するのだろうか。そう疑問を抱かざるを得ない。自分には前世の記憶があるが、誰も彼もがそういうわけではないはずだ。あるいは、もしかしたら、神様が偶然か気まぐれで俺を選んだのだろうか。だとしたら、その神とやらをぶっ殺してやりたいものだ。
だが、来世なんて本当に存在するのだろうか。そう疑問を抱かざるを得ない。自分には前世の記憶があるが、誰も彼もがそういうわけではないはずだ。あるいは、もしかしたら、神様が偶然か気まぐれで俺を選んだのだろうか。だとしたら、その神とやらをぶっ殺してやりたいものだ。
そんなことを考えながら、俺は馬車に戻った。
だが、体が限界だった。頭痛と目眩が激しい。足もふらつきやがる。もう、ダメだ。
だが、体が限界だった。頭痛と目眩が激しい。足もふらつきやがる。もう、ダメだ。
かろうじて近くの毛布に倒れ込んだ俺は――そこで意識を失った。