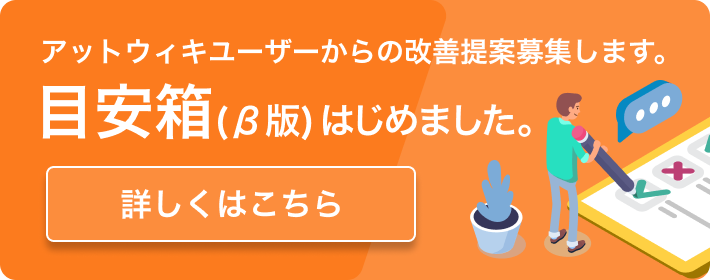身売りされた貴族のお話 03
翌日。
俺はヘレンと一緒に外出していた。朝食を終えて暇を持て余していたところ、「お前も来るか?」とヘレンに誘われたからだ。ずっと室内に閉じこもっているのもいかがなものかと思っていたので、俺はとくに迷わず頷いたのだった。
俺はヘレンと一緒に外出していた。朝食を終えて暇を持て余していたところ、「お前も来るか?」とヘレンに誘われたからだ。ずっと室内に閉じこもっているのもいかがなものかと思っていたので、俺はとくに迷わず頷いたのだった。
宿屋を出てから十数分後、裏通りを歩いて着いたのは、魔法関連の品を扱う店だった。だが、看板は薄汚れて目立たないし、商売のやる気が感じられない。本当にここが目的地で合っているのだろうか、と疑念を抱いてヘレンを見上げたが、彼女はよどみない足取りで店に入っていく。慌てて、俺も彼女に追従してドアをくぐった。
薄暗い。
それが最初の感想だった。日の高い時間であるというのに、窓はどれもカーテンで遮られている。そのうえ、魔法照明も弱々しいものしか設置されていない。普通の店では、ありえない内装だろう。
だが、こと魔法道具や秘薬を扱う店としては、めずらしいものではない。というのも、一部の秘薬などは日光によって効能が変化してしまうことがあるからだ。あるいは、魔法関係の貴重な書物なども置いている店では、日焼けなどの劣化を防ぐ目的もある。いずれにしても、こういう魔法店は見てくれより中身を重視する傾向にあるので、外観はちょっと尻込みしてしまうようなところが多い。……らしい。道中でヘレンから聞いた蘊蓄だった。
それが最初の感想だった。日の高い時間であるというのに、窓はどれもカーテンで遮られている。そのうえ、魔法照明も弱々しいものしか設置されていない。普通の店では、ありえない内装だろう。
だが、こと魔法道具や秘薬を扱う店としては、めずらしいものではない。というのも、一部の秘薬などは日光によって効能が変化してしまうことがあるからだ。あるいは、魔法関係の貴重な書物なども置いている店では、日焼けなどの劣化を防ぐ目的もある。いずれにしても、こういう魔法店は見てくれより中身を重視する傾向にあるので、外観はちょっと尻込みしてしまうようなところが多い。……らしい。道中でヘレンから聞いた蘊蓄だった。
店の奥のカウンターには、初老の男性が座っていた。どうやら読書をしているようだ。……この薄暗い中で? と思ったら、その目に魔力が宿っていることを、俺はわずかながらに感じ取れた。おそらく“暗視”の魔法でも使って、無理やり文字を読めるようにしているのだろう。たいした根性である。
「商品の説明が欲しかったら、聞け」
本から少しも目を話さずに、男性は言葉を発した。感情が込められていない、機械的な声色だった。
……こんな営業スタイルで大丈夫なのだろうか。いや、大丈夫だからこそ、こんな感じなのだろうか。魔法を使っているところを見ると、彼は引退した貴族といった風情だ。もしかしたら、この店は趣味でやっているのかもしれない。
……こんな営業スタイルで大丈夫なのだろうか。いや、大丈夫だからこそ、こんな感じなのだろうか。魔法を使っているところを見ると、彼は引退した貴族といった風情だ。もしかしたら、この店は趣味でやっているのかもしれない。
ヘレンとは別に、俺も適当に店内の商品を見て回る。といっても、身長が低いので棚の最下段しか覗けないが。
ふと、気になるものを見つけて、俺は足を止めた。その棚には、瓶がいくつも置かれていた。その中には、水のような液体が入れられている。
俺は瓶の一つに手を触れてみた。魔力をさやかに感じる。これは……そうか。“癒し”の魔法を込めた水を、瓶に詰めているのだろう。もちろん高価な水の秘薬ほどの効力はないが、これでも些細な傷ならば簡単に治癒させることができるはずだ。
こうしたものは、どちらかといえば魔法の使えない平民向けの治療薬だ。傷や病を治すことのできる水魔法は、日常生活上の需要が非常に高い。このような簡易な“癒しの水 ”でも、それなりの値段で売ることができるだろう。
ふと、気になるものを見つけて、俺は足を止めた。その棚には、瓶がいくつも置かれていた。その中には、水のような液体が入れられている。
俺は瓶の一つに手を触れてみた。魔力をさやかに感じる。これは……そうか。“癒し”の魔法を込めた水を、瓶に詰めているのだろう。もちろん高価な水の秘薬ほどの効力はないが、これでも些細な傷ならば簡単に治癒させることができるはずだ。
こうしたものは、どちらかといえば魔法の使えない平民向けの治療薬だ。傷や病を治すことのできる水魔法は、日常生活上の需要が非常に高い。このような簡易な“
もし独力で生きていかなければならなくなったら、どうするのか。そう考えたとき真っ先に上がる候補は、己の魔法を売っていくということだった。たとえ専門的な知識がなくとも、トライアングルクラスの癒しの魔法があれば、そこらの平民よりもよっぽど裕福に暮らせるだろう。
だからこそ。
もしも、あの時。三人で無事に逃げられていたら。俺はそうして彼女たちに人並み以上の生活をさせてやれたかもしれない。
だからこそ。
もしも、あの時。三人で無事に逃げられていたら。俺はそうして彼女たちに人並み以上の生活をさせてやれたかもしれない。
……過ぎたことだ。これ以上、考えるな。俺はそう自分に命令して、意識を戻した。
それから俺は、怪しげな魔道書やら、籠や瓶に入った奇妙な生物やらを、適当に見物していた。しばらくすると、買い物を済ませたヘレンが戻ってくる。どうやら、目当てのものは手に入れられたようだ。彼女と一緒に店を出る。
「私の用事は済んだが、どうする?」
ヘレンが聞いてきた。どうする、とはどういうことだろうか。俺が首をかしげて言葉を探していると、
「……お前がいやでないのであれば、街を歩き回ってもかまわん」
ああ、なるほど。きっと、俺のことを気遣ってくれているのだろう。
ここで断るのは気後れするし、それに、まだ外にいたいという気持ちも強かった。だから、お願いします、と頭を下げて頼む。
ここで断るのは気後れするし、それに、まだ外にいたいという気持ちも強かった。だから、お願いします、と頭を下げて頼む。
「では、行こうか」
ヘレンは足取りを、街の中央のほうへ向けた。俺も彼女についていく。
当たり前の話だが、歩幅はこちらのほうが断然小さい。だから、ヘレンも俺に合わせてゆっくりと歩いてくれる。それをありがたく思うのと同時に、つくづく手間のかかる自分の身体に辟易しそうになる。
当たり前の話だが、歩幅はこちらのほうが断然小さい。だから、ヘレンも俺に合わせてゆっくりと歩いてくれる。それをありがたく思うのと同時に、つくづく手間のかかる自分の身体に辟易しそうになる。
遅々とした歩みを続けて、しばらくすると大通りに出た。やはり、人が多い。こうして通りで雑踏を目前にすると、なおさらそれを実感した。
圧倒されて棒立ちしていた俺だったが、ヘレンがふたたび歩き出したのを見て、慌ててあとを追う。だが、田舎者の性には抗えないようだ。自然と、目線と意識が周囲の店や通行人たちに向いてしまう。
そして、それは不注意という形となった。前から来た男に、ぶつかってしまったのだ。相手のがたいは普通であったが、やはりこちらの体躯が小さいということもあって、俺はバランスを崩して尻餅をついてしまった。
圧倒されて棒立ちしていた俺だったが、ヘレンがふたたび歩き出したのを見て、慌ててあとを追う。だが、田舎者の性には抗えないようだ。自然と、目線と意識が周囲の店や通行人たちに向いてしまう。
そして、それは不注意という形となった。前から来た男に、ぶつかってしまったのだ。相手のがたいは普通であったが、やはりこちらの体躯が小さいということもあって、俺はバランスを崩して尻餅をついてしまった。
無様なものだ。
溜息をついて、立ち上がる。
溜息をついて、立ち上がる。
と、その時。俺の手が掴まれた。見上げると……ヘレンだった。
「気をつけろ」
「……はい」
「……はい」
その手をしっかりと握り返して、返事をする。人ごみの間を、俺とヘレンはそうやって手をつないで歩く。
ふと、思う。この様子は、周りの人間からどう見えているのだろうか。
一番に浮かんだのは、「親子」という単語だった。はっ、と血迷った考えを笑い飛ばしたくなる。傭兵然とした女メイジと、生気のないクソガキという取り合わせで親子など、滑稽極まりない。
ふと、思う。この様子は、周りの人間からどう見えているのだろうか。
一番に浮かんだのは、「親子」という単語だった。はっ、と血迷った考えを笑い飛ばしたくなる。傭兵然とした女メイジと、生気のないクソガキという取り合わせで親子など、滑稽極まりない。
……だが。
そう思われたとしても、悪くはない。
この手の暖かさを感じながら、俺は不覚にもそんなことを抱懐してしまった。
そう思われたとしても、悪くはない。
この手の暖かさを感じながら、俺は不覚にもそんなことを抱懐してしまった。
◇
都市観光を終えて、宿屋に戻ったのは、昼を過ぎたあたりの時刻だった。そこで遅めの昼食を取ってから、ふたたび所用で外出するヘレンと別れることになった。ちなみにチャーリーやほかの傭兵たちも、宿屋の中にはいない。おそらく、積み荷などを街の商人に買い取ってもらえるよう、交渉しにいっているのだろう。その具体的な手順だとかについては、都市生活や商売に関してはめっぽう知識と経験が浅いため、俺では推測しかねるが。
そんなわけで、残されたのは俺ひとりというわけだ。
……暇。
まさに現状を表す言葉が、それだった。ポートランドの領地にいたときは、手持ち無沙汰な時間をほとんど魔法の練習に充てていたが、この街中ではそれも不可能だろう。
まさに現状を表す言葉が、それだった。ポートランドの領地にいたときは、手持ち無沙汰な時間をほとんど魔法の練習に充てていたが、この街中ではそれも不可能だろう。
俺は嘆息した。こうしていても仕方がない。また外に出て、散歩でもしていたほうが健康的というものである。
サウスゴータの街なりなんざまるで知らないが、この宿屋の周辺を出歩く程度なら迷うこともないだろう。それに、いざとなったら飛行 の魔法でも使って飛んで帰ればよい。
サウスゴータの街なりなんざまるで知らないが、この宿屋の周辺を出歩く程度なら迷うこともないだろう。それに、いざとなったら
そう考えて、部屋を出ようとドアを開けたところで、彼と鉢合わせした。
「……あ、その……」
必要以上に動揺している様子を見ると、むしろこの部屋が目当てだったのかもしれない。彼のドアをノックする決心がつく前に、俺がさっさと出てきてしまった、といったところだろうか。
「モーリス」
相手が話を切り出すのを待つというのも、ちょっと気の毒だろう。そんなわけで、俺から聞いてみることにした。
「一緒に、遊ぶ?」
「……う、うん!」
「……う、うん!」
子供らしく、モーリスは元気に頷いた。
こちらとしても、ありがたいことだ。少なくとも、ひとりで当てのない散歩などというものよりは、よほど建設的といえるだろう。
こちらとしても、ありがたいことだ。少なくとも、ひとりで当てのない散歩などというものよりは、よほど建設的といえるだろう。
そして、その後は夕暮れまで、昨日と同じようにモーリスと遊ぶことになった。たかがトランプで、しかも二人遊びというものでも、俺は時間を忘れるほど楽しめた。存外、娯楽の少ない世界の生活に馴染みすぎていたのかもしれない。
お店の手伝いに戻らなきゃ、というモーリスと別れて、ふたたび部屋には静寂が訪れた。それは、俺にすることがなくなったことも表している。この時間でいまさら散歩に出かけるというのも、おかしなものだろう。ヘレンは日暮れごろに戻ると言っていたから、そろそろ帰ってくるはずだが……。
お店の手伝いに戻らなきゃ、というモーリスと別れて、ふたたび部屋には静寂が訪れた。それは、俺にすることがなくなったことも表している。この時間でいまさら散歩に出かけるというのも、おかしなものだろう。ヘレンは日暮れごろに戻ると言っていたから、そろそろ帰ってくるはずだが……。
そう思っていた瞬間だった。
乱雑にドアを開けられる音が響いた。びくりと振り向くと、そこにはヘレンが立っていた。息が少し荒く、その表情には焦燥が浮かんでいた。
――彼女らしくない様子だ。何か緊急の事態か、と俺は体を強張らせた。
乱雑にドアを開けられる音が響いた。びくりと振り向くと、そこにはヘレンが立っていた。息が少し荒く、その表情には焦燥が浮かんでいた。
――彼女らしくない様子だ。何か緊急の事態か、と俺は体を強張らせた。
しかし……どうも、状況は違ったようだ。ヘレンは俺を見て、一瞬ながら顔色を安堵に変化させた。つまり、俺の身に何か起こったのではないか、と考えて彼女は駆けつけてきたのか。しかし、そんな心配をさせるような心当たりは、俺にはなかった。
驚きと訝しみが混ざり合った状態の俺に、ヘレンが声をかける。
驚きと訝しみが混ざり合った状態の俺に、ヘレンが声をかける。
「アシュリー」
場を改めるように、呼吸を落ちつけてから、ヘレンは俺の前に近寄った。そして、目線を合わせるためにしゃがんで、俺の肩をしっかりと掴む。
「よく聞け。……この街で、お前を探している人間がいるようだ。お前の身の売買に関わっていた人間かもしれん。すまないが、明日から外に出ないようにしてもらえないか」
なんだと? 俺は目を瞬かせた。
たしかに、俺は大事な商品だったのかもしれない。だが、そこまでしてこだわるほどの存在なのか。自分の価値がそれほどあるとは思えないだけに、納得しがたいものがある。
動揺している俺に、「わかったか」とヘレンが念を押す。……ここで首を横に振っても、意味はない。わかりました、と現状の理解度に反する言葉を口にして、俺はぎこちなく頷いた。
たしかに、俺は大事な商品だったのかもしれない。だが、そこまでしてこだわるほどの存在なのか。自分の価値がそれほどあるとは思えないだけに、納得しがたいものがある。
動揺している俺に、「わかったか」とヘレンが念を押す。……ここで首を横に振っても、意味はない。わかりました、と現状の理解度に反する言葉を口にして、俺はぎこちなく頷いた。
その夜、俺は夕食を済ませると、すぐに自室へ戻った。ヘレンは、またチャーリーの部屋で何かを話しているようだ。十中八九、俺に関することだろう。
――どうして、そんなにこだわるんだ?
昨日の、チャーリーの声を思い出す。あれはヘレンに向けた言葉だった。そう……たしかに、改めて疑念が湧く。
俺が何者かから狙われているとわかったいま、たとえ水魔法を多少使えるとはいえ、わざわざ身内に置いておくほどのメリットはないのではないか。しかも、ヘレンたちは傭兵団なのだ。その職業柄、みずからが被るリスクに関しては、誰よりも鋭敏なはずだ。なのに……“どうして、そんなにこだわるんだ?”
俺が何者かから狙われているとわかったいま、たとえ水魔法を多少使えるとはいえ、わざわざ身内に置いておくほどのメリットはないのではないか。しかも、ヘレンたちは傭兵団なのだ。その職業柄、みずからが被るリスクに関しては、誰よりも鋭敏なはずだ。なのに……“どうして、そんなにこだわるんだ?”
わからない。もどかしさに、拳を握り締める。
ここ何年、碌に人間と関わっていなかった弊害か、俺にはひとの心理や行動を分析する能力が、ごっそりと抜け落ちてしまったようだ。それらを犠牲にして得たものは、自己満足でしかない魔法の技能くらいなものか。等価交換にはほど遠いな、と俺は嗤いたくなった。
ここ何年、碌に人間と関わっていなかった弊害か、俺にはひとの心理や行動を分析する能力が、ごっそりと抜け落ちてしまったようだ。それらを犠牲にして得たものは、自己満足でしかない魔法の技能くらいなものか。等価交換にはほど遠いな、と俺は嗤いたくなった。
……寝よう。
ぼそりとそう呟いて、俺はベッドに倒れ込んだ。働かない頭脳で考えつづけても仕方ない。それに、抑えがたい眠気が体を蝕みはじめている。子供というものは、成人よりも多量の睡眠を必要とするのだ。
まったくもって不便な身体を嘆きながら、俺は静かに眠りに落ちた。
ぼそりとそう呟いて、俺はベッドに倒れ込んだ。働かない頭脳で考えつづけても仕方ない。それに、抑えがたい眠気が体を蝕みはじめている。子供というものは、成人よりも多量の睡眠を必要とするのだ。
まったくもって不便な身体を嘆きながら、俺は静かに眠りに落ちた。
◇
翌朝、朝食後。
室内で、左耳に癒しの魔法をかけおえて、一息つく。傷の痛みも、ほとんどなくなってきた。これに関しては、もう心配することもないだろう。
室内で、左耳に癒しの魔法をかけおえて、一息つく。傷の痛みも、ほとんどなくなってきた。これに関しては、もう心配することもないだろう。
それよりも。
注意すべきは、己の置かれた立場だ。もしかしたら、一歩踏み外せば崖下に転落するような立ち位置なのかもしれない。だが……めくらの俺には、周囲が暗闇だった。どこへ歩けばよいのかもわからず、立ち往生しているだけだ。我ながら、様がなさすぎて情けなくなる。
しかし、だからといって、闇雲に足を踏み出すのも無謀というものだ。そう、目が見えぬのであれば……誰かの手を借りればよい。
少なくとも、これまでの様子からして、ヘレンが俺に害意を持っているということはない。むしろ、過剰なまでに厚意を持っているように思えてならない。それに甘えるようで悪いが、俺に分別がつかぬ以上、当分は彼女の指示に従っていたほうが安全なのかもしれない。
しかし、だからといって、闇雲に足を踏み出すのも無謀というものだ。そう、目が見えぬのであれば……誰かの手を借りればよい。
少なくとも、これまでの様子からして、ヘレンが俺に害意を持っているということはない。むしろ、過剰なまでに厚意を持っているように思えてならない。それに甘えるようで悪いが、俺に分別がつかぬ以上、当分は彼女の指示に従っていたほうが安全なのかもしれない。
――などと思考するが、結局は他人任せということだ。言い訳がましい己に嘆息しながら、窓の外を眺める。雲一つない快晴だったが、俺の心中は晴れないままだった。
その時、トントンとドアをノックする音がした。反射的に、俺は座っていた椅子から飛び降りた。そして、そんな自分の様子に気づいて、苦い表情を浮かべる。まるで子供のような反応だ。だが然り、俺はまさにガキなのだろう。
「……モーリス」
俺は表情を苦笑に変えて、彼を出迎えた。だが、やはり表情を繕いきれていなかったのか、「アシュリー、どうしたの……?」とモーリスが尋ねてくる。
無理をしてもぼろが出るだけだ、と諦めた俺は、作った笑みを消して口を開いた。
無理をしてもぼろが出るだけだ、と諦めた俺は、作った笑みを消して口を開いた。
「モーリス。一緒に、遊んでくれる?」
「……うん、もちろん!」
「……うん、もちろん!」
俺を元気づけるかのように、モーリスは満面の笑みを浮かべた。最初の時とはまるで逆だな、となんとない感想を抱く。やはり人との関係性を欲しているのは、俺がいちばん強いのかもしれない。
それから昼時まで、俺はモーリスとカード遊びをした。初日では手加減しても俺が勝ち越していたのだが、モーリスもだんだんとルールや戦略を理解しはじめてきたのか、いくつかのルールでは負け越しそうになる場合もあった。この調子でいけば、明日や明後日には本気でやってもいい勝負になるかもしれない。
そんなふうに密かな期待をしながら、二人で階段を下りる。一階の酒場に着くと、店の手伝いをしなくてはならないというモーリスに、「またね」と手を振って別れた。
そんなふうに密かな期待をしながら、二人で階段を下りる。一階の酒場に着くと、店の手伝いをしなくてはならないというモーリスに、「またね」と手を振って別れた。
そして、改めて店内を見回す。
まだ客入りの少ない時間帯なので、その人影を見つけるのは容易だった。――隅のほうのテーブル席に、見知った顔の男が二人。今朝、ヘレンから「お前たちは宿に残っていろ」と言われていた傭兵団のメンバーである。おそらく、俺の目付け役ということなのだろう。
まだ客入りの少ない時間帯なので、その人影を見つけるのは容易だった。――隅のほうのテーブル席に、見知った顔の男が二人。今朝、ヘレンから「お前たちは宿に残っていろ」と言われていた傭兵団のメンバーである。おそらく、俺の目付け役ということなのだろう。
無駄に心配させても悪いか。そう思い、俺はあいさつをしようと、男たちの席の近くまで歩み寄る。そして、彼らが行なっていることにようやく気づく。……どうやら、酒を飲みながら将棋 をしているようだ。しかも将棋盤のそばに金貨が積まれているところを見ると、賭けで勝負をしているものと思われる。なんというか、昼間からよくやるものだ。まあモーリスと室内で遊んでばかりの俺も、人のことを言える身分ではないが。
若干の呆れを抱きながらそばに近づくと、ようやく彼らも俺の存在に気づいたようだ。こんにちは、とテーブルの下から顔を覗かせた俺に、男たちは慌てたようにあいさつを返す。この様子を見ると、俺の存在などとうに忘却していたのではなかろうか。そんなことで大丈夫なのかと、こっちが心配してしまうくらいだった。
さて、あいさつも済ませた俺は、彼らのすぐ隣のテーブルに座って昼食を取ることにした。基本的な食事は、傭兵団が受け持ってくれている宿代に含まれているので、給仕に言えばすぐに出してもらうことができた。
食事内容はというと、パンとコンソメ、それに塩をかけた蒸かし芋というシンプルな品目だった。味は悪くなかったが……やはり、小食なだけに食べきるのに時間がかかった。こればっかりは、成長しないとどうにもならないことだが。
食事内容はというと、パンとコンソメ、それに塩をかけた蒸かし芋というシンプルな品目だった。味は悪くなかったが……やはり、小食なだけに食べきるのに時間がかかった。こればっかりは、成長しないとどうにもならないことだが。
「――アシュリー」
満腹になって一息ついていると、聞き慣れた声で名前を呼ばれた。そちらへ目を向けると、やはり彼――モーリスがいた。盆を抱えているところを見ると、食器を回収しにきたのだろう。
「お皿、持っていくね」
「うん、ありがとう」
「うん、ありがとう」
まだ小さいのに、偉いものだ。……いや。何を言っているのだ、俺は。これが普通なのだ。平民が生活をしていくためには、こうして仕事をこなさなくてはならないのだ。怠惰にしていても裕福に暮らせるのは、領地持ちの貴族くらいだろう。
自分の世間知らずを実感して、思わず歯噛みをする。幸いにもモーリスには気づかれなかったようで、彼は「じゃあね」と重そうに盆を持って、戻ろうとする。
自分の世間知らずを実感して、思わず歯噛みをする。幸いにもモーリスには気づかれなかったようで、彼は「じゃあね」と重そうに盆を持って、戻ろうとする。
うん、またあとで。
そう口を開こうとした時だった。
そう口を開こうとした時だった。
――腕を掴まれた。
「ポートランド伯爵家のアシュリーか」
問いかけというよりは、ほぼ確信した言い方だった。完全にばれている――そう理解した俺は、まだ自由な右腕を使って、ポケットから杖を取り出した。だが、ルーンを唱えて魔法を行使しようとした瞬間、男に手首を握られて杖を手放してしまう。
……こうなってしまったら、拘束を抜け出す術がない。なんたる不甲斐なさだ、くそ!
……こうなってしまったら、拘束を抜け出す術がない。なんたる不甲斐なさだ、くそ!
「なにしてやがる、てめえ!」
隣の席にいた傭兵団の二人も反応して、立ち上がる。その手はすでに剣の柄にかけられていた。この近距離なら、仮に男がメイジだとしても、傭兵たちの一太刀のほうが速いはずだ。相手はどうするつもりだ……?
――そう思ったのも束の間だった。
俺の腕を掴んでいる男が、不敵な笑みを浮かべた瞬間、傭兵たちが風の槌を食らって壁に打ちつけられた。うめき声を上げてはいるが、今の衝撃ではしばらく立ち上がることができないだろう。
俺の腕を掴んでいる男が、不敵な笑みを浮かべた瞬間、傭兵たちが風の槌を食らって壁に打ちつけられた。うめき声を上げてはいるが、今の衝撃ではしばらく立ち上がることができないだろう。
……俺の目前の男は、杖を振るっていない。魔法を放ったのは、別の人間だった。少し離れた位置に立っているコートを着た人物、そいつは杖を手にしていた。この男の仲間なのだろう。
もはや、抵抗も無駄だ。そう諦めた時だった。男たちに怒鳴る声が響いた。
もはや、抵抗も無駄だ。そう諦めた時だった。男たちに怒鳴る声が響いた。
「アシュリーを放せ!」
モーリスだった。彼は、俺を取り押さえている男の腕に掴みかかった。
――やめろ、バカ!
そう叫ぶ前に、男はもう動いていた。うざったい蝿を退けるような動作。だが、力の込められたその振り払いは、子供の体躯であるモーリスをいともたやすく吹き飛ばした。
がん、と強く殴打する音。背後にあったテーブルに頭をぶつけたモーリスが、力なく頽れる。
がん、と強く殴打する音。背後にあったテーブルに頭をぶつけたモーリスが、力なく頽れる。
俺は顔を青くした。もし打ち所が悪ければ、取り返しのつかないことになるかもしれない。……気休め程度でもいいから、せめて、俺の癒しの魔法さえかけられれば!
「放せぇッ!」
自分でも想像しないほどの大声で叫び、必死にもがく。しかし、その程度では屈強な男の手を開かせるには至らない。焦燥が頂点に達した俺は、ある行動に出た。
それは、男の腕を噛むことだった。獣のように、肉を食いちぎる気概で顎に力を込める。さすがに効果があったようで、男は悲鳴を上げると噛まれた腕を乱雑に振り上げた。
「ぐぁっ……」
口内に痛みが走る。その衝撃で前歯が何本か折れたようだ。だが……拘束は抜け出せた! 動くなら今しかない!
痛みと血の味に気分が悪くなりながらも、なりふりかまわず床に落ちている杖に飛び付く。そして血塗れの口で、癒しの魔法のルーンを唱える。
痛みと血の味に気分が悪くなりながらも、なりふりかまわず床に落ちている杖に飛び付く。そして血塗れの口で、癒しの魔法のルーンを唱える。
――スペルを完成させ、杖を振る直前。
視界が濃霧に覆われた。
これは……。
そうか、眠りの雲か。もう片方のメイジが魔法を使ったのだろう。
そうか、眠りの雲か。もう片方のメイジが魔法を使ったのだろう。
眠気が押し寄せ、感覚が薄れる。ダメだ、気を保て! せめて一度だけでも、モーリスに癒しの魔法を……!
腕に力を込める。
だが……所詮は、非力なガキだったのだ、俺は。
だが……所詮は、非力なガキだったのだ、俺は。
最後の杖の一振りすら叶わず――俺は意識を失った。