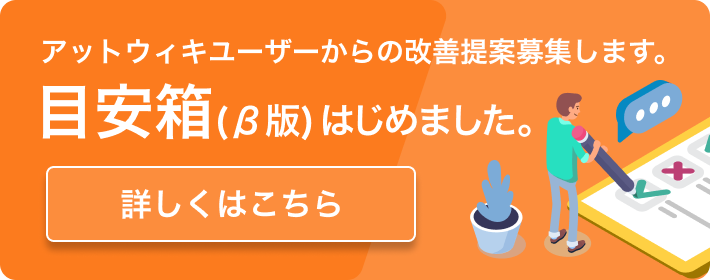身売りされた貴族のお話 02
目を覚ますと、薄汚れた馬車の中だった。
またか、と俺は呟きそうになった。この馬車は、俺が最後に倒れたところとは別物だった。
つまり、俺は何者かに拾われたのだろう。相手が悪い人間でなければよいが。そんなことを思いながら、身を起こした時、ちょうどその人が姿を現した。
つまり、俺は何者かに拾われたのだろう。相手が悪い人間でなければよいが。そんなことを思いながら、身を起こした時、ちょうどその人が姿を現した。
「起きたようだな」
赤茶けた短髪の女性だった。歳は三十過ぎといったところだろうか。この鋭い眼光と、警戒した佇まいは、ただの商人ではないだろう。傭兵か、何かか。
「ここは?」
「サウスゴータの街の近くだ。街道の途中でお前を拾ったのだが……何があった?」
「サウスゴータの街の近くだ。街道の途中でお前を拾ったのだが……何があった?」
少し考えてから、俺は答えた。
「……覚えて、いない」
あの男どもを俺が殺したと、どうして言えようか。体のよい嘘をつくのも諦めて、俺はそう答えた。
女性はしばらく、俺をじっと見つめていたが――
女性はしばらく、俺をじっと見つめていたが――
「ふん、そうか。……少し、待っていろ」
そう言って、いったん姿を消した。
その隙に、俺はポケットのものを確認した。大丈夫だ。杖はなくなっていない。
少なくとも、あの女性には今すぐ俺をどうこうしようという意思はなさそうだ。ひとまず様子見するが……いざというときには動けるように、心構えをしておこう。
少なくとも、あの女性には今すぐ俺をどうこうしようという意思はなさそうだ。ひとまず様子見するが……いざというときには動けるように、心構えをしておこう。
しばらくして、二十代後半と思われる男がやってきた。理知的な雰囲気の顔つきだが、体は十二分に鍛えられている。やはり傭兵の類か。
チャーリーと名乗った彼は、パンと干し肉を乗せた皿を差し出した。
チャーリーと名乗った彼は、パンと干し肉を乗せた皿を差し出した。
「余裕があったら、お食べなさい」
ついに肉が追加されたか。涙を禁じえないね。
俺は自嘲気味の笑みを浮かべながら、礼を言った。
俺は自嘲気味の笑みを浮かべながら、礼を言った。
「ところで」
俺がパンを咀嚼していると、チャーリーが聞いてきた。
「きみは貴族の子かな?」
その目線は、俺のポケットに向けられているようにも思える。杖の存在に気づいているのか。あるいは、俺も考えすぎかもしれないが……こんな状況では、下手に嘘を重ねると不利になりかねない。
はい、と俺は素直に答えた。
はい、と俺は素直に答えた。
「ふむ。となると、賊か何かに攫われてきたのかな?」
「い、いえ……違います」
「い、いえ……違います」
俺は慌てて答えた。攫われた、と認識されてしまうと、では子供を家に戻してやろう、という善人的な行為に走られる可能性もなきにしもあらずだった。誰があそこに戻るものか。そう思い、俺は真実の一部を伝えた。
「私は、売られたのです」
「なに?」
「なに?」
チャーリーは予想外だと言うように眉をひそめた。
「それ、本当かい?」
「はい」
「……きみの両親が、きみを売ると決めたのかい?」
「そうです」
「……ふむ、なるほど」
「はい」
「……きみの両親が、きみを売ると決めたのかい?」
「そうです」
「……ふむ、なるほど」
チャーリーは口に手を当てて、考え込むような仕草をした。そして小さく「下級貴族あたりか……?」と呟くのを、俺は聞き逃さなかった。なんにしても、誤解してくれたのならありがたいものだ。
そのほか、いくつかの問答を乗り越えたのち、ようやく俺は質問攻めから解放された。結局、身売りされた貴族の子供を連れた商人たちが、何者かに襲撃されて壊滅し、子供だけが生き残った、と解釈されたようだった。仔細については、俺は気絶していて何も知らないと突き通した。俺の見てくれがガキだったおかげか、それ以上は深く追及されなかった。
そのほか、いくつかの問答を乗り越えたのち、ようやく俺は質問攻めから解放された。結局、身売りされた貴族の子供を連れた商人たちが、何者かに襲撃されて壊滅し、子供だけが生き残った、と解釈されたようだった。仔細については、俺は気絶していて何も知らないと突き通した。俺の見てくれがガキだったおかげか、それ以上は深く追及されなかった。
それから俺は、チャーリーから彼ら自身のことについて話された。基本的にはやはり傭兵集団で、仕事のない平時は交易をしながら旅をしているらしい。「きみを拾ったついでに、いいものも手に入れられたよ」と笑っていたが、おそらく、あの男たちの馬車にあった積み荷を回収したのだろう。そのしたたかさに呆れたが、こうして保護されている手前、俺からは何も言えまい。
「ああ、そうだ。大事なことを忘れていた」
しまったというような顔で、チャーリーは思い出したように言った。
「きみの名前、聞いてなかったね。すまない。よければ、教えてくれないか?」
ああ、そういえば。
べつのことに考えが寄っていただけに、初歩的なことにすら気づかなかった。まったく、冷静にならないとダメだな。
べつのことに考えが寄っていただけに、初歩的なことにすら気づかなかった。まったく、冷静にならないとダメだな。
俺はせめて好印象を抱かせるように、にっこりと笑みを浮かべて答えた。
「私の名前は、アシュリー」
なぜかチャーリーがわずかに顔を強張らせたのが、印象に残った。
◇
サウスゴータの街についたその夜、俺は傭兵団と一緒に、安宿に泊まっていた。団のリーダーである、赤茶けた短髪の女性――ヘレンに「当てがないのであれば来い」と言われたからだ。まだ怪我も治っておらず、無茶もできない状態だったので、俺はありがたくこの誘いに乗ったのだった。
宿の一室は、俺とヘレンが相部屋だった。その室内で、俺は椅子に座って、ヘレンにいまだ痛む傷を診てもらっていた。
宿の一室は、俺とヘレンが相部屋だった。その室内で、俺は椅子に座って、ヘレンにいまだ痛む傷を診てもらっていた。
「外耳の大部分が抉られているが、聴覚に問題はなさそうだ」
これが風魔法だったら鼓膜までやられていたかもしれない、とヘレンは言った。風系統のメイジである彼女が言うのだから、それは正しいのだろう。だとしたら、これだけで済んだのは幸いだったのかもしれない。
それから、俺の大雑把な応急処置ではなく、消毒をしてからしっかりとした包帯を巻いてもらった。とりあえず、これで傷については、一安心と言えよう。
それから、俺の大雑把な応急処置ではなく、消毒をしてからしっかりとした包帯を巻いてもらった。とりあえず、これで傷については、一安心と言えよう。
「お前は、魔法は使えるか?」
ふと、ヘレンが俺をまっすぐ見つめながら問うた。
俺は逡巡した。トライアングルのメイジだと正直に答えれば、その異常性に妙な疑念を抱かれかねない。かといって、魔法がまったく使えないとわかれば、価値がないと判断されてすぐに厄介払いされかねない。独りでもやっていけないことはないが、今の状態ではかなりつらいだろう。
俺は逡巡した。トライアングルのメイジだと正直に答えれば、その異常性に妙な疑念を抱かれかねない。かといって、魔法がまったく使えないとわかれば、価値がないと判断されてすぐに厄介払いされかねない。独りでもやっていけないことはないが、今の状態ではかなりつらいだろう。
「……少しだけ、使えます」
妥協した答えが、それだった。ついでに、水系統の癒しの魔法を使えるということも伝えておいた。
「ふむ。ならば、暇があれば自分で傷を癒しておくといいだろう。多少は治りが早くなるはずだ」
どうやら、とくに疑われなかったようだ。俺は安堵しながら、素直に頷いた。
その後、ヘレンは「早めに寝ておけ」と俺に言って、部屋を出ていった。チャーリーやほかの仲間たちと、話をしてくるらしい。俺のことについて、何か話し合うのかもしれない。気になるとはいえ、聞き耳を立てようにも、音や気配に敏感な風メイジである彼女がいる時点で不可能だろう。
それに、やはり俺は疲労していた。所詮は体力のないガキである。休息を訴える肉体に従って、俺はベッドに潜り込んだ。
それに、やはり俺は疲労していた。所詮は体力のないガキである。休息を訴える肉体に従って、俺はベッドに潜り込んだ。
翌日。
鳥のさえずりに、俺は目を覚ました。体を起こして、まず目に入ったのは、窓際に立っているヘレンの姿だった。そして気づく。よく見ると、彼女の肩には小さな生き物がとまっていた。それは、指一本分くらいの全長しかない小鳥だった。
ヘレンは、その小鳥にパンくずをやっているようだった。
ヘレンは、その小鳥にパンくずをやっているようだった。
「こいつは、私の使い魔のモリグだ」
俺が起きて眺めているのを、察知していたのだろう。ヘレンは己の使い魔に餌を与えながら、そう言った。
使い魔。そうか、使い魔か。俺には縁がなかった存在なだけに、そういう可能性を忘れていた。
使い魔。そうか、使い魔か。俺には縁がなかった存在なだけに、そういう可能性を忘れていた。
サモン・サーヴァント――使い魔召喚の魔法は、メイジ自身が肉体的にも技能的にも、ある程度の成長をしてから行使するのがよいとされる。本人が熟練しないうちに召喚する使い魔は、やはり相応の下等な生物が呼ばれやすい傾向にあるからだ。スクウェアに至り、最終的には竜を呼んだ偉大なメイジでさえも、少年の頃は単なる蛇を使い魔にしていた、という例もある。そういうわけだから、俺にはまだ不必要な魔法だと考えて、ほとんど忘却していた。
だが、それでよかったのだろうか。
たとえば、そう。つい先日の、あの馬車から脱出する時。あそこでサモン・サーヴァントを行使して、空を翔る幻獣でも召喚できていれば、面倒事を回避してさっさと三人で逃げ果せることができていたかもしれない。あるいは、べつの使い魔でも、戦闘に参加できるような能力を持つ生物であれば、戦況と結果を変えられていたかもしれない。
いや……それだけではないはずだ。考えてみれば、あの場ではもっと適切で有用な判断があったのではないか。何も殺す必要はなかった。俺のレベルの“眠りの雲”であれば、警戒していない相手をほぼ一瞬で眠りに落とすことができたのではないか。それが成功していれば、シェリーが悲鳴を上げることもなく、すべてが無事に終わっていたかもしれない。
たとえば、そう。つい先日の、あの馬車から脱出する時。あそこでサモン・サーヴァントを行使して、空を翔る幻獣でも召喚できていれば、面倒事を回避してさっさと三人で逃げ果せることができていたかもしれない。あるいは、べつの使い魔でも、戦闘に参加できるような能力を持つ生物であれば、戦況と結果を変えられていたかもしれない。
いや……それだけではないはずだ。考えてみれば、あの場ではもっと適切で有用な判断があったのではないか。何も殺す必要はなかった。俺のレベルの“眠りの雲”であれば、警戒していない相手をほぼ一瞬で眠りに落とすことができたのではないか。それが成功していれば、シェリーが悲鳴を上げることもなく、すべてが無事に終わっていたかもしれない。
――いつも、そうだ。俺は己を嘲笑した。失敗してから、気づくのだ。あの時、何が必要だったのか。あの時、何をすべきだったのか。それをもっと早く察する能力が俺にあれば、こんな凋落もなかったのかもしれない。
「支度をしたら、下で食事をしておけ」
深淵に沈みかけていた俺の思考を引き上げたのは、ヘレンの朝食を促す言葉だった。
はい、と俺は頷いた。やめよう。後悔だけ続けていたって、何も意味はない。大切なのは、これから正しい判断をどのようにしていくかだ。
はい、と俺は頷いた。やめよう。後悔だけ続けていたって、何も意味はない。大切なのは、これから正しい判断をどのようにしていくかだ。
室内にある桶に張った水で顔を洗い、下着だけの状態から子供用のローブに着替える。元から着ていた服は、血塗れがひどくて破棄していた。いま身につけている衣服は、それほど上質なものでもないので、着心地はお察しである。だが、贅沢は言えないだろう。
宿屋の一階は、酒場になっている。階段を下りると、傭兵団の一員が声をかけてきた。俺はあいさつをしながら、彼らのテーブルに同席した。
この傭兵団には、メイジは二人しかいない。魔法が使えるのはヘレンとチャーリーだけである。したがって、それ以外のメンバーは剣や弓などを得物として戦う。そうなると、メイジ以上に体力と筋肉が必要なわけで……。
この傭兵団には、メイジは二人しかいない。魔法が使えるのはヘレンとチャーリーだけである。したがって、それ以外のメンバーは剣や弓などを得物として戦う。そうなると、メイジ以上に体力と筋肉が必要なわけで……。
わかりやすく言おう。
どいつもこいつも、デカくてゴツいのである。そして……むさかった。
どいつもこいつも、デカくてゴツいのである。そして……むさかった。
「ほらほら、もっと食べんと大きくなれんぞぉ!」
「遠慮はいらんぞ! 肉も食うんだ!」
「遠慮はいらんぞ! 肉も食うんだ!」
などと、大声で言われるのである。が、食の細い体なので、そんなに食えるはずもない。勘弁してくれ、と俺は苦笑いを浮かべて言った。
「い、いえ、もう、お腹いっぱい、なので」
「…………む、そうか」
「…………む、そうか」
意外なほど、あっさりと引いてくれた。というか、ちょっと気まずそうな顔をしている。厚意を無下にしてしまったか、と俺は一瞬心配したが、すぐに傭兵たちは笑顔に戻った。
「ようし、じゃあ部屋に戻って休んできな。まだ怪我も治っていないんだろ?」
たしかに、まだ傷はじんじんと痛んでいた。下手に悪化させても、皆を心配させるだけだろう。「それでは、失礼します」と言って、俺は二階の部屋で安静しに戻ることにした。
階段を上がって、廊下の途中。
「どうして、そんなにこだわるんだ?」
チャーリーの声。足を止める。彼の部屋の前だった。ドア越しに、わずかながらに声が聞こえる。
なんのことについて、話をしている? 気になり、耳を集中させるが、いきなり無音が訪れた。不自然な現象だった。おそらく――“サイレント”の魔法を使ったのだ。俺がここにいることに気づいて。
と、いうことは。チャーリーの話し相手は、ヘレンだったのだろう。だが、会話の内容については、情報が少なすぎて特定できない。……いろいろと、邪推はできることはできるが。
まあ、これ以上はどうしようもないだろう。諦めて、俺は自室に戻った。
なんのことについて、話をしている? 気になり、耳を集中させるが、いきなり無音が訪れた。不自然な現象だった。おそらく――“サイレント”の魔法を使ったのだ。俺がここにいることに気づいて。
と、いうことは。チャーリーの話し相手は、ヘレンだったのだろう。だが、会話の内容については、情報が少なすぎて特定できない。……いろいろと、邪推はできることはできるが。
まあ、これ以上はどうしようもないだろう。諦めて、俺は自室に戻った。
室内の窓を開ける。通りに面した客室なので、景色はそれなりに広い。俺は窓枠に頬杖をついて、ぼうっと外を眺めた。
人が多い。
感想がそれだった。これまで、ほとんど領地内の屋敷で暮らしていたのだ。田舎の地方と比べると、こうした都市の様子は新鮮だった。たとえ、この街が二回目の訪問であっても。
感想がそれだった。これまで、ほとんど領地内の屋敷で暮らしていたのだ。田舎の地方と比べると、こうした都市の様子は新鮮だった。たとえ、この街が二回目の訪問であっても。
そう、あれは、ちょうど二年前だったか。両親に連れられて、サウスゴータの街へ旅行にやってきたのだ。あの頃は、まだ父と母は俺を見る眼がマシだった気がする。いや……待て。……違う。あの頃を境として、彼らの俺を見る眼が徐々に変わっていったような気がする。……なぜだ? 当時の俺は……初めての街に、柄にもなく浮かれていたが、とくに普段と違った行動も取らなかったはずだ。……いや、本当にそうか? あの数日の滞在のなかで、すべての自分の言動を逐一思い出せるか? ……無理だ、できない。たった二年前のことなのに、俺の記憶はあまりにもおぼろげだった。
ぎり、と歯ぎしりをする。儘ならない。神がいるのなら文句を言ってやりたかった。どうせ生まれ変わらせるのなら、犬畜生並みの脳味噌ではなく、人智を越えた頭脳を持たせてくれりゃよかった。そうすれば、こんなクソみたいな悩みを抱くこともなかっただろうに。
溜まった負の感情を吐き出すように、俺は大きく深呼吸をした。このままでは、ダメだ。何か、気分転換をしなければ――
その時、ドアを開く音がした。反射的に、振り返る。ヘレンだった。彼女は、まるで全てを見透かしたような目で、聞いてきた。
「気分はどうだ?」
最悪だ。そう答えるわけにもいかず、平気です、と俺はほほえんだ。
「……そうか。だが困ったことがあれば、いつでも話せ」
この人は、いつも無愛想だ。今の言葉の際も、一欠片の笑顔さえ浮かべていない。なのに――そこに誰よりも優しさが込められているように、感じてしまった。
ふと、心中の何もかもを吐露したい誘惑に駆られる。だが、理性がそれを嘲笑う。じつは私は転生した人間なのです、などと口外するのか? まったくもって、馬鹿らしい。頭のイカれた可哀そうな子、と思われるのがオチである。
ふと、心中の何もかもを吐露したい誘惑に駆られる。だが、理性がそれを嘲笑う。じつは私は転生した人間なのです、などと口外するのか? まったくもって、馬鹿らしい。頭のイカれた可哀そうな子、と思われるのがオチである。
愚考を吐き捨てて、俺は口を開いた。
「……何か、私でも、手伝えることは、ありませんか?」
このままじっとしているだけでは、発狂しそうになる。それに、ヘレンの本心がどのようなものかは不明だが、こうしていろいろと助けてもらっているのだ。何か俺でもできることがあれば、と思った。
「怪我人に無理はさせられぬ」
ヘレンは否定の言葉を述べた。それを聞いて、少しだけ落胆した俺に、彼女は言葉を続ける。
「だが、暇潰しの方法ならある」
そう言って、ヘレンは部屋に置いてある荷物を漁り、何かを取り出した。そして、窓際にあるテーブルの上に置く。
それはトランプだった。なるほど、カード遊びか。古今東西で盛行しているように、これを使ったゲームの楽しさは裏打ちされている。――大勢でプレイすれば、であるが。
独りでカード遊びをするとなれば……ソリティアか? だが、一般的なソリティアについては、正直ルールもほとんど覚えていない。いっそのこと、自分で勝手にルールを作ってもよいかもしれないが。
それはトランプだった。なるほど、カード遊びか。古今東西で盛行しているように、これを使ったゲームの楽しさは裏打ちされている。――大勢でプレイすれば、であるが。
独りでカード遊びをするとなれば……ソリティアか? だが、一般的なソリティアについては、正直ルールもほとんど覚えていない。いっそのこと、自分で勝手にルールを作ってもよいかもしれないが。
「少し、待っていろ」
ヘレンは部屋を出ていった。ほかに何か、暇潰しの道具でも持ってきてくれるのだろうか。まあ、大人しく待っているとしよう。
ぱらぱらとカードを眺める。ポートランドの屋敷でも、こうしたものを使った遊びは何度かしたことがあった。その遊び相手は、もっぱら屋敷のメイド長の息子であるコリーという少年であったが。二年前を過ぎてからは、彼と、そして俺の幼い妹の二人以外は、たとえ屋敷勤めの平民であってもまともに話すことがなかった。たんに俺を気味悪がっていたのか、伯爵が関わらぬよう言いつけていたのか、今となっては判断する手はない。
ぱらぱらとカードを眺める。ポートランドの屋敷でも、こうしたものを使った遊びは何度かしたことがあった。その遊び相手は、もっぱら屋敷のメイド長の息子であるコリーという少年であったが。二年前を過ぎてからは、彼と、そして俺の幼い妹の二人以外は、たとえ屋敷勤めの平民であってもまともに話すことがなかった。たんに俺を気味悪がっていたのか、伯爵が関わらぬよう言いつけていたのか、今となっては判断する手はない。
しばらくして、がちゃりとドアが開いた。そこにいたのはヘレン――ではなかった。
誰だ? 俺が眉根を寄せると、そこにいる栗毛の少年――彼は、おどおどとした様子で口を開いた。
誰だ? 俺が眉根を寄せると、そこにいる栗毛の少年――彼は、おどおどとした様子で口を開いた。
「えっと、その……」
だが、すぐに口籠もってしまう。これでは事情を把握できない。どうしたものか。
そんなことを思った時、少年の背後からヘレンが姿を現した。
そんなことを思った時、少年の背後からヘレンが姿を現した。
「この子は、宿の主人の息子だ。店の手伝いが必要になる夕方まで、遊び相手になってもらえるよう約束した。……かまわないか?」
そういうことか。得心して頷き、俺は少年に目を向けた。俺と同じか、一つぐらい年上といったところだろうか。これなら、ゲームのルールを理解することぐらいはできるだろう。まあ、コリーを相手にしたときと同じ要領でやればよかろう。
俺は少年の前まで近づいて、にっこりと笑顔を浮かべた。
俺は少年の前まで近づいて、にっこりと笑顔を浮かべた。
「初めまして。私は、アシュリー。きみの、名前は?」
一瞬、彼はびくりとした。……ずいぶんと人見知りのようだ。だが、少ししてゆっくりと話しはじめる。
「……ぼくは、モーリス。あの、いっしょに遊んでくれる……?」
「うん、もちろん」
「うん、もちろん」
そう頷いて、俺は彼の手を引いた。あまり積極的な性格ではなさそうだから、こちらからリードしてやるのが正解だろう。
「……ヘレン、ありがとう」
ちらりと彼女を見て、小さく礼を述べる。その時、無表情だったヘレンの口元がわずかに揺れ動いた。
笑った――のかもしれない。
けれども、彼女はすぐに部屋を出てしまったので、確信は持てなかった。
笑った――のかもしれない。
けれども、彼女はすぐに部屋を出てしまったので、確信は持てなかった。
「……アシュリー?」
モーリスの声に、意識を引き戻される。そうだ、今はこの子の相手をしてあげなければ。
……いや、違うか。むしろ、俺が相手をしてもらう側なのかもしれない。
……いや、違うか。むしろ、俺が相手をしてもらう側なのかもしれない。
孤独な闇への沈潜から、逃れるために。
昏い汚泥に呑みこまれて、朽ち果てないために。
昏い汚泥に呑みこまれて、朽ち果てないために。
俺は、誰よりも誰かを必要としていた。
モーリスとカード遊びをしているなかで、俺はそのことに気づいて、心中で薄笑いを浮かべた。
そう、結局は。
きっと俺は、人が恋しかったのだろう。