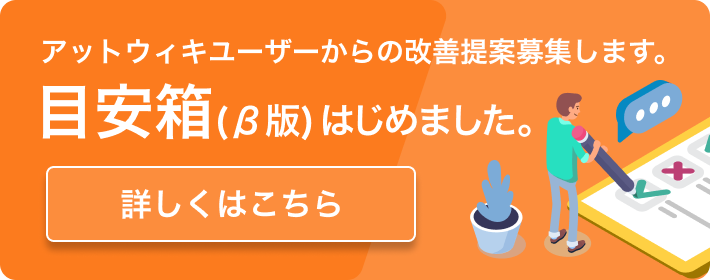身売りされた貴族のお話 04
意識が覚醒する。それと同時に、俺は跳ね起きた。辺りに……人はいない。
大きく一呼吸。頭を落ち着かせて、現在の状況を確認する。
大きく一呼吸。頭を落ち着かせて、現在の状況を確認する。
まず、ここは牢獄の中だ。三方は無骨な石の壁でできており、残る一方は鉄格子で封じられている。獄中はそれなりに広いが、物はほとんど置かれていない。いま俺の下にある就寝用の毛布と、向こうに排泄用と思われる容器があるくらいだ。
次に、自分の体を確認する。服装を見ると、ゆったりとしたローブが着せられていた。下着も確認してみると、やはり見覚えのない別物だ。眠らされている間に、身ぐるみを変えられたのだろう。既存の服に何かを仕込んでいる可能性を考えれば、こうして取り替えておくのは当然といえば当然か。
次に、自分の体を確認する。服装を見ると、ゆったりとしたローブが着せられていた。下着も確認してみると、やはり見覚えのない別物だ。眠らされている間に、身ぐるみを変えられたのだろう。既存の服に何かを仕込んでいる可能性を考えれば、こうして取り替えておくのは当然といえば当然か。
ふと、気づく。
口内で前歯が折れた部分に舌を当ててみるが、血餅すらなく完全に傷が治癒されていた。おそらく、水魔法によるものだろう。左耳も触ってみるが、こちらも治りかけだったものが完治している。わざわざ、ご丁寧なことである。
口内で前歯が折れた部分に舌を当ててみるが、血餅すらなく完全に傷が治癒されていた。おそらく、水魔法によるものだろう。左耳も触ってみるが、こちらも治りかけだったものが完治している。わざわざ、ご丁寧なことである。
溜息をついて、天井を仰ぐ。
「……モーリス」
あのあと、彼はどうなったのだろうか。不安で仕方がないが、今の俺には確認する術がなかった。せめて、大した怪我でないことを祈るばかりである。
……無力。己の現実を痛感する。
杖もなくなり、そしてこの場には、魔法行使のための契約を施せる物体も見当たらない。魔法が使えなければ、まったくもってただの貧弱な子供である。たとえ前世の記憶があるといえども……脱獄に役立つ知識や技術なんてものは、持ち合わせていなかった。
杖もなくなり、そしてこの場には、魔法行使のための契約を施せる物体も見当たらない。魔法が使えなければ、まったくもってただの貧弱な子供である。たとえ前世の記憶があるといえども……脱獄に役立つ知識や技術なんてものは、持ち合わせていなかった。
ふたたび、溜息をつく。
やるせなさが全身にのしかかるが、なんとか気を保って頭を働かせる。
やるせなさが全身にのしかかるが、なんとか気を保って頭を働かせる。
……それにしても。ここは、どこなのだろうか。
感じる空気の湿っぽさなどから、なんとなく地下牢なのだということは想像がつく。
しかし、サウスゴータの街からはそう遠くに離れていないはずだ。魔法や薬で眠らせるにしても、だいたい丸一日程度が限度なうえに、こうして地下牢に運んで、着替えや治療を行なう手間なども考えると――街から数時間で移動できる場所か。
感じる空気の湿っぽさなどから、なんとなく地下牢なのだということは想像がつく。
しかし、サウスゴータの街からはそう遠くに離れていないはずだ。魔法や薬で眠らせるにしても、だいたい丸一日程度が限度なうえに、こうして地下牢に運んで、着替えや治療を行なう手間なども考えると――街から数時間で移動できる場所か。
ならば、とわずかながらに希望を抱いてしまう。
もしかしたら――ヘレンたちが助けに来てくれるのではないか?
そう思ってしまい、俺は自分の顔をぶっ飛ばしたくなった。いったい、どれだけ他人に頼りきっているのだろうか。性根の腐った自分に吐き気がする。
常識的に考えてみろ。たまたま道中で拾ったガキが、たまたま魔法を使える身分だったので、そばに置いていただけだ。それが攫われたからといって、どこにあるかもわからぬ牢獄をわざわざ探し出して、奪還までしようなどと誰が考えるものか。彼女たちは傭兵だ。俺を助けようなどということが、どれほど危険なことか、どれだけリターンが見合っていないことか、よくわかっているだろう。
常識的に考えてみろ。たまたま道中で拾ったガキが、たまたま魔法を使える身分だったので、そばに置いていただけだ。それが攫われたからといって、どこにあるかもわからぬ牢獄をわざわざ探し出して、奪還までしようなどと誰が考えるものか。彼女たちは傭兵だ。俺を助けようなどということが、どれほど危険なことか、どれだけリターンが見合っていないことか、よくわかっているだろう。
つまりは、そう。
もはや俺が助かる見込みは、限りなくゼロに近いのである。
もはや俺が助かる見込みは、限りなくゼロに近いのである。
そんな非情な現実に思考が行き着き、えも言われぬ虚脱感が押し寄せてくる。ここから逃げ出したい――そうは思っていても、脱出する術もなければ、俺を救いに来るような人間もいるはずがない。まさしく、詰みの状態である。
……これから、俺はどうなるのか。
街中の宿屋で魔法をぶっ放してまで、俺を捕まえに来たのだ。それだけ重大な何かを、俺にしようとしているのだろう。やはり……最初に考えたように、魔法関係の実験なのだろうか。このハルケギニアにおける魔法研究が、どのように行なわれているか、俺はあまり知らない。だが、もしかしたら、幼少のメイジを使った研究が存在するのかもしれない。――それがどのような内容か、あまり想像したくないが。
俺は床にある毛布を、小さな手で強く握った。こんなものでも、鉄格子に括りつけて首を吊れば、自殺は不可能ではないはずだ。まだ、その気はないが、本当にいざというときは考えなければなるまい。
そんな悲観的な想定をした瞬間。
――足音が聞こえた。
――足音が聞こえた。
反射的に身構える。その足音は……徐々に、近づいている。どうやら、階段を下りてきているようだ。やはり、ここは地下牢なのだろう。
その人影のもたらす音が大きくなるにつれて、俺の胸の鼓動も激しさを増す。落ち着け。冷静になれ。緊張と焦燥は、判断のミスを招くだけだ。そう自分に言い聞かせる。
その人影のもたらす音が大きくなるにつれて、俺の胸の鼓動も激しさを増す。落ち着け。冷静になれ。緊張と焦燥は、判断のミスを招くだけだ。そう自分に言い聞かせる。
睨むように、鉄格子の向こうを見つめる。しばらくすると……ゆっくりと、男が姿を現した。
この空間は、弱い魔法照明がおぼろげな光を放っているだけのはずだ。だが――その男の顔は、やけにはっきりと認識できた。
この空間は、弱い魔法照明がおぼろげな光を放っているだけのはずだ。だが――その男の顔は、やけにはっきりと認識できた。
輝くようなプラチナブロンド。その髪に劣らぬほど整った顔立ち。碧眼の瞳は、すべてを見透かすような色合いだ。
白いケープに身を包んだ美青年は、にっこりとほほえんだ。
白いケープに身を包んだ美青年は、にっこりとほほえんだ。
「気分はどうだい?」
最悪だ、と吐き捨てる余裕すらなかった。
俺は震えていた。
なぜなら、俺は、こいつを――
なぜなら、俺は、こいつを――
「おや……どこか、具合が悪いのかい? それとも、寒いのかな?」
くつくつと男は笑う。そのふざけた挙動に、怒気が湧きあがる。おかげで……少しは、震えを収めることができた。
俺は、乾いた口を開いた。
「ダッシュウッド男爵……なぜ、あなたが、ここに」
「なぜ、だって? 妙なことを聞くんだね。――ぼくが、きみを買ったんだよ。それくらい、わかるだろう? “きみなら”」
「なぜ、だって? 妙なことを聞くんだね。――ぼくが、きみを買ったんだよ。それくらい、わかるだろう? “きみなら”」
彼は、含みを持たせた物言いをした。
ばらばらだった断片が、すべてつながった気がした。
そう……彼――フランシス・ダッシュウッドと初めて出会ったのは、二年前だった。俺が両親と一緒に、サウスゴータの街へ行った時だ。そこで、父の知人として、彼と顔を合わせたのだ。
そう……彼――フランシス・ダッシュウッドと初めて出会ったのは、二年前だった。俺が両親と一緒に、サウスゴータの街へ行った時だ。そこで、父の知人として、彼と顔を合わせたのだ。
「ポートランド伯爵は、幼くして魔法を扱うきみを天才と思いつつも、年齢に見合わぬ言動を見せることに不安を抱いていたよ。だから、あの日、ぼくは伯爵の“相談”に乗ってあげたのさ」
そうだ。宿の一室のなか、二人は直前まで何かを話し合っているようだった。そこへ、ちょうど俺が現れた。その時……父が俺を見て、初めて嫌悪というものを顔に浮かべたような気がする。あれが、きっかけだったというのか? だとしたら、何を話していたというのだ。
「ぼくは、伯爵からきみの日常の行動について聞きだした。じつに驚いたよ。言葉もまだたどたどしいというのに、きみの知能は異常だった。単純な足し引きならまだしも、四歳児には不可能としか思えない掛け割りの計算を瞬時に行ない、その答えを口にするエピソードを聞いた。そんな数学的思考を、きみはいったいどこで学んだというのかな? それだけじゃない。たった四歳の子供が、どうして魔法を器用に使いこなすのか。きみも知っているとおり、魔法というものは精神力を必要とする。幼い子供は、精神が未熟でまともに魔法を発現させることもむずかしいはずだ。だというのに、きみはなぜ、その幼さで魔法を使う精神力を有しているのかな?」
……わかっているさ。俺は異常だ。そして、こいつはそれによく気がついている。
「きみの異常性を、ぼくは伯爵に力説してあげたよ。そして……もっとも重要なのは、きみがどうしてそのような異常を抱えているか、だ。ぼくは、その理由を伯爵に教えてあげたよ。――悪魔の子だから、とね」
なるほど、そうか。俺は納得した。だから、のちのちになって両親は、俺をそう罵倒するようになったわけか。
「悪魔の子だって? あっはっは! ばからしい。だが、伯爵はばかだったおかげで、たやすく信じてくれたよ。そして、ぼくのことも信用してくれるようになった。そのおかげで、何度も伯爵に会う機会ができたし、きみとも接触できるようになった」
あの邂逅以降、こいつはポートランドの屋敷を定期的に訪れていた。父と話をしていたのは、おそらく俺に関することだったのだろう。
だが……それだけではない。何も知らなかった俺は、こいつが屋敷に来たときは、喜々として魔法の教えを乞うていたのだ。つまり、俺の目は節穴だったというわけである。
だが……それだけではない。何も知らなかった俺は、こいつが屋敷に来たときは、喜々として魔法の教えを乞うていたのだ。つまり、俺の目は節穴だったというわけである。
「きみと関わるうちに、ますますぼくは確信した。――きみは、前世の知識を持ったまま、生まれ変わった存在だとね」
どこまで見透かされているのだろうか、俺は。あまりにも図星すぎて、笑いたくなってしまう。もしかしたら、こいつは、何もかも知っているのかもしれない。
「生まれ変わり、だって?」
俺はうそぶくように言った。
「そんなのは……ありえない」
「いや、あるね」
「いや、あるね」
ダッシュウッド男爵は断言した。
何を根拠に? そう問うまでもなく、彼はべらべらと解説してくれる。
何を根拠に? そう問うまでもなく、彼はべらべらと解説してくれる。
「いくつかの自叙伝の書物において、自分のことを生まれ変わりの存在だと述べたものがある。まあ、その著者がどれも凡人ならば信じるに値しないんだが、じつはそうでもなくてね。彼らの来歴を調べてみると……皆が一様に、幼い頃から非凡な才能を現している。十歳に満たずしてスクウェアとなり、国に尽くして英雄として名を連ねた偉大なメイジ。一代で大商人となり、ゲルマニアで莫大な富を築いた平民。今まで誰も想像しなかったような物語や絵画を世に送り出した、優れた作家や芸術家たち。そんな人間たちが晩年、自分は生まれ変わりの存在だと主張する書物を残しているわけだ。ほとんどが禁書となっているから、ぼくが手に入れられた実物や写本は少数だけどね。実際のところ、名乗り出ないだけで、そういう人間はもっといっぱいいるんじゃないかな?」
きみのようにね、とダッシュウッド男爵は笑う。俺は否定の言葉を口にすることができなかった。
「彼らの記述を読んでみると、なかなか共通点があって面白い。どうやら、彼らはハルケギニアとは別の世界が存在すると考えているようだ。そして、自身はそこで死亡して、こちらの世界で生まれ変わったのだという。なかには、神に会って転生させられたと主張する人間もいたようだ。ところできみは、その神とやらには対面しているのかい?」
知るか。もし神がいたのなら、ぶん殴ってやりたいくらいだ。
無言でいる俺に、ダッシュウッド男爵は肩をすくめる。
無言でいる俺に、ダッシュウッド男爵は肩をすくめる。
「ま、いいさ。しかし、向こうの世界から神によって転生させられていると考えれば、きみは悪魔の子ではないことになる。むしろ逆だ。そう――神の子、と呼ぶべきだろうね」
神の子だと? 鼻で笑いたくなるフレーズだ。
だが、眼前の青年は大真面目にそれを信じているようだ。狂信しているようにも見える。
だが、眼前の青年は大真面目にそれを信じているようだ。狂信しているようにも見える。
「神の子であるきみは貴重な存在だ。なんとしてでも、手に入れたかった。だから、ぼくは二年前からずっと伯爵に働きかけていた。きみを邪悪な存在だと思いこませ、ぼくに引き取らせるように説得しつづけた。そして……ようやく、念願が達成されたというわけだよ。まあ、多少のトラブルはあったけどね」
トラブル――サウスゴータへ運ぶ途中に、俺が脱走したことを指しているのだろう。あの時の俺は、あれでもう自由になったと勘違いしていた。だが、実際はこの男の手中で足掻いていただけだったようだ。
「……私を……どうする、つもりだ……」
俺は憮然として呟いた。気力をすべて削ぎ落とされて、表情を取り繕う余裕さえも残っていなかった。
……ここまでして、俺を手に入れる理由。目的がまともなものではないことだけは確かだ。
……ここまでして、俺を手に入れる理由。目的がまともなものではないことだけは確かだ。
「ああ、安心するといい。今すぐ、きみを食おうってわけじゃないさ。きみには聞きたいことも多いからね。とくに――向こうの世界について」
つまり、この頭の中にある情報が欲しいということか。だが、そう簡単に教えてやるほど、俺もお人好しではない。
口を閉ざした俺に、ダッシュウッド男爵はやれやれと首を振る。
口を閉ざした俺に、ダッシュウッド男爵はやれやれと首を振る。
「あまり協力的ではなさそうだね。仕方がないか。それじゃあ……何かきみの要望があれば、聞いてあげよう。ただし、牢獄から出せというのはなしでね」
要望? そんなものは……いや、ある。
俺にとって、もっとも気になっている人間のこと。そう――モーリスのことだ。彼はどうなったのか。はたして無事でいるのか。どうしても、それを知りたかった。
俺にとって、もっとも気になっている人間のこと。そう――モーリスのことだ。彼はどうなったのか。はたして無事でいるのか。どうしても、それを知りたかった。
こんな男にお願いするというのも癪だったが、背に腹は替えられない。苦々しい顔で、俺は口を開いた。
「……モーリスは、どうなった」
「モーリス? 誰のことだい?」
「私がいた……宿屋の、主人の息子。巻き込まれて……怪我を、していた」
「……ふむ。ぼくが雇った傭兵からは、何も聞いていないね。まあ、明日にでも調べるとしよう」
「モーリス? 誰のことだい?」
「私がいた……宿屋の、主人の息子。巻き込まれて……怪我を、していた」
「……ふむ。ぼくが雇った傭兵からは、何も聞いていないね。まあ、明日にでも調べるとしよう」
それで、ほかに何かあるかな? と、ダッシュウッド男爵はにこやかに聞いてくる。
「…………要望、じゃないが……質問が、ある。最終的に……私を、どうする、つもりだ」
「おっと、これは答えづらいね。今はまだ、はっきりとは教えたくないかな。でも、安心するといいさ。――“痛み”を与えたりはしないつもりだ」
「おっと、これは答えづらいね。今はまだ、はっきりとは教えたくないかな。でも、安心するといいさ。――“痛み”を与えたりはしないつもりだ」
なんとも嘘くさい言葉だ。これを聞いて安心できるのは、純心無垢な子供くらいなものだろう。当然ながら、俺は疑心を抱かずにはいられなかった。
「やれやれ、本当のことを言ったつもりなんだけどな」
睨めつけている俺に肩をすくめたダッシュウッド男爵だったが、ふいに懐中時計を確認して「時間か」と呟いた。
そして彼は、相変わらず詐欺師のごとく満面の笑顔を浮かべた。
そして彼は、相変わらず詐欺師のごとく満面の笑顔を浮かべた。
「夕食だよ。今から持ってきてあげよう」
そいつは、ありがたいことで。
そう皮肉を放った俺には目もくれず、ダッシュウッド男爵は踵を返して消えていった。本当にむかつく男だ。
そう皮肉を放った俺には目もくれず、ダッシュウッド男爵は踵を返して消えていった。本当にむかつく男だ。
静寂の戻った牢獄の中で、俺は毛布の上に仰向けになって倒れた。ぼんやりと天井を見つめながら、ダッシュウッド男爵のことを思い返す。
彼は、水を得意とするスクウェアのメイジだった。それだけでなく、魔法に関する知識全般も学者顔負けに備えていたのを覚えている。だからこそ、俺は彼に魔法を教えてもらっていたのだ。屋敷の人間と違って、彼は俺にも分け隔てなく接してくれていた。だが、その顔は本心を隠す仮面で覆われていたのだろう。
彼は、水を得意とするスクウェアのメイジだった。それだけでなく、魔法に関する知識全般も学者顔負けに備えていたのを覚えている。だからこそ、俺は彼に魔法を教えてもらっていたのだ。屋敷の人間と違って、彼は俺にも分け隔てなく接してくれていた。だが、その顔は本心を隠す仮面で覆われていたのだろう。
「――向こうの世界……生まれ変わり……」
ダッシュウッド男爵の語った、転生者の存在。おそらく、あれは真実なのだろう。自分以外にもそういう人間はいるのではないか、そう考えたことは何度かあったが、こうしてほかの転生者が実在する証拠を聞かされると、やはり驚きを抑えられなかった。
そうした“同胞”たちは、どうやって生きていたのだろうか。ダッシュウッド男爵の話に出てきた人物は、どれも皆、成功した人生を送っていたようだった。けれども、全員がそうだったわけではないはずだ。もしかしたら……その特異性から、破滅の道へ歩んだ人間もいたかもしれない。
そうした“同胞”たちは、どうやって生きていたのだろうか。ダッシュウッド男爵の話に出てきた人物は、どれも皆、成功した人生を送っていたようだった。けれども、全員がそうだったわけではないはずだ。もしかしたら……その特異性から、破滅の道へ歩んだ人間もいたかもしれない。
俺は後者になるのだろうな。すぐにそう思って、自嘲の笑みを浮かべる。
ダッシュウッド男爵がこの脳内の知識を絞り取ったら、もはや残りカスとなった俺は用済みだろう。生かしておく意味はないはずだ。“痛み”を与えないと言っていたのは、最期は楽に殺してやるということなのかもしれない。
だとしても、終始無言を貫くことはできるのか。それを考えて、俺は力なく首を振った。素直に話さないとなれば、ダッシュウッド男爵はいかなる手段だろうと使ってくるはずだ。本音を言ってしまえば、おそらく拷問されれば簡単に吐いてしまうだろう。それが容易に想像できてしまうほど、自分の精神は脆弱であると自覚している。……情けないものである。
だとしても、終始無言を貫くことはできるのか。それを考えて、俺は力なく首を振った。素直に話さないとなれば、ダッシュウッド男爵はいかなる手段だろうと使ってくるはずだ。本音を言ってしまえば、おそらく拷問されれば簡単に吐いてしまうだろう。それが容易に想像できてしまうほど、自分の精神は脆弱であると自覚している。……情けないものである。
結局、もはや一縷の望みもないわけだ。
俺は小さく笑った。これまでの人生、そして己自身の存在。どれも馬鹿らしい。無意味。無価値。なんのために、この世界に生まれてきたのやら。
「食事だよ」
いつの間にか、鉄格子の向こうにダッシュウッド男爵が立っていた。タクト型の杖でレビテーションを使い、食器の置かれたトレーを浮かべている。彼が杖を振ると、トレーがいったん床に置かれた。そしてアンロックと念力の魔法で鉄格子の扉を開け、そこから食事を俺に渡す。
「……豪勢な、ことだ」
用意された夕食を目にして、鼻を鳴らす。裕福な大貴族のような品目だ。一目で上質な肉とわかるステーキも目立つが、それと並んで職人が作ったようなケーキ菓子も存在感が大きい。食い物で手懐けようってことか?
「体力はつけてもらいたいからね。途中で衰弱死なんてされたら、たまったもんじゃないよ」
冗談っぽく笑うダッシュウッド男爵を無視して、食事に手をつける。前歯が数本欠けているので、噛み合わせに慣れるまで少し時間がかかったが、なんとか食べ進められた。正直なところ、空腹だったこともあって、かなり美味しく感じてしまった。どうせそのうち死ぬのだと思うと、こうして獄中の食事を楽しむこともできそうだ。我ながら、なんともふてぶてしい。
腹が満たされるまで口にしてから、俺はトレーを返した。量が多かったので、半分以上は食べ残しているが、その辺は彼も気にしないようだ。
腹が満たされるまで口にしてから、俺はトレーを返した。量が多かったので、半分以上は食べ残しているが、その辺は彼も気にしないようだ。
「ま、残りはぼくが貰うよ」
肩をすくめたダッシュウッド男爵に、俺は眉をしかめた。
「……残飯漁りが、趣味か?」
「おいおい、誤解しないでくれよ。もともと、これは“ぼくの食事”として作らせたものなんだから。きみの存在をできるだけ隠すためには、二人分の食事を作らせるわけにはいかないからね」
「おいおい、誤解しないでくれよ。もともと、これは“ぼくの食事”として作らせたものなんだから。きみの存在をできるだけ隠すためには、二人分の食事を作らせるわけにはいかないからね」
その発言で、俺は納得した。そういえば、サウスゴータの街から少し離れた郊外に、彼が屋敷を持っていると聞いたことがある。つまり、そこの地下に俺はいるのだろう。
とはいえ、場所がわかったところでどうしようもないが。ここで叫び声を上げたって、防音措置はしているだろうから、上のほうまで聞こえるわけがない。主人が屋敷の地下に出入りしているのを不審に思った使用人が……などという三文小説じみた展開も、望み薄である。
とはいえ、場所がわかったところでどうしようもないが。ここで叫び声を上げたって、防音措置はしているだろうから、上のほうまで聞こえるわけがない。主人が屋敷の地下に出入りしているのを不審に思った使用人が……などという三文小説じみた展開も、望み薄である。
「さて、ぼくはこれで失礼しよう。――また明日」
鉄格子の扉を閉めたダッシュウッド男爵は、そう言って去っていった。
満腹になった体を、石の壁に預ける。それから大きく深呼吸して、目を閉じる。
これから、こんなふうに過ごして、そして死ぬのだろうか。
……きっと、そのとおりなのだろう。しかし、不自由ではあるが、頭をからっぽにすれば受け入れられるかもしれない。脱出不可能な現実を目の前にして、そんな諦観をしてしまいそうになる。
これから、こんなふうに過ごして、そして死ぬのだろうか。
……きっと、そのとおりなのだろう。しかし、不自由ではあるが、頭をからっぽにすれば受け入れられるかもしれない。脱出不可能な現実を目の前にして、そんな諦観をしてしまいそうになる。
本当は……死にたくない。
けれども、その思いは、もしかしたら、贅沢なのかもしれない。
けれども、その思いは、もしかしたら、贅沢なのかもしれない。
「――私は、どこから、間違っていたんだ」
呟いた言葉は、虚空に消えていった。