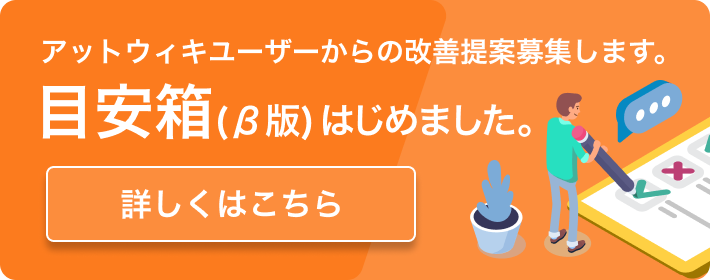仮想シンデレラ
1
「――シンデレラ、これも洗っておいてちょうだい」
「はぁい」
「このドレスの綻びを直しておいて。それから、ブルーのドレス。あれ、もう着ないから処分して。流行遅れだもの」
「はぁい」
「今日は熱いシチューが食べたいわ」
「はぁい」
洗濯かごを、左右の手にひとつずつ。シンデレラと呼ばれた少女は、洗い物が増えた事、姉のドレスがほつれている事と拝借できるドレスがひとつある事、それから夕飯にシチューを作る事を間延びした返事で記憶した。
少女はこの家の娘であるにもかかわらず、父の再婚者とその連れ子の二人の姉によって、家政婦のような生活を余議なくされていた。シンデレラ(はいかぶり)と呼ばれ、アレをしろ、コレをしろとありとあらゆる事を要求される。しかし、そんな事はどうでもいい。
少女は料理が好きだった。掃除も洗濯も裁縫も、少女は楽しんでやっていた。埃ひとつない綺麗な部屋に満足し、笑みを浮かべるのは、父が再婚する前から少女の日課だったのだから。母と二人の姉たちの横柄な物言いさえ割り切ることが出来れば、そこそこに充実した日々なのだ。
しかし、ひとつだけ。『シンデレラ』という呼ばれ方だけはどうにも、好きにはなれなかった。確かに、毎日掃除をしているからエプロンは汚れている。洗ってはいるが、もう落ちなくなっている汚れも少なくない。暖炉掃除をした時などは、その文字通りに灰をかぶる。しかし、何の捻りもないその呼び名はどうにも、好きになれなかった。
“薄墨”とか、“ネズミ”とか、“雨雲”とか、“灰”から連想できる名前は他にはなかったのかしら、と少女は三人の語彙の少なさに、はぁ、とひとつ溜め息を吐いた。
灰色は綺麗な色だし、ネズミも良く見れば可愛い顔をしている。雨雲は重苦しいが、雨が降った後の空気は清々しい。自分を貶めるための呼び名だということは分かっているが、しかしそんな直球では嘆けるものも嘆けない。いやな思いをさせるという目的だけは果たされているが。
毎日は穏やかだ。
良く分からないイベントさえなければ、とても穏やか。
「はぁい」
「このドレスの綻びを直しておいて。それから、ブルーのドレス。あれ、もう着ないから処分して。流行遅れだもの」
「はぁい」
「今日は熱いシチューが食べたいわ」
「はぁい」
洗濯かごを、左右の手にひとつずつ。シンデレラと呼ばれた少女は、洗い物が増えた事、姉のドレスがほつれている事と拝借できるドレスがひとつある事、それから夕飯にシチューを作る事を間延びした返事で記憶した。
少女はこの家の娘であるにもかかわらず、父の再婚者とその連れ子の二人の姉によって、家政婦のような生活を余議なくされていた。シンデレラ(はいかぶり)と呼ばれ、アレをしろ、コレをしろとありとあらゆる事を要求される。しかし、そんな事はどうでもいい。
少女は料理が好きだった。掃除も洗濯も裁縫も、少女は楽しんでやっていた。埃ひとつない綺麗な部屋に満足し、笑みを浮かべるのは、父が再婚する前から少女の日課だったのだから。母と二人の姉たちの横柄な物言いさえ割り切ることが出来れば、そこそこに充実した日々なのだ。
しかし、ひとつだけ。『シンデレラ』という呼ばれ方だけはどうにも、好きにはなれなかった。確かに、毎日掃除をしているからエプロンは汚れている。洗ってはいるが、もう落ちなくなっている汚れも少なくない。暖炉掃除をした時などは、その文字通りに灰をかぶる。しかし、何の捻りもないその呼び名はどうにも、好きになれなかった。
“薄墨”とか、“ネズミ”とか、“雨雲”とか、“灰”から連想できる名前は他にはなかったのかしら、と少女は三人の語彙の少なさに、はぁ、とひとつ溜め息を吐いた。
灰色は綺麗な色だし、ネズミも良く見れば可愛い顔をしている。雨雲は重苦しいが、雨が降った後の空気は清々しい。自分を貶めるための呼び名だということは分かっているが、しかしそんな直球では嘆けるものも嘆けない。いやな思いをさせるという目的だけは果たされているが。
毎日は穏やかだ。
良く分からないイベントさえなければ、とても穏やか。
その日の午後、お城からの使いだというひとりの男性が家を訪れた。招待状を、携えて。
何でも王子様の姫君を決めるパーティーを行うのだとか。ああ面倒くさい、と少女はそれを見て思った。
姫君なんて、近隣の国のお姫様の中から選べばいいのに。隣国なんて、確か女ばかりの5人姉妹だったはずだ。なのにどうして、王族でもない家の娘に招待状等持ってくるのか。
自分はともかく、母と姉たちがパーティーに行くという事は、毎日行っている家事に加えて母や姉たちを着飾らせるという大仕事をしなければいけないということだ。仕事増やしやがって、と少女は心中で毒づく。
「貴方も是非、パーティーにいらしてください」
穏やかな笑みを浮かべたお城からの使いは、そんなことを言い出した。なんということだ。
なんて、面倒な!
少女は口には出さず心の中でそう叫んだ。手のかかる子供がもうすでに三人も居るのだ。三人でもう手一杯なのだ。
なのに、その上自分の事までやれというのか! それに、もし過労で倒れでもしたら、一体誰が家事をするのだ。きっと誰もやらない。そうなれば家がすたれるだけだ。
少女は取り敢えず、その場で辞退を申し上げたのだった。
何でも王子様の姫君を決めるパーティーを行うのだとか。ああ面倒くさい、と少女はそれを見て思った。
姫君なんて、近隣の国のお姫様の中から選べばいいのに。隣国なんて、確か女ばかりの5人姉妹だったはずだ。なのにどうして、王族でもない家の娘に招待状等持ってくるのか。
自分はともかく、母と姉たちがパーティーに行くという事は、毎日行っている家事に加えて母や姉たちを着飾らせるという大仕事をしなければいけないということだ。仕事増やしやがって、と少女は心中で毒づく。
「貴方も是非、パーティーにいらしてください」
穏やかな笑みを浮かべたお城からの使いは、そんなことを言い出した。なんということだ。
なんて、面倒な!
少女は口には出さず心の中でそう叫んだ。手のかかる子供がもうすでに三人も居るのだ。三人でもう手一杯なのだ。
なのに、その上自分の事までやれというのか! それに、もし過労で倒れでもしたら、一体誰が家事をするのだ。きっと誰もやらない。そうなれば家がすたれるだけだ。
少女は取り敢えず、その場で辞退を申し上げたのだった。
*
「出ればいいじゃないの」
断ったにも関わらず、まぁ考えてみてくださいなどと言われ、その事を姉に話してみたところ、何も問題はないでしょう、とさらりとした一言が返ってきた。
「お城からの招待を無碍にするなんて失礼だもの」
そう言って、にっこりとほほ笑んだ。きっと希望通りの美味しいシチューに満足しているのだろう。銀のスプーンを口に運びながら上機嫌でそう言った。少女の前に、皿はない。味見という名のつまみ食いで十分な量を食べているため、いつも夕飯のときにはものを食べないのだ。
姉の言葉に、少女は確かにそうかもしれないとふぅむと唸る。面倒だという理由だけでお城からの招待を無碍にするのは、確かに、少しばかり失礼にあたるかもしれない。
「でもまぁ、着ていけるドレスがあるなら、の話だけど」
もう一人の姉が、そう言ってくすくすと笑った。
ドレスはあるのだ。
処分しろと言われたドレスは、実は全部取ってあるのだから。それに、少女は裁縫が大の得意だった。流行遅れのドレスを丁寧に分解し、自分の体と流行にぴったりと合うように作り変えたドレスが、何着か手元にある。けれどそれはひとりの時にこっそりと楽しむためだけに作ったものだし、そもそも物を作りかえるという発想を持たない姉たちに見せたところで、作った事など信じては貰えないだろうと思い、誰にも見せてはいなかった。どこから盗んできたのかなどと言われたら、弁解が酷く億劫だ。
「そう、ですよねぇ」
着ていけるドレスがあるのなら、行くべきである。
少女は渋々ながら、パーティーに参加する事に決めた。ああ全く面倒くさいと呟き、溜め息を吐きながら。
断ったにも関わらず、まぁ考えてみてくださいなどと言われ、その事を姉に話してみたところ、何も問題はないでしょう、とさらりとした一言が返ってきた。
「お城からの招待を無碍にするなんて失礼だもの」
そう言って、にっこりとほほ笑んだ。きっと希望通りの美味しいシチューに満足しているのだろう。銀のスプーンを口に運びながら上機嫌でそう言った。少女の前に、皿はない。味見という名のつまみ食いで十分な量を食べているため、いつも夕飯のときにはものを食べないのだ。
姉の言葉に、少女は確かにそうかもしれないとふぅむと唸る。面倒だという理由だけでお城からの招待を無碍にするのは、確かに、少しばかり失礼にあたるかもしれない。
「でもまぁ、着ていけるドレスがあるなら、の話だけど」
もう一人の姉が、そう言ってくすくすと笑った。
ドレスはあるのだ。
処分しろと言われたドレスは、実は全部取ってあるのだから。それに、少女は裁縫が大の得意だった。流行遅れのドレスを丁寧に分解し、自分の体と流行にぴったりと合うように作り変えたドレスが、何着か手元にある。けれどそれはひとりの時にこっそりと楽しむためだけに作ったものだし、そもそも物を作りかえるという発想を持たない姉たちに見せたところで、作った事など信じては貰えないだろうと思い、誰にも見せてはいなかった。どこから盗んできたのかなどと言われたら、弁解が酷く億劫だ。
「そう、ですよねぇ」
着ていけるドレスがあるのなら、行くべきである。
少女は渋々ながら、パーティーに参加する事に決めた。ああ全く面倒くさいと呟き、溜め息を吐きながら。
2
パーティー当日。
少女は姉に呼ばれ、母に呼ばれ、もうひとりの姉に呼ばれ、また母に呼ばれ、家中を駆け回っていた。
新しいドレスがきついとか、ルビーのブローチは何処にあるのとか、もっと大きな羽飾りはないのとか、レースの手袋を持ってきてとか、このドレスにはどの靴が合うかしらとか、なんでパーティーなんてあるのかしらと思いながらも、少女は要望のひとつひとつに律儀に応えていった。
きついドレスは直し、ジュエリーボックスからルビーのブローチを探し出し、大きな羽飾りを在り合わせのもので作り、レースの手袋を引き出しの奥から引っ張り出し、ローズピンクのドレスには白地に薔薇の刺繍が施されたハイヒールを用意した。
「行ってきまぁーす」
「行ってらっしゃいませー……」
もうすでに疲労困憊である。しかし、これから自分の用意をしなければならないのだ。がんばれ自分、と少女は重い腰を上げた。
まずはシャワーを浴び、汗と埃を落とした。そして、手作りのドレスを着る。淡いブルーとオフホワイトで、レースとフリルをたっぷりと使った品の良い一着である。姉の化粧品を少しばかり拝借して化粧をし、長い金髪はくるりとひとつにまとめて櫛で固定した。この櫛も、処分してと言われたものだ。靴も、姉たちの履き古したものの中から選んだ。
きらきらと硝子のように光る美しい靴。ヒールにも小さな宝石が幾つか散りばめられており、細やかな細工が施された見事な靴だ。確かこれは、サイズが合わなくなって処分となったものだった。姉のお気に入りだったはずだが、何度も履かないうちに小さくなってしまったのだ。残念ですねとその時は言ったけれど、内心、儲け物だと思ったのは少女一人の秘密である。
さて、と少女は思案した。これで身繕いは完璧なのだが、馬車がない事に今更になって気がついた。
……馬で良いか。
少女の思考は単純明快だ。
歩いて行くには、お城は遠い。馬は居る。それも、良く懐いた大人しい子。馬に付ける車はない。ないものは出せない。乗馬は出来る。幼い頃から動物との戯れが好きだったから。
そうなれば、選択肢などありはしない。
自ら馬に乗るだけである。幸い、少女は馬の世話も毎日欠かさずにやっている。馬だって身綺麗なのだ。どこかに引っ掛けたりさえしなければ、ドレスで乗っても問題はないだろう。
そうして、少女は物語の中の勇者よろしく、馬に乗って城へと向かったのだった。
少女は姉に呼ばれ、母に呼ばれ、もうひとりの姉に呼ばれ、また母に呼ばれ、家中を駆け回っていた。
新しいドレスがきついとか、ルビーのブローチは何処にあるのとか、もっと大きな羽飾りはないのとか、レースの手袋を持ってきてとか、このドレスにはどの靴が合うかしらとか、なんでパーティーなんてあるのかしらと思いながらも、少女は要望のひとつひとつに律儀に応えていった。
きついドレスは直し、ジュエリーボックスからルビーのブローチを探し出し、大きな羽飾りを在り合わせのもので作り、レースの手袋を引き出しの奥から引っ張り出し、ローズピンクのドレスには白地に薔薇の刺繍が施されたハイヒールを用意した。
「行ってきまぁーす」
「行ってらっしゃいませー……」
もうすでに疲労困憊である。しかし、これから自分の用意をしなければならないのだ。がんばれ自分、と少女は重い腰を上げた。
まずはシャワーを浴び、汗と埃を落とした。そして、手作りのドレスを着る。淡いブルーとオフホワイトで、レースとフリルをたっぷりと使った品の良い一着である。姉の化粧品を少しばかり拝借して化粧をし、長い金髪はくるりとひとつにまとめて櫛で固定した。この櫛も、処分してと言われたものだ。靴も、姉たちの履き古したものの中から選んだ。
きらきらと硝子のように光る美しい靴。ヒールにも小さな宝石が幾つか散りばめられており、細やかな細工が施された見事な靴だ。確かこれは、サイズが合わなくなって処分となったものだった。姉のお気に入りだったはずだが、何度も履かないうちに小さくなってしまったのだ。残念ですねとその時は言ったけれど、内心、儲け物だと思ったのは少女一人の秘密である。
さて、と少女は思案した。これで身繕いは完璧なのだが、馬車がない事に今更になって気がついた。
……馬で良いか。
少女の思考は単純明快だ。
歩いて行くには、お城は遠い。馬は居る。それも、良く懐いた大人しい子。馬に付ける車はない。ないものは出せない。乗馬は出来る。幼い頃から動物との戯れが好きだったから。
そうなれば、選択肢などありはしない。
自ら馬に乗るだけである。幸い、少女は馬の世話も毎日欠かさずにやっている。馬だって身綺麗なのだ。どこかに引っ掛けたりさえしなければ、ドレスで乗っても問題はないだろう。
そうして、少女は物語の中の勇者よろしく、馬に乗って城へと向かったのだった。
*
「どうだ、素敵な娘は居るか?」
王子は父親――つまり国王の一言に対し酷く迷惑そうな表情を浮かべた。国中の娘を集めてのパーティーを行うなんて、この男は一体何をトチ狂っているのか。確かに、言った。早く結婚しろという父親に辟易し、この国で最も美しい娘ならば結婚しましょうと戯れ半分、断り半分でそう言った。しかしだからと言ってこの暴挙は何事だ。
「コンテストを開くのも案として出ていたのだが、やはり何を美しいとするかは個人によって異なるからな。しっかりと、自分の目で見極めると良い」
上機嫌でいう父親に、そういえばこの人は国王だったんだよなぁ、と諦め混じりの溜め息を吐く。正直、女は面倒くさいのだ。姉も妹もきゃあきゃあ煩いし、近隣諸国の姫君たちなど、化粧臭いわ香水臭いわ煩いわ。しかも自分の事すら自分で出来ないときている。そんな相手など求めてはいないのだ。どこかで張り合いの持てる相手でなければ詰らないではないか。それに、事あるごとに使用人を呼び付けるその姿はいっそ滑稽だ。雇用対策にはなるかもしれないが、決して、嫁に貰おうなどとは思えない。
しかし、これだけの盛大なパーティーを開いておきながら、やっぱり決められませんでしたゴメンナサイでは済まされないだろうということも分かっている王子は、もうひとつ、先程よりも長く深い溜め息を吐いた。
ならば、出来るだけ男友達のようにさっぱりと付き合える女性を探すまでである。さばさばとしていて、自分の事は自分で出来て、きゃあきゃあ甲高い声で騒がなくて、共に乗馬や狩りを楽しめる女性。いっそ、このパーティー自体を面倒だと思っているくらいの人だと理想的だ。
いないだろうなぁ、と呟いた。せめて最初の二つくらいはクリアしている人が良いなぁ、と王子は数段高くなっている自分の席から、集まった女性たちを眺めていた。
「……ん?」
「どうした?」
「……あの子」
指差したその先に居る、ひとりの少女。輝くばかりの美しい娘なのだが、先程から踊るでもなく、誰かと談笑するでもなく、壁際の椅子に座ってひたすらに御馳走を食べている。しかも、酷く退屈そうにして、早く終わればいいのにとでもいうような表情をしている。
澄まして立っていれば、どこの貴族かと噂にもなりそうなのに。
誰もが目を奪われるような可憐な美貌を持っているのに。
しかし良く見れば化粧も薄く、髪型も少々おざなりだ。羽や宝石の飾りでごてごての他の娘たちとは全然違う。
「ああ、あの娘か」
「はい。他の娘たちとはどうにも違うように見えたものですから」
その言葉に、父親はそうだなぁ、と答えた。
「あの娘、自分で馬に乗ってきたからなぁ、従者も何も付けずに。だから腹も減っているのだろう。
なかなか勇ましい娘だそうだぞ。門番が言っていたのだが、馬に乗り、乗馬鞭を振って『パーティーの会場はここですか』と、怖気づくこともなく聞いてきたらしい」
勇ましく乗馬のできる女の子!
なかなかに興味深いぞ、と王子は使用人にオペラグラスを持ってこさせた。そして、その乗馬少女を観察する。
食事を終えたのか、少女は近くを通った使用人を呼びとめ、空になった皿を渡していた。そして、満腹だとでも言うように腹を撫で、椅子の背もたれにくたりと凭れる。しばらくぼぅっとしていたかと思えば、今度は欠伸。
明らかに、少女は異質だった。
「……彼女、面白いな」
「呼ぼうか? ここに」
「いえ、こちらから行きます」
立ち上がった王子の後ろ姿に、変わった娘が好みだったのか、と国王は少しばかりずれた感想を漏らしたのだった。
王子は父親――つまり国王の一言に対し酷く迷惑そうな表情を浮かべた。国中の娘を集めてのパーティーを行うなんて、この男は一体何をトチ狂っているのか。確かに、言った。早く結婚しろという父親に辟易し、この国で最も美しい娘ならば結婚しましょうと戯れ半分、断り半分でそう言った。しかしだからと言ってこの暴挙は何事だ。
「コンテストを開くのも案として出ていたのだが、やはり何を美しいとするかは個人によって異なるからな。しっかりと、自分の目で見極めると良い」
上機嫌でいう父親に、そういえばこの人は国王だったんだよなぁ、と諦め混じりの溜め息を吐く。正直、女は面倒くさいのだ。姉も妹もきゃあきゃあ煩いし、近隣諸国の姫君たちなど、化粧臭いわ香水臭いわ煩いわ。しかも自分の事すら自分で出来ないときている。そんな相手など求めてはいないのだ。どこかで張り合いの持てる相手でなければ詰らないではないか。それに、事あるごとに使用人を呼び付けるその姿はいっそ滑稽だ。雇用対策にはなるかもしれないが、決して、嫁に貰おうなどとは思えない。
しかし、これだけの盛大なパーティーを開いておきながら、やっぱり決められませんでしたゴメンナサイでは済まされないだろうということも分かっている王子は、もうひとつ、先程よりも長く深い溜め息を吐いた。
ならば、出来るだけ男友達のようにさっぱりと付き合える女性を探すまでである。さばさばとしていて、自分の事は自分で出来て、きゃあきゃあ甲高い声で騒がなくて、共に乗馬や狩りを楽しめる女性。いっそ、このパーティー自体を面倒だと思っているくらいの人だと理想的だ。
いないだろうなぁ、と呟いた。せめて最初の二つくらいはクリアしている人が良いなぁ、と王子は数段高くなっている自分の席から、集まった女性たちを眺めていた。
「……ん?」
「どうした?」
「……あの子」
指差したその先に居る、ひとりの少女。輝くばかりの美しい娘なのだが、先程から踊るでもなく、誰かと談笑するでもなく、壁際の椅子に座ってひたすらに御馳走を食べている。しかも、酷く退屈そうにして、早く終わればいいのにとでもいうような表情をしている。
澄まして立っていれば、どこの貴族かと噂にもなりそうなのに。
誰もが目を奪われるような可憐な美貌を持っているのに。
しかし良く見れば化粧も薄く、髪型も少々おざなりだ。羽や宝石の飾りでごてごての他の娘たちとは全然違う。
「ああ、あの娘か」
「はい。他の娘たちとはどうにも違うように見えたものですから」
その言葉に、父親はそうだなぁ、と答えた。
「あの娘、自分で馬に乗ってきたからなぁ、従者も何も付けずに。だから腹も減っているのだろう。
なかなか勇ましい娘だそうだぞ。門番が言っていたのだが、馬に乗り、乗馬鞭を振って『パーティーの会場はここですか』と、怖気づくこともなく聞いてきたらしい」
勇ましく乗馬のできる女の子!
なかなかに興味深いぞ、と王子は使用人にオペラグラスを持ってこさせた。そして、その乗馬少女を観察する。
食事を終えたのか、少女は近くを通った使用人を呼びとめ、空になった皿を渡していた。そして、満腹だとでも言うように腹を撫で、椅子の背もたれにくたりと凭れる。しばらくぼぅっとしていたかと思えば、今度は欠伸。
明らかに、少女は異質だった。
「……彼女、面白いな」
「呼ぼうか? ここに」
「いえ、こちらから行きます」
立ち上がった王子の後ろ姿に、変わった娘が好みだったのか、と国王は少しばかりずれた感想を漏らしたのだった。
「――今晩は、レディ。パーティーは楽しんでいますか?」
唐突に、ひとりの男性から話しかけられた少女は、一瞬驚いたように目を見開き、二、三度ぱちぱちと瞬きをした。そして、困ったように少しだけ眉を寄せた。
「……今晩は。……あの、どこかでお会いしましたかしら? 申し訳ないのですが、ちょっと覚えがなくて……」
「……今日のパーティーの主旨は、ご存知ですか?」
少女はわずかに首を傾げ、「王子様のお嫁様探し」と答えた。それに、男性はにこりと笑って頷いた。
「よかった。食事会、とか言われたらどうしようかと思っていたんだ」
その言葉に、少女は再び首を傾げた。
「君の事気に入ったから、声を掛けに来たんだ。向こうで少し、お話しないかい?」
「……はぁ」
事態を上手く把握できていないまま、少女は男性に手を引かれ、別室へと連れて行かれた。
唐突に、ひとりの男性から話しかけられた少女は、一瞬驚いたように目を見開き、二、三度ぱちぱちと瞬きをした。そして、困ったように少しだけ眉を寄せた。
「……今晩は。……あの、どこかでお会いしましたかしら? 申し訳ないのですが、ちょっと覚えがなくて……」
「……今日のパーティーの主旨は、ご存知ですか?」
少女はわずかに首を傾げ、「王子様のお嫁様探し」と答えた。それに、男性はにこりと笑って頷いた。
「よかった。食事会、とか言われたらどうしようかと思っていたんだ」
その言葉に、少女は再び首を傾げた。
「君の事気に入ったから、声を掛けに来たんだ。向こうで少し、お話しないかい?」
「……はぁ」
事態を上手く把握できていないまま、少女は男性に手を引かれ、別室へと連れて行かれた。
『どこかでお会いしましたかしら? 申し訳ないのですが、ちょっと覚えがなくて……』
少女の台詞に、王子は感動すら覚えていた。
パーティーの主旨は辛うじて理解していたようだが、その主役の顔すら知らずに来ていたとは! 何とも面白い娘だ!
緩みそうになる頬を何とか抑えつつ、王子は少女の手を引いて別室へと移動した。気に入った娘が居た時、ゆっくりと話が出来るように、と国王が気を利かせて造らせた個室である。ブラウンとオフホワイトを基調に、ワインレッドやゴールドの小物を配した豪奢な、けれど落ち着いた部屋である。
「……ここは?」
「王子と姫君候補の面談室」
「王子様は、どちらに居らっしゃるのですか?」
「ここに」
「……貴方が?」
嘘でしょとでも言うように、少女は眉間に皺を寄せ、王子を凝視した。そして、にっこりと笑む王子に対しまた、嘘でしょとでも言うように首を振った。
「信じられないわ。だって、王子様が私を選ぶはずなんてないもの。選ばれるような事してないもの。それに、美しい人はいくらでも居たでしょう?」
それに、ここにだって正直来たくなかったのに。面倒だったから。
「僕は美しい人なんて求めてないんだよね。僕はね、さばさばとしていて、自分の事は自分で出来て、きゃあきゃあ甲高い声で騒がなくて、共に乗馬や狩りを楽しめる女性が良いなって思っていたんだから。君、結構それに当てはまりそうな感じだったからさ」
「あら、まぁ」
なんて面白い人なのかしら、と少女は呟いた。
「君さ、乗馬とか好き?」
「それはもう。あ、でも血は見たくないから狩りはしないわ」
「出来れば自分の事は自分で出来る子がいいなと思っているんだけど。どう?」
「まぁ、出来る方ではないかしら。家事とか、結構好きよ」
「そう、良かった。あと、きゃあきゃあ騒がしい女は好きではないんだけど、君はそうでもなさそうだよね」
「そうね。あまり騒いだら疲れてしまうじゃない」
「……疲れる、ねぇ」
「だってやる事がたくさんあるんだもの。お掃除にお料理、お洋服がほつれたら繕うのも私。母さまや姉さまはアレもコレもと煩いし。いちいち騒いでいたら何も終わらないし、疲れるだけだし。何の意味もないわ」
「嫌ではないの? その生活」
「嫌ではないわ。基本的に家事は好きなのよ。小煩い人たちがいなければ楽にはなるだろうなとは思うけれど」
くすくすと楽しげな声を漏らしながら受けこたえるそのさまはとても可憐で、とても優雅だった。乗馬してパーティーに来るような突拍子もない事をする娘だが、きっと育ちは良いのだろう。もしかしたら、もとは貴族の出なのかもしれない。家では使用人のような生活をしているようだが、ドレスを綺麗に着こなす事も、軽やかに乗馬をする事も、そうでなければなかなかできない事だろう。それに、所作のひとつひとつに品を感じる。にじみ出るような品の良さは、付け焼刃では身に付かない。身に染みついたものだから自然に出すことが出来るのだ。
この人なら、愛することが出来るかもしれない。もちろん、今はまだ愛してなどいない。出会ったばかりなのだから当然だ。しかし、この少女は理想としていた条件にぴったりと当てはまる。しかも美しく、品の良い女性だ。求めていた以上に素晴らしい女性。きっと、彼女以上の人とはもう出会う事は出来ないだろう。
「決めた」
王子はとても楽しそうに、嬉しそうにぱん、と手を叩いて少女に向き直った。
「君さえよければ、僕と結婚してくれないかい?」
「お断りするわ」
にっこりと、少女は辞退した。
「私は別に貴方の事を愛している訳じゃないもの。それに、貴方と結婚なんかしたら母や姉の面倒は一体誰が見ると言うの? 他に使用人を雇ったとしても、あの我儘娘たちを御す事は難しいわよ? それにね、私はもともとこのパーティー自体を面倒だと思っていたの。参加するつもりなんて、さらさらなかったの。これっぽっちもなかったの。姉さまに言われて仕方なく、ここに来ているのだもの。きっと私以外の子の方が貴方のことを想っているだろうし、貴方も自分を想ってくれる人が相手の方が幸せなんじゃないかしら」
「それは困った。僕は別に愛してくれる人とか想ってくれる人を求めている訳じゃないんだよね。それに、他の人は大体が玉の輿狙いの守銭奴たちさ。金と名誉しか求めてないんだから。家族が心配ならうちの優秀な使用人をやるから、その辺は安心してよ。確かにこのパーティーは一応嫁探しなんて名目で開かれているし僕以外はそういう心積もりなんだろうけど、僕としては友達探しっていう感覚の方が強いんだよね。さっぱりすっきり付き合える、一緒に居て楽しいと思えるような友人。化粧と香水の悪臭を撒き散らしながら何も出来ないくせに威張って使用人にアレもコレもと要求しているような女を友人になんてしたくはないんだ。見ていてイライラするような奴なんて、傍に居て欲しくないだろ? その点、君は僕の理想とする友人像にぴったりと当てはまる。君以外の女性なんて考えられないんだけどね」
「――分かった」
少女は意外と押しの強い王子の言葉にこくりと頷く。そして、前向きに検討してみるわ、とほほ笑んだ。
「でも少し、考える時間が欲しいわ。だから、そうね……」
呟いて、少女は美しい靴を脱ぎ、その片方を王子に渡した。
「私を探し出して見せて。片方ずつの靴を持って、これを合わせる事が出来たら、そしたら、ちゃんと返事をするわ」
「分かった」
王子は硝子のように輝く靴を、片方だけ受けとった。そして、君は何を穿いて家に帰るの? と少女に声を掛けた。
「馬小屋に乗馬用のブーツを置いてあるの」
じゃあね、明日の料理の準備をしなくちゃならないから、と少女は笑ってお城を後にした。
時刻はちょうど十二時。
どこかで、鐘の音が高らかに響いていた。
少女の台詞に、王子は感動すら覚えていた。
パーティーの主旨は辛うじて理解していたようだが、その主役の顔すら知らずに来ていたとは! 何とも面白い娘だ!
緩みそうになる頬を何とか抑えつつ、王子は少女の手を引いて別室へと移動した。気に入った娘が居た時、ゆっくりと話が出来るように、と国王が気を利かせて造らせた個室である。ブラウンとオフホワイトを基調に、ワインレッドやゴールドの小物を配した豪奢な、けれど落ち着いた部屋である。
「……ここは?」
「王子と姫君候補の面談室」
「王子様は、どちらに居らっしゃるのですか?」
「ここに」
「……貴方が?」
嘘でしょとでも言うように、少女は眉間に皺を寄せ、王子を凝視した。そして、にっこりと笑む王子に対しまた、嘘でしょとでも言うように首を振った。
「信じられないわ。だって、王子様が私を選ぶはずなんてないもの。選ばれるような事してないもの。それに、美しい人はいくらでも居たでしょう?」
それに、ここにだって正直来たくなかったのに。面倒だったから。
「僕は美しい人なんて求めてないんだよね。僕はね、さばさばとしていて、自分の事は自分で出来て、きゃあきゃあ甲高い声で騒がなくて、共に乗馬や狩りを楽しめる女性が良いなって思っていたんだから。君、結構それに当てはまりそうな感じだったからさ」
「あら、まぁ」
なんて面白い人なのかしら、と少女は呟いた。
「君さ、乗馬とか好き?」
「それはもう。あ、でも血は見たくないから狩りはしないわ」
「出来れば自分の事は自分で出来る子がいいなと思っているんだけど。どう?」
「まぁ、出来る方ではないかしら。家事とか、結構好きよ」
「そう、良かった。あと、きゃあきゃあ騒がしい女は好きではないんだけど、君はそうでもなさそうだよね」
「そうね。あまり騒いだら疲れてしまうじゃない」
「……疲れる、ねぇ」
「だってやる事がたくさんあるんだもの。お掃除にお料理、お洋服がほつれたら繕うのも私。母さまや姉さまはアレもコレもと煩いし。いちいち騒いでいたら何も終わらないし、疲れるだけだし。何の意味もないわ」
「嫌ではないの? その生活」
「嫌ではないわ。基本的に家事は好きなのよ。小煩い人たちがいなければ楽にはなるだろうなとは思うけれど」
くすくすと楽しげな声を漏らしながら受けこたえるそのさまはとても可憐で、とても優雅だった。乗馬してパーティーに来るような突拍子もない事をする娘だが、きっと育ちは良いのだろう。もしかしたら、もとは貴族の出なのかもしれない。家では使用人のような生活をしているようだが、ドレスを綺麗に着こなす事も、軽やかに乗馬をする事も、そうでなければなかなかできない事だろう。それに、所作のひとつひとつに品を感じる。にじみ出るような品の良さは、付け焼刃では身に付かない。身に染みついたものだから自然に出すことが出来るのだ。
この人なら、愛することが出来るかもしれない。もちろん、今はまだ愛してなどいない。出会ったばかりなのだから当然だ。しかし、この少女は理想としていた条件にぴったりと当てはまる。しかも美しく、品の良い女性だ。求めていた以上に素晴らしい女性。きっと、彼女以上の人とはもう出会う事は出来ないだろう。
「決めた」
王子はとても楽しそうに、嬉しそうにぱん、と手を叩いて少女に向き直った。
「君さえよければ、僕と結婚してくれないかい?」
「お断りするわ」
にっこりと、少女は辞退した。
「私は別に貴方の事を愛している訳じゃないもの。それに、貴方と結婚なんかしたら母や姉の面倒は一体誰が見ると言うの? 他に使用人を雇ったとしても、あの我儘娘たちを御す事は難しいわよ? それにね、私はもともとこのパーティー自体を面倒だと思っていたの。参加するつもりなんて、さらさらなかったの。これっぽっちもなかったの。姉さまに言われて仕方なく、ここに来ているのだもの。きっと私以外の子の方が貴方のことを想っているだろうし、貴方も自分を想ってくれる人が相手の方が幸せなんじゃないかしら」
「それは困った。僕は別に愛してくれる人とか想ってくれる人を求めている訳じゃないんだよね。それに、他の人は大体が玉の輿狙いの守銭奴たちさ。金と名誉しか求めてないんだから。家族が心配ならうちの優秀な使用人をやるから、その辺は安心してよ。確かにこのパーティーは一応嫁探しなんて名目で開かれているし僕以外はそういう心積もりなんだろうけど、僕としては友達探しっていう感覚の方が強いんだよね。さっぱりすっきり付き合える、一緒に居て楽しいと思えるような友人。化粧と香水の悪臭を撒き散らしながら何も出来ないくせに威張って使用人にアレもコレもと要求しているような女を友人になんてしたくはないんだ。見ていてイライラするような奴なんて、傍に居て欲しくないだろ? その点、君は僕の理想とする友人像にぴったりと当てはまる。君以外の女性なんて考えられないんだけどね」
「――分かった」
少女は意外と押しの強い王子の言葉にこくりと頷く。そして、前向きに検討してみるわ、とほほ笑んだ。
「でも少し、考える時間が欲しいわ。だから、そうね……」
呟いて、少女は美しい靴を脱ぎ、その片方を王子に渡した。
「私を探し出して見せて。片方ずつの靴を持って、これを合わせる事が出来たら、そしたら、ちゃんと返事をするわ」
「分かった」
王子は硝子のように輝く靴を、片方だけ受けとった。そして、君は何を穿いて家に帰るの? と少女に声を掛けた。
「馬小屋に乗馬用のブーツを置いてあるの」
じゃあね、明日の料理の準備をしなくちゃならないから、と少女は笑ってお城を後にした。
時刻はちょうど十二時。
どこかで、鐘の音が高らかに響いていた。
3
あの王子と結婚をしたら。そしたら、私はどうなるのかしら。
少女はキャベツを刻みながら様々な事を考えていた。結婚をしたら、きっと料理も裁縫も私以外の誰かがやるのよね。させてはもらえないのかしら。ああ、でも王子は友人を探していると言っていたし、いくらかは自由にさせてもらえるかしら。お掃除とかもやらせてもらえると嬉しいのだけど。
切った野菜たちを鍋に入れ、煮立たせる。
「……もう少しお塩を入れた方がいいかしら」
味見をし、呟いた。今日の夕食はポトフとチキンのソテー、それからサラダにクロワッサン。バターをたっぷり使って焼き上げたクロワッサンはさくさくふわふわで、味見をしているうちに三つも消費してしまった。もうお腹はいっぱいだ。
少女は何が最善の選択かしら、と小さく唸る。正直なところ、結婚をしたとしても彼を愛することが出来るのかどうかはまだ分からなかった。しかし、良い友人にはなれそうだと、共に乗馬を楽しめる友人が出来るのはとても良いかもしれないと、なんとなく気持ちは揺れ動く。
「……取り敢えず、ご飯だわ」
ポトフもチキンのソテーもサラダもクロワッサンも、どれもとても良い出来だ。今日の料理もしっかりと楽しみ、少女はそれぞれの料理を美しく皿に盛り付けた。
少女はキャベツを刻みながら様々な事を考えていた。結婚をしたら、きっと料理も裁縫も私以外の誰かがやるのよね。させてはもらえないのかしら。ああ、でも王子は友人を探していると言っていたし、いくらかは自由にさせてもらえるかしら。お掃除とかもやらせてもらえると嬉しいのだけど。
切った野菜たちを鍋に入れ、煮立たせる。
「……もう少しお塩を入れた方がいいかしら」
味見をし、呟いた。今日の夕食はポトフとチキンのソテー、それからサラダにクロワッサン。バターをたっぷり使って焼き上げたクロワッサンはさくさくふわふわで、味見をしているうちに三つも消費してしまった。もうお腹はいっぱいだ。
少女は何が最善の選択かしら、と小さく唸る。正直なところ、結婚をしたとしても彼を愛することが出来るのかどうかはまだ分からなかった。しかし、良い友人にはなれそうだと、共に乗馬を楽しめる友人が出来るのはとても良いかもしれないと、なんとなく気持ちは揺れ動く。
「……取り敢えず、ご飯だわ」
ポトフもチキンのソテーもサラダもクロワッサンも、どれもとても良い出来だ。今日の料理もしっかりと楽しみ、少女はそれぞれの料理を美しく皿に盛り付けた。
*
「こちらに、この靴の片方を持った方はいらっしゃいませんか?」
王子は各国を回り、靴の持ち主を探していた。しかし、なかなか見つからない。あれから、もう一カ月が経過している。
何かヒントはないかと考えつつ、彼女の言葉に訛りはなかったため、地方は除外し、捜索範囲を狭める。取り敢えず、名前を聞いて置くべきだった、と初歩的なミスに溜め息を吐く。
「……思いの他近場だったりして」
地面に座り込み、呟いた。そしてもう一度溜め息を吐く。
「あら王子様、いらっしゃい」
「……え?」
顔を上げると、そこには探し求めていた一人の少女。
「思ったより、遅かったわねぇ」
「えぇー……」
両手に洗濯かごを持ち、三角巾にエプロン。零れた一房の髪が、太陽に照らされて金色に輝いている。汚れたエプロン姿も麗しい。ああ、一ケ月にも及ぶ苦労の為か、初めて出会った時より何倍も美しく思えるよ。
「洗濯中?」
「ええ。今日は天気が良いから」
絶好のお洗濯日和よ、と少女は満面の笑みを浮かべた。どうやらここは彼女の家の土地らしい。知らないうちに入り込んでしまっていたのか。
「ねぇ、今さら何だけどさあ」
「どうかしました?」
王子は眉を寄せ、少し困ったように笑って見せた。
「名前、教えてよ」
王子は各国を回り、靴の持ち主を探していた。しかし、なかなか見つからない。あれから、もう一カ月が経過している。
何かヒントはないかと考えつつ、彼女の言葉に訛りはなかったため、地方は除外し、捜索範囲を狭める。取り敢えず、名前を聞いて置くべきだった、と初歩的なミスに溜め息を吐く。
「……思いの他近場だったりして」
地面に座り込み、呟いた。そしてもう一度溜め息を吐く。
「あら王子様、いらっしゃい」
「……え?」
顔を上げると、そこには探し求めていた一人の少女。
「思ったより、遅かったわねぇ」
「えぇー……」
両手に洗濯かごを持ち、三角巾にエプロン。零れた一房の髪が、太陽に照らされて金色に輝いている。汚れたエプロン姿も麗しい。ああ、一ケ月にも及ぶ苦労の為か、初めて出会った時より何倍も美しく思えるよ。
「洗濯中?」
「ええ。今日は天気が良いから」
絶好のお洗濯日和よ、と少女は満面の笑みを浮かべた。どうやらここは彼女の家の土地らしい。知らないうちに入り込んでしまっていたのか。
「ねぇ、今さら何だけどさあ」
「どうかしました?」
王子は眉を寄せ、少し困ったように笑って見せた。
「名前、教えてよ」
*
「靴は持って来てくれた?」
「もちろん」
少女はくすくすと楽しげに笑いながら、貸して、と手を伸ばした。手渡された靴は相変わらず硝子のような輝きを放っていて、少女は、やっぱりいつ見ても美しいわ、と呟いた。
「私ね、ここではもうずぅーっと、『シンデレラ』って呼ばれているの。本当の名前は、忘れちゃったわ」
片方ずつの靴を揃えると、少女は汚れたエプロンと三角巾を外し、小さな足をそっと靴の中に収める。品良く散りばめられた幾つかの宝石が、きらきらと瞬いた。
「とても美しい名前だったような気もするのだけど、どうしてかしら、思い出せないのよね」
だから名前を教えてほしいと言われても教える事が出来ないのよね、と少女は笑った。
「名前を貰えるなら、貴方と結婚しても良いかなって、思ってる」
どうかしら? と少女は王子を見て笑った。王子は、静かに頷き、ほほ笑んだ。
「今まで、人にも物にも名前なんかつけた事はないから、僕のネーミングセンスには期待しないで欲しいのだけど」
呟き、王子は続けた。
「それでもいいなら、僕と結婚してほしいな」
「『シンデレラ』以外なら何でもいいわ」
互いに顔を見合わせ、にやりと口角を上げる。そして、二人は強く、握手した。
「もちろん」
少女はくすくすと楽しげに笑いながら、貸して、と手を伸ばした。手渡された靴は相変わらず硝子のような輝きを放っていて、少女は、やっぱりいつ見ても美しいわ、と呟いた。
「私ね、ここではもうずぅーっと、『シンデレラ』って呼ばれているの。本当の名前は、忘れちゃったわ」
片方ずつの靴を揃えると、少女は汚れたエプロンと三角巾を外し、小さな足をそっと靴の中に収める。品良く散りばめられた幾つかの宝石が、きらきらと瞬いた。
「とても美しい名前だったような気もするのだけど、どうしてかしら、思い出せないのよね」
だから名前を教えてほしいと言われても教える事が出来ないのよね、と少女は笑った。
「名前を貰えるなら、貴方と結婚しても良いかなって、思ってる」
どうかしら? と少女は王子を見て笑った。王子は、静かに頷き、ほほ笑んだ。
「今まで、人にも物にも名前なんかつけた事はないから、僕のネーミングセンスには期待しないで欲しいのだけど」
呟き、王子は続けた。
「それでもいいなら、僕と結婚してほしいな」
「『シンデレラ』以外なら何でもいいわ」
互いに顔を見合わせ、にやりと口角を上げる。そして、二人は強く、握手した。
4
その一・炊事、洗濯など家事をさせてくれる事。
その二・共に乗馬などを楽しむ事。
その三・馬の世話をさせてくれる事。
その四・母、姉たちの面倒を見れる使用人を用意する事。
その五・新しい名前を付けてくれる事。
その二・共に乗馬などを楽しむ事。
その三・馬の世話をさせてくれる事。
その四・母、姉たちの面倒を見れる使用人を用意する事。
その五・新しい名前を付けてくれる事。
少女が結婚の条件として提示したものは、なんとも、一般家庭の男性が喜びそうな内容だった。王子もすんなりと承諾、問題と思われた母親と二人の姉も、どうにかこうにか宥めすかしてあやして結婚を承諾させた。
「べ、別に寂しくなんかないんだからねっ!」
「あんたを選ぶなんて絶対どこか可笑しいわ。なんなら結婚止めて家に居たっていいのよ?」
「シンデレラが居なくなるのは清々するけど、王子と結婚っていうのは気に食わない! いつでも離婚して戻ってくると良いわ」
揃いも揃ってハンカチで目元を押さえ、子供のように頬を膨らまし、王子を睨みつけるその様は実に微笑ましい。少女が『三人娘』と称するそれは、実に言いえて妙というか、絶妙だった。
「べ、別に寂しくなんかないんだからねっ!」
「あんたを選ぶなんて絶対どこか可笑しいわ。なんなら結婚止めて家に居たっていいのよ?」
「シンデレラが居なくなるのは清々するけど、王子と結婚っていうのは気に食わない! いつでも離婚して戻ってくると良いわ」
揃いも揃ってハンカチで目元を押さえ、子供のように頬を膨らまし、王子を睨みつけるその様は実に微笑ましい。少女が『三人娘』と称するそれは、実に言いえて妙というか、絶妙だった。
斯くして、少女は王子と結婚しお姫様になり、王子は良い友人と良い妻を手に入れた。母親と二人の姉はしばらくの間ぐずぐずといじけていたが、それは三人だけの秘密である。
*
「ねえ、いつになったら名前くれるのよ! ねえ!」
「ちょっと待って、今考えてるから」
何かぶつぶつと呟きながら、王子は手元の本にかじりついていた。王子の手元と周囲には、名付けの為の沢山の本。少女も、遅い、早くしてと急かしながらも、とても楽しそうに微笑んでいた。
「ちょっと待って、今考えてるから」
何かぶつぶつと呟きながら、王子は手元の本にかじりついていた。王子の手元と周囲には、名付けの為の沢山の本。少女も、遅い、早くしてと急かしながらも、とても楽しそうに微笑んでいた。
少女と王子は、いつもでも、幸せに暮らしましたとさ。
おしまい