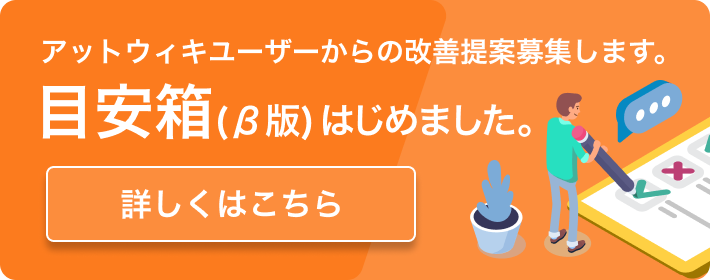月夜にワルツを
0
彼女はまるで、妖精のようだ。
蝋燭の炎と淡く差し込む月の光で明かりを取る、仄かに暗い部屋。広い室内には、二人しかいない住人で使うには大きすぎるテーブルと、幾つもの椅子。食卓に並ぶのは紅い薔薇。
その空間の中で、僕は愛しい女性を見つめる。そしてほぅとひとつ、感嘆の溜め息を吐いた。
透き通った、今にも消えてしまいそうなほど白くすべらかな肌に、触れれば壊れてしまいそうなほど細く、華奢な身体。絹糸のように光る銀色の髪に、アメジストか何か、宝石を嵌め込んだかのような深い紫の瞳……。
もっとも、とても幻想的な彼女の事を表すには、こんな言葉じゃちっとも足りないのだけど。絹糸も宝石も、彼女を表すには不相応。そんな陳腐な言葉じゃ表し切れないほど、本当であれば何かに例える事など出来ないくらい、彼女に見合う何かなど考えもつかないくらい、美しい。
僕は毎日、彼女の家にある温室から真っ赤な薔薇の花を摘みに行く。一輪一輪、丁寧に。ひとつひとつ棘を取って、彼女に捧げる。紅い薔薇の持つ言葉にわずかに期待し、想いを込めて捧げるのだ。
彼女は毎日その薔薇を見つめ、そして口に運んで行く。僕の想い人は今日も大きな月を見上げ、紅い薔薇を食べる。細く長い指先で一輪一輪摘まみ上げ、口に入れ、飲み下し、そして「足りない、足りない」とまた手を伸ばす。
「……僕の血を吸っても良いんだよ」
自分の首筋をとんとんと指先でたたきながら、僕は彼女に言った。
彼女は吸血鬼だ。
そして僕は、その僕(しもべ)。
僕は彼女の僕として、食料として、この広い屋敷に暮らす事を選んだ。しかし麗しき主はただ静かに首を振るばかりで、自ら望んだ役目を果たさせてはくれない。ネクタイを緩め、シャツのボタンを二つはずし、肌を晒す。そして再び自分の首筋を指先でたたきながら、「どうぞ?」と彼女の前に跪いた。
僕は出来る限り、彼女の傍にあり続けたいと願っている。だから、勧める。聞くところによると、吸血鬼に首筋から血を吸われると、その血を吸われた者も吸血鬼になるのだという。千年の命を持つ、吸血鬼に。
千年の命を持ち、彼女の傍で、永遠とも思えるような長い日々を過ごせたら。嗚呼、そうすることが出来たら一体どれだけ幸せだろう。
けれど、幾ら勧めても彼女はいつも左右に首を振るだけ。困ったような笑みを浮かべて僕の額に唇を当てる。ちゅ、と小さな音を立てて、そんな悲しいことを言わないで、と嘆くように呟くのだ。
「もし貴方を手に掛けたら、私は死ぬまで後悔する。人よりもずっと長い時間、後悔するの。……だから、お願い」
吸血鬼になりたいなんて、思わないで。
口にしなくても、言葉の続きが僕には分かる。悲しくなるくらい、彼女の声が聞こえてくる。
「……そう」
呟いて、僕はスーツのポケットの中から細いナイフを取り出し、自分の指先に傷を付けた。赤い線がゆっくりと滲みだし、ぷくりと、赤い珠が浮かんだ。零れ落ちてしまわないうちにと、僕はその指で彼女の唇をなぞる。
血の気の失せた唇が、僕の血で紅く色づいた。
綺麗な血色の花よりも、きっと僕の血の方がおいしいよ。紅い花も、紅い食べ物も、そんなものはただの気休め。本物の血の方が、僕の血の方が、きっときっとおいしいはずだよ。
「せめて、ここから血を飲んで」
じゃないと、君がまた倒れてしまう。初めて出会った時のように。
ふいと顔を背けようとする彼女の顎を押さえ、僕はもう一度その唇に血のあふれる指を押し付けた。
彼女の唇は何度触れても柔らかく、そしていつでも、少しかさついていた。
蝋燭の炎と淡く差し込む月の光で明かりを取る、仄かに暗い部屋。広い室内には、二人しかいない住人で使うには大きすぎるテーブルと、幾つもの椅子。食卓に並ぶのは紅い薔薇。
その空間の中で、僕は愛しい女性を見つめる。そしてほぅとひとつ、感嘆の溜め息を吐いた。
透き通った、今にも消えてしまいそうなほど白くすべらかな肌に、触れれば壊れてしまいそうなほど細く、華奢な身体。絹糸のように光る銀色の髪に、アメジストか何か、宝石を嵌め込んだかのような深い紫の瞳……。
もっとも、とても幻想的な彼女の事を表すには、こんな言葉じゃちっとも足りないのだけど。絹糸も宝石も、彼女を表すには不相応。そんな陳腐な言葉じゃ表し切れないほど、本当であれば何かに例える事など出来ないくらい、彼女に見合う何かなど考えもつかないくらい、美しい。
僕は毎日、彼女の家にある温室から真っ赤な薔薇の花を摘みに行く。一輪一輪、丁寧に。ひとつひとつ棘を取って、彼女に捧げる。紅い薔薇の持つ言葉にわずかに期待し、想いを込めて捧げるのだ。
彼女は毎日その薔薇を見つめ、そして口に運んで行く。僕の想い人は今日も大きな月を見上げ、紅い薔薇を食べる。細く長い指先で一輪一輪摘まみ上げ、口に入れ、飲み下し、そして「足りない、足りない」とまた手を伸ばす。
「……僕の血を吸っても良いんだよ」
自分の首筋をとんとんと指先でたたきながら、僕は彼女に言った。
彼女は吸血鬼だ。
そして僕は、その僕(しもべ)。
僕は彼女の僕として、食料として、この広い屋敷に暮らす事を選んだ。しかし麗しき主はただ静かに首を振るばかりで、自ら望んだ役目を果たさせてはくれない。ネクタイを緩め、シャツのボタンを二つはずし、肌を晒す。そして再び自分の首筋を指先でたたきながら、「どうぞ?」と彼女の前に跪いた。
僕は出来る限り、彼女の傍にあり続けたいと願っている。だから、勧める。聞くところによると、吸血鬼に首筋から血を吸われると、その血を吸われた者も吸血鬼になるのだという。千年の命を持つ、吸血鬼に。
千年の命を持ち、彼女の傍で、永遠とも思えるような長い日々を過ごせたら。嗚呼、そうすることが出来たら一体どれだけ幸せだろう。
けれど、幾ら勧めても彼女はいつも左右に首を振るだけ。困ったような笑みを浮かべて僕の額に唇を当てる。ちゅ、と小さな音を立てて、そんな悲しいことを言わないで、と嘆くように呟くのだ。
「もし貴方を手に掛けたら、私は死ぬまで後悔する。人よりもずっと長い時間、後悔するの。……だから、お願い」
吸血鬼になりたいなんて、思わないで。
口にしなくても、言葉の続きが僕には分かる。悲しくなるくらい、彼女の声が聞こえてくる。
「……そう」
呟いて、僕はスーツのポケットの中から細いナイフを取り出し、自分の指先に傷を付けた。赤い線がゆっくりと滲みだし、ぷくりと、赤い珠が浮かんだ。零れ落ちてしまわないうちにと、僕はその指で彼女の唇をなぞる。
血の気の失せた唇が、僕の血で紅く色づいた。
綺麗な血色の花よりも、きっと僕の血の方がおいしいよ。紅い花も、紅い食べ物も、そんなものはただの気休め。本物の血の方が、僕の血の方が、きっときっとおいしいはずだよ。
「せめて、ここから血を飲んで」
じゃないと、君がまた倒れてしまう。初めて出会った時のように。
ふいと顔を背けようとする彼女の顎を押さえ、僕はもう一度その唇に血のあふれる指を押し付けた。
彼女の唇は何度触れても柔らかく、そしていつでも、少しかさついていた。
1
「――私、吸血鬼なの」
『ユウガオ』と名乗るその小柄な女性は、そう言ってほほ笑んだ。可笑しな名前だと僕は思った。あまり、耳に馴染まない。そう言うと、彼女はわずかに目を伏せて続けた。
「 “a bottle gourd ”の和名なの。だけど“ユウガオ”の方が、響きが綺麗でしょ? ……昔は他の名前だったのだけど、そっちのはどうしても気に入らなくて、だいぶ昔に捨てちゃった」
街から家に帰る途中、近道をしようと入った路地裏で人を拾った。真っ青な唇で、息をしているのが不思議なくらい弱々しく、細い身体を震わせていた。人目を避けるように身体を小さく丸め、倒れていた。
なんだか猫みたいだ。
不謹慎にそんなことを思って、その女性を家に連れ帰りベッドで寝かせた。目を覚ました時、何か食べたいものはあるかと聞いたら彼女は血が飲みたいと言った。良ければ、貴方の血を飲ませて欲しいと。
可笑しな女。
だけど、自分の事なんかどうでもよくて、誰かの為になるのなら自分の血を与えるのも良いかもしれないなんて、そんなことも思った。
だから、僕は果物ナイフで自分の指に傷をつけ、彼女に与えた。
「……綺麗な色」
呟いて、彼女は僕の指を咥えた。傷口を抉るように舌を動かし、歯を食い込ませる。指先の痛みと酷く官能的なその眺めに、僕は思わず喉を鳴らした。
このまま死んでしまっても良いかもしれないな、と思う。血を全部吸われたら、このまま死ねるんだよな、などと考えた。それも、良いかもしれない。
「……本当の名前、」
ああ、でも、一つだけ聞いておこう。僕の命を誰に捧げるのかくらい、聞いても良いだろう。
「ん?」
僕の指から口を離し、彼女はわずかに首を傾げた。
「君の前の名前、聞いても良い?」
「そんな面白い名前じゃないけど」
いいから、と僕は彼女の髪を指で梳いた。
「――リナリア」
言って、彼女は頭の上の僕の手を払った。
「花言葉が、嫌いなの。“幻想 ”という花言葉。何から何まで否定されているような、全てが偽物なんだとでも言われているような気になるから。だから、この名前は嫌い」
綺麗な名前なのに。美しい彼女に、美しい花の名前。しっくりと馴染む、綺麗な名前なのに。もったいないと思いながら、もうひとつ、疑問を投げかける。
「……ユウガオは?」
「安らかな死」
良い名前でしょう? とでも言うように、彼女は笑った。そして僕の服の袖を勝手に上げ、そこに牙を付きたてた。ぢゅっ、と液体をすする音がした。
「足りなかった?」
「全然足りない」
僕の腕を咥えたまま、器用に喋る。
「君はどうして倒れていたの?」
「死にたくて、絶食してた」
「じゃあ、どうして僕の血を吸うの?」
「空腹がつらくて、耐えられなくなったから」
「ふぅん」
静かに頷いて僕は彼女の髪をもう一度梳いた。
「まぁ、そういう日もあるよね」
「うん。そういう日もある」
死にたい日だってあるし、生きたい日だってある。そう言って、彼女は僕の腕から口を離した。
「どうして、死にたかったの?」
「……人間がね、好きなの。無知で愚かで、見ていて飽きない」
「それだけなら、僕は人嫌いになっていると思うけど」
「……そう? でも、好きなの。人の血を吸うことに、どうしてかとても勇気が居るの。本当に貰っていいのだろうか、このまま吸いつくして仕舞っていいのだろうか、この人には守るべき家族が居るのではないだろうか、この人を仲間にしたら私はどうなるのだろうか、この人に恨まれるのではないだろうか、この人の家族に恨まれるのではないだろうか。……そんな風に、色々なことを考えてしまう」
彼女はきっと、とても優しいのだ。その人の人生を考えすぎるあまり、手が出せなくなってしまうのだろう。ああ、なんて愛おしい。
「……いや、人が好き、な訳ではないのかも。自分の身を守る事を考え出すと、何も出来なくなるだけ、かな」
その所為で栄養失調になっていたらただの笑い話だけど。自嘲するように彼女は言った。
「違う、と思う」
心の声が、言葉に出ていた。
「君は、優しすぎるだけだよ。優しすぎて、その人の事を考え過ぎて、手が出せなくなっているんだ」
「ものは言いようね。どんなふうに解釈してくれても構わないけど、貴方は、私が貴方の意見を聞いたからと言って考えを変える訳ではないということも理解しておいた方がいい」
「そうだろうね。でも、言うか言わないかで君の僕に対する見方は少し変わるかもしれないよ? まあ、良い方にも、悪い方にもだけど」
彼女は、一瞬ぽかんと口を開き、可笑しな人ねと言ってくすくすと笑った。私の事を恐れない、見ず知らずの、人では無いものに食事を与え、寝床を与え、話し相手にもなってくれる。普通の人間ではないみたい。そう言って、まっ白な両手で僕の頬をそっと包んだ。
「普通ではない、っていうのは、当たりかもしれない」
「でしょうね」
微笑み、僕を見つめる。深い紫の瞳が、綺麗だと思った。まるで、アメジストか何かをはめ込んだみたいで、とても綺麗で、目を離せなくなった。
「……ねえ、貴方の名前を教えて?」
そう言って、彼女は細い指先で僕の唇をなぞった。それは静かで、とても優しい手付きだった。
『ユウガオ』と名乗るその小柄な女性は、そう言ってほほ笑んだ。可笑しな名前だと僕は思った。あまり、耳に馴染まない。そう言うと、彼女はわずかに目を伏せて続けた。
「 “a bottle gourd ”の和名なの。だけど“ユウガオ”の方が、響きが綺麗でしょ? ……昔は他の名前だったのだけど、そっちのはどうしても気に入らなくて、だいぶ昔に捨てちゃった」
街から家に帰る途中、近道をしようと入った路地裏で人を拾った。真っ青な唇で、息をしているのが不思議なくらい弱々しく、細い身体を震わせていた。人目を避けるように身体を小さく丸め、倒れていた。
なんだか猫みたいだ。
不謹慎にそんなことを思って、その女性を家に連れ帰りベッドで寝かせた。目を覚ました時、何か食べたいものはあるかと聞いたら彼女は血が飲みたいと言った。良ければ、貴方の血を飲ませて欲しいと。
可笑しな女。
だけど、自分の事なんかどうでもよくて、誰かの為になるのなら自分の血を与えるのも良いかもしれないなんて、そんなことも思った。
だから、僕は果物ナイフで自分の指に傷をつけ、彼女に与えた。
「……綺麗な色」
呟いて、彼女は僕の指を咥えた。傷口を抉るように舌を動かし、歯を食い込ませる。指先の痛みと酷く官能的なその眺めに、僕は思わず喉を鳴らした。
このまま死んでしまっても良いかもしれないな、と思う。血を全部吸われたら、このまま死ねるんだよな、などと考えた。それも、良いかもしれない。
「……本当の名前、」
ああ、でも、一つだけ聞いておこう。僕の命を誰に捧げるのかくらい、聞いても良いだろう。
「ん?」
僕の指から口を離し、彼女はわずかに首を傾げた。
「君の前の名前、聞いても良い?」
「そんな面白い名前じゃないけど」
いいから、と僕は彼女の髪を指で梳いた。
「――リナリア」
言って、彼女は頭の上の僕の手を払った。
「花言葉が、嫌いなの。“幻想 ”という花言葉。何から何まで否定されているような、全てが偽物なんだとでも言われているような気になるから。だから、この名前は嫌い」
綺麗な名前なのに。美しい彼女に、美しい花の名前。しっくりと馴染む、綺麗な名前なのに。もったいないと思いながら、もうひとつ、疑問を投げかける。
「……ユウガオは?」
「安らかな死」
良い名前でしょう? とでも言うように、彼女は笑った。そして僕の服の袖を勝手に上げ、そこに牙を付きたてた。ぢゅっ、と液体をすする音がした。
「足りなかった?」
「全然足りない」
僕の腕を咥えたまま、器用に喋る。
「君はどうして倒れていたの?」
「死にたくて、絶食してた」
「じゃあ、どうして僕の血を吸うの?」
「空腹がつらくて、耐えられなくなったから」
「ふぅん」
静かに頷いて僕は彼女の髪をもう一度梳いた。
「まぁ、そういう日もあるよね」
「うん。そういう日もある」
死にたい日だってあるし、生きたい日だってある。そう言って、彼女は僕の腕から口を離した。
「どうして、死にたかったの?」
「……人間がね、好きなの。無知で愚かで、見ていて飽きない」
「それだけなら、僕は人嫌いになっていると思うけど」
「……そう? でも、好きなの。人の血を吸うことに、どうしてかとても勇気が居るの。本当に貰っていいのだろうか、このまま吸いつくして仕舞っていいのだろうか、この人には守るべき家族が居るのではないだろうか、この人を仲間にしたら私はどうなるのだろうか、この人に恨まれるのではないだろうか、この人の家族に恨まれるのではないだろうか。……そんな風に、色々なことを考えてしまう」
彼女はきっと、とても優しいのだ。その人の人生を考えすぎるあまり、手が出せなくなってしまうのだろう。ああ、なんて愛おしい。
「……いや、人が好き、な訳ではないのかも。自分の身を守る事を考え出すと、何も出来なくなるだけ、かな」
その所為で栄養失調になっていたらただの笑い話だけど。自嘲するように彼女は言った。
「違う、と思う」
心の声が、言葉に出ていた。
「君は、優しすぎるだけだよ。優しすぎて、その人の事を考え過ぎて、手が出せなくなっているんだ」
「ものは言いようね。どんなふうに解釈してくれても構わないけど、貴方は、私が貴方の意見を聞いたからと言って考えを変える訳ではないということも理解しておいた方がいい」
「そうだろうね。でも、言うか言わないかで君の僕に対する見方は少し変わるかもしれないよ? まあ、良い方にも、悪い方にもだけど」
彼女は、一瞬ぽかんと口を開き、可笑しな人ねと言ってくすくすと笑った。私の事を恐れない、見ず知らずの、人では無いものに食事を与え、寝床を与え、話し相手にもなってくれる。普通の人間ではないみたい。そう言って、まっ白な両手で僕の頬をそっと包んだ。
「普通ではない、っていうのは、当たりかもしれない」
「でしょうね」
微笑み、僕を見つめる。深い紫の瞳が、綺麗だと思った。まるで、アメジストか何かをはめ込んだみたいで、とても綺麗で、目を離せなくなった。
「……ねえ、貴方の名前を教えて?」
そう言って、彼女は細い指先で僕の唇をなぞった。それは静かで、とても優しい手付きだった。
†
彼は、『カイ』と名乗った。
癖の強い栗色の髪に、ブルーグレーの瞳。綺麗な弧を描く眉に、常に笑みの形を作る薄い唇。随分と女性的な顔立ちをした人だと思った。それに、彼の穏やかな笑みやテノールの声は、とても心地がいい。
彼は少し前までピアニストとして活動していたらしい。言われてその指先を見てみると、なるほどと思うような、ピアニストらしい、長くてしなやかな指をしていた。まだ若いのに、今は辞めてしまったのかと聞けば、彼は手に怪我をして弾けなくなったんだ、と答えた。
「そこそこにね、有名にはなっていたんだよ。“ザントマン”なんて呼ばれて」
「ザントマン?」
「眠りの妖精。僕の弾くピアノを聴くと、どうも眠たくなるみたい」
それは喜ばしい事なのかと問うと、彼はそれなりに、と答えた。
「前にね、不眠症の王様の為にピアノを弾いてくれないかって依頼が来たことがあるんだ。弾いたら、王様は眠ってくれたよ。とても気持ちよさそうに」
じゃあ、ピアノを辞めてしまったのは残念ねと声を掛けると、彼は実はそうでもないんだと答えた。
訳がわからない。
「元々、ピアノなんかどうでも良かったんだ。生活の術として考えられるものの中でピアノが一番手っ取り早かった。簡単なんだ、指の運びを覚えるだけ。指の運びを考えるだけ。ただ指を動かすだけだから、誰かに何かを与えようとして弾いている訳ではないから」
だからきっと、皆眠たくなるんだろうね、と彼は笑った。
「良く分からないのだけど」
「ようするにさ、ピアニストって職業に何の未練もないのさ。だから腕に怪我をした時、何の躊躇いもなく『じゃあピアノは辞めよう』って考えられたんだ。躊躇いなく指に傷をつけられるんだ。もとより、僕のピアノをちゃんと聞いている人なんていない訳だしね」
何せ僕はザントマンだからね。そう言って、彼は笑った。不思議なくらい、綺麗な笑みを浮かべていた。
「美しすぎるものは理解されるのに時間が掛かるもの。眠りを誘う貴方のピアノも、そういう類のものだったのかもしれない」
「分からないよ。僕は自分のピアノを聴く側に回ったことなんかないんだから」
可笑しな人。
だけど、とても寂しそうに言葉を紡ぐ人。
霞んだ空色の瞳が、とても穏やかに微笑んでいた。
「……そうね」
霞んだ空色の瞳がとても穏やかに微笑んでいて、今にも雨が降りそうだと、そう思った。
「貴方の血、とても美味しい」
「それは良かった」
「また御馳走になりに来ても良い?」
「いつでもどうぞ」
こうして、私たちの関係が始まった。
癖の強い栗色の髪に、ブルーグレーの瞳。綺麗な弧を描く眉に、常に笑みの形を作る薄い唇。随分と女性的な顔立ちをした人だと思った。それに、彼の穏やかな笑みやテノールの声は、とても心地がいい。
彼は少し前までピアニストとして活動していたらしい。言われてその指先を見てみると、なるほどと思うような、ピアニストらしい、長くてしなやかな指をしていた。まだ若いのに、今は辞めてしまったのかと聞けば、彼は手に怪我をして弾けなくなったんだ、と答えた。
「そこそこにね、有名にはなっていたんだよ。“ザントマン”なんて呼ばれて」
「ザントマン?」
「眠りの妖精。僕の弾くピアノを聴くと、どうも眠たくなるみたい」
それは喜ばしい事なのかと問うと、彼はそれなりに、と答えた。
「前にね、不眠症の王様の為にピアノを弾いてくれないかって依頼が来たことがあるんだ。弾いたら、王様は眠ってくれたよ。とても気持ちよさそうに」
じゃあ、ピアノを辞めてしまったのは残念ねと声を掛けると、彼は実はそうでもないんだと答えた。
訳がわからない。
「元々、ピアノなんかどうでも良かったんだ。生活の術として考えられるものの中でピアノが一番手っ取り早かった。簡単なんだ、指の運びを覚えるだけ。指の運びを考えるだけ。ただ指を動かすだけだから、誰かに何かを与えようとして弾いている訳ではないから」
だからきっと、皆眠たくなるんだろうね、と彼は笑った。
「良く分からないのだけど」
「ようするにさ、ピアニストって職業に何の未練もないのさ。だから腕に怪我をした時、何の躊躇いもなく『じゃあピアノは辞めよう』って考えられたんだ。躊躇いなく指に傷をつけられるんだ。もとより、僕のピアノをちゃんと聞いている人なんていない訳だしね」
何せ僕はザントマンだからね。そう言って、彼は笑った。不思議なくらい、綺麗な笑みを浮かべていた。
「美しすぎるものは理解されるのに時間が掛かるもの。眠りを誘う貴方のピアノも、そういう類のものだったのかもしれない」
「分からないよ。僕は自分のピアノを聴く側に回ったことなんかないんだから」
可笑しな人。
だけど、とても寂しそうに言葉を紡ぐ人。
霞んだ空色の瞳が、とても穏やかに微笑んでいた。
「……そうね」
霞んだ空色の瞳がとても穏やかに微笑んでいて、今にも雨が降りそうだと、そう思った。
「貴方の血、とても美味しい」
「それは良かった」
「また御馳走になりに来ても良い?」
「いつでもどうぞ」
こうして、私たちの関係が始まった。
2
「――彼女は僕の主だよ」
ユウガオが僕の家に来るようになってから、友人たちに綺麗な人を見つけたなと言われるようになった。
恋人か? いや、違うな。友人かい? それも、違う。ならば、何? 決まっている。僕の、主さ。
友人たちは僕を見て、顔を見合わせ帰っていく。ん? 彼ら、『友人』なのかな? 取り敢えず一緒に居る事は多いけど、別に一緒に居なくても良いし、居ても居なくてもという感じだけど。まぁ、そんなことはどうでも良い。
取り敢えず、僕たちの関係を表す言葉として一番しっくりと来るのは、『主』と、『僕(しもべ)』。
主の居ない生活? 無理だ。考えられない。彼女が僕の所に来た時、僕はとても幸せなのだ。それこそ、彼女のためならば生きてもいいとさえ思えるほどに。
彼女との時間。それはまるで精神を雁字搦(がんじがら)めにされているようで、繋がれているようで、とても心地がいい。彼女が来るたび腕に残していく傷跡が、僕を甘美な世界に連れて行ってくれる。
ああ、僕はあまりにも、彼女に囚われ過ぎている。
「――じゃあ、お前の主はわざわざお前の為に此処まで来ているのかい?」
僕と彼女の関係を聞いて、そう言った男が居た。確かに。これは、可笑しい、かな? まぁ、仕方ない。僕は彼女が何処に住んでいるのかも何をしているのかも知らないのだから。彼女は僕に、何も教えてはくれないのだから。僕が聞かないからかもしれないが、なんとなく、そういう話は彼女から聞きたい。
彼女は月に二、三回ほどの頻度で僕の家に来る。いつもげっそりとやつれて、今にも死にそうな顔をして。また何も食べないでいたんだな、と僕は毎回無言のまま彼女の頬を撫で、自分の腕を差し出すのだ。
「……カイは、とても綺麗な血をしている」
「美味しいの?」
「とても」
僕の腕に牙を突き刺したまま、彼女は器用に話す。
時折、ぢゅっ、という音と共に血を吸い上げ、零れ落ちそうになった血を真っ赤な舌でべろりとなめ上げる。彼女の食事風景は酷く官能的で、僕はいつも喉を鳴らしてしまう。
「ねえ、ユウガオ?」
「ん?」
血を啜りながら、僕を見た。
「僕を、君の所に連れて行ってくれないかい?」
ユウガオが僕の家に来るようになってから、友人たちに綺麗な人を見つけたなと言われるようになった。
恋人か? いや、違うな。友人かい? それも、違う。ならば、何? 決まっている。僕の、主さ。
友人たちは僕を見て、顔を見合わせ帰っていく。ん? 彼ら、『友人』なのかな? 取り敢えず一緒に居る事は多いけど、別に一緒に居なくても良いし、居ても居なくてもという感じだけど。まぁ、そんなことはどうでも良い。
取り敢えず、僕たちの関係を表す言葉として一番しっくりと来るのは、『主』と、『僕(しもべ)』。
主の居ない生活? 無理だ。考えられない。彼女が僕の所に来た時、僕はとても幸せなのだ。それこそ、彼女のためならば生きてもいいとさえ思えるほどに。
彼女との時間。それはまるで精神を雁字搦(がんじがら)めにされているようで、繋がれているようで、とても心地がいい。彼女が来るたび腕に残していく傷跡が、僕を甘美な世界に連れて行ってくれる。
ああ、僕はあまりにも、彼女に囚われ過ぎている。
「――じゃあ、お前の主はわざわざお前の為に此処まで来ているのかい?」
僕と彼女の関係を聞いて、そう言った男が居た。確かに。これは、可笑しい、かな? まぁ、仕方ない。僕は彼女が何処に住んでいるのかも何をしているのかも知らないのだから。彼女は僕に、何も教えてはくれないのだから。僕が聞かないからかもしれないが、なんとなく、そういう話は彼女から聞きたい。
彼女は月に二、三回ほどの頻度で僕の家に来る。いつもげっそりとやつれて、今にも死にそうな顔をして。また何も食べないでいたんだな、と僕は毎回無言のまま彼女の頬を撫で、自分の腕を差し出すのだ。
「……カイは、とても綺麗な血をしている」
「美味しいの?」
「とても」
僕の腕に牙を突き刺したまま、彼女は器用に話す。
時折、ぢゅっ、という音と共に血を吸い上げ、零れ落ちそうになった血を真っ赤な舌でべろりとなめ上げる。彼女の食事風景は酷く官能的で、僕はいつも喉を鳴らしてしまう。
「ねえ、ユウガオ?」
「ん?」
血を啜りながら、僕を見た。
「僕を、君の所に連れて行ってくれないかい?」
†
『主』と、『僕』。
多分、これが私たちの関係を表す言葉として、一番適切なものだろうと思う。
綺麗な血、美味しい血。悲しい瞳、柔らかな髪。
私は、彼に囚われ過ぎている。ああ、こんなにも愛しいと思ったのは何時振りだろう。何年も、何百年も、忘れていた。
小動物を捕まえて血を飲んでも、最近は身体が受け付けない。この間も一度、人を襲って血を飲んでみたけれど、その場で吐き出してしまった。
かつて、この血を吸うという行為は人との主従契約であった。人を仲間として引き込み、僕として降(くだ)す為の行為であった。ああ、きっと、結んでしまったのだ。彼との主従契約を。選んでしまったのだ、彼の僕として降る事を。
「――ねえ、ユウガオ?」
静かに紡がれる頭上の声に、私は小さく呻いて返事を返した。
「僕を、君の所に連れて行ってくれないかい?」
ああ、そんな、断れるわけがないのに。貴方の言葉を、主の言葉を、どうして断る事が出来ようか。主と共に在る事を許されたこの喜び。断ること等、出来るわけがない。
「……もちろん」
「良かった」
心底安心したような声に、私は彼の腕から口を離し、その頬に口付をした。私が貴方を拒む訳がない。その想いをこめて、口付をした。
多分、これが私たちの関係を表す言葉として、一番適切なものだろうと思う。
綺麗な血、美味しい血。悲しい瞳、柔らかな髪。
私は、彼に囚われ過ぎている。ああ、こんなにも愛しいと思ったのは何時振りだろう。何年も、何百年も、忘れていた。
小動物を捕まえて血を飲んでも、最近は身体が受け付けない。この間も一度、人を襲って血を飲んでみたけれど、その場で吐き出してしまった。
かつて、この血を吸うという行為は人との主従契約であった。人を仲間として引き込み、僕として降(くだ)す為の行為であった。ああ、きっと、結んでしまったのだ。彼との主従契約を。選んでしまったのだ、彼の僕として降る事を。
「――ねえ、ユウガオ?」
静かに紡がれる頭上の声に、私は小さく呻いて返事を返した。
「僕を、君の所に連れて行ってくれないかい?」
ああ、そんな、断れるわけがないのに。貴方の言葉を、主の言葉を、どうして断る事が出来ようか。主と共に在る事を許されたこの喜び。断ること等、出来るわけがない。
「……もちろん」
「良かった」
心底安心したような声に、私は彼の腕から口を離し、その頬に口付をした。私が貴方を拒む訳がない。その想いをこめて、口付をした。
3
僕とユウガオの生活が始まった。
僕は毎日三回、温室へ真っ赤な薔薇の花を摘みに行く。血は飲みたくないと、毎日ぐずる主の為に。真っ赤な薔薇。綺麗な血の色だと、彼女は笑う。
真っ赤なものを、彼女は次々と口に運ぶ。
気休めだと言いながら、これで生きていくことが出来ればいいのにと笑う。ヴァンパイアには、血液が必要だ。どうしてなのか良く分からないが、人の血液からでなければ栄養を摂取できないのだという。なのに、彼女は要らないという。極力、別なもので補おうとする。夕食の時、僕は彼女にこう問いかけた。
「どうして、血を拒むの? 生きるのに必要なものなら、受け入れないと」
「……そうね。人が私と同じ形の生き物でなければ受け入れられたかもしれない」
囁くように紡がれる言葉に、僕は少しだけ眉を寄せた。
「今まで、君はどうしていたの? これまで生きていたなら、血を飲んできたということだろう?」
「その辺で兎や何かを捕まえてきて血を吸ってた。……でも、やっぱり人の血でないと身体が持たないから、たまに人を襲って、少しだけ血を貰っていたの。薬で眠らせて、腕とかからね」
首筋からじゃ、人ではなくなってしまうから。
そう続けて、彼女は薔薇の花をもう一輪口に運ぶ。花弁が一枚、ひらりと落ちた。僕はそれを拾い上げ、自分の口に運んでみる。不味い。
「やっぱり、僕の血を飲みなよ」
いっそ、喰らい尽くしてくれればいいのに。血も肉も、この身体全部、何もかも貪り尽くして、一緒にしてくれればいいのに。そんな事を思いながら、僕は自分の首筋を人差し指でとんとんと叩く。
「あまり吸いすぎると貴方が死んでしまう。……他の人のはもう、身体が受け付けないのに」
その呟きに、思わず笑ってしまった。
まるで、貴方がいなければ生きられないとでも言われているようで、酷く依存的な告白を受けているようで、思わず、笑ってしまった。
彼女は“食料”として僕を見ているだけなのに。
依存しているのは僕なのに。
腕に残る傷跡を見る度、腕に増える傷跡を見る度、癒えていく傷跡を見る度、その度にここから離れられなくなっている。
腕の傷跡は、彼女との関係を証明するもの。増えた傷跡は、彼女との関係が増えた証。癒えていく傷跡は、ここが現実の世界であると証明するもの。
全部ぜんぶ、僕のもの。
想う度、ここから離れられなくなっている。
まあ、もともと離れる気なんかないけれど。
「ねえ、カイ?」
綺麗なソプラノの声。それに、何? と一言答える。
「……」
「……ユウガオ?」
僕の名を呼んだきり、彼女は黙る。だから、彼女の名を呼んでみた。ユウガオ、……ユウガオ?
二度、三度。でも、彼女はただ左右に首を振った。そして、何でもないと微笑んだ。
僕は毎日三回、温室へ真っ赤な薔薇の花を摘みに行く。血は飲みたくないと、毎日ぐずる主の為に。真っ赤な薔薇。綺麗な血の色だと、彼女は笑う。
真っ赤なものを、彼女は次々と口に運ぶ。
気休めだと言いながら、これで生きていくことが出来ればいいのにと笑う。ヴァンパイアには、血液が必要だ。どうしてなのか良く分からないが、人の血液からでなければ栄養を摂取できないのだという。なのに、彼女は要らないという。極力、別なもので補おうとする。夕食の時、僕は彼女にこう問いかけた。
「どうして、血を拒むの? 生きるのに必要なものなら、受け入れないと」
「……そうね。人が私と同じ形の生き物でなければ受け入れられたかもしれない」
囁くように紡がれる言葉に、僕は少しだけ眉を寄せた。
「今まで、君はどうしていたの? これまで生きていたなら、血を飲んできたということだろう?」
「その辺で兎や何かを捕まえてきて血を吸ってた。……でも、やっぱり人の血でないと身体が持たないから、たまに人を襲って、少しだけ血を貰っていたの。薬で眠らせて、腕とかからね」
首筋からじゃ、人ではなくなってしまうから。
そう続けて、彼女は薔薇の花をもう一輪口に運ぶ。花弁が一枚、ひらりと落ちた。僕はそれを拾い上げ、自分の口に運んでみる。不味い。
「やっぱり、僕の血を飲みなよ」
いっそ、喰らい尽くしてくれればいいのに。血も肉も、この身体全部、何もかも貪り尽くして、一緒にしてくれればいいのに。そんな事を思いながら、僕は自分の首筋を人差し指でとんとんと叩く。
「あまり吸いすぎると貴方が死んでしまう。……他の人のはもう、身体が受け付けないのに」
その呟きに、思わず笑ってしまった。
まるで、貴方がいなければ生きられないとでも言われているようで、酷く依存的な告白を受けているようで、思わず、笑ってしまった。
彼女は“食料”として僕を見ているだけなのに。
依存しているのは僕なのに。
腕に残る傷跡を見る度、腕に増える傷跡を見る度、癒えていく傷跡を見る度、その度にここから離れられなくなっている。
腕の傷跡は、彼女との関係を証明するもの。増えた傷跡は、彼女との関係が増えた証。癒えていく傷跡は、ここが現実の世界であると証明するもの。
全部ぜんぶ、僕のもの。
想う度、ここから離れられなくなっている。
まあ、もともと離れる気なんかないけれど。
「ねえ、カイ?」
綺麗なソプラノの声。それに、何? と一言答える。
「……」
「……ユウガオ?」
僕の名を呼んだきり、彼女は黙る。だから、彼女の名を呼んでみた。ユウガオ、……ユウガオ?
二度、三度。でも、彼女はただ左右に首を振った。そして、何でもないと微笑んだ。
†
「ねえ、カイ?」
「何?」
柔らかに笑む彼の目に、一瞬見惚れた。
「……ユウガオ?」
言葉が、出てこなかった。二度、三度、彼は私の名を呼ぶ。穏やかなテノール。優しい声に、私は目を閉じて左右に首を振った。
……この人は、知っているのだろうか。私がどれだけの年月を生きてきたのか。いや、知らないだろう。教えていないのだから、当然だ。
私はもう、何百年も生きてきた。
なのに、彼は私と同じになりたいと言う。ああ、彼は分かっているのだろうか。もし私と同じになったら、私が死んだ後、何百年もひとりで生きなければいけないのだということを。
人の生と比べたら、私はまだ、とても長い年月を生きる事が出来る。だけど、吸血鬼としての命はもう半分以上が終わっているのだ。
ああ、早く、気付いてくれればいいのに。一言、聞いてくれればいいのに。
薔薇を口に運びながら、ただひたすらに彼を想う。
想っても、考えても空しいだけなのに。
私は何百年も生きてきた。何百年も生きて、色々な物を見てきた。色々な事を知った。色々な事をした。
なのに、何も出来ない。
私は今までどうやって生きてきたのだろう。
たったひとりの人間に、私はこんなにも囚われている。彼が死んだら、私は一体どうやって生きていくのだろう。
「……ユウガオ?」
頬に、ひやりとした手のひらが添えられた。彼の手は、気持ちいい。その手に自分の手を添えると、彼は目を細め、細い眉をわずかに寄せた。
「泣いているように見えた」
優しい瞳は、相変わらず。何かあった? と心彼は配そうに首をかしげる。
「何でもない」
彼の目を見ている事が出来なかった。だから彼の手を振り払い、窓の外に視線をそらす。まぁるい月が、空に居た。
「……なんて、綺麗」
「月?」
無言で、頷く。
だけど、あまりにも綺麗で、綺麗過ぎて、なんだか、耐えられなくなった。彼の目も、空の月も、見ていると狂ってしまいそう。ねえ、今にも壊れてしまいそう。崩れてしまいそう。
「――ユウガオ」
その声に、ゆるりと彼を見る。
「ピアノの、レコードがあるんだ。一緒に聞かない?」
静かに、頷いた。
優しい瞳も、優しい声も、相変わらず。だけどやっぱり直視することは出来なくて、私の視線は彼のスーツの胸元辺りを行き来する。ふわふわと焦点の定まらない視線。彼は私の髪を二、三度撫でて、ちょっと待っててねと部屋を後にした。
その後ろ姿にでさえ、私はぼんやりと、見惚れていた。
「何?」
柔らかに笑む彼の目に、一瞬見惚れた。
「……ユウガオ?」
言葉が、出てこなかった。二度、三度、彼は私の名を呼ぶ。穏やかなテノール。優しい声に、私は目を閉じて左右に首を振った。
……この人は、知っているのだろうか。私がどれだけの年月を生きてきたのか。いや、知らないだろう。教えていないのだから、当然だ。
私はもう、何百年も生きてきた。
なのに、彼は私と同じになりたいと言う。ああ、彼は分かっているのだろうか。もし私と同じになったら、私が死んだ後、何百年もひとりで生きなければいけないのだということを。
人の生と比べたら、私はまだ、とても長い年月を生きる事が出来る。だけど、吸血鬼としての命はもう半分以上が終わっているのだ。
ああ、早く、気付いてくれればいいのに。一言、聞いてくれればいいのに。
薔薇を口に運びながら、ただひたすらに彼を想う。
想っても、考えても空しいだけなのに。
私は何百年も生きてきた。何百年も生きて、色々な物を見てきた。色々な事を知った。色々な事をした。
なのに、何も出来ない。
私は今までどうやって生きてきたのだろう。
たったひとりの人間に、私はこんなにも囚われている。彼が死んだら、私は一体どうやって生きていくのだろう。
「……ユウガオ?」
頬に、ひやりとした手のひらが添えられた。彼の手は、気持ちいい。その手に自分の手を添えると、彼は目を細め、細い眉をわずかに寄せた。
「泣いているように見えた」
優しい瞳は、相変わらず。何かあった? と心彼は配そうに首をかしげる。
「何でもない」
彼の目を見ている事が出来なかった。だから彼の手を振り払い、窓の外に視線をそらす。まぁるい月が、空に居た。
「……なんて、綺麗」
「月?」
無言で、頷く。
だけど、あまりにも綺麗で、綺麗過ぎて、なんだか、耐えられなくなった。彼の目も、空の月も、見ていると狂ってしまいそう。ねえ、今にも壊れてしまいそう。崩れてしまいそう。
「――ユウガオ」
その声に、ゆるりと彼を見る。
「ピアノの、レコードがあるんだ。一緒に聞かない?」
静かに、頷いた。
優しい瞳も、優しい声も、相変わらず。だけどやっぱり直視することは出来なくて、私の視線は彼のスーツの胸元辺りを行き来する。ふわふわと焦点の定まらない視線。彼は私の髪を二、三度撫でて、ちょっと待っててねと部屋を後にした。
その後ろ姿にでさえ、私はぼんやりと、見惚れていた。
4
軽やかな、三拍子。
旧式の蓄音機から、たまに音の飛ぶワルツが流れる。
「この曲は?」
「僕が作曲したものだよ。なかなか綺麗でしょ?」
柔らかに歌う蓄音機に目を向け、私は無言のまま頷く。とても、綺麗な曲。子守唄のような柔らかさを持った、穏やかで優しい曲。
「……今にも、眠りに落ちてしまいそう」
「そう? これでも、明るい感じに作ったはずなんだけど」
違う、と私は左右に首を振った。
「退屈だとか、そういうのではないの。ただ……この曲を聴いていると、とても落ち着く。すごく、綺麗」
それは良かった、と彼はにこりと笑った。今までに見たことがないくらい、華やかな笑み。ああ、やっぱり彼はピアノを愛していたんだと、目を閉じて耳を傾ける。
「……ユウガオの為なら、ピアノを弾いても良かったかもしれないな」
「弾いてくれるの?」
「指さえ、うまく動けばね」
ああ、そうか。怪我をして弾けなくなったんだっけ。日常生活に支障はないらしいけど、なんて惜しい。こんなに綺麗な旋律は、誰にも真似は出来ないだろうに。……そうだ。
「ねえ、ワルツは踊れる?」
彼は曖昧に微笑んで、一応、と小さく答える。そして、あまり得意ではないのだけど、と困ったように付け足した。
「構わない。私と、踊ってくれる? ……何かで気を紛らわせていないと、今にも狂ってしまいそうなの」
静かに、頷いてくれた。彼はテーブルに残る薔薇の花を二輪手に取ると、一輪を私の髪に挿し、もう一輪を自分の胸ポケットに挿した。そしてその場に跪き、私の右手の甲にそっと唇をあてた。
「僕でよければ、いくらでもお相手いたしましょう」
旧式の蓄音機から、たまに音の飛ぶワルツが流れる。
「この曲は?」
「僕が作曲したものだよ。なかなか綺麗でしょ?」
柔らかに歌う蓄音機に目を向け、私は無言のまま頷く。とても、綺麗な曲。子守唄のような柔らかさを持った、穏やかで優しい曲。
「……今にも、眠りに落ちてしまいそう」
「そう? これでも、明るい感じに作ったはずなんだけど」
違う、と私は左右に首を振った。
「退屈だとか、そういうのではないの。ただ……この曲を聴いていると、とても落ち着く。すごく、綺麗」
それは良かった、と彼はにこりと笑った。今までに見たことがないくらい、華やかな笑み。ああ、やっぱり彼はピアノを愛していたんだと、目を閉じて耳を傾ける。
「……ユウガオの為なら、ピアノを弾いても良かったかもしれないな」
「弾いてくれるの?」
「指さえ、うまく動けばね」
ああ、そうか。怪我をして弾けなくなったんだっけ。日常生活に支障はないらしいけど、なんて惜しい。こんなに綺麗な旋律は、誰にも真似は出来ないだろうに。……そうだ。
「ねえ、ワルツは踊れる?」
彼は曖昧に微笑んで、一応、と小さく答える。そして、あまり得意ではないのだけど、と困ったように付け足した。
「構わない。私と、踊ってくれる? ……何かで気を紛らわせていないと、今にも狂ってしまいそうなの」
静かに、頷いてくれた。彼はテーブルに残る薔薇の花を二輪手に取ると、一輪を私の髪に挿し、もう一輪を自分の胸ポケットに挿した。そしてその場に跪き、私の右手の甲にそっと唇をあてた。
「僕でよければ、いくらでもお相手いたしましょう」
†
音の飛ぶワルツに、時折つまずくステップ。それはとても滑稽で、とても愉快なものだった。
「……どうしてか、」
唐突に、彼女はそう言って息を吐いた。僕の不器用なステップをリードするように動きながら、わずかに目を伏せる。
「満月の夜はとても心細くなる」
「吸血鬼としての本能じゃない? ほら、狼男が満月の夜に覚醒するような、そういう感じの」
「そうなのかな。……うん、そうなの、かもしれない」
異形としての、本能。
そう呟いて、頷く。
「……とても綺麗な、本能だよね」
そう言うと、彼女はわずかに首を傾げた。急に動きが緩慢になるものだから、またつまずきそうになってしまった。彼女は足を止め、僕を見上げた。音楽だけが、変わらずに流れ続けている。
「……綺麗?」
「月の明かりはとても美しいだろう? 曖昧で、透明で、密やかで、なのに華やかで、心地良く光ってる」
月明かりは魔の力を高める、なんて言われて敬遠されていたりもするけれど、多分それは間違いだ。ただ人が、その美しさに気付いていないだけ。もしくは、その美しさに恐れているだけ。
そして、異形(かの)の(じ)者(ょ)たちは月の明かりに魅せられている。きっと、月に手が届かない事を嘆いているのだ。
「ねえユウガオ、僕が居るよ。心細く感じる必要なんて、何もないんだ。……僕が、傍に居るんだから」
抱きしめると、その細い体は今にも折れてしまいそうだった。何かの病気か何かなのではと疑いたくなるほど、あまりにも頼りない身体だった。
……吸血鬼(なかま)にしてくれれば、ずっと一緒に居られるのに。いや、それとも人でなければ、彼女の食料として在り続ける事すら叶わないのだろうか。
ねえ、ユウガオ?
君は僕の事をどう思っているの?
僕の事をどう考えているの?
ねえ……。
「……ユウガオ」
小さく細い身体を抱きしめ、僕は呟く。それは幼い子供の願望か、それともただのひとり言か。
「君の傍に居るには、僕はどうしたらいいのかな」
彼女はきっと、答えたりはしないだろう。
「……どうしてか、」
唐突に、彼女はそう言って息を吐いた。僕の不器用なステップをリードするように動きながら、わずかに目を伏せる。
「満月の夜はとても心細くなる」
「吸血鬼としての本能じゃない? ほら、狼男が満月の夜に覚醒するような、そういう感じの」
「そうなのかな。……うん、そうなの、かもしれない」
異形としての、本能。
そう呟いて、頷く。
「……とても綺麗な、本能だよね」
そう言うと、彼女はわずかに首を傾げた。急に動きが緩慢になるものだから、またつまずきそうになってしまった。彼女は足を止め、僕を見上げた。音楽だけが、変わらずに流れ続けている。
「……綺麗?」
「月の明かりはとても美しいだろう? 曖昧で、透明で、密やかで、なのに華やかで、心地良く光ってる」
月明かりは魔の力を高める、なんて言われて敬遠されていたりもするけれど、多分それは間違いだ。ただ人が、その美しさに気付いていないだけ。もしくは、その美しさに恐れているだけ。
そして、異形(かの)の(じ)者(ょ)たちは月の明かりに魅せられている。きっと、月に手が届かない事を嘆いているのだ。
「ねえユウガオ、僕が居るよ。心細く感じる必要なんて、何もないんだ。……僕が、傍に居るんだから」
抱きしめると、その細い体は今にも折れてしまいそうだった。何かの病気か何かなのではと疑いたくなるほど、あまりにも頼りない身体だった。
……吸血鬼(なかま)にしてくれれば、ずっと一緒に居られるのに。いや、それとも人でなければ、彼女の食料として在り続ける事すら叶わないのだろうか。
ねえ、ユウガオ?
君は僕の事をどう思っているの?
僕の事をどう考えているの?
ねえ……。
「……ユウガオ」
小さく細い身体を抱きしめ、僕は呟く。それは幼い子供の願望か、それともただのひとり言か。
「君の傍に居るには、僕はどうしたらいいのかな」
彼女はきっと、答えたりはしないだろう。
†
「――君の傍に居るには、僕はどうしたらいいのかな」
私を抱きしめ、彼はそう言った。
疑問の形は取らず、ただの呟きのようにも聞こえる言葉。……私の、傍に居るには? ああ、なんて酔狂な。本当、可笑しな人。私の傍に居たところで、幸せになどなれないのに。
「私の、傍に居るには……?」
彼の言葉を繰り返して、私はもう一度口を開いた。
「……じゃあ、生きて」
「……え?」
彼の腕の中から離れ、私は静かにその目を覗いた。
「私の傍にいたいなら、人のまま、長く、長く生きて。出来る限り、ずっと、長く生きていて。そうしたら私は、自分の意思で生き続ける。貴方の傍に居る事が出来る」
彼は目を細め、そう、と囁くように言うと、胸の薔薇を抜き取り私に差出してきた。
「……リナリア(・・・・)」
それは、捨てたはずの名前。
……どうして?
どうして、その名で私を呼ぶの?
「ねえ、リナリア。どうか、受け取って。……この薔薇が、僕の想いだから」
彼の言葉に、私は一歩後退りした。その名前は、『幻想』の花は、偽物も否定も嫌いだと、前に話したはずなのに。
「……どうして、その名で私を呼ぶの? やめて、どうか、私は……私は、『幻想』なんていらないのに!」
「リナリア」
手を、掴まれた。
彼はワルツの続きを求めるように優しく、けれど力強く私の右手を掴んだ。……逃げられない。振りほどこうにも、紡がれる言葉すべてが悲痛に響いて、動けなくなる。
「『私の想いを知ってください』」
カイは、そう言った。
「僕も、幻想なんか要らない。偽物も否定も、要らない。欲しいのはリナリアだけなんだ! だからどうか……受け取って」
紅い薔薇の花言葉は、『愛情』。そして、『貴方に尽くします』。
差し出された、紅い薔薇。甘く匂い立つ綺麗な花弁。
「『安らかな死』も、今は要らない。僕たちは今、ここに居るんだから……」
泣きそうな声で紡がれる言葉。ああ、どうして。悲しい響きが、私を捉えて離さない。離してくれない。
ああ。なんて愛しい。
私も真っ赤な薔薇を彼に捧げ、そして、その花にそっと手を伸ばした。
私を抱きしめ、彼はそう言った。
疑問の形は取らず、ただの呟きのようにも聞こえる言葉。……私の、傍に居るには? ああ、なんて酔狂な。本当、可笑しな人。私の傍に居たところで、幸せになどなれないのに。
「私の、傍に居るには……?」
彼の言葉を繰り返して、私はもう一度口を開いた。
「……じゃあ、生きて」
「……え?」
彼の腕の中から離れ、私は静かにその目を覗いた。
「私の傍にいたいなら、人のまま、長く、長く生きて。出来る限り、ずっと、長く生きていて。そうしたら私は、自分の意思で生き続ける。貴方の傍に居る事が出来る」
彼は目を細め、そう、と囁くように言うと、胸の薔薇を抜き取り私に差出してきた。
「……リナリア(・・・・)」
それは、捨てたはずの名前。
……どうして?
どうして、その名で私を呼ぶの?
「ねえ、リナリア。どうか、受け取って。……この薔薇が、僕の想いだから」
彼の言葉に、私は一歩後退りした。その名前は、『幻想』の花は、偽物も否定も嫌いだと、前に話したはずなのに。
「……どうして、その名で私を呼ぶの? やめて、どうか、私は……私は、『幻想』なんていらないのに!」
「リナリア」
手を、掴まれた。
彼はワルツの続きを求めるように優しく、けれど力強く私の右手を掴んだ。……逃げられない。振りほどこうにも、紡がれる言葉すべてが悲痛に響いて、動けなくなる。
「『私の想いを知ってください』」
カイは、そう言った。
「僕も、幻想なんか要らない。偽物も否定も、要らない。欲しいのはリナリアだけなんだ! だからどうか……受け取って」
紅い薔薇の花言葉は、『愛情』。そして、『貴方に尽くします』。
差し出された、紅い薔薇。甘く匂い立つ綺麗な花弁。
「『安らかな死』も、今は要らない。僕たちは今、ここに居るんだから……」
泣きそうな声で紡がれる言葉。ああ、どうして。悲しい響きが、私を捉えて離さない。離してくれない。
ああ。なんて愛しい。
私も真っ赤な薔薇を彼に捧げ、そして、その花にそっと手を伸ばした。
5
『私の想いを知ってください』
リナリアの、もう一つの花言葉。
祈りのようなその言葉が、とても綺麗だと思った。
愛されているのだと、感じた。
愛しても良いのだと感じた。
そして、生きたくなった。
なにもかも、あの人の所為。死ねなくなったのも、生きたくなったのも、全部、あの人の所為だ。
人の命は短すぎる。
吸血鬼の命は長すぎる。
ああ、なんて厄介なのだろう。それを知りながら生き続ける事を選んでしまうなんて。
真っ赤な血と、真っ赤な薔薇。
静かな狂気と、依存関係。
アメジストの瞳と、傷だらけの腕。
軽やかなワルツと、覚束ないステップ。
手を取り合い、腰に手を回し、見つめ合い、古い蓄音器から流れるピアノにターンとステップ。
くるくる、くるり。
貴方のために、いつまでも回り続けよう。
――この命、果てるまで。
リナリアの、もう一つの花言葉。
祈りのようなその言葉が、とても綺麗だと思った。
愛されているのだと、感じた。
愛しても良いのだと感じた。
そして、生きたくなった。
なにもかも、あの人の所為。死ねなくなったのも、生きたくなったのも、全部、あの人の所為だ。
人の命は短すぎる。
吸血鬼の命は長すぎる。
ああ、なんて厄介なのだろう。それを知りながら生き続ける事を選んでしまうなんて。
真っ赤な血と、真っ赤な薔薇。
静かな狂気と、依存関係。
アメジストの瞳と、傷だらけの腕。
軽やかなワルツと、覚束ないステップ。
手を取り合い、腰に手を回し、見つめ合い、古い蓄音器から流れるピアノにターンとステップ。
くるくる、くるり。
貴方のために、いつまでも回り続けよう。
――この命、果てるまで。
多分そのうち書きなおす。多分。