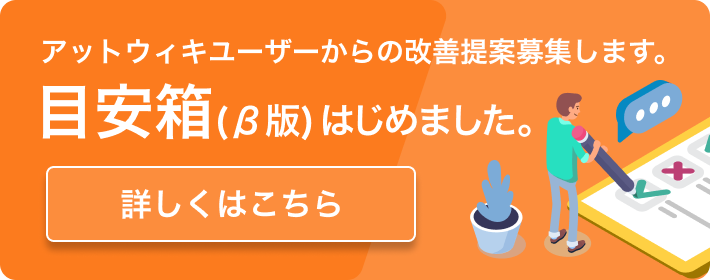『例えば』の話
0
強きを挫き弱きを助ける? 馬鹿馬鹿しい。強い者が『悪』で弱い者が『善』だなんて、一体どこの誰が決めたんだ?
1
例えば、満員電車の中の耐え難い香水の臭い。
そんな感じの世界で、俺は生きている。自分でも変な例えだとは思う。だけどきっと、俺にはこれ以上にしっくりとくる表現は見つけられないだろう。匂いは、強すぎると臭いに変わる。それに四方を囲まれたらと考えて欲しい。移動の為の手段であるそれが、苦痛の小箱となる。
そこは耐え難いけれどあからさまに嫌な顔をすることもできず、面と向かって文句を言うこともできず、ただじっと耐えるしかないという苦行さながらの狭い空間。
ここは、そんな世界だ。
「おはよ、ガル。なあ、お前、もうすぐ任務だよな?」
「お早う」
軽い調子で聞いてきた同僚、アスカ・バルザックは俺の顔を覗き込み、わずかに口角を上げた。一言だけそっけなく返し、俺は書類の整理を続ける。
「その任務なんだけど、僕も行くことになったから。お知らせ」
「……了解」
アスカは整った顔立ちの、女顔の男だ。
もうすぐ三十路だというのに女装をして街に行き、声を掛けてきた男をからかって遊ぶのが楽しいのだという、性格と根性と趣味の悪い奴である。どうでも良いから早く落ち着けと説教したくなる。この男は浮足立つどころかふわふわと浮きっぱなしで、苛々するくらい落ち着きがない。
『このつぶらな瞳にたくさんの男が騙されるんだ。むさ苦しい男たちの落胆した顔を見るのはとても快感だよ』などと嘯いていたこともあったか。
一七〇センチにも満たない彼は細身で、まるで東洋人のように童顔だ。その所為か、まだ二十歳くらいにも見える。下手をしたら、まだ十代と間違われることすらあるかもしれない。
彼から時折聞かされる、『化粧をしてにっこり微笑んでみたりとかしたら、その辺の女の子なんか目じゃないよ』という言葉も、きっと嘘ではないのだろう。幸いなことに、俺はまだその女装姿を見たことはない。不可思議な思考の持ち主ばかりが集まるこの職場に居るアスカが、仕事場に女装で来ないだけの分別を持っていることに俺はひそかに感謝する。男にしてはかなり長い、セミロングの髪を二つに結んでいたり編んでいたりすることも稀(まれ)にあるが、それはまぁ、許容範囲内だろう。
しかし、何にせよこれが先輩なのだと思うと若干不愉快になる。敬語を使おうとかそういう思考は、出会って一週間でなくなった。ああ、こいつとの任務か。なんだか、厄介者を押し付けられた気分だ。
書類の整理を黙々と続ける俺に、アスカは不思議そうに首を傾げた。
「そんな雑用なんか自分でやることないじゃん。下っ端にやらせようよー。使える奴くらいいくらでもいるでしょー?」
「俺はこういう事務仕事の方が性に合っているんだ。任務とか、正直行きたくない」
「あははっ、何それ。我らの『アテナ』様がよく言うよ」
ギリシャ神話か。
最高神ゼウスの頭から生まれたという、知恵と戦の女神アテナ。そんな勇ましい神に例えられるほど、俺は大層な人間じゃない。睨みつけると、アスカは何を思ったのかにこりと笑って俺の頭に顎を乗せた。
「『アテナ』様が嫌なら『ニケ』様でも良いよ? アテナを勝利に導く有翼の女神様。…ああ、もしかしたらガルにはニケの方が合っているかもしれないね。サポートとかの方が得意だもんね。――でもさ、ガルだってある程度覚悟をしてこっちに移動してきたんでしょ? そういう文句は胸の内に潜めておかなくっちゃ」
苛々する。この男は俺に何を求めている? 訳が分からない。一体何を言いたいんだ。どうしてだろう、この男は浮ついている。へらへらと、にやにやと、何かを企んでいるような笑顔が酷く不愉快だ。
「……まだ何か用があるのか? 書類の整理が終わったら明日の準備をしないといけないんだ。早めに終わらせてくれ。それから、喋るたびに顎が刺さる。そこに頭を乗せている間は口を開くな」
「つれないねぇ。僕だってちょっとくらい浮いた話題が欲しいんだよ」
俺の頭の上から肩の上に顔を置く場所を変え、アスカはそう言った。
「そこらの女にでも声掛けてみろよ。お前くらい綺麗な顔だったら着いてくる女なんかいくらでもいるだろ」
そうだね、とアスカはまるで無垢な少女のように笑って俺に抱きついてきた。
まったく、これが本当に可愛らしい女性の抱擁ならばどれほどいいだろう。それなら頬にキスのひとつくらい返してやるのに。なのにどうしてこいつなんだ、と俺は少し眉を寄せる。
何が楽しくてやっているのかは分からないが、とにかく不快だ。不愉快だ。失せろ、と肩の上の端整な顔に裏拳を入れる。アスカはへびゃぁっと妙な声を出すと、顔を押えてうずくまった。
「生憎だが、俺に男色の気はない」
「知ってる。僕だって男なんか願い下げだよ、むさ苦しいし、汗臭いし。……ところで、もう話はしたの?」
「何の?」
アスカの鼻が少し赤くなっていた。若干、目が潤んでいる。この男は自分も男だということに気付いているのだろうか。すべての男がむさ苦しくて汗臭いというのなら、当然その中に自分も含まれているはずなのだが。まあ、こいつの事だから自分は特別だと考えているのは聞くまでもないが。
「この仕事のコト。彼女さんには言ったの?」
まだ鼻の頭をさすりながらアスカは言った。俺はわずかに目を伏せ、自嘲するように口角を上げた。
「……今のところ、俺は警察ってことになってるよ。…そうだな。死んだら、幽霊にでもなって自分で伝えに行くさ」
「その冗談、全然面白くないよ。でも、“警察”かぁ。当たらずも遠からずってカンジだねぇ。……でもまぁ、警察の機関の一つなのは確かだから…一応、ウソではないの、かな。それにしても、ホント律義だよねぇ、ガルは。必ずしもウソとは言えないようなウソを吐くんだから。健気だね、彼女には心配かけたくないんだ」
「…だから?」
「ガルは優しいねぇ。君の彼女は幸せもんだねぇ、そんなに愛されて」
僕もそのくらい愛してくれる可愛い恋人が欲しーなー、とアスカは床にへたりと座り込み、ぱたぱたとまるで駄々っ子のように足をばたつかせる。そんな馬鹿なことをやっているうちは絶対に無理だろう、と俺は口には出さず心中で呟く。
「いつかは話してやりなよ。そういう態度は、場合によっては相手を余計に不安にさせるんだから」
「…守秘義務があるだろう? まぁ、死人には課されないだろうが」
「守秘義務? そんなもの、愛の前には無意味だよ。僕だったら彼女にだけは伝えるよ。で、言いふらさないようにって言い含めるけど」
要はさ、会社にバレなきゃいいんだ。
アスカはそう言って狡賢そうな目をそっと細めた。
正直にすべてを語るのもどうかと思うけれど。そんなにペラペラ喋っていたら、話さないでいるよりも更に心配させる結果になるんじゃないか? …そりゃあ、俺だっていつかは話してやらなければとは思っている。だけど、彼女を汚したくないんだ。彼女は俺の、博愛の花だから。
「彼女にはこんな世界があるなんてこと教えたくないんだ。こんな薄汚れた世界のことなんて、知らないでいて欲しいんだ。……ここは、汚れ過ぎているから」
知らなくても良い。知らないでいる方が良いことだってあるんだ。何も知らないでいる方が、きっと、ずっと気楽に、幸せに生きられる。…それだったら話さないでいる方が、偽りを語り続ける方がいいんじゃないか?
「何も語らずに死んじゃったりしたら、お前、絶対に後悔するよ? ……いや、違うな。お前はそれで良いかもしれない。だけど彼女さんの方はきっと、何も知らずにお前が死んだりしたら悔やんでも悔やみきれないだろうと思うよ」
「縁起でもないことを言うなよ。お前の軽口は何故か本当になるんだから、そういうことを口走るのは止めてくれ」
お前が言うと、本当になりそうで怖いんだ。
「そんなの、ここの職場じゃ別に珍しいことでもないでしょ? 今月だって、もう二人殉職してるじゃん」
そういえば、その片方はアスカに『死にそうな顔してるね』などとからかわれていたっけ。ああ全く、本当に縁起でもない。この仕事は生と死の狭間にあるのだ。いつでも、真っ黒な死神がうろついている。
「いい加減、彼女さんの事信じてあげなよ。こういうことは、大切な人にこそ話してあげるべきだよ」
信じてるさ。彼女がどんな人より気丈なことも知ってる。だけど、怖いんだ。
「それに、嘘っていうのはいつかはバレるもんだよ。絶対にね」
正直に言って失望されたらどうする。
あいつの幻想を壊してしまったらどうする。
あいつが滅多なことじゃ泣かないということくらい俺だって知っているさ。だけど、もし泣かれたら? 真実を語って、もし泣かれてしまったら。そしたら、俺は一体どうしたら良いんだ?
俺はあいつの泣き顔なんか見たくない。俺は常に、“正義の味方”でいなければいけないんだ。例え彼女が、俺の過去を知っていたとしても。彼女はいつも、過去ではなく今を見ている。だから俺は、彼女を心配させちゃいけないんだ。
「じゃあね、お説教はこのくらいにしておく。後でコーヒー奢ってやるよ」
俺の思考を読み取ったみたいに、ぽんぽんと俺の肩を叩き、慰めるような声でアスカはそう言った。俺がコーヒーを飲めないことを知っているクセに。
「おい」
「ん? なぁに?」
細身の背に投げた言葉に、アスカはにっと笑って振り返った。
「コーヒーなんてあんな苦いもん飲めるか。奢ってもらうならココアだ」
「いーよ。甘~いココアにお砂糖とクリームもたーっぷり追加してやるよ。ちゃんと全部飲めよー?」
きっと飽和状態を通り過ぎたじゃりじゃりしたココアを飲まされるな。
吹き出してしまいそうなほど甘い、まるで罰ゲームのようなココア。あの人はそういう訳の分からないところでよく分からない嫌がらせをしてくるから。
『――ガレット・コールマン、ガレット・コールマン。至急、会議室まで来て下さい。繰り返します。ガレット・コールマン、ガレット…』
社内放送だ。
ああ、行かないと。
そんな感じの世界で、俺は生きている。自分でも変な例えだとは思う。だけどきっと、俺にはこれ以上にしっくりとくる表現は見つけられないだろう。匂いは、強すぎると臭いに変わる。それに四方を囲まれたらと考えて欲しい。移動の為の手段であるそれが、苦痛の小箱となる。
そこは耐え難いけれどあからさまに嫌な顔をすることもできず、面と向かって文句を言うこともできず、ただじっと耐えるしかないという苦行さながらの狭い空間。
ここは、そんな世界だ。
「おはよ、ガル。なあ、お前、もうすぐ任務だよな?」
「お早う」
軽い調子で聞いてきた同僚、アスカ・バルザックは俺の顔を覗き込み、わずかに口角を上げた。一言だけそっけなく返し、俺は書類の整理を続ける。
「その任務なんだけど、僕も行くことになったから。お知らせ」
「……了解」
アスカは整った顔立ちの、女顔の男だ。
もうすぐ三十路だというのに女装をして街に行き、声を掛けてきた男をからかって遊ぶのが楽しいのだという、性格と根性と趣味の悪い奴である。どうでも良いから早く落ち着けと説教したくなる。この男は浮足立つどころかふわふわと浮きっぱなしで、苛々するくらい落ち着きがない。
『このつぶらな瞳にたくさんの男が騙されるんだ。むさ苦しい男たちの落胆した顔を見るのはとても快感だよ』などと嘯いていたこともあったか。
一七〇センチにも満たない彼は細身で、まるで東洋人のように童顔だ。その所為か、まだ二十歳くらいにも見える。下手をしたら、まだ十代と間違われることすらあるかもしれない。
彼から時折聞かされる、『化粧をしてにっこり微笑んでみたりとかしたら、その辺の女の子なんか目じゃないよ』という言葉も、きっと嘘ではないのだろう。幸いなことに、俺はまだその女装姿を見たことはない。不可思議な思考の持ち主ばかりが集まるこの職場に居るアスカが、仕事場に女装で来ないだけの分別を持っていることに俺はひそかに感謝する。男にしてはかなり長い、セミロングの髪を二つに結んでいたり編んでいたりすることも稀(まれ)にあるが、それはまぁ、許容範囲内だろう。
しかし、何にせよこれが先輩なのだと思うと若干不愉快になる。敬語を使おうとかそういう思考は、出会って一週間でなくなった。ああ、こいつとの任務か。なんだか、厄介者を押し付けられた気分だ。
書類の整理を黙々と続ける俺に、アスカは不思議そうに首を傾げた。
「そんな雑用なんか自分でやることないじゃん。下っ端にやらせようよー。使える奴くらいいくらでもいるでしょー?」
「俺はこういう事務仕事の方が性に合っているんだ。任務とか、正直行きたくない」
「あははっ、何それ。我らの『アテナ』様がよく言うよ」
ギリシャ神話か。
最高神ゼウスの頭から生まれたという、知恵と戦の女神アテナ。そんな勇ましい神に例えられるほど、俺は大層な人間じゃない。睨みつけると、アスカは何を思ったのかにこりと笑って俺の頭に顎を乗せた。
「『アテナ』様が嫌なら『ニケ』様でも良いよ? アテナを勝利に導く有翼の女神様。…ああ、もしかしたらガルにはニケの方が合っているかもしれないね。サポートとかの方が得意だもんね。――でもさ、ガルだってある程度覚悟をしてこっちに移動してきたんでしょ? そういう文句は胸の内に潜めておかなくっちゃ」
苛々する。この男は俺に何を求めている? 訳が分からない。一体何を言いたいんだ。どうしてだろう、この男は浮ついている。へらへらと、にやにやと、何かを企んでいるような笑顔が酷く不愉快だ。
「……まだ何か用があるのか? 書類の整理が終わったら明日の準備をしないといけないんだ。早めに終わらせてくれ。それから、喋るたびに顎が刺さる。そこに頭を乗せている間は口を開くな」
「つれないねぇ。僕だってちょっとくらい浮いた話題が欲しいんだよ」
俺の頭の上から肩の上に顔を置く場所を変え、アスカはそう言った。
「そこらの女にでも声掛けてみろよ。お前くらい綺麗な顔だったら着いてくる女なんかいくらでもいるだろ」
そうだね、とアスカはまるで無垢な少女のように笑って俺に抱きついてきた。
まったく、これが本当に可愛らしい女性の抱擁ならばどれほどいいだろう。それなら頬にキスのひとつくらい返してやるのに。なのにどうしてこいつなんだ、と俺は少し眉を寄せる。
何が楽しくてやっているのかは分からないが、とにかく不快だ。不愉快だ。失せろ、と肩の上の端整な顔に裏拳を入れる。アスカはへびゃぁっと妙な声を出すと、顔を押えてうずくまった。
「生憎だが、俺に男色の気はない」
「知ってる。僕だって男なんか願い下げだよ、むさ苦しいし、汗臭いし。……ところで、もう話はしたの?」
「何の?」
アスカの鼻が少し赤くなっていた。若干、目が潤んでいる。この男は自分も男だということに気付いているのだろうか。すべての男がむさ苦しくて汗臭いというのなら、当然その中に自分も含まれているはずなのだが。まあ、こいつの事だから自分は特別だと考えているのは聞くまでもないが。
「この仕事のコト。彼女さんには言ったの?」
まだ鼻の頭をさすりながらアスカは言った。俺はわずかに目を伏せ、自嘲するように口角を上げた。
「……今のところ、俺は警察ってことになってるよ。…そうだな。死んだら、幽霊にでもなって自分で伝えに行くさ」
「その冗談、全然面白くないよ。でも、“警察”かぁ。当たらずも遠からずってカンジだねぇ。……でもまぁ、警察の機関の一つなのは確かだから…一応、ウソではないの、かな。それにしても、ホント律義だよねぇ、ガルは。必ずしもウソとは言えないようなウソを吐くんだから。健気だね、彼女には心配かけたくないんだ」
「…だから?」
「ガルは優しいねぇ。君の彼女は幸せもんだねぇ、そんなに愛されて」
僕もそのくらい愛してくれる可愛い恋人が欲しーなー、とアスカは床にへたりと座り込み、ぱたぱたとまるで駄々っ子のように足をばたつかせる。そんな馬鹿なことをやっているうちは絶対に無理だろう、と俺は口には出さず心中で呟く。
「いつかは話してやりなよ。そういう態度は、場合によっては相手を余計に不安にさせるんだから」
「…守秘義務があるだろう? まぁ、死人には課されないだろうが」
「守秘義務? そんなもの、愛の前には無意味だよ。僕だったら彼女にだけは伝えるよ。で、言いふらさないようにって言い含めるけど」
要はさ、会社にバレなきゃいいんだ。
アスカはそう言って狡賢そうな目をそっと細めた。
正直にすべてを語るのもどうかと思うけれど。そんなにペラペラ喋っていたら、話さないでいるよりも更に心配させる結果になるんじゃないか? …そりゃあ、俺だっていつかは話してやらなければとは思っている。だけど、彼女を汚したくないんだ。彼女は俺の、博愛の花だから。
「彼女にはこんな世界があるなんてこと教えたくないんだ。こんな薄汚れた世界のことなんて、知らないでいて欲しいんだ。……ここは、汚れ過ぎているから」
知らなくても良い。知らないでいる方が良いことだってあるんだ。何も知らないでいる方が、きっと、ずっと気楽に、幸せに生きられる。…それだったら話さないでいる方が、偽りを語り続ける方がいいんじゃないか?
「何も語らずに死んじゃったりしたら、お前、絶対に後悔するよ? ……いや、違うな。お前はそれで良いかもしれない。だけど彼女さんの方はきっと、何も知らずにお前が死んだりしたら悔やんでも悔やみきれないだろうと思うよ」
「縁起でもないことを言うなよ。お前の軽口は何故か本当になるんだから、そういうことを口走るのは止めてくれ」
お前が言うと、本当になりそうで怖いんだ。
「そんなの、ここの職場じゃ別に珍しいことでもないでしょ? 今月だって、もう二人殉職してるじゃん」
そういえば、その片方はアスカに『死にそうな顔してるね』などとからかわれていたっけ。ああ全く、本当に縁起でもない。この仕事は生と死の狭間にあるのだ。いつでも、真っ黒な死神がうろついている。
「いい加減、彼女さんの事信じてあげなよ。こういうことは、大切な人にこそ話してあげるべきだよ」
信じてるさ。彼女がどんな人より気丈なことも知ってる。だけど、怖いんだ。
「それに、嘘っていうのはいつかはバレるもんだよ。絶対にね」
正直に言って失望されたらどうする。
あいつの幻想を壊してしまったらどうする。
あいつが滅多なことじゃ泣かないということくらい俺だって知っているさ。だけど、もし泣かれたら? 真実を語って、もし泣かれてしまったら。そしたら、俺は一体どうしたら良いんだ?
俺はあいつの泣き顔なんか見たくない。俺は常に、“正義の味方”でいなければいけないんだ。例え彼女が、俺の過去を知っていたとしても。彼女はいつも、過去ではなく今を見ている。だから俺は、彼女を心配させちゃいけないんだ。
「じゃあね、お説教はこのくらいにしておく。後でコーヒー奢ってやるよ」
俺の思考を読み取ったみたいに、ぽんぽんと俺の肩を叩き、慰めるような声でアスカはそう言った。俺がコーヒーを飲めないことを知っているクセに。
「おい」
「ん? なぁに?」
細身の背に投げた言葉に、アスカはにっと笑って振り返った。
「コーヒーなんてあんな苦いもん飲めるか。奢ってもらうならココアだ」
「いーよ。甘~いココアにお砂糖とクリームもたーっぷり追加してやるよ。ちゃんと全部飲めよー?」
きっと飽和状態を通り過ぎたじゃりじゃりしたココアを飲まされるな。
吹き出してしまいそうなほど甘い、まるで罰ゲームのようなココア。あの人はそういう訳の分からないところでよく分からない嫌がらせをしてくるから。
『――ガレット・コールマン、ガレット・コールマン。至急、会議室まで来て下さい。繰り返します。ガレット・コールマン、ガレット…』
社内放送だ。
ああ、行かないと。