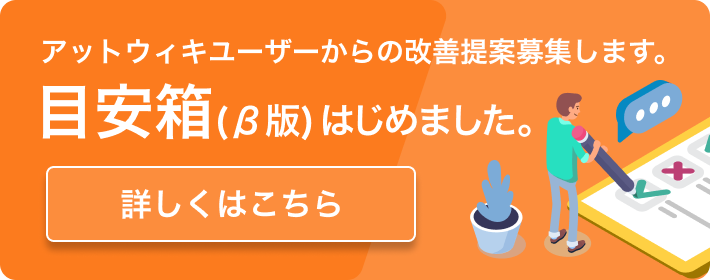序章
「――例えばさ、」
情事のあと、眠りの中に居たあたしは彼の声にうっすらと目を開いた。
背中に、彼の体温を感じた。カーテン越しに部屋を照らす白い光に、あたしはわずかに目を細める。目覚まし時計で時間を確認すると、短針はまだ四を指していた。
こんなに早い時間から体を起こすつもりなどない。そう思って、あたしは無言のままもぞもぞと体を動かした。外気に晒していた腕を布団に中に隠すと、彼はそれを横目で確認して微笑み、静かに目を閉じて続けた。
薄闇の中の、優しく囁くような声。頬を撫でるような吐息。安心する。なんて心地よい声だろう。
「例えば、俺が死んだらどうする?」
なんて質問をするのだろう、とあたしは寝返りを打って彼の方を向いた。そして彼の頬にそっと触れ、どうするだろうねと淡白に答える。
幼いころからの、少し低い抑揚のない声。
いつも可愛げがないと言われていた単調なあたしの口調を、彼だけは落ち着いた良い声だと言ってくれた。穏やかで聞いていて心地がいいと。
あたしは生まれて初めて、自分の声を、口調を褒められた。
「……あなたが死んだら、か。そんなの考えたこともなかったわ。あなたが死んだら、あたしはどうなるのかしら」
少し考えて、あたしはまた口を開く。
「…きっとね、どうもしないと思う。普通にお葬式に出て、涙も見せないなんて随分と薄情な彼女だなって誰かに陰口叩かれて、それから、いつも通りの生活に戻るんだと思う。……多分ね」
今までだって他人(ひと)のお葬式で泣いたことなんて一度もないもの、とあたしは続けた。友人との別れも、大切にしていたものが壊れても、ごく身近な人が亡くなったときでさえ、あたしは決して涙を見せることはなかった。
幼いころから、あたしは本当に泣かない子だった。
怒られても叩かれても、何をされても泣かないものだから、あんたの目には涙腺がないんじゃないの、などと言われたこともある。それも、嫌悪に満ちた口調で。けれど彼だけは、そんなあたしのことを気丈だねと言ってくれた。それは心の強い証拠だと。
あたしは生まれて初めて、この淡白な性格を褒められた。
「……あたしが死んだら?」
ぽつりと、あたしは言った。
「もしあたしが死んだら、そしたら、あなたはどうする?」
彼はあたしと同じように、どうするだろうねと言って笑った。
いつもと同じ、気の弱い、困ったような笑み。あたしは彼の、この軟弱な表情が好きだった。どこまでも穏やかで、静かで、優しい人。程よく筋肉の付いた腕であたしを抱きしめて、彼は答えた。
「そんなの、その時になってみないと分からないよ。
…だけど多分、ロミオのように自ら君の後を追うんだと思うよ。…まぁ、ロミオのは勘違いだったわけだけど。ジュリエットも可哀そうだよね、恋人の早とちりのせいで自ら死を選ぶことになってしまうんだから」
あの話はあんまり好きじゃないんだけどね、と一言続けて、口を閉じる。
あたしも、あの物語はあまり好きじゃない。あれは悲しくなるくらい、救いようのない物語だから。モンタギュー家もキャピュレット家も、ロミオもジュリエットも、好きじゃない。あの二人は確かに愛し合っていたかもしれないけれど、酷く愚かだった。きっと、恋に落ちるにはあまりにも幼かったのだ。
…ああ、夜の空気が、まだかすかに残っているような気がする。なんだか、彼の甘い声に酔ってしまいそうだった。彼の香りに埋もれてしまいたくて、あたしは彼の胸にわずかにすり寄った。
とくん、とくん。
彼の規則的な心臓の音があたしの頬を撫でる。
あまりの心地良さに、うとうととまた目を閉じてしまいそうになる。彼の音はどうやら、あたしの子守唄にもなるらしい。
「……あたしが、死に際に『生きていて欲しい』って言ったら?」
あたしの頭を撫で、彼は少し迷うように唸り、もう一度どうするだろうねと呟いた。
「それじゃあ、君の死体を冷蔵庫の中に入れて毎日話しかけるよ」
そうしたら生きていけるんじゃないかな、などと笑顔で嘯く彼に、あたしは少し呆れの混じる笑みを向けた。
「まるで変質者だわ。ねえ、知ってる? 死体遺棄って犯罪なのよ」
「どうして人間の死体だと『保存』って言葉は使われないんだろうね」
直球で投げたボールを変化球で投げ返してくる彼に、あたしはふふっと笑った。そしてもう一つだけ、質問をした。
「それじゃあ、もしあたしがあなたに『死ね』って言ったら、どうする?」
彼は笑ったまま、躊躇いなく答える。
「死ぬよ。きっと、その言葉のままに死ぬんだと思う。最後に、君に深いキスをせがんで、熱い抱擁を求めて、犯して、殺して、君の血をすべて飲みほして、そしてそれから、自殺する。
…それか、君の手で直接殺してもらうのも良いかもしれないね。俺は生も死も、すべてを君にゆだねるよ。君のためだったらきっと、惜しむことなく命を落とせる」
答えて、なんて話をしているんだろうねとあたしを抱く腕にきゅっと力を入れた。これじゃあ本当にただの変質者だよね、などと言いながら。
直接に伝わってくる彼の体温。
なんて気だるい、情事の後。
「話を始めたのはあなたよ」
「そうだったね」
そうやって、かすかな狂気の中で共に笑い合ったのは二週間ほど前のこと。
彼は、死んだ。殺されたのだ。
深い深い闇の中に、彼は堕とされた。
愛しい人のいない世界は、時間は、まるで色彩を失ってしまったようで酷く空虚。音声のない、古くて退屈なモノクロの映画の中みたいだった。
彼と入れ替わりに現れたのは見知らぬ少年だった。
ファウンテン・ブルーの瞳が美しい、小柄な少年。
あたしと言葉を交わすよりも早く、彼は静かにこう言った。
情事のあと、眠りの中に居たあたしは彼の声にうっすらと目を開いた。
背中に、彼の体温を感じた。カーテン越しに部屋を照らす白い光に、あたしはわずかに目を細める。目覚まし時計で時間を確認すると、短針はまだ四を指していた。
こんなに早い時間から体を起こすつもりなどない。そう思って、あたしは無言のままもぞもぞと体を動かした。外気に晒していた腕を布団に中に隠すと、彼はそれを横目で確認して微笑み、静かに目を閉じて続けた。
薄闇の中の、優しく囁くような声。頬を撫でるような吐息。安心する。なんて心地よい声だろう。
「例えば、俺が死んだらどうする?」
なんて質問をするのだろう、とあたしは寝返りを打って彼の方を向いた。そして彼の頬にそっと触れ、どうするだろうねと淡白に答える。
幼いころからの、少し低い抑揚のない声。
いつも可愛げがないと言われていた単調なあたしの口調を、彼だけは落ち着いた良い声だと言ってくれた。穏やかで聞いていて心地がいいと。
あたしは生まれて初めて、自分の声を、口調を褒められた。
「……あなたが死んだら、か。そんなの考えたこともなかったわ。あなたが死んだら、あたしはどうなるのかしら」
少し考えて、あたしはまた口を開く。
「…きっとね、どうもしないと思う。普通にお葬式に出て、涙も見せないなんて随分と薄情な彼女だなって誰かに陰口叩かれて、それから、いつも通りの生活に戻るんだと思う。……多分ね」
今までだって他人(ひと)のお葬式で泣いたことなんて一度もないもの、とあたしは続けた。友人との別れも、大切にしていたものが壊れても、ごく身近な人が亡くなったときでさえ、あたしは決して涙を見せることはなかった。
幼いころから、あたしは本当に泣かない子だった。
怒られても叩かれても、何をされても泣かないものだから、あんたの目には涙腺がないんじゃないの、などと言われたこともある。それも、嫌悪に満ちた口調で。けれど彼だけは、そんなあたしのことを気丈だねと言ってくれた。それは心の強い証拠だと。
あたしは生まれて初めて、この淡白な性格を褒められた。
「……あたしが死んだら?」
ぽつりと、あたしは言った。
「もしあたしが死んだら、そしたら、あなたはどうする?」
彼はあたしと同じように、どうするだろうねと言って笑った。
いつもと同じ、気の弱い、困ったような笑み。あたしは彼の、この軟弱な表情が好きだった。どこまでも穏やかで、静かで、優しい人。程よく筋肉の付いた腕であたしを抱きしめて、彼は答えた。
「そんなの、その時になってみないと分からないよ。
…だけど多分、ロミオのように自ら君の後を追うんだと思うよ。…まぁ、ロミオのは勘違いだったわけだけど。ジュリエットも可哀そうだよね、恋人の早とちりのせいで自ら死を選ぶことになってしまうんだから」
あの話はあんまり好きじゃないんだけどね、と一言続けて、口を閉じる。
あたしも、あの物語はあまり好きじゃない。あれは悲しくなるくらい、救いようのない物語だから。モンタギュー家もキャピュレット家も、ロミオもジュリエットも、好きじゃない。あの二人は確かに愛し合っていたかもしれないけれど、酷く愚かだった。きっと、恋に落ちるにはあまりにも幼かったのだ。
…ああ、夜の空気が、まだかすかに残っているような気がする。なんだか、彼の甘い声に酔ってしまいそうだった。彼の香りに埋もれてしまいたくて、あたしは彼の胸にわずかにすり寄った。
とくん、とくん。
彼の規則的な心臓の音があたしの頬を撫でる。
あまりの心地良さに、うとうととまた目を閉じてしまいそうになる。彼の音はどうやら、あたしの子守唄にもなるらしい。
「……あたしが、死に際に『生きていて欲しい』って言ったら?」
あたしの頭を撫で、彼は少し迷うように唸り、もう一度どうするだろうねと呟いた。
「それじゃあ、君の死体を冷蔵庫の中に入れて毎日話しかけるよ」
そうしたら生きていけるんじゃないかな、などと笑顔で嘯く彼に、あたしは少し呆れの混じる笑みを向けた。
「まるで変質者だわ。ねえ、知ってる? 死体遺棄って犯罪なのよ」
「どうして人間の死体だと『保存』って言葉は使われないんだろうね」
直球で投げたボールを変化球で投げ返してくる彼に、あたしはふふっと笑った。そしてもう一つだけ、質問をした。
「それじゃあ、もしあたしがあなたに『死ね』って言ったら、どうする?」
彼は笑ったまま、躊躇いなく答える。
「死ぬよ。きっと、その言葉のままに死ぬんだと思う。最後に、君に深いキスをせがんで、熱い抱擁を求めて、犯して、殺して、君の血をすべて飲みほして、そしてそれから、自殺する。
…それか、君の手で直接殺してもらうのも良いかもしれないね。俺は生も死も、すべてを君にゆだねるよ。君のためだったらきっと、惜しむことなく命を落とせる」
答えて、なんて話をしているんだろうねとあたしを抱く腕にきゅっと力を入れた。これじゃあ本当にただの変質者だよね、などと言いながら。
直接に伝わってくる彼の体温。
なんて気だるい、情事の後。
「話を始めたのはあなたよ」
「そうだったね」
そうやって、かすかな狂気の中で共に笑い合ったのは二週間ほど前のこと。
彼は、死んだ。殺されたのだ。
深い深い闇の中に、彼は堕とされた。
愛しい人のいない世界は、時間は、まるで色彩を失ってしまったようで酷く空虚。音声のない、古くて退屈なモノクロの映画の中みたいだった。
彼と入れ替わりに現れたのは見知らぬ少年だった。
ファウンテン・ブルーの瞳が美しい、小柄な少年。
あたしと言葉を交わすよりも早く、彼は静かにこう言った。
『――君の恋人、亡くなったよ』
愛しい愛しい彼の死を、伝えに来たのは青い瞳の饒舌な少年。
あたしは信じることを拒み続けた。
信じる必要性を、感じなかった。
だから拒んだ。
いつまでも、彼は死んだと続ける少年に苛立ちながら。
けれど少年の纏う香水の甘い香りに、あたしはいつもふわふわと、くらくらと揺らいでいた。
まるで、不安定な器になみなみと入れられた液体のように。足元の覚束ない、生まれたばかりの幼子のように。
甘い香りに酔いしれ、あたしは今にも零れてしまいそうだった。
それは、とても身近なものだったから。
『俺はホントのコトしか言わないよ』
そう言う彼の言葉は、酷く静かで穏やかだった。
あたしは信じることを拒み続けた。
信じる必要性を、感じなかった。
だから拒んだ。
いつまでも、彼は死んだと続ける少年に苛立ちながら。
けれど少年の纏う香水の甘い香りに、あたしはいつもふわふわと、くらくらと揺らいでいた。
まるで、不安定な器になみなみと入れられた液体のように。足元の覚束ない、生まれたばかりの幼子のように。
甘い香りに酔いしれ、あたしは今にも零れてしまいそうだった。
それは、とても身近なものだったから。
『俺はホントのコトしか言わないよ』
そう言う彼の言葉は、酷く静かで穏やかだった。