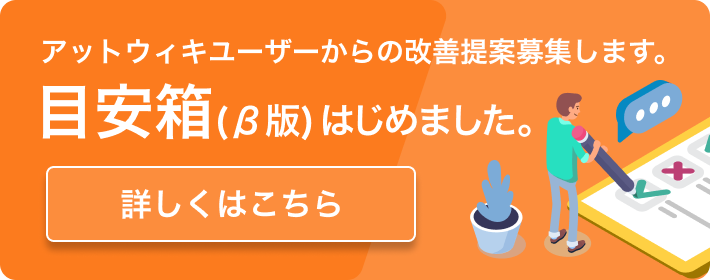0
どこからか、羽音がした。
1
彼の帰りを待っていた。
いつもと同じように、彼との家の、彼との部屋で。あたしの足元を、チャコールグレーの猫がうろうろと歩きまわっている。我が家の小さな飼い猫――リトル・レディは退屈そうにうにゃあと鳴いた。
ソファーに座ってテーブルの上のリモコンを手に取り、なんとなくテレビを付ける。面白い番組なんて何にもやってなくて、あたしは次々とボタンを押し、チャンネルを変えていく。そして最後に、ニュース番組にチャンネルを合わせてリモコンをテーブルに戻し、ソファーの背もたれにくたりともたれ掛かった。
明日の天気や、どこか遠く離れたところで起きた事件なんかを何度も繰り返し、怠惰に流し続けている退屈なニュースを見るともなしにぼんやりと眺めながら、あたしは二人掛けのソファーにだらしなく座っていた。
「レディ、くすぐったいわ」
長い尻尾であたしの足をふわふわと撫でながら歩き回るリトル・レディを抱き上げ、膝の上に乗せた。リトル・レディは嬉しそうに、あたしの頬をひとつぺろりと舐めた。この子はもともと、捨て猫だった。彼と二人で出掛けた時になぜだか着いて来てしまい、そのまま家で飼うことになったのだ。
しばらくの間は彼から離れようとしなかったのだけど、最近ではあたしにも懐いてくれるようになってきた。この子の種類は分からないけど、毛足が長くて人懐っこいところとかは、少しソマリに似ているかもしれない。
リトル・レディの背を二、三度撫でて、もう一度テレビに視線を向ける。見慣れたアナウンサーのお兄さんが、どこそこでこんな事件が起きましたと至極真面目な顔をして言う。ニュースというのは、何故こんなにも同じ内容ばかりを流すのだろうか。今朝にも見たはずのニュースを、どういう訳かあたしはまた眺めている。
「…?」
ふわりと、香る。……香水?
「――君の恋人、亡くなったよ」
無防備だった。
柔らかなソファーに身を委ねていたせいで、その声に反応するのが少し遅れてしまった。だぁれ? とあたしはワンテンポ遅れた返事をして、振り返る。そこに居たのは青い瞳の少年だった。
……この香りは、オードランジュヴェルト?
シトラスやミントの甘さを秘めた、清涼感のある爽やかな香りがかすかに鼻腔をくすぐる。リトル・レディもその香りを感じ取ったのか、どこか楽しげにうにゃあと鳴いた。
「…誰なの?」
「誰でも良いじゃん。そんなことより、君、“エリカ”だよね?」
この少年はどうして、あたしの名前を知っているのだろうか。……いや、そんなことよりもまず、この少年はどうやってこの家の中に入って来たのだろうか。
あたしはソファーから立ち上がり、取り敢えず玄関と窓の鍵を確認した。ここは八階建てのマンションの五階だし、玄関の鍵も窓の鍵もきちんと閉めてある。物音だって何もしなかったはず。鍵も持たずに、ここに入れる訳がないのに。
あたしは一つの答えを導き出して、一か八かと穏やかな笑みを浮かべる少年に一つ問いかけてみた。
「……どうして、あたしの前に現われたの?」
こんな突拍子もない質問に、彼は何ということもなく口を開いた。
「『どこから入って来たの』じゃないんだ。面白いね」
あはは、と少年は楽しげに声を漏らす。
楽しげに笑うその反応に、ならばこの答えは正しかったのか、とあたしは少し嬉しくなって少年を見た。子供らしい無邪気な笑顔に、あたしは少しだけ警戒を解いた。悪い人ではなさそうだから。
その瞳は、まるで澄んだ湖の色を映したかのような綺麗な青。ファウンテン・ブルーの瞳は小波一つ立ちはしない。端整な顔立ちに映える淡い青が、酷く目を引く。少年がリトル・レディを馴れた手つきで抱き上げると、リトル・レディは一つ、少年に頬ずりをした。人見知りをする子なのに、とあたしは少し驚いた。
「それじゃあエリカは、俺が何なのかもう分かってるんだ?」
「何かは、だけね。どこの誰なのかは知らないけど」
珍しいこともあるものねと言うと、少年はそうだねと頷いた。
少年の柔らかなテノールの声は聞いていてとても心地が良い。子供特有の甲高い声ではなく、落ち着いた男性の声と言ってもいいだろう。けれど、それは十歳に満たないであろう少年の姿からは酷くかけ離れていて、不自然だった。
あたしはソファーにゆっくりと腰を降ろし、少年に隣に座るよう勧めた。無言でぽんぽんとあたしの隣の位置を叩くと、彼は素直に頷き、リトル・レディを抱いたままソファーに座った。ふわふわと跳ねる茶色の猫っ毛。柔らかそうなそれに、あたしはそっと触れてみた。見た目通りの感触に、あたしは少しだけ目を細める。
「……エリカさぁ、俺が最初に言ったことちゃんと聞いてた? それが、俺がここに来た理由なんだけど」
「さあ。ガレットが死んだとか言っていたような気がするけど?」
「ああ。俺の話、ちゃんと聞いていたんだね。良かった。俺はね、エリカにそれを伝えに来たんだ」
ガレットというのは、あたしの恋人の名前。甘い甘いパイの名前を持つ彼は、本当に甘くて優しい人。その優しさはすべてのものに向いているものだから、あたしは時々嫉妬してしまうのだった。
以前、彼と買い物に出掛けた時、彼は何かにつまずいて転んだ女の人を抱え上げ、擦り剥いた膝に絆創膏を貼ってやり、そしてさらにおまじないですと言ってその上にキスをしたのだ。それも、あたしの目の前で。問い詰めると、彼はきょとんとしてあれくらい普通でしょ、と笑った。
リトル・レディの時もそうだった。ガレットの後をふらふらと着いて来る痩せこけた子猫に気が付くと、彼はその小さな体を抱き上げて、誰もがクラリと眩暈を起こしてしまいそうなほど爽やかな笑顔を浮かべてこう言ったのだ。
『――帰るところがないのかい、小さなお嬢さん(リトル・レディ)?』
リトル・レディもきっと、その笑顔に眩暈を起こしたのだろう。ここに来てからしばらくの間は、追い出してやろうかと思うくらい彼にべったりだった。彼の横にちょこんと座ってごろごろと甘えるリトル・レディを捕まえ、そこはあたしの場所なのよと諭した回数は片手の指ではもう足りないくらいだ。
彼は本当に、甘い甘いパイのような人なのだ。ちっぽけな猫でさえ落としてしまう、無自覚な女ったらし。
「それで、愛しい人が亡くなったと聞いたご感想は?」
「別に。目を開けたまま寝言を言うことができる人もいるのねっていう新鮮な驚きを感じただけよ」
「あははっ。まぁ、すぐには信じられないよね。だけど冗談でも寝言でもないよ。俺は、ホントのことしか言ってないからね」
「そう、不思議ね。君の存在は信じられるのに」
クッションを抱きしめ、目を閉じた。
「彼は死んでなんかいないわ」
「どうしてそう言い切れるの? 人間なんて、すごく脆い生き物なんだよ。どんなに健康な人でもどんなに強い人でも、いつ死んだって可笑しくない。……俺も、君の恋人も、エリカだってそうだよ。今ここで、いきなり死んでしまったとしても何ら不思議なことじゃないのに」
「……来週、あたしの誕生日なの。二十二歳になる。彼、言ったもの。『特別な日にしてあげるね』って」
「ふぅん。それで、エリカは何を頼んだの? ガラスの靴? それとも、千匹皮の金の指輪かな?」
左右に揺れるリトル・レディの長い尻尾を目で追いながら退屈そうに言う少年に、なんだか少し苛ついた。
少年の人を小馬鹿にしたような口調や表情は、酷く癪に障る。あたしは思い切り少年を睨みつけた。少年はそれに気が付いていないように、リトル・レディの尻尾を掴んでは放しを繰り返しながら続けた。
「馬鹿だね。人の生死には約束なんてものは関係ないんだよ。そんなもの、バットエンドの童話くらい不自然だ。そもそも、未来を確定させようとするその行為自体が間違っているんだから。…人間ってさ、不安定なものとか不確定なものが近くにあると落ち着かなくなる生き物なんだよ。だから無意識のうちにそれをどうにかしようとするんだ。取り除くか、むりやり確定させるか、何らかの方法でね。そして、その確定させる方法のひとつが“約束”という行為。それ自体が酷く空虚で曖昧で不確かなものであるにも関わらず、それで未来が確定されたって錯覚して、安心するんだ。あははっ、愚かしいよね、人間ってさ!」
「何よ、それ……っ」
一度怒鳴りつけてやろうかと、少年の肩を掴んだ。けれど少年は今までと何も変わらない穏やかな表情であたしを見続けている。そして、饒舌に語る。
「…一つ、いいことを教えてあげるよ。
『約束』って言うのはね、自分を安心させる為にするものなんだよ。自分の世界は今と過去だけで構成されている訳じゃない、自分たちにはこれからの人生が、未来があるんだ、…ってさ。言葉によって未来を確定させることで、その自分の理想とする未来が確実にそこに存在するものなんだって思い込むために。
皆、自分の未来は誰かと共有できて、確実に楽しいものになるって思いたいし、信じたいんだ。たとえそれが、どんなに空虚で曖昧なものだったとしてもね。……だから人はいつも、誰かと『約束』をするんだ」
…なんて悲しいことを言うのだろう。
思って、その静かに紡がれる言葉にあたしは動きを止めた。
――彼は、正しいことしか言っていない。
ガレットの生死に関する事はともかく、彼の言っていることは正しい。『約束』は、あくまでも予定であって確実な未来ではない。百%のものなんて、存在しない。完璧ではないのだ。あたしは少年の華奢な肩からゆっくりと手を離した。頭の奥の方が、すぅっと冷めていくのを感じた。
『約束』の在り方は、よく考えると酷く不自然だ。
……本当に、どうしてこんな簡単なことに今まで気付くことが出来なかったのだろう。
未来なんて、確定出来るものではないのに。
「……君って、本当に嫌だ。憎たらしい」
「どうして?」
オードランジュヴェルトの香り。
……ああ。これは彼が、あたしに贈ってくれた香りだ。
感情に任せて怒鳴りつけてやりたいけれど、もうどこをどう攻めればいいのかも分からない。甘い香りが、少年の静かな目が、あたしにブレーキを掛ける。
「瞳の色がね、ガレットと同じなのよ。綺麗なファウンテン・ブルー。顔立ちも、少し似てるかな。…怒る気失せる」
はぁと一つ溜め息を吐き、こちょこちょとリトル・レディの喉元を撫でている少年の頭にデコピンをした。パチンっと、小気味良い音がした。
「いってェ! 何だよ、何すんだよ!」
「八当たりのデコピンよ。…そんなことより、君の名前、教えてくれない? 君が何者なのかとかそういうことには別に興味ないから、偽名でも何でもいいのだけど」
少年は何だよそれ、と不貞腐れたように言った。まだ痛そうに額を撫でている。
そういえば最近爪を切っていなかったな、とあたしは爪の伸びた指先を見た。確かに、この指でデコピンをされたら相当痛いだろう。後でちゃんと切っておかないと。
「一緒に居る時間が少しでもある以上、取り敢えず便宜上名前が必要になるじゃない。呼びたい時に名前も知らないんじゃ、とても不便だわ。いつまでも『君』って呼ぶ訳にもいかないし、変じゃない。それに『おい』とか『お前』なんて呼びたくないしね。そんな呼び方されるの、君だって嫌でしょう?」
あたしはガレットと結婚し、『お前』『あなた』で呼び合いながら仲睦まじくつつましく暮らすのが夢なのだ。こんな得体のしれない少年とそんな仲良し夫婦みたいなことはしたくない。
少年はあたしの顔をちらと見て、つんと唇を尖らせた。年相応のその表情に、思いがけず笑いが込み上げてきて、あたしはクスリと声を漏らした。少年はなんだようと小さくぼやく。
「…で、名前は?」
「……それじゃあ、“ヘザー”って呼んでよ」
「変な名前」
「なら呼ばなくても良いよ」
不服そうに口を尖らせる様子はとても可愛らしい。冗談よ、とあたしは悪戯っぽく笑って見せた。
「ヘザー、ね。良い名前だわ。気に入った」
あたしはヘザーの頭から手を離し、立ち上がった。そしてくうっと一つ、伸びをした。
「お茶入れるけど、飲む?」
「…お茶よりココアが良い」
「了解」
言うと、すっごく甘いやつね、と付け足してあたしを見た。あたしはもう一度了解、と笑んだ。
「お砂糖、いくつ入れる?」
「三つ」
「三つも? まるでこども……」
――子供みたいね。
言い掛けて、相手が本当に子供なのだと思い至った。
見たところ、十歳にも満たないように思う。…いや、実年齢までは知らないが、何故だか子供の相手をしている気にならないのだ。どこかが違う。これは…、そう。“子供”ではなく“子供っぽい人”を相手にしているような感じ。“子供っぽい”、大人の人。
一歩引いて付き合うことのできる大人でありながら、子供のような無邪気な表情を見せる人。
まさかね。
ただきっと、この子が少し大人びているだけ。
雪平鍋で牛乳を温めながら、食器棚からガレットを一緒に使っているお揃いのマグカップを取り出し、ココアの粉末を入れた。ココアの粉っぽさが残らないよう、温めた牛乳を少しずつ入れ、掻き混ぜる。時間を掛けて作ったココアは、ふんわりと柔らかな香りを放ち、鼻腔をくすぐる。
「へザー、できたよ」
「ありがとう」
落ち着いたテノールの声は、やはりヘザーの見た目には酷く不似合いだ。けれど、湯気の立つココアにふうふうと息を吹きかけている姿は年相応で、違和感がある。もしこれが可愛らしいボーイソプラノの声とかだったらここまで違和感はなかっただろうし、大人びているとも思わなかったのかもしれない。
そう思いながら、ヘザーを眺めて一口、ココアを飲んだ。
猫舌なのだろうか。ヘザーは少しだけマグカップに口を着けたが、すぐに口から離し、再び息を吹き掛け始めた。
「ヘザーって不思議ね」
「何が?」
「本当に死んでいるのはあたしの方だったりしない?」
ヘザーはくすりと笑ってあたしを見た。
「エリカは生きているよ」
「…それも、“ホントのこと”しか言ってないのよね?」
「俺はウソなんか吐かないよ。口を閉ざすことはあってもね」
あたしはどうして、こんなにも穏やかなのだろう。子供は苦手だったはずなのに。どうしてヘザーが相手だとこんなにも穏やかな気持ちになれるのだろうか。分かるような気はするけれど、なんだかはっきりしなくて、曖昧な感じだ。
本当に、なんて不思議な人なのだろう。
あたしはもう一口ココアを飲んだ。
「……ガレット、帰ってこないね。遅くなるなら電話してくれればいいのに」
「彼は死んだんだよ。帰っては来ない」
「…まだ、信じない」
気弱な笑みを浮かべることのない彼の姿を見るまでは、決して、信じない。
「まだ、信じたくないわ」
困ったような笑みを浮かべることのない彼の姿を見るまでは、幻想の中にいたい。まだ、幻想の中に居させて。
もう考えることを放棄したくて、あたしはヘザーの髪を撫でた。
なんだようとあたしの手を払い除けようとするその動きは、どことなく小動物じみていて可愛らしい。そういえばガレットは動物に好かれる人だったな、と何となく懐かしくなって、あたしはもう一度ヘザーの頭を撫で回した。
「エリカ」
「何?」
ヘザーは程よく冷めたココアを一気に飲み干すと、ずい、と空になったマグカップをあたしの手に押し付けてきた。
「ココア、お代り」
「…はいはい」
空になったマグカップを受け取り、あたしはまたキッチンへと向かった。リトル・レディはヘザーの膝の上から飛び降り、その後を追って行く。
いつもと同じように、彼との家の、彼との部屋で。あたしの足元を、チャコールグレーの猫がうろうろと歩きまわっている。我が家の小さな飼い猫――リトル・レディは退屈そうにうにゃあと鳴いた。
ソファーに座ってテーブルの上のリモコンを手に取り、なんとなくテレビを付ける。面白い番組なんて何にもやってなくて、あたしは次々とボタンを押し、チャンネルを変えていく。そして最後に、ニュース番組にチャンネルを合わせてリモコンをテーブルに戻し、ソファーの背もたれにくたりともたれ掛かった。
明日の天気や、どこか遠く離れたところで起きた事件なんかを何度も繰り返し、怠惰に流し続けている退屈なニュースを見るともなしにぼんやりと眺めながら、あたしは二人掛けのソファーにだらしなく座っていた。
「レディ、くすぐったいわ」
長い尻尾であたしの足をふわふわと撫でながら歩き回るリトル・レディを抱き上げ、膝の上に乗せた。リトル・レディは嬉しそうに、あたしの頬をひとつぺろりと舐めた。この子はもともと、捨て猫だった。彼と二人で出掛けた時になぜだか着いて来てしまい、そのまま家で飼うことになったのだ。
しばらくの間は彼から離れようとしなかったのだけど、最近ではあたしにも懐いてくれるようになってきた。この子の種類は分からないけど、毛足が長くて人懐っこいところとかは、少しソマリに似ているかもしれない。
リトル・レディの背を二、三度撫でて、もう一度テレビに視線を向ける。見慣れたアナウンサーのお兄さんが、どこそこでこんな事件が起きましたと至極真面目な顔をして言う。ニュースというのは、何故こんなにも同じ内容ばかりを流すのだろうか。今朝にも見たはずのニュースを、どういう訳かあたしはまた眺めている。
「…?」
ふわりと、香る。……香水?
「――君の恋人、亡くなったよ」
無防備だった。
柔らかなソファーに身を委ねていたせいで、その声に反応するのが少し遅れてしまった。だぁれ? とあたしはワンテンポ遅れた返事をして、振り返る。そこに居たのは青い瞳の少年だった。
……この香りは、オードランジュヴェルト?
シトラスやミントの甘さを秘めた、清涼感のある爽やかな香りがかすかに鼻腔をくすぐる。リトル・レディもその香りを感じ取ったのか、どこか楽しげにうにゃあと鳴いた。
「…誰なの?」
「誰でも良いじゃん。そんなことより、君、“エリカ”だよね?」
この少年はどうして、あたしの名前を知っているのだろうか。……いや、そんなことよりもまず、この少年はどうやってこの家の中に入って来たのだろうか。
あたしはソファーから立ち上がり、取り敢えず玄関と窓の鍵を確認した。ここは八階建てのマンションの五階だし、玄関の鍵も窓の鍵もきちんと閉めてある。物音だって何もしなかったはず。鍵も持たずに、ここに入れる訳がないのに。
あたしは一つの答えを導き出して、一か八かと穏やかな笑みを浮かべる少年に一つ問いかけてみた。
「……どうして、あたしの前に現われたの?」
こんな突拍子もない質問に、彼は何ということもなく口を開いた。
「『どこから入って来たの』じゃないんだ。面白いね」
あはは、と少年は楽しげに声を漏らす。
楽しげに笑うその反応に、ならばこの答えは正しかったのか、とあたしは少し嬉しくなって少年を見た。子供らしい無邪気な笑顔に、あたしは少しだけ警戒を解いた。悪い人ではなさそうだから。
その瞳は、まるで澄んだ湖の色を映したかのような綺麗な青。ファウンテン・ブルーの瞳は小波一つ立ちはしない。端整な顔立ちに映える淡い青が、酷く目を引く。少年がリトル・レディを馴れた手つきで抱き上げると、リトル・レディは一つ、少年に頬ずりをした。人見知りをする子なのに、とあたしは少し驚いた。
「それじゃあエリカは、俺が何なのかもう分かってるんだ?」
「何かは、だけね。どこの誰なのかは知らないけど」
珍しいこともあるものねと言うと、少年はそうだねと頷いた。
少年の柔らかなテノールの声は聞いていてとても心地が良い。子供特有の甲高い声ではなく、落ち着いた男性の声と言ってもいいだろう。けれど、それは十歳に満たないであろう少年の姿からは酷くかけ離れていて、不自然だった。
あたしはソファーにゆっくりと腰を降ろし、少年に隣に座るよう勧めた。無言でぽんぽんとあたしの隣の位置を叩くと、彼は素直に頷き、リトル・レディを抱いたままソファーに座った。ふわふわと跳ねる茶色の猫っ毛。柔らかそうなそれに、あたしはそっと触れてみた。見た目通りの感触に、あたしは少しだけ目を細める。
「……エリカさぁ、俺が最初に言ったことちゃんと聞いてた? それが、俺がここに来た理由なんだけど」
「さあ。ガレットが死んだとか言っていたような気がするけど?」
「ああ。俺の話、ちゃんと聞いていたんだね。良かった。俺はね、エリカにそれを伝えに来たんだ」
ガレットというのは、あたしの恋人の名前。甘い甘いパイの名前を持つ彼は、本当に甘くて優しい人。その優しさはすべてのものに向いているものだから、あたしは時々嫉妬してしまうのだった。
以前、彼と買い物に出掛けた時、彼は何かにつまずいて転んだ女の人を抱え上げ、擦り剥いた膝に絆創膏を貼ってやり、そしてさらにおまじないですと言ってその上にキスをしたのだ。それも、あたしの目の前で。問い詰めると、彼はきょとんとしてあれくらい普通でしょ、と笑った。
リトル・レディの時もそうだった。ガレットの後をふらふらと着いて来る痩せこけた子猫に気が付くと、彼はその小さな体を抱き上げて、誰もがクラリと眩暈を起こしてしまいそうなほど爽やかな笑顔を浮かべてこう言ったのだ。
『――帰るところがないのかい、小さなお嬢さん(リトル・レディ)?』
リトル・レディもきっと、その笑顔に眩暈を起こしたのだろう。ここに来てからしばらくの間は、追い出してやろうかと思うくらい彼にべったりだった。彼の横にちょこんと座ってごろごろと甘えるリトル・レディを捕まえ、そこはあたしの場所なのよと諭した回数は片手の指ではもう足りないくらいだ。
彼は本当に、甘い甘いパイのような人なのだ。ちっぽけな猫でさえ落としてしまう、無自覚な女ったらし。
「それで、愛しい人が亡くなったと聞いたご感想は?」
「別に。目を開けたまま寝言を言うことができる人もいるのねっていう新鮮な驚きを感じただけよ」
「あははっ。まぁ、すぐには信じられないよね。だけど冗談でも寝言でもないよ。俺は、ホントのことしか言ってないからね」
「そう、不思議ね。君の存在は信じられるのに」
クッションを抱きしめ、目を閉じた。
「彼は死んでなんかいないわ」
「どうしてそう言い切れるの? 人間なんて、すごく脆い生き物なんだよ。どんなに健康な人でもどんなに強い人でも、いつ死んだって可笑しくない。……俺も、君の恋人も、エリカだってそうだよ。今ここで、いきなり死んでしまったとしても何ら不思議なことじゃないのに」
「……来週、あたしの誕生日なの。二十二歳になる。彼、言ったもの。『特別な日にしてあげるね』って」
「ふぅん。それで、エリカは何を頼んだの? ガラスの靴? それとも、千匹皮の金の指輪かな?」
左右に揺れるリトル・レディの長い尻尾を目で追いながら退屈そうに言う少年に、なんだか少し苛ついた。
少年の人を小馬鹿にしたような口調や表情は、酷く癪に障る。あたしは思い切り少年を睨みつけた。少年はそれに気が付いていないように、リトル・レディの尻尾を掴んでは放しを繰り返しながら続けた。
「馬鹿だね。人の生死には約束なんてものは関係ないんだよ。そんなもの、バットエンドの童話くらい不自然だ。そもそも、未来を確定させようとするその行為自体が間違っているんだから。…人間ってさ、不安定なものとか不確定なものが近くにあると落ち着かなくなる生き物なんだよ。だから無意識のうちにそれをどうにかしようとするんだ。取り除くか、むりやり確定させるか、何らかの方法でね。そして、その確定させる方法のひとつが“約束”という行為。それ自体が酷く空虚で曖昧で不確かなものであるにも関わらず、それで未来が確定されたって錯覚して、安心するんだ。あははっ、愚かしいよね、人間ってさ!」
「何よ、それ……っ」
一度怒鳴りつけてやろうかと、少年の肩を掴んだ。けれど少年は今までと何も変わらない穏やかな表情であたしを見続けている。そして、饒舌に語る。
「…一つ、いいことを教えてあげるよ。
『約束』って言うのはね、自分を安心させる為にするものなんだよ。自分の世界は今と過去だけで構成されている訳じゃない、自分たちにはこれからの人生が、未来があるんだ、…ってさ。言葉によって未来を確定させることで、その自分の理想とする未来が確実にそこに存在するものなんだって思い込むために。
皆、自分の未来は誰かと共有できて、確実に楽しいものになるって思いたいし、信じたいんだ。たとえそれが、どんなに空虚で曖昧なものだったとしてもね。……だから人はいつも、誰かと『約束』をするんだ」
…なんて悲しいことを言うのだろう。
思って、その静かに紡がれる言葉にあたしは動きを止めた。
――彼は、正しいことしか言っていない。
ガレットの生死に関する事はともかく、彼の言っていることは正しい。『約束』は、あくまでも予定であって確実な未来ではない。百%のものなんて、存在しない。完璧ではないのだ。あたしは少年の華奢な肩からゆっくりと手を離した。頭の奥の方が、すぅっと冷めていくのを感じた。
『約束』の在り方は、よく考えると酷く不自然だ。
……本当に、どうしてこんな簡単なことに今まで気付くことが出来なかったのだろう。
未来なんて、確定出来るものではないのに。
「……君って、本当に嫌だ。憎たらしい」
「どうして?」
オードランジュヴェルトの香り。
……ああ。これは彼が、あたしに贈ってくれた香りだ。
感情に任せて怒鳴りつけてやりたいけれど、もうどこをどう攻めればいいのかも分からない。甘い香りが、少年の静かな目が、あたしにブレーキを掛ける。
「瞳の色がね、ガレットと同じなのよ。綺麗なファウンテン・ブルー。顔立ちも、少し似てるかな。…怒る気失せる」
はぁと一つ溜め息を吐き、こちょこちょとリトル・レディの喉元を撫でている少年の頭にデコピンをした。パチンっと、小気味良い音がした。
「いってェ! 何だよ、何すんだよ!」
「八当たりのデコピンよ。…そんなことより、君の名前、教えてくれない? 君が何者なのかとかそういうことには別に興味ないから、偽名でも何でもいいのだけど」
少年は何だよそれ、と不貞腐れたように言った。まだ痛そうに額を撫でている。
そういえば最近爪を切っていなかったな、とあたしは爪の伸びた指先を見た。確かに、この指でデコピンをされたら相当痛いだろう。後でちゃんと切っておかないと。
「一緒に居る時間が少しでもある以上、取り敢えず便宜上名前が必要になるじゃない。呼びたい時に名前も知らないんじゃ、とても不便だわ。いつまでも『君』って呼ぶ訳にもいかないし、変じゃない。それに『おい』とか『お前』なんて呼びたくないしね。そんな呼び方されるの、君だって嫌でしょう?」
あたしはガレットと結婚し、『お前』『あなた』で呼び合いながら仲睦まじくつつましく暮らすのが夢なのだ。こんな得体のしれない少年とそんな仲良し夫婦みたいなことはしたくない。
少年はあたしの顔をちらと見て、つんと唇を尖らせた。年相応のその表情に、思いがけず笑いが込み上げてきて、あたしはクスリと声を漏らした。少年はなんだようと小さくぼやく。
「…で、名前は?」
「……それじゃあ、“ヘザー”って呼んでよ」
「変な名前」
「なら呼ばなくても良いよ」
不服そうに口を尖らせる様子はとても可愛らしい。冗談よ、とあたしは悪戯っぽく笑って見せた。
「ヘザー、ね。良い名前だわ。気に入った」
あたしはヘザーの頭から手を離し、立ち上がった。そしてくうっと一つ、伸びをした。
「お茶入れるけど、飲む?」
「…お茶よりココアが良い」
「了解」
言うと、すっごく甘いやつね、と付け足してあたしを見た。あたしはもう一度了解、と笑んだ。
「お砂糖、いくつ入れる?」
「三つ」
「三つも? まるでこども……」
――子供みたいね。
言い掛けて、相手が本当に子供なのだと思い至った。
見たところ、十歳にも満たないように思う。…いや、実年齢までは知らないが、何故だか子供の相手をしている気にならないのだ。どこかが違う。これは…、そう。“子供”ではなく“子供っぽい人”を相手にしているような感じ。“子供っぽい”、大人の人。
一歩引いて付き合うことのできる大人でありながら、子供のような無邪気な表情を見せる人。
まさかね。
ただきっと、この子が少し大人びているだけ。
雪平鍋で牛乳を温めながら、食器棚からガレットを一緒に使っているお揃いのマグカップを取り出し、ココアの粉末を入れた。ココアの粉っぽさが残らないよう、温めた牛乳を少しずつ入れ、掻き混ぜる。時間を掛けて作ったココアは、ふんわりと柔らかな香りを放ち、鼻腔をくすぐる。
「へザー、できたよ」
「ありがとう」
落ち着いたテノールの声は、やはりヘザーの見た目には酷く不似合いだ。けれど、湯気の立つココアにふうふうと息を吹きかけている姿は年相応で、違和感がある。もしこれが可愛らしいボーイソプラノの声とかだったらここまで違和感はなかっただろうし、大人びているとも思わなかったのかもしれない。
そう思いながら、ヘザーを眺めて一口、ココアを飲んだ。
猫舌なのだろうか。ヘザーは少しだけマグカップに口を着けたが、すぐに口から離し、再び息を吹き掛け始めた。
「ヘザーって不思議ね」
「何が?」
「本当に死んでいるのはあたしの方だったりしない?」
ヘザーはくすりと笑ってあたしを見た。
「エリカは生きているよ」
「…それも、“ホントのこと”しか言ってないのよね?」
「俺はウソなんか吐かないよ。口を閉ざすことはあってもね」
あたしはどうして、こんなにも穏やかなのだろう。子供は苦手だったはずなのに。どうしてヘザーが相手だとこんなにも穏やかな気持ちになれるのだろうか。分かるような気はするけれど、なんだかはっきりしなくて、曖昧な感じだ。
本当に、なんて不思議な人なのだろう。
あたしはもう一口ココアを飲んだ。
「……ガレット、帰ってこないね。遅くなるなら電話してくれればいいのに」
「彼は死んだんだよ。帰っては来ない」
「…まだ、信じない」
気弱な笑みを浮かべることのない彼の姿を見るまでは、決して、信じない。
「まだ、信じたくないわ」
困ったような笑みを浮かべることのない彼の姿を見るまでは、幻想の中にいたい。まだ、幻想の中に居させて。
もう考えることを放棄したくて、あたしはヘザーの髪を撫でた。
なんだようとあたしの手を払い除けようとするその動きは、どことなく小動物じみていて可愛らしい。そういえばガレットは動物に好かれる人だったな、と何となく懐かしくなって、あたしはもう一度ヘザーの頭を撫で回した。
「エリカ」
「何?」
ヘザーは程よく冷めたココアを一気に飲み干すと、ずい、と空になったマグカップをあたしの手に押し付けてきた。
「ココア、お代り」
「…はいはい」
空になったマグカップを受け取り、あたしはまたキッチンへと向かった。リトル・レディはヘザーの膝の上から飛び降り、その後を追って行く。
「――どうして気付かないかなぁ」
エリカの後ろ姿にヘザーはぽつりと呟いた。
自分だけに聞こえるように。
エリカの後ろ姿にヘザーはぽつりと呟いた。
自分だけに聞こえるように。