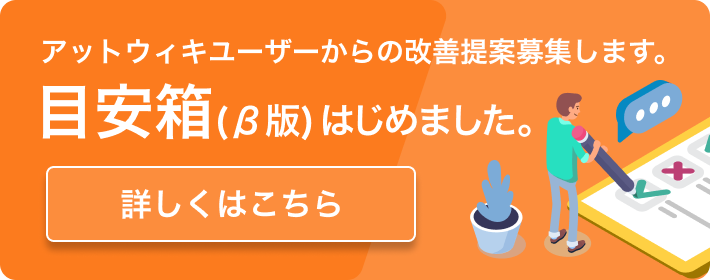もう、三月なのに。そんな呟きが気だるげに街中を覆っていく。灰色の空からは、雪が
ちらちらと降ってくるものだから、私も少し空を見上げて、ひとつ溜め息を吐いたりした。
子供の頃、あんなに雪に対して心が躍っていた気持ちは一体、今はどこに隠れてしまっ
てるのだろう。そりゃあ皆といるときだったら舞い上がったりもするだろうけど、今はこ
うして、二人きりな訳だし。
「持つべきものは、温かい手の恋人」
失った温もりを捜し求めて、彼女は私の手を握る。振り解く理由もないけれど、何だか
複雑な気持ちが胸にうずまく。私は結局、あなたの暖房機程度の存在、かしら。
「こんな日に外出なんて。って、後悔してる?」
「ううん。ぜんぜん」
赤ら顔のまま微笑んで、彼女はそう答える。私の手を握る力が少しだけ強くなったから、
それが彼女の本心であると信じることにした。元々、気の効いた嘘なんかつける性格じゃ
ないのだ。
すっかり寂れてしまっていた場末の水族館は、バブル期の忘れ物のようだった。
子供に向けたアニメばかり上映していた映画館では、さすがの私たちも退屈をしのげそ
うになかったから、そのまま近くに見えた喫茶店に入って、真昼間から取り留めもない雑
談のみでしばらく盛り上がると、何だか人の入りも増えてきたので、さてと二人して立ち
上がったときには、もう窓の外ではすっかり、雪がちらちら見えていたらしい。
伝票を彼女に取られてしまった悔しさも忘れられないまま、外を見ると雪まで降ってる
し、何だか気分が少しめげてしまいそうだった。
「ねぇ、つむぎ」
横を向くと、悪戯っぽい表情の上に、更に微笑を乗っけて、彼女は私の反応を窺ってい
るようだった。
少なからず驚いてしまったのは、もちろん。普段の呼び名とは違う呼び方で名前を呼ば
れたから。呼び方が変わると、何だか声の取り巻く雰囲気まで一変したように錯覚してし
まう。どうしてだろう。目の前にいるのは、いつもの彼女なのに。
「なぁに? ゆい」
仕返しのつもりで便乗してみても、不思議と私が恥ずかしいだけだった。
通りはやたらと車が混んでいた。赤信号が待ちきれないドライバーの、開けた窓から飛
び出る逞しい右手の人差し指と中指の間には、白い煙草が挟まっていた。ゆっくりと下り
てくる雪に逆らって、煙草の煙は空高く上っていく。
だが、白い煙はその途中で、冷たい空気の中に、雪みたいに消えていくのだ。
後ろからゆっくり走ってくるバスが私たちを抜かしていって、少し先のバス亭で停車す
るのが見えた。扉が開いて、何人かの人達が降りていく流れを眺めていると、何故だか急
に、私たち二人を恋人同士であると認識できた人は、あの中には一体何人くらいいるのだ
ろうか? なんて、答えのわかりっこない疑問に辿りつく。
手も繋いでいるし、二人とも、頬は赤いし。よく観察すれば、わかると思うのだけれど。
「私のはつ恋って、何歳の頃かわかる? つむぎ」
ああ、もう。まだその悪ふざけ、続いてたの? と心の中で呟いて、眉根を寄せる。
人通りは、目にみえて少なくなっていく。まるで恋人たちのためだけの街通りみたいだ。
「さあ。唯ちゃんのことだから、幼稚園とか?」
答え終えた辺りで、ポケットの中の携帯電話が鳴っているのに気がついた。マナーモー
ドだから音は鳴らないけれど、バイブが震えて、私にそれを知らせる。誰かからの着信で
あった。
けれど私は、それに応じない。だって、今は彼女と、二人きりだから。
「えー。なんで私のことだから、幼稚園?」
「だって、惚れっぽいじゃない?」
私がそう言うと、彼女はいかにも心外であると言いたげな表情で私を見た。
「そんなことないもん。つむぎには、わかんないだろうけどさ」
口を前に尖らせて、不満げに反論を述べる彼女は、やたらに子供っぽい。
「じゃあ、何歳なの? 言ってみて」
「もう、だめ。つむぎには教えないー」
亜麻色の緩くウェーブの掛かった彼女の髪に、白い雪がたくさん踊っている。長い睫の上
とか、赤味の差した頬の真ん中とかにも、雪がちらちらと乗っている。
あてもなく歩いていく内に、段々と街の外れの方に向かっていく。あまり歩いたことのな
い方角だから、何があるのかわからないけれど、こうして二人して話しながら散歩している
だけで、空の上を飛び回ってるみたいに楽しいんだもの。歩みを止められそうにない。
三月の雪は、あまり寒さを感じない。私の体温が高いだけかもしれないけれど、隣の彼女
も私の腕にくっついて、少しも寒そうじゃない。
「どうして、つむぎ、って言うんだろうね」
人気のない並木道に、彼女の声は高く木魂していく。風にあおられて揺れる木々から、小
さな雪の塊がたくさん落ちてきて、その音に驚いた小鳥は、一斉に南の方へ飛び立っていく。
「お父様が名付けてくださったらしいの。でも、詳しい理由とかは、聞いてないわ」
「可愛いくて、ぴったりだね」
褒められているらしい。けれど何故だか、素直に受け入れたくない。
「ねぇ。はつ恋はいつなの?」
「だからそれは、もう教えない」
仕返し。というふうに、私に向けて舌を出した。
「お願い。気になってきちゃった」
ひとつだけ溜め息を吐いて、それから、しばしの静寂。胸に心地よい沈黙は、彼女と紡い
できた良好な関係の賜物であると思う。そりゃあ、たまに喧嘩することくらい、あるけどさ。
「……つむぎが聞いたら、きっといい気になるから、嫌」
あ。何だかその返答で、ちょっとだけわかった気がした。
辺りは静けさに包まれて、もうすぐ夕闇も下りてくる。けれど時計は見ない。彼女と二人
きりでいるときに、そんな野暮なことはしない。
呆けてるみたいに、彼女の口は半開きで、もしかしたら、それは私のキスを待っていたか
らなのかもしれない。
「ありがとね」
何に対して感謝の言葉を送ったのかも、よくわからない。よくわからないけれど、なぜだ
か無性に私は、その言葉が言いたかったのだ。だからそれは、仕方がない。
街に暗幕が下がって、街灯がゆらめく明かりで仄暗い道を照らし出す。白い空に隠れた太
陽からは、もう光が見えてこない。さすがに、少しだけ寒くなってきた。
「ねぇ。だから、……幸せにしてね」
いつか、別れてしまうかもしれない。別れないかもしれない。だから不安に思うし、一縷
だけれど、希望も湧いてくる。
言葉だけは本物だし、温もりだけは確かだから。だから私たちは不安定なバランスのまま、
口付けをするし、セックスもする。それだけしかないと言われたらそれまでだけれど、じゃ
あ他に一体、何が必要なのだろう。
愛と、愛を確かめ合うだけの肉体と。他に一体、何が。
「ずっと一緒だなんて、陳腐な言葉でも、良いかしら」
少し背の低い彼女の身体を、思い切り抱き寄せると、壊れてしまいそうで悲しかった。
私の問いに、彼女は何度も力強く頷く。
舞い降りてくる雪のせいで、奪われていく私たち二人分の体温を、どうにか繋ぎとめよう
と、精一杯だった。
少し背の低い彼女の身体を、思い切り抱き寄せると、壊れてしまいそうで悲しかった。
私の問いに、彼女は何度も力強く頷く。
舞い降りてくる雪のせいで、奪われていく私たち二人分の体温を、どうにか繋ぎとめようと、精一杯だった。
ちらちらと降ってくるものだから、私も少し空を見上げて、ひとつ溜め息を吐いたりした。
子供の頃、あんなに雪に対して心が躍っていた気持ちは一体、今はどこに隠れてしまっ
てるのだろう。そりゃあ皆といるときだったら舞い上がったりもするだろうけど、今はこ
うして、二人きりな訳だし。
「持つべきものは、温かい手の恋人」
失った温もりを捜し求めて、彼女は私の手を握る。振り解く理由もないけれど、何だか
複雑な気持ちが胸にうずまく。私は結局、あなたの暖房機程度の存在、かしら。
「こんな日に外出なんて。って、後悔してる?」
「ううん。ぜんぜん」
赤ら顔のまま微笑んで、彼女はそう答える。私の手を握る力が少しだけ強くなったから、
それが彼女の本心であると信じることにした。元々、気の効いた嘘なんかつける性格じゃ
ないのだ。
すっかり寂れてしまっていた場末の水族館は、バブル期の忘れ物のようだった。
子供に向けたアニメばかり上映していた映画館では、さすがの私たちも退屈をしのげそ
うになかったから、そのまま近くに見えた喫茶店に入って、真昼間から取り留めもない雑
談のみでしばらく盛り上がると、何だか人の入りも増えてきたので、さてと二人して立ち
上がったときには、もう窓の外ではすっかり、雪がちらちら見えていたらしい。
伝票を彼女に取られてしまった悔しさも忘れられないまま、外を見ると雪まで降ってる
し、何だか気分が少しめげてしまいそうだった。
「ねぇ、つむぎ」
横を向くと、悪戯っぽい表情の上に、更に微笑を乗っけて、彼女は私の反応を窺ってい
るようだった。
少なからず驚いてしまったのは、もちろん。普段の呼び名とは違う呼び方で名前を呼ば
れたから。呼び方が変わると、何だか声の取り巻く雰囲気まで一変したように錯覚してし
まう。どうしてだろう。目の前にいるのは、いつもの彼女なのに。
「なぁに? ゆい」
仕返しのつもりで便乗してみても、不思議と私が恥ずかしいだけだった。
通りはやたらと車が混んでいた。赤信号が待ちきれないドライバーの、開けた窓から飛
び出る逞しい右手の人差し指と中指の間には、白い煙草が挟まっていた。ゆっくりと下り
てくる雪に逆らって、煙草の煙は空高く上っていく。
だが、白い煙はその途中で、冷たい空気の中に、雪みたいに消えていくのだ。
後ろからゆっくり走ってくるバスが私たちを抜かしていって、少し先のバス亭で停車す
るのが見えた。扉が開いて、何人かの人達が降りていく流れを眺めていると、何故だか急
に、私たち二人を恋人同士であると認識できた人は、あの中には一体何人くらいいるのだ
ろうか? なんて、答えのわかりっこない疑問に辿りつく。
手も繋いでいるし、二人とも、頬は赤いし。よく観察すれば、わかると思うのだけれど。
「私のはつ恋って、何歳の頃かわかる? つむぎ」
ああ、もう。まだその悪ふざけ、続いてたの? と心の中で呟いて、眉根を寄せる。
人通りは、目にみえて少なくなっていく。まるで恋人たちのためだけの街通りみたいだ。
「さあ。唯ちゃんのことだから、幼稚園とか?」
答え終えた辺りで、ポケットの中の携帯電話が鳴っているのに気がついた。マナーモー
ドだから音は鳴らないけれど、バイブが震えて、私にそれを知らせる。誰かからの着信で
あった。
けれど私は、それに応じない。だって、今は彼女と、二人きりだから。
「えー。なんで私のことだから、幼稚園?」
「だって、惚れっぽいじゃない?」
私がそう言うと、彼女はいかにも心外であると言いたげな表情で私を見た。
「そんなことないもん。つむぎには、わかんないだろうけどさ」
口を前に尖らせて、不満げに反論を述べる彼女は、やたらに子供っぽい。
「じゃあ、何歳なの? 言ってみて」
「もう、だめ。つむぎには教えないー」
亜麻色の緩くウェーブの掛かった彼女の髪に、白い雪がたくさん踊っている。長い睫の上
とか、赤味の差した頬の真ん中とかにも、雪がちらちらと乗っている。
あてもなく歩いていく内に、段々と街の外れの方に向かっていく。あまり歩いたことのな
い方角だから、何があるのかわからないけれど、こうして二人して話しながら散歩している
だけで、空の上を飛び回ってるみたいに楽しいんだもの。歩みを止められそうにない。
三月の雪は、あまり寒さを感じない。私の体温が高いだけかもしれないけれど、隣の彼女
も私の腕にくっついて、少しも寒そうじゃない。
「どうして、つむぎ、って言うんだろうね」
人気のない並木道に、彼女の声は高く木魂していく。風にあおられて揺れる木々から、小
さな雪の塊がたくさん落ちてきて、その音に驚いた小鳥は、一斉に南の方へ飛び立っていく。
「お父様が名付けてくださったらしいの。でも、詳しい理由とかは、聞いてないわ」
「可愛いくて、ぴったりだね」
褒められているらしい。けれど何故だか、素直に受け入れたくない。
「ねぇ。はつ恋はいつなの?」
「だからそれは、もう教えない」
仕返し。というふうに、私に向けて舌を出した。
「お願い。気になってきちゃった」
ひとつだけ溜め息を吐いて、それから、しばしの静寂。胸に心地よい沈黙は、彼女と紡い
できた良好な関係の賜物であると思う。そりゃあ、たまに喧嘩することくらい、あるけどさ。
「……つむぎが聞いたら、きっといい気になるから、嫌」
あ。何だかその返答で、ちょっとだけわかった気がした。
辺りは静けさに包まれて、もうすぐ夕闇も下りてくる。けれど時計は見ない。彼女と二人
きりでいるときに、そんな野暮なことはしない。
呆けてるみたいに、彼女の口は半開きで、もしかしたら、それは私のキスを待っていたか
らなのかもしれない。
「ありがとね」
何に対して感謝の言葉を送ったのかも、よくわからない。よくわからないけれど、なぜだ
か無性に私は、その言葉が言いたかったのだ。だからそれは、仕方がない。
街に暗幕が下がって、街灯がゆらめく明かりで仄暗い道を照らし出す。白い空に隠れた太
陽からは、もう光が見えてこない。さすがに、少しだけ寒くなってきた。
「ねぇ。だから、……幸せにしてね」
いつか、別れてしまうかもしれない。別れないかもしれない。だから不安に思うし、一縷
だけれど、希望も湧いてくる。
言葉だけは本物だし、温もりだけは確かだから。だから私たちは不安定なバランスのまま、
口付けをするし、セックスもする。それだけしかないと言われたらそれまでだけれど、じゃ
あ他に一体、何が必要なのだろう。
愛と、愛を確かめ合うだけの肉体と。他に一体、何が。
「ずっと一緒だなんて、陳腐な言葉でも、良いかしら」
少し背の低い彼女の身体を、思い切り抱き寄せると、壊れてしまいそうで悲しかった。
私の問いに、彼女は何度も力強く頷く。
舞い降りてくる雪のせいで、奪われていく私たち二人分の体温を、どうにか繋ぎとめよう
と、精一杯だった。
少し背の低い彼女の身体を、思い切り抱き寄せると、壊れてしまいそうで悲しかった。
私の問いに、彼女は何度も力強く頷く。
舞い降りてくる雪のせいで、奪われていく私たち二人分の体温を、どうにか繋ぎとめようと、精一杯だった。