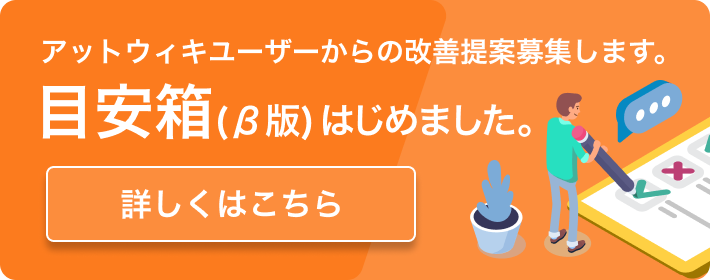「070321_2」(2007/04/16 (月) 14:46:39) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
****Jungle'sValentine.5(二:43-51)
<<5>>
→A:すぐに学校に行って教室で転校生を待とう。
余計な事をして面倒な目に遭うのはやはり避けたい。オレは駆け足で学校に向かう事にした。
元々、歩いても30分とかからない距離にある学校だ。走れば10分もあれば着く。
オレの通う学校の名前は『私立雀友学園』。「雀友」は「ジャングル」と読むらしい。どんな当て字なんだかさっぱりだが、
どうせ知ったところで無駄な知識がまた脳のキャパシティを切迫するだけだからあえてグゥには聞いていない。
雀友学園は小・中・高までを一つの敷地内に収める巨大な学校だ。グプタはその高校校舎にいるはずだが、そちら側には
見えない壁があってどうしても行く事が出来なかった。
最初はこの細くうねった道路…グゥによると日本の道路はこんな風らしい…にも困惑したけど、今や目を瞑ってでも学校まで
行ける自信がある。この道はいつも車も通っていないし、歩行者もいない。リタのいる曲がり角までは遠慮なく走り抜けられる。
リタとの遭遇ポイントはあと二つ先の曲がり角だ。オレは走る速度をぐんぐんと上げ、スピードを落とさず一つ目の角を曲がった。
「…む?」
「え、うわっ!?」
───居ないはずだった。……誰もそこには、居ないはずだった。
勢い良くカーブを曲がろうとした瞬間、突然現れた人影に驚き、オレは足がもつれそのままの勢いでその人影に
激突してしまった。
(──あれ……?)
しかし激突の衝撃はまるで無く、代わりにふわりと身体が浮いたような感覚だけがその身を包んだ。
オレはまるで空を飛んでいるような感覚を覚えながら、激突の際の勢いを失うまでその人影と共に宙を舞っていた。
そのうちにすとんと、何の衝撃も無く足が地面に着く。一体今の浮遊感は何だったのか、慌てて後ろを振り返ると、
今自分が立っている場所は曲がり角から数メートル先の地点だった。
信じ難い事だが、その人影はまるで自身をクッションにするかのように瞬時にオレを抱きかかえたまま後ろに飛び、
その勢いを殺した、と解釈するしか無かった。
「大丈夫か」
「え? あ、え!?」
いまだ混乱する脳を更に揺さぶる、やけに感情の篭らない淡白な声。その聞き覚えのある声のした方を見上げると、
そこにはやはり見覚えのある顔があった。
透き通るような白い肌。風に揺れる桜色の長い髪。切れ長の目の奥には、髪の色を深くしたような朱が淡く輝く。
オレを優しく抱き締める腕からはその繊細さに見合わぬ力強さを感じる。そしてオレを全身で受け止めてくれたその身体は
女性ならではの柔らかさを持ち、特に顔に触れている部分のそれは今もクッションの様なふくよかな心地よさと温もりを
オレに与えてくれた。先ほどの空中遊泳で強張った身体の緊張も、解れて行く……この感触は……。
「──って、ご、ごごごごめんなさい!!」
「む?」
オレは自分よりも頭二つ分近くも背の高い女性に抱えられる形になっていた。思いっきり身体ごとぶつかって、オレの方からも
無意識にぎゅっと抱き締めてしまい、自らの顔でその女性の柔らかい二つの膨らみを思い切り押し潰してしまっていたのだ。
その感触の正体に気付いた瞬間、オレは自分でも驚く程の勢いで弾かれるように後ろに下がった。肩をしっかり抱えられて
いたため、離れたのは顔と手だけだったけど……。
「どうした?」
「いや、あのその……ありがと……?」
「……ふふっ、謝ったり礼を言ったり、忙しいな、ハレは」
ダメだ、まだ頭が混乱している。まるで思考がまとまらない。聞きたい事も言いたい事もいっぱいあるはずなのに。
いまだ顔に残る先ほどの感触の余韻が、その感触の元である至近距離で眼前に広がる二つの膨らみが、オレの頭を沸騰させる。
「Oh……ジャパニーズ・バカップルね」
いよいよオレの脳が混乱を極めている中、前方から珍妙なイントネーションの声が聞こえた。
そしてグゥの背後から、オレよりも頭半分くらい背の高い金髪の少女の姿が現われる。
少女は物珍しげな目線を投げかけながら、トコトコとオレの横を通り過ぎていく。
そうか、オレがここでグゥとぶつかっちゃったから、リタの方は無事に曲がり角を抜けられたのか。
「これハごちそうさまデース」
そのまま、よく解らないコトを口走りながら少女は曲がり角の向こうへ消えて行った。
……リタ……いつも思ってたけど、なんでこの世界じゃそんなキャラなんだ……?
「痛む箇所は無いか?」
「へ? え、あ……う、うん」
変なタイミングが重なり、逆に頭の回転が戻ってきた。リタとのフラグはこれで折れてしまっただろうけど、まぁいいか。
おかげで少し冷静になれたし。
「大丈夫……かな、多分」
オレの言葉に彼女は薄く微笑み、そうか、と返すとようやく身体を離してくれた。そして目の前にしゃがみこむとオレの身体の
無事を確認するようにぽんぽんと肩や腰に手を触れる。
「……怪我は無いようだな」
再び、カァッと顔が熱くなる。大人状態とはいえ、オレの良く知る人物と同じ姿をした人にそんな風に子供扱いされた事も、
先ほどまで一人でわたわたと狼狽していた事も、なんだかとてつもなく恥ずかしく思えてしまった。
「あああの、改めて…ありがと、助けてくれて! それにぶつかっちゃって、ごめんっ」
「ん? ふふ……うん、私も少し驚いたぞ」
言いながら、オレはグゥから逃れるように手を前に掲げ後ずさる。そんなオレの様子にまたグゥは微笑みを向けた。
……うう、死ぬほど恥ずかしい。
それでも何故か、その顔を見ているうちに先ほどよりは頭の熱は収まった。代わりに身体の表面が燃えるように熱いが……。
とにかく、思ったとおりに口が利けるくらいには回復出来たようだ。これもリタのおかげ、なのかな?
「グ、グゥ……?」
「ん、何だ?」
オレの問いかけに、彼女は微笑みを崩さぬまま真っ直ぐに応える。
やはり、グゥで間違いないようだ。ただグゥと言ってもオレの良く知る性悪少女では無く、その腹の中にだけ存在する
もう一人のグゥ。本物とは性格も口調も、随分と違うイメージを持つこの大人の女性をただグゥとだけ呼んで良いのかは
解らないが、他に呼びようが無いしずっとグゥ(大)と呼ぶのもなんだか気が引ける。まあ今はグゥ、と呼ばせてもらおう。
「えっと、何でこんな所にいるの?」
「……少し、散歩をしていたのだ」
「散歩?」
「ああ、この世界は実に興味深い」
グゥはしゃがんだまま、オレの両肩を支えにするように手を置き空を見上げる。言葉の意味は良く解らなかったけど、
オレは彼女のそんな仕草を見るだけで、なんだか体温がまた上昇してしまった気がした。
慌ててオレもグゥの姿をその目に映さぬように空を見上げる。そこには鳥一つ飛んではいなかったけど、その青空は
現実世界と同じように、どこまでも続いているようだった。
「……………」
「……え、な、何?」
気付けば、彼女の目線は既に空に無く、オレに真っ直ぐに注がれていた。体温と共にドキンと、鼓動までが上がってしまう。
「うむ、しばらく会わぬうちに随分と見違えたな」
「は…?」
グゥは一人で何かを納得したようにうんうんと頷くと、オレの首元に手を添えて来る。少し驚き身を引いてしまったが、グゥは
構わず指を伸ばし、よれていたネクタイに指をかけ、キュッと真っ直ぐに正してくれた。
「このような格好をしているから尚更か。凛々しいぞ、ハレ」
「…え……あ、そ、そんなこと……」
そんな言葉と共に、ニコリと微笑みまで投げ掛けられる。ついでに再度肩に置かれたその手にもきゅ、と力が込められる。
もうそれだけで、ボボッと音が出んばかりに、身体から湯気が出そうな程に体温が上昇してしまう。
何故こんなことがこんなに恥ずかしいのか。それが解らなくてまた恥ずかしくなって、身体の熱も心臓の音も再現なく
高まり続けてしまう。
オレは動揺を悟られぬように、グゥの微笑みから逃れるように目線を下に切った。しかしその先からもオレを困惑させるものが
視界に飛び込んでくる。
先ほどまで顔を埋めていた膨らみの先に見える、すらりと伸びた真っ白な脚。立て膝を付く形で縦に開いた脚は、立っていても
膝まで届くとは到底思えない長さのスカートを自然に捲くり上げ、本来そのヒラヒラとした布地が覆うべき場所をほとんど
申し訳程度に隠しているだけだった。
何故今まで気付かなかったのか、良く見てみればグゥの服装も普段のものではなく、まるで今朝見たマリィのような格好をしていた。
淡い桃色の上着は普通のシャツのようにボタンの付いた前留めタイプ。幅広の襟と袖には濃いピンクのラインが一本入り、
胸元はVの字に大きく開かれていた。藍色のリボンはマリィの制服のように大きな物ではなく、細いリボンタイを蝶結びにした
シンプルなもの。スカートは太い線と細い線が交互に、縦横に入るチェック柄。生地も柄も、配色は青系統で統一されている。
デザインこそ違えど、やはりそれはこの世界の、恐らくは日本の学校で使用されている制服と呼ばれているものに相違無かった。
そして明らかにその丈は、グゥの高身長に適合しているようには思えなかった。ワンサイズ以上小さくないか……?
「グ、グゥこそどうしたのさ、その格好」
「ん?おお、これか。この世界が今のように変わった後に、ともよに手渡されてな」
オレは慌ててもう一度目線を外し、中空に目を泳がせる。もうグゥの姿そのものを見ていられない。傍目から見たらかなり
挙動不審に映っていただろうが、グゥはさして気にした様子も無くオレの質問に応えてくれた。
「私もたまには、見栄えくらいは変化を付けようと思い着てみたのだが……どうだ、少しは変わったか?」
グゥはスックと立ち上がると、その場でファッションモデルのようにくるんと回ってみせる。その動きに合わせ、やはり
想像通りの短さだったスカートがふわりと浮かび、その白い肢体を惜しげもなく晒す。
オレの目はいよいよその置き所を失い、ますます挙動不審にきょろきょろとグゥの周囲を泳いでしまう。
「なんだ、ハレはあまり好きではないようだな」
「い、いやそんなことは無いんだけど……オレは普段の格好の方が好きかなぁ~……」
自分でも何故そんなにその格好にドギマギしてしまうのか、良く解らなかった。肌の露出によるものか、とも考えたが、
普段着ている、全身を包み込む筒のようなワンピースを胸に巻かれた布で止めているだけの服装だって肩や胸元が大きく
露出しているのだ。でも、あの格好をそんなに意識した憶えは無い。今の格好は肩の代わりに脚が大きく露出しているが、
ここまで自分が動揺してしまう程のものとは思えなかった。元々オレは常夏のジャングルに住んでいるのだ。露出度で言えば、
村の大人の女性の姿は今のグゥの比では無い。母さんに至っては家じゃ裸がユニフォームだ。まぁ母さんの場合は、ただ肉親って
だけじゃなく下着姿のまま外にも出歩いてしまうような人間をオレが女として認識していないせいかもしれないが。
「ハレはあの格好の方が良いのか……」
グゥは、体操をするように身体を捻り自分の姿を確認しながら、そうか、ふむ、などとぶつぶつ呟いている。
その声は少し残念そうで、チクリと心が痛んだ。
「あ、あの、別に似合ってないってワケじゃないんだよ? ただあんまりグゥのそーゆー格好見慣れてなくて……」
「良い、良い。私もいつもの格好の方が落ち着くのだ」
取って付けた様なオレの言い訳にもグゥは素直に頷いてくれる。……いや、言い訳じゃあない。自分で言って気付いたが、
今オレがドギマギしてるのはやっぱり、グゥがあまりに見慣れない格好をしているからに違い無い。
いつもなら、この世界がどう変わろうともグゥだけは普段と変わらぬ姿を保っていたのだ。あの三人の薦めとは言え、
グゥがこんな女の子っぽい格好をするとは想像もしていなかった。
「それに、これはどうも下半身が薄ら寒くてな」
「うわぁっ!? ちょ、ダメダメ!」
グゥはそう言うと、おもむろにスカートの端をつまみ、何の躊躇も無くペロンと持ち上げた。
オレは慌ててグゥの手を制止したが、その時に…バッチリと見えてしまった。ふわりと浮かんだチェック模様の布地の
奥にある、普段絶対に見る事の無い部分を。
そこにはマリィのようなかわいらしいものじゃあなく、母さんあたりが穿いていそうな実に大人っぽいものだった。
それも、母さんが普段穿いているようなものよりもずっとその生地の面積は狭く、両サイドを紐で結んだそのデザインは
海水浴に行った時に見かけた見知らぬ女性の着けていた水着を思い出させる。あの時は、あんなちょっと紐が引っかかっただけで
大変な事になりそうなモノをよく平気で着けられるものだと思っていたが、まさかそれをこのグゥが着けようとは。
一瞬、ほんの一瞬だけど、確かに目に映ったその光景はオレの目の奥にしっかりと焼き付いて離れてくれなかった。
もう、体温も動悸も臨界点を突破してしまって、自分でもどうなっているのかなんて解りゃあしない。
「…なんだ、どうした?」
「お…、女の人がそんな風にスカート捲くっちゃダメなのっ!」
「ふむ……だがこの腰の紐は気持ち悪いから取りたいのだが……」
「ンなっ!? そ、それはもっとダメ!!」
そう言いながら、グゥは今度はスカートの中に手を入れ、ゴソゴソと下着の位置を直し出す。よっぽど気持ち悪いようだ。
それよりもグゥは自分のしている事を良く解っていないみたいだ。これまで、女性の嗜みなどとはトンと無縁だったらしい。
グゥによると、その下着も制服と一緒に山田さんに渡されたものだそうだ。もしかして普段は何も着けていないのだろうか。
いつもの服装が、足首までかかる程の長いワンピースで良かったと妙な安堵を覚えてしまう。しかし今の格好ではそうも
言ってられない。せめてオレの前だけでも、激しい動きは控えて頂かねば。
「そうか、ハレを不快にさせてしまったようだな。これからは注意しよう」
「いや、不快っちゅーか何ちゅーか……まぁ、気をつけてくれたらいいよ。女の人はもっとお淑やかにしなきゃね」
「お淑やか、か。例えばどんな風にすればいいのだ?」
「え? っと……あんまり脚を広げたりしなけりゃそれでいいんじゃないかな。歩く時もこう、静かにね」
淑やかさ、なんてオレにも良く解らない。母さんの逆、と言えば解る人にはよーっく解るだろうが、彼女にはその説明も
通じまい。とりあえず見えちゃダメなものが見えさえしなけりゃそれでいい。オレはなるべくスカートが舞い上がらないような、
お行儀の良い歩き方を実演してみせる。
「成程、ハレは女に詳しいのだな。勉強になるぞ」
「そりゃ良かったけどそんな言われ方は甚だ心外だなあ……」
グゥは心底関心した様子で、オレの真似をしてしゃなりしゃなりと足元を確認しながら歩く。すらりとした細身の長身で、
それでも出るところはきっちり出ているバランスの良い体型の彼女がそうして歩く姿は、ますますもってモデルのようだった。
「ところで……ハレはどこかに行くところでは無かったのか?」
「あ………」
歩き方の練習をするようにしばらく短い距離を往復していた足をピタリと止め、くるりとこちらに向き直るグゥの言葉に
ようやくオレは当初の目的を思い出した。
そうだ、オレは学校に向かう途中だったんだ。予期せぬ人物の登場でその事をすっかり失念していた。
時計を持っていないので今が何時くらいなのか解らないが、この分だと教室に入るのは二時限目からになりそうだ。
どうせ転校生が来るのは昼過ぎだし特に問題は無いのだが、とりあえず早めに学校に行っておいて損は無い。
「ごめん、オレもう行かなきゃ!」
「うむ、私のせいで時間を取らせてしまったな」
「ううん、元はと言えばオレがぶつかっちゃったのが悪いんだしね。それじゃ、バイバイ!」
「……待て」
「え……わわっ!?」
別れの挨拶もそこそこに、走り出そうとしたオレを呼び止める声。まだ何かあるのか、と頭だけを振り向いた瞬間、
いつからそこにあったのか、目の前に広がる薄い桃色のセーラー服に顔を押し付けられる。そして腰に何かが
巻きついたかと思うと、身体がふわりと宙に浮いた。
「学校、と言うところに行くのだろう?」
一体何が起こったのか、状況を確認すべく前に向き直る。が、視界に飛び込んで来た光景はいよいよオレの理解を超えたものだった。
その目に映るはまず家屋の屋根。そして屋根を踏み台に、空を走る電線を飛び越え更に上空を飛ぶ。まるでテレビで見る
空撮のような景色が高速で移動しながら眼前に迫ったり、離れたりを繰り返していた。
風を切る音と風圧を全身に感じながらも、その感覚はあまりに現実離れしすぎており、自分が今どう言う状態にあるのか
まるで把握出来なかった。
「ふふ、またお淑やかにしろと言われてしまいそうだな」
強烈な風切り音に紛れて誰かの声が聞こえたが、こちらはそれに耳を傾けている余裕も無い。たとえちゃんと声が聞けて
いたとしても、オレの口は呼吸をするので手一杯で、返事なんてとてもじゃないが出来やしないのだが。
それでもどうにか現状を認識すべく目を凝らす。視界が激しく上下に揺れる度に、巨大な建造物がぐんぐんと近づいて
来るのが解る。あの建物はオレも良く知っている。なんせ、これからそこに向かうところだったのだ。
その建物がいよいよ目前に迫って来た瞬間、オレの身体は一際高く宙を飛んだ。そのまま建物を飛び越えんばかりに高度を上げ、
屋上が一望できる高さまで上がるとそこに向かって急降下する。
オレはその墜落感と、襲い来るであろう衝撃に備え身を縮めたが、それまでの猛烈な勢いに比べその着地はあっけないほどに
ゆるやかで、まるで重力に逆らうかのようにふわりと屋上に舞い降りたのだった。
「着いたぞ。少しは遅れた時間も取り戻せただろう」
腰に巻きついていたものが緩み、ようやくその床に足を付いた途端、オレは情けなくもそのままへたりこんでしまう。
胸に手を当てると、今にも飛び出しそうな程にドクドクとその鼓動を上げているのが解った。一体、何がどうなったのか。
声のした方を見上げると、桜色の長い髪が風に流され大きく揺れていた。その人物が、オレをここまで運んだ張本人であろう事は
疑う余地も無い。その方法は定かではないが……いや、何となくの想像は着くが、あまり考えたくないし思い出したくも無いので
このさい不問とさせて頂きたい。どうあれ、二度と体験したくないものだって事に変わりは無いのだ。
とにかく彼女のおかげで随分とショートカットさせて貰ったようだ。ありがたいやら、勘弁して欲しいやら。
「それと、これはハレのものだろう?忘れてはならぬぞ」
そう言うと彼女は、オレの脇にトンと学生カバンを置いた。
ぶつかった時にでも落としてしまっていたのだろう、すっかり失念していたが、そう言えばオレはずっと手ぶらだった。
ここに来る間も彼女が持ってくれていたようだ。オレが持っていたら、確実にどこかで手放してしまっていただろうな。
「どうした、ハレ? 急いでいるのでは無かったか」
「え? あ、えっとその……グゥは、どうするの?」
「ん……風が心地よいからな。しばらくここに居るつもりだ」
「そう、オ、オレももうちょっとここで涼んでから行こうかなぁ~」
……と言うか、身体が動かないだけなのだが、さすがに男としてそれは言えない。
グゥは特に詮索するでもなく、そうか、と言うと空を見上げた。オレも同じように目線を動かすが、どこまで見上げても
グゥの姿が視界から途切れる事は無かった。
風に揺れる髪が太陽に照らされ、キラキラとそれ自身が輝いているかのように見える。ここは風が強いのか、オレの髪も
バサバサと激しく揺れてかなり鬱陶しいが、グゥはオレよりもずっと長いその髪を抑える気も無いようだ。
その代わりにグゥの両手は今、自らの股間に伸びていた。風に煽られないようにしっかりとスカートを抑えている。
ちゃんとオレの言い付けを覚えてくれていたようだ。しかし、あのグゥに突然そんなに女の子らしい仕草をされてもなんだか
心休まらない、なんて思ってしまうのはさすがに我侭だろうか。
「ハレよ……私はお前たちに感謝している」
「え…?」
グゥは床にへたりこんでいるオレの隣に来ると、足を揃え正座を崩した姿勢で座った。スカートを気にする必要が無くなった
からか、
片手を膝の上に置き、もう片方の手で髪を抑えている。髪がオレにかからないようにしてくれているようだった。
「私は、人の意識が作り出した幻のような存在だ。ここに来るまでは、自我というものもほとんど無かった」
そう、このグゥは元々、ボーアの潜在的な恐怖が具現化した、本物のグゥとは全く別の存在なんだ。
「他人の夢の中で、胸毛を毟るためだけに存在していた私に、お前たちは生きる喜びを与えてくれたのだ」
「グゥ……」
言葉に、詰まる。元々の存在理由が、あまりにも哀れすぎて何も言えない。夢の中の存在を飲み込むなんて、あの時は
なんて無茶な事をするのかと思ったものだけど、今考えるとそれが正解だったんだろうな。
「私はこの世界を愛している。……しかしふと、外の世界に憧れを抱く時もある。私は誠一やともよ、ひろこと違って
外に出ることは適わぬ身……そこに不満などは無いのだがな……」
グゥはオレに肩をとん、と預けると、そのままゆっくりと後ろに倒れ込む。オレもそれにつられ、ぺたんと床に背中を付けた。
先ほどまで強く身体を煽っていた風は、爽やかにその身を通り抜ける優しいものへと変化していた。
「目まぐるしく変化するこの世界を見ていると、よほど楽しいところなのだろうな、と思うのだ」
指の間から太陽の光を通すように、グゥは片手を真っ直ぐに上げる。
自らの手で影を作り、その表情からは感情が読み取れない。無感情に、淡々と語るその流麗な声も、いつもと変わらない
凛とした端麗さを保っている。
他者との違いを妬むでも、恨むでも無い。寂しさも悲しさも、諦観の念すら感じられない。それが自分と言う存在なのだと
当たり前のように、ある種の清々しささえ感じるその声が何故か、オレの耳には何よりも悲く響いた。
それはオレなんかがどれだけ考えても、どうにもならない問題だろう。でもせめて一時だけでも、グゥを外の世界に
居るような気分にさせてやることは出来ないだろうか。
オレは身体を起こし、寝転がっているグゥに顔を向け真っ直ぐにオレの気持ちを伝えた。
A.一緒にどこかに遊びに行く
B.一緒に教室に入り授業を受ける
C.一緒に街中を散歩する
って、こんな場面でも勝手に頭の中に選択肢を浮かべてしまう。本当に自分がこの世界に染まりつつある気がして背筋が
冷たくなる。オレは頭をブンブンと振り、最初に思い浮かんだ気持ちを大きく声に出した。
→A.一緒にどこかに遊びに行く
「ねぇ、グゥ。これからオレと一緒に遊びに行かない?」
「………………」
……しまった。これじゃまるでナンパだ。
グゥはオレの言葉に、呆気に取られたような顔をしている。流石に唐突過ぎたか。
「ハレ………」
「いやその、グゥがダメだったら良いんだけど……いきなり何言ってんだろオレ、あはは~……」
「それは喜ばしい提案だなっ」
「へ……?」
グゥもむくりと半身を起こし、両手を胸の前でパンと叩く。満面の笑みを浮かべるその顔は、まるで子供のようだった。
この女性のそんな無邪気な表情や仕草ははじめて見る。ついでにグゥがオレの提案に快い声で応えてくれた事にも驚き、
二重の意味で不意を突かれ、オレはしばし呆然としてしまう。
「しかし、ハレはここに用事があるのではなかったのか?」
「え、あ…うん、あるにはあったんだけど、そっちはもういいんだ」
そうだ、元々攻略なんてもうしなくてもいいんだ。転校生の事は少し気になるが、それよりも今はグゥを放っておけない。
何故かは解らないけど、今は彼女の傍に居る方がずっと大事な事のような気がした。
「ふむ……デートか?」
「ぐはっ」
グゥの口から飛び出したまさかの言葉が脳天に直撃し思わずつんのめる。どこでそんな言葉覚えたんだ……。
「デートなんだな?」
「まぁその……デートって言わないでもないかもしれないような気がしないでもない感じで……」
グゥは立て膝を付き、後ろにつんのめるオレを追いかけるようにずずい、と迫り、念を押してくる。
オレは背中が床に着きそうなほど思いきりのけぞり、しどろもどろに曖昧な返事を返した。
「うん、私も一度してみたかったのだ。そうか、デートか」
グゥはうんうんと何かに納得するように頷くと、きゅっと強くオレの両手を握りブンブンと振って来る。その手を離されたら
オレはそのまま床に後頭部を打ちつけてしまうだろう。いつの間にやらグゥに生殺与奪を握られてしまった。
ってかこの人、こんな性格だっけ……?あんまり喋ったこと無いから知らなかったけど、見た目と違い案外子供っぽいのかもしれない。
「しかし本当に良いのか? 随分と急いでいたではないか。大事な用だったのではないか?」
「い、いやホント大丈夫だから落ち着いて……」
オレを気遣ってか、グゥはやけに遠慮気味だ。その口はオレの用事の方を優先してくれようとしているのは解るけど、
とりあえずそのあり得ないほど強く握り締めてる手を離して貰わないと、どっちにしろどこにも行けないのですが。
「うむ、で、どこに行くのだ」
グゥはオレの身体を起こすと、両手を離しペタンと正座を崩して座る。その顔も声も、いつも通り淡白そのものだったけど
瞳の奥に凛々と輝く光はなんだか、何かの期待にワクワクと興奮しているように見える。
ううん、何をそんなに期待して貰っているのかは解らないが、とりあえず乗り気になってくれたようだからまぁ、良いか。
「そうだなぁ……どうせなら、普段この世界じゃ出来ないことがいいよね」
オレは中空に指をかざすと、何も無い空間にボタンを押すように指を立てる。するとタイトル画面で出ていたような
ウィンドウが空中に音も無く現れた。
そこには現在のオレのステータスが大きく表示されている。知力、体力、時の運等など……基本的に何の役にも立たない
情報なのでそれらは軽く無視するとして、ウィンドウの右上に並んでいるアイコンに目を向ける。
それぞれのアイコンを押すと、各キャラ毎の好感度チェックや持ち物、日付、所持金などが確認出来るウィンドウが現れるが
それらも基本的には役に立たない。持ち物や所持金はゲームみたいにデータで管理されているワケじゃない。どうせ手に持てる
以上の物は所持出来ないんだ。お金だって財布の中身を確認した方が早いくらいかもしれない。好感度などは、オレの主観による
チェック表でしかないので実質ただのメモ帳程度の存在だ。
それでも、役に立つ機能も一応ある。「場所移動」のアイコンだ。この世界はいくら凝って作られていると言っても
道が繋がっているのは自宅から学校までくらいのもので、他の場所に行くにはこの場所移動でワープするしかない。
プレゼントを買うためのお店や、デートスポットなどに瞬時に飛ぶ事が出来るこの機能だけは実に重宝させて貰っている。
開発者であるあの少女的にはただ途中経路を作るのが面倒だっただけなのだろうが、その手の手抜きはオレはもろ手を上げて
歓迎するぞ。
場所移動アイコンを押すと、オレの目の前にパネル状にウィンドウが広がる。それぞれのパネルが、移動可能な場所を
表示している。
いける場所はいつも同じ。商店街、百貨店、水族館、動物園、遊園地、映画館……といった所だ。
「おお、それは何だ?」
グゥは空中に浮かぶウィンドウに、興味深げに手を触れる。グゥの手はそのままウィンドウをすり抜けて向こう側へ
貫通してしまったが、このウィンドウが見えるだけでもオレにはかなり驚きだ。
これまで誰の前でこのウィンドウを展開しても、気付いた人間はいなかったのだ。グゥがこの世界の住人だからだろうか。
それでも、コレに触れられるのは結局プレイヤーであるオレだけらしい。
「遊園地にしようよ。外の世界にもあるものなんだ。グゥもきっと気に入ると思うよ」
「私は外のことは解らないからな。ハレに任せよう」
本物の遊園地に行った経験はオレにも無いけど、この世界でなら何度か行った事がある。
色々なアトラクションがあるし、グゥも退屈しないだろう。
「ちょっとビックリするかもしれないけど、安心して手、握っててね」
「……うむ」
オレはグゥの手を握り、遊園地の絵が描かれたパネルに手を触れる。すると瞬時に周囲も、オレ自身も真っ白な光に
包まれて行き、しばらくすると、まるで靄が晴れるように周囲にまた色が戻っていく。完全に靄が晴れた時には既に、
オレとグゥは遊園地の中に足を踏み入れていた。
この時ばかりは、こんな感覚ゲームの中じゃないと味わえないよな、なんてソコソコこの世界を楽しんでいる自分が居たりする。
「さて、と。最初はどれに乗ろっかな?」
[[戻る<<>070321]] [5] [[>>進む>070331]]
****Jungle'sValentine.5(二:43-51)
<<5>>
→A:すぐに学校に行って教室で転校生を待とう。
余計な事をして面倒な目に遭うのはやはり避けたい。オレは駆け足で学校に向かう事にした。
元々、歩いても30分とかからない距離にある学校だ。走れば10分もあれば着く。
オレの通う学校の名前は『私立雀友学園』。「雀友」は「ジャングル」と読むらしい。どんな当て字なんだかさっぱりだが、
どうせ知ったところで無駄な知識がまた脳のキャパシティを切迫するだけだからあえてグゥには聞いていない。
雀友学園は小・中・高までを一つの敷地内に収める巨大な学校だ。グプタはその高校校舎にいるはずだが、そちら側には
見えない壁があってどうしても行く事が出来なかった。
最初はこの細くうねった道路…グゥによると日本の道路はこんな風らしい…にも困惑したけど、今や目を瞑ってでも学校まで
行ける自信がある。この道はいつも車も通っていないし、歩行者もいない。リタのいる曲がり角までは遠慮なく走り抜けられる。
リタとの遭遇ポイントはあと二つ先の曲がり角だ。オレは走る速度をぐんぐんと上げ、スピードを落とさず一つ目の角を曲がった。
「…む?」
「え、うわっ!?」
───居ないはずだった。……誰もそこには、居ないはずだった。
勢い良くカーブを曲がろうとした瞬間、突然現れた人影に驚き、オレは足がもつれそのままの勢いでその人影に
激突してしまった。
(──あれ……?)
しかし激突の衝撃はまるで無く、代わりにふわりと身体が浮いたような感覚だけがその身を包んだ。
オレはまるで空を飛んでいるような感覚を覚えながら、激突の際の勢いを失うまでその人影と共に宙を舞っていた。
そのうちにすとんと、何の衝撃も無く足が地面に着く。一体今の浮遊感は何だったのか、慌てて後ろを振り返ると、
今自分が立っている場所は曲がり角から数メートル先の地点だった。
信じ難い事だが、その人影はまるで自身をクッションにするかのように瞬時にオレを抱きかかえたまま後ろに飛び、
その勢いを殺した、と解釈するしか無かった。
「大丈夫か」
「え? あ、え!?」
いまだ混乱する脳を更に揺さぶる、やけに感情の篭らない淡白な声。その聞き覚えのある声のした方を見上げると、
そこにはやはり見覚えのある顔があった。
透き通るような白い肌。風に揺れる桜色の長い髪。切れ長の目の奥には、髪の色を深くしたような朱が淡く輝く。
オレを優しく抱き締める腕からはその繊細さに見合わぬ力強さを感じる。そしてオレを全身で受け止めてくれたその身体は
女性ならではの柔らかさを持ち、特に顔に触れている部分のそれは今もクッションの様なふくよかな心地よさと温もりを
オレに与えてくれた。先ほどの空中遊泳で強張った身体の緊張も、解れて行く……この感触は……。
「──って、ご、ごごごごめんなさい!!」
「む?」
オレは自分よりも頭二つ分近くも背の高い女性に抱えられる形になっていた。思いっきり身体ごとぶつかって、オレの方からも
無意識にぎゅっと抱き締めてしまい、自らの顔でその女性の柔らかい二つの膨らみを思い切り押し潰してしまっていたのだ。
その感触の正体に気付いた瞬間、オレは自分でも驚く程の勢いで弾かれるように後ろに下がった。肩をしっかり抱えられて
いたため、離れたのは顔と手だけだったけど……。
「どうした?」
「いや、あのその……ありがと……?」
「……ふふっ、謝ったり礼を言ったり、忙しいな、ハレは」
ダメだ、まだ頭が混乱している。まるで思考がまとまらない。聞きたい事も言いたい事もいっぱいあるはずなのに。
いまだ顔に残る先ほどの感触の余韻が、その感触の元である至近距離で眼前に広がる二つの膨らみが、オレの頭を沸騰させる。
「Oh……ジャパニーズ・バカップルね」
いよいよオレの脳が混乱を極めている中、前方から珍妙なイントネーションの声が聞こえた。
そしてグゥの背後から、オレよりも頭半分くらい背の高い金髪の少女の姿が現われる。
少女は物珍しげな目線を投げかけながら、トコトコとオレの横を通り過ぎていく。
そうか、オレがここでグゥとぶつかっちゃったから、リタの方は無事に曲がり角を抜けられたのか。
「これハごちそうさまデース」
そのまま、よく解らないコトを口走りながら少女は曲がり角の向こうへ消えて行った。
……リタ……いつも思ってたけど、なんでこの世界じゃそんなキャラなんだ……?
「痛む箇所は無いか?」
「へ? え、あ……う、うん」
変なタイミングが重なり、逆に頭の回転が戻ってきた。リタとのフラグはこれで折れてしまっただろうけど、まぁいいか。
おかげで少し冷静になれたし。
「大丈夫……かな、多分」
オレの言葉に彼女は薄く微笑み、そうか、と返すとようやく身体を離してくれた。そして目の前にしゃがみこむとオレの身体の
無事を確認するようにぽんぽんと肩や腰に手を触れる。
「……怪我は無いようだな」
再び、カァッと顔が熱くなる。大人状態とはいえ、オレの良く知る人物と同じ姿をした人にそんな風に子供扱いされた事も、
先ほどまで一人でわたわたと狼狽していた事も、なんだかとてつもなく恥ずかしく思えてしまった。
「あああの、改めて…ありがと、助けてくれて! それにぶつかっちゃって、ごめんっ」
「ん? ふふ……うん、私も少し驚いたぞ」
言いながら、オレはグゥから逃れるように手を前に掲げ後ずさる。そんなオレの様子にまたグゥは微笑みを向けた。
……うう、死ぬほど恥ずかしい。
それでも何故か、その顔を見ているうちに先ほどよりは頭の熱は収まった。代わりに身体の表面が燃えるように熱いが……。
とにかく、思ったとおりに口が利けるくらいには回復出来たようだ。これもリタのおかげ、なのかな?
「グ、グゥ……?」
「ん、何だ?」
オレの問いかけに、彼女は微笑みを崩さぬまま真っ直ぐに応える。
やはり、グゥで間違いないようだ。ただグゥと言ってもオレの良く知る性悪少女では無く、その腹の中にだけ存在する
もう一人のグゥ。本物とは性格も口調も、随分と違うイメージを持つこの大人の女性をただグゥとだけ呼んで良いのかは
解らないが、他に呼びようが無いしずっとグゥ(大)と呼ぶのもなんだか気が引ける。まあ今はグゥ、と呼ばせてもらおう。
「えっと、何でこんな所にいるの?」
「……少し、散歩をしていたのだ」
「散歩?」
「ああ、この世界は実に興味深い」
グゥはしゃがんだまま、オレの両肩を支えにするように手を置き空を見上げる。言葉の意味は良く解らなかったけど、
オレは彼女のそんな仕草を見るだけで、なんだか体温がまた上昇してしまった気がした。
慌ててオレもグゥの姿をその目に映さぬように空を見上げる。そこには鳥一つ飛んではいなかったけど、その青空は
現実世界と同じように、どこまでも続いているようだった。
「……………」
「……え、な、何?」
気付けば、彼女の目線は既に空に無く、オレに真っ直ぐに注がれていた。体温と共にドキンと、鼓動までが上がってしまう。
「うむ、しばらく会わぬうちに随分と見違えたな」
「は…?」
グゥは一人で何かを納得したようにうんうんと頷くと、オレの首元に手を添えて来る。少し驚き身を引いてしまったが、グゥは
構わず指を伸ばし、よれていたネクタイに指をかけ、キュッと真っ直ぐに正してくれた。
「このような格好をしているから尚更か。凛々しいぞ、ハレ」
「…え……あ、そ、そんなこと……」
そんな言葉と共に、ニコリと微笑みまで投げ掛けられる。ついでに再度肩に置かれたその手にもきゅ、と力が込められる。
もうそれだけで、ボボッと音が出んばかりに、身体から湯気が出そうな程に体温が上昇してしまう。
何故こんなことがこんなに恥ずかしいのか。それが解らなくてまた恥ずかしくなって、身体の熱も心臓の音も再現なく
高まり続けてしまう。
オレは動揺を悟られぬように、グゥの微笑みから逃れるように目線を下に切った。しかしその先からもオレを困惑させるものが
視界に飛び込んでくる。
先ほどまで顔を埋めていた膨らみの先に見える、すらりと伸びた真っ白な脚。立て膝を付く形で縦に開いた脚は、立っていても
膝まで届くとは到底思えない長さのスカートを自然に捲くり上げ、本来そのヒラヒラとした布地が覆うべき場所をほとんど
申し訳程度に隠しているだけだった。
何故今まで気付かなかったのか、良く見てみればグゥの服装も普段のものではなく、まるで今朝見たマリィのような格好をしていた。
淡い桃色の上着は普通のシャツのようにボタンの付いた前留めタイプ。幅広の襟と袖には濃いピンクのラインが一本入り、
胸元はVの字に大きく開かれていた。藍色のリボンはマリィの制服のように大きな物ではなく、細いリボンタイを蝶結びにした
シンプルなもの。スカートは太い線と細い線が交互に、縦横に入るチェック柄。生地も柄も、配色は青系統で統一されている。
デザインこそ違えど、やはりそれはこの世界の、恐らくは日本の学校で使用されている制服と呼ばれているものに相違無かった。
そして明らかにその丈は、グゥの高身長に適合しているようには思えなかった。ワンサイズ以上小さくないか……?
「グ、グゥこそどうしたのさ、その格好」
「ん?おお、これか。この世界が今のように変わった後に、ともよに手渡されてな」
オレは慌ててもう一度目線を外し、中空に目を泳がせる。もうグゥの姿そのものを見ていられない。傍目から見たらかなり
挙動不審に映っていただろうが、グゥはさして気にした様子も無くオレの質問に応えてくれた。
「私もたまには、見栄えくらいは変化を付けようと思い着てみたのだが……どうだ、少しは変わったか?」
グゥはスックと立ち上がると、その場でファッションモデルのようにくるんと回ってみせる。その動きに合わせ、やはり
想像通りの短さだったスカートがふわりと浮かび、その白い肢体を惜しげもなく晒す。
オレの目はいよいよその置き所を失い、ますます挙動不審にきょろきょろとグゥの周囲を泳いでしまう。
「なんだ、ハレはあまり好きではないようだな」
「い、いやそんなことは無いんだけど……オレは普段の格好の方が好きかなぁ~……」
自分でも何故そんなにその格好にドギマギしてしまうのか、良く解らなかった。肌の露出によるものか、とも考えたが、
普段着ている、全身を包み込む筒のようなワンピースを胸に巻かれた布で止めているだけの服装だって肩や胸元が大きく
露出しているのだ。でも、あの格好をそんなに意識した憶えは無い。今の格好は肩の代わりに脚が大きく露出しているが、
ここまで自分が動揺してしまう程のものとは思えなかった。元々オレは常夏のジャングルに住んでいるのだ。露出度で言えば、
村の大人の女性の姿は今のグゥの比では無い。母さんに至っては家じゃ裸がユニフォームだ。まぁ母さんの場合は、ただ肉親って
だけじゃなく下着姿のまま外にも出歩いてしまうような人間をオレが女として認識していないせいかもしれないが。
「ハレはあの格好の方が良いのか……」
グゥは、体操をするように身体を捻り自分の姿を確認しながら、そうか、ふむ、などとぶつぶつ呟いている。
その声は少し残念そうで、チクリと心が痛んだ。
「あ、あの、別に似合ってないってワケじゃないんだよ? ただあんまりグゥのそーゆー格好見慣れてなくて……」
「良い、良い。私もいつもの格好の方が落ち着くのだ」
取って付けた様なオレの言い訳にもグゥは素直に頷いてくれる。……いや、言い訳じゃあない。自分で言って気付いたが、
今オレがドギマギしてるのはやっぱり、グゥがあまりに見慣れない格好をしているからに違い無い。
いつもなら、この世界がどう変わろうともグゥだけは普段と変わらぬ姿を保っていたのだ。あの三人の薦めとは言え、
グゥがこんな女の子っぽい格好をするとは想像もしていなかった。
「それに、これはどうも下半身が薄ら寒くてな」
「うわぁっ!? ちょ、ダメダメ!」
グゥはそう言うと、おもむろにスカートの端をつまみ、何の躊躇も無くペロンと持ち上げた。
オレは慌ててグゥの手を制止したが、その時に…バッチリと見えてしまった。ふわりと浮かんだチェック模様の布地の
奥にある、普段絶対に見る事の無い部分を。
そこにはマリィのようなかわいらしいものじゃあなく、母さんあたりが穿いていそうな実に大人っぽいものだった。
それも、母さんが普段穿いているようなものよりもずっとその生地の面積は狭く、両サイドを紐で結んだそのデザインは
海水浴に行った時に見かけた見知らぬ女性の着けていた水着を思い出させる。あの時は、あんなちょっと紐が引っかかっただけで
大変な事になりそうなモノをよく平気で着けられるものだと思っていたが、まさかそれをこのグゥが着けようとは。
一瞬、ほんの一瞬だけど、確かに目に映ったその光景はオレの目の奥にしっかりと焼き付いて離れてくれなかった。
もう、体温も動悸も臨界点を突破してしまって、自分でもどうなっているのかなんて解りゃあしない。
「…なんだ、どうした?」
「お…、女の人がそんな風にスカート捲くっちゃダメなのっ!」
「ふむ……だがこの腰の紐は気持ち悪いから取りたいのだが……」
「ンなっ!? そ、それはもっとダメ!!」
そう言いながら、グゥは今度はスカートの中に手を入れ、ゴソゴソと下着の位置を直し出す。よっぽど気持ち悪いようだ。
それよりもグゥは自分のしている事を良く解っていないみたいだ。これまで、女性の嗜みなどとはトンと無縁だったらしい。
グゥによると、その下着も制服と一緒に山田さんに渡されたものだそうだ。もしかして普段は何も着けていないのだろうか。
いつもの服装が、足首までかかる程の長いワンピースで良かったと妙な安堵を覚えてしまう。しかし今の格好ではそうも
言ってられない。せめてオレの前だけでも、激しい動きは控えて頂かねば。
「そうか、ハレを不快にさせてしまったようだな。これからは注意しよう」
「いや、不快っちゅーか何ちゅーか……まぁ、気をつけてくれたらいいよ。女の人はもっとお淑やかにしなきゃね」
「お淑やか、か。例えばどんな風にすればいいのだ?」
「え? っと……あんまり脚を広げたりしなけりゃそれでいいんじゃないかな。歩く時もこう、静かにね」
淑やかさ、なんてオレにも良く解らない。母さんの逆、と言えば解る人にはよーっく解るだろうが、彼女にはその説明も
通じまい。とりあえず見えちゃダメなものが見えさえしなけりゃそれでいい。オレはなるべくスカートが舞い上がらないような、
お行儀の良い歩き方を実演してみせる。
「成程、ハレは女に詳しいのだな。勉強になるぞ」
「そりゃ良かったけどそんな言われ方は甚だ心外だなあ……」
グゥは心底関心した様子で、オレの真似をしてしゃなりしゃなりと足元を確認しながら歩く。すらりとした細身の長身で、
それでも出るところはきっちり出ているバランスの良い体型の彼女がそうして歩く姿は、ますますもってモデルのようだった。
「ところで……ハレはどこかに行くところでは無かったのか?」
「あ………」
歩き方の練習をするようにしばらく短い距離を往復していた足をピタリと止め、くるりとこちらに向き直るグゥの言葉に
ようやくオレは当初の目的を思い出した。
そうだ、オレは学校に向かう途中だったんだ。予期せぬ人物の登場でその事をすっかり失念していた。
時計を持っていないので今が何時くらいなのか解らないが、この分だと教室に入るのは二時限目からになりそうだ。
どうせ転校生が来るのは昼過ぎだし特に問題は無いのだが、とりあえず早めに学校に行っておいて損は無い。
「ごめん、オレもう行かなきゃ!」
「うむ、私のせいで時間を取らせてしまったな」
「ううん、元はと言えばオレがぶつかっちゃったのが悪いんだしね。それじゃ、バイバイ!」
「……待て」
「え……わわっ!?」
別れの挨拶もそこそこに、走り出そうとしたオレを呼び止める声。まだ何かあるのか、と頭だけを振り向いた瞬間、
いつからそこにあったのか、目の前に広がる薄い桃色のセーラー服に顔を押し付けられる。そして腰に何かが
巻きついたかと思うと、身体がふわりと宙に浮いた。
「学校、と言うところに行くのだろう?」
一体何が起こったのか、状況を確認すべく前に向き直る。が、視界に飛び込んで来た光景はいよいよオレの理解を超えたものだった。
その目に映るはまず家屋の屋根。そして屋根を踏み台に、空を走る電線を飛び越え更に上空を飛ぶ。まるでテレビで見る
空撮のような景色が高速で移動しながら眼前に迫ったり、離れたりを繰り返していた。
風を切る音と風圧を全身に感じながらも、その感覚はあまりに現実離れしすぎており、自分が今どう言う状態にあるのか
まるで把握出来なかった。
「ふふ、またお淑やかにしろと言われてしまいそうだな」
強烈な風切り音に紛れて誰かの声が聞こえたが、こちらはそれに耳を傾けている余裕も無い。たとえちゃんと声が聞けて
いたとしても、オレの口は呼吸をするので手一杯で、返事なんてとてもじゃないが出来やしないのだが。
それでもどうにか現状を認識すべく目を凝らす。視界が激しく上下に揺れる度に、巨大な建造物がぐんぐんと近づいて
来るのが解る。あの建物はオレも良く知っている。なんせ、これからそこに向かうところだったのだ。
その建物がいよいよ目前に迫って来た瞬間、オレの身体は一際高く宙を飛んだ。そのまま建物を飛び越えんばかりに高度を上げ、
屋上が一望できる高さまで上がるとそこに向かって急降下する。
オレはその墜落感と、襲い来るであろう衝撃に備え身を縮めたが、それまでの猛烈な勢いに比べその着地はあっけないほどに
ゆるやかで、まるで重力に逆らうかのようにふわりと屋上に舞い降りたのだった。
「着いたぞ。少しは遅れた時間も取り戻せただろう」
腰に巻きついていたものが緩み、ようやくその床に足を付いた途端、オレは情けなくもそのままへたりこんでしまう。
胸に手を当てると、今にも飛び出しそうな程にドクドクとその鼓動を上げているのが解った。一体、何がどうなったのか。
声のした方を見上げると、桜色の長い髪が風に流され大きく揺れていた。その人物が、オレをここまで運んだ張本人であろう事は
疑う余地も無い。その方法は定かではないが……いや、何となくの想像は着くが、あまり考えたくないし思い出したくも無いので
このさい不問とさせて頂きたい。どうあれ、二度と体験したくないものだって事に変わりは無いのだ。
とにかく彼女のおかげで随分とショートカットさせて貰ったようだ。ありがたいやら、勘弁して欲しいやら。
「それと、これはハレのものだろう?忘れてはならぬぞ」
そう言うと彼女は、オレの脇にトンと学生カバンを置いた。
ぶつかった時にでも落としてしまっていたのだろう、すっかり失念していたが、そう言えばオレはずっと手ぶらだった。
ここに来る間も彼女が持ってくれていたようだ。オレが持っていたら、確実にどこかで手放してしまっていただろうな。
「どうした、ハレ? 急いでいるのでは無かったか」
「え? あ、えっとその……グゥは、どうするの?」
「ん……風が心地よいからな。しばらくここに居るつもりだ」
「そう、オ、オレももうちょっとここで涼んでから行こうかなぁ~」
……と言うか、身体が動かないだけなのだが、さすがに男としてそれは言えない。
グゥは特に詮索するでもなく、そうか、と言うと空を見上げた。オレも同じように目線を動かすが、どこまで見上げても
グゥの姿が視界から途切れる事は無かった。
風に揺れる髪が太陽に照らされ、キラキラとそれ自身が輝いているかのように見える。ここは風が強いのか、オレの髪も
バサバサと激しく揺れてかなり鬱陶しいが、グゥはオレよりもずっと長いその髪を抑える気も無いようだ。
その代わりにグゥの両手は今、自らの股間に伸びていた。風に煽られないようにしっかりとスカートを抑えている。
ちゃんとオレの言い付けを覚えてくれていたようだ。しかし、あのグゥに突然そんなに女の子らしい仕草をされてもなんだか
心休まらない、なんて思ってしまうのはさすがに我侭だろうか。
「ハレよ……私はお前たちに感謝している」
「え…?」
グゥは床にへたりこんでいるオレの隣に来ると、足を揃え正座を崩した姿勢で座った。スカートを気にする必要が無くなった
からか、
片手を膝の上に置き、もう片方の手で髪を抑えている。髪がオレにかからないようにしてくれているようだった。
「私は、人の意識が作り出した幻のような存在だ。ここに来るまでは、自我というものもほとんど無かった」
そう、このグゥは元々、ボーアの潜在的な恐怖が具現化した、本物のグゥとは全く別の存在なんだ。
「他人の夢の中で、胸毛を毟るためだけに存在していた私に、お前たちは生きる喜びを与えてくれたのだ」
「グゥ……」
言葉に、詰まる。元々の存在理由が、あまりにも哀れすぎて何も言えない。夢の中の存在を飲み込むなんて、あの時は
なんて無茶な事をするのかと思ったものだけど、今考えるとそれが正解だったんだろうな。
「私はこの世界を愛している。……しかしふと、外の世界に憧れを抱く時もある。私は誠一やともよ、ひろこと違って
外に出ることは適わぬ身……そこに不満などは無いのだがな……」
グゥはオレに肩をとん、と預けると、そのままゆっくりと後ろに倒れ込む。オレもそれにつられ、ぺたんと床に背中を付けた。
先ほどまで強く身体を煽っていた風は、爽やかにその身を通り抜ける優しいものへと変化していた。
「目まぐるしく変化するこの世界を見ていると、よほど楽しいところなのだろうな、と思うのだ」
指の間から太陽の光を通すように、グゥは片手を真っ直ぐに上げる。
自らの手で影を作り、その表情からは感情が読み取れない。無感情に、淡々と語るその流麗な声も、いつもと変わらない
凛とした端麗さを保っている。
他者との違いを妬むでも、恨むでも無い。寂しさも悲しさも、諦観の念すら感じられない。それが自分と言う存在なのだと
当たり前のように、ある種の清々しささえ感じるその声が何故か、オレの耳には何よりも悲く響いた。
それはオレなんかがどれだけ考えても、どうにもならない問題だろう。でもせめて一時だけでも、グゥを外の世界に
居るような気分にさせてやることは出来ないだろうか。
オレは身体を起こし、寝転がっているグゥに顔を向け真っ直ぐにオレの気持ちを伝えた。
A.一緒にどこかに遊びに行く
B.一緒に教室に入り授業を受ける
C.一緒に街中を散歩する
って、こんな場面でも勝手に頭の中に選択肢を浮かべてしまう。本当に自分がこの世界に染まりつつある気がして背筋が
冷たくなる。オレは頭をブンブンと振り、最初に思い浮かんだ気持ちを大きく声に出した。
→A.一緒にどこかに遊びに行く
「ねぇ、グゥ。これからオレと一緒に遊びに行かない?」
「………………」
……しまった。これじゃまるでナンパだ。
グゥはオレの言葉に、呆気に取られたような顔をしている。流石に唐突過ぎたか。
「ハレ………」
「いやその、グゥがダメだったら良いんだけど……いきなり何言ってんだろオレ、あはは~……」
「それは喜ばしい提案だなっ」
「へ……?」
グゥもむくりと半身を起こし、両手を胸の前でパンと叩く。満面の笑みを浮かべるその顔は、まるで子供のようだった。
この女性のそんな無邪気な表情や仕草ははじめて見る。ついでにグゥがオレの提案に快い声で応えてくれた事にも驚き、
二重の意味で不意を突かれ、オレはしばし呆然としてしまう。
「しかし、ハレはここに用事があるのではなかったのか?」
「え、あ…うん、あるにはあったんだけど、そっちはもういいんだ」
そうだ、元々攻略なんてもうしなくてもいいんだ。転校生の事は少し気になるが、それよりも今はグゥを放っておけない。
何故かは解らないけど、今は彼女の傍に居る方がずっと大事な事のような気がした。
「ふむ……デートか?」
「ぐはっ」
グゥの口から飛び出したまさかの言葉が脳天に直撃し思わずつんのめる。どこでそんな言葉覚えたんだ……。
「デートなんだな?」
「まぁその……デートって言わないでもないかもしれないような気がしないでもない感じで……」
グゥは立て膝を付き、後ろにつんのめるオレを追いかけるようにずずい、と迫り、念を押してくる。
オレは背中が床に着きそうなほど思いきりのけぞり、しどろもどろに曖昧な返事を返した。
「うん、私も一度してみたかったのだ。そうか、デートか」
グゥはうんうんと何かに納得するように頷くと、きゅっと強くオレの両手を握りブンブンと振って来る。その手を離されたら
オレはそのまま床に後頭部を打ちつけてしまうだろう。いつの間にやらグゥに生殺与奪を握られてしまった。
ってかこの人、こんな性格だっけ……?あんまり喋ったこと無いから知らなかったけど、見た目と違い案外子供っぽいのかもしれない。
「しかし本当に良いのか? 随分と急いでいたではないか。大事な用だったのではないか?」
「い、いやホント大丈夫だから落ち着いて……」
オレを気遣ってか、グゥはやけに遠慮気味だ。その口はオレの用事の方を優先してくれようとしているのは解るけど、
とりあえずそのあり得ないほど強く握り締めてる手を離して貰わないと、どっちにしろどこにも行けないのですが。
「うむ、で、どこに行くのだ」
グゥはオレの身体を起こすと、両手を離しペタンと正座を崩して座る。その顔も声も、いつも通り淡白そのものだったけど
瞳の奥に凛々と輝く光はなんだか、何かの期待にワクワクと興奮しているように見える。
ううん、何をそんなに期待して貰っているのかは解らないが、とりあえず乗り気になってくれたようだからまぁ、良いか。
「そうだなぁ……どうせなら、普段この世界じゃ出来ないことがいいよね」
オレは中空に指をかざすと、何も無い空間にボタンを押すように指を立てる。するとタイトル画面で出ていたような
ウィンドウが空中に音も無く現れた。
そこには現在のオレのステータスが大きく表示されている。知力、体力、時の運等など……基本的に何の役にも立たない
情報なのでそれらは軽く無視するとして、ウィンドウの右上に並んでいるアイコンに目を向ける。
それぞれのアイコンを押すと、各キャラ毎の好感度チェックや持ち物、日付、所持金などが確認出来るウィンドウが現れるが
それらも基本的には役に立たない。持ち物や所持金はゲームみたいにデータで管理されているワケじゃない。どうせ手に持てる
以上の物は所持出来ないんだ。お金だって財布の中身を確認した方が早いくらいかもしれない。好感度などは、オレの主観による
チェック表でしかないので実質ただのメモ帳程度の存在だ。
それでも、役に立つ機能も一応ある。「場所移動」のアイコンだ。この世界はいくら凝って作られていると言っても
道が繋がっているのは自宅から学校までくらいのもので、他の場所に行くにはこの場所移動でワープするしかない。
プレゼントを買うためのお店や、デートスポットなどに瞬時に飛ぶ事が出来るこの機能だけは実に重宝させて貰っている。
開発者であるあの少女的にはただ途中経路を作るのが面倒だっただけなのだろうが、その手の手抜きはオレはもろ手を上げて
歓迎するぞ。
場所移動アイコンを押すと、オレの目の前にパネル状にウィンドウが広がる。それぞれのパネルが、移動可能な場所を
表示している。
いける場所はいつも同じ。商店街、百貨店、水族館、動物園、遊園地、映画館……といった所だ。
「おお、それは何だ?」
グゥは空中に浮かぶウィンドウに、興味深げに手を触れる。グゥの手はそのままウィンドウをすり抜けて向こう側へ
貫通してしまったが、このウィンドウが見えるだけでもオレにはかなり驚きだ。
これまで誰の前でこのウィンドウを展開しても、気付いた人間はいなかったのだ。グゥがこの世界の住人だからだろうか。
それでも、コレに触れられるのは結局プレイヤーであるオレだけらしい。
「遊園地にしようよ。外の世界にもあるものなんだ。グゥもきっと気に入ると思うよ」
「私は外のことは解らないからな。ハレに任せよう」
本物の遊園地に行った経験はオレにも無いけど、この世界でなら何度か行った事がある。
色々なアトラクションがあるし、グゥも退屈しないだろう。
「ちょっとビックリするかもしれないけど、安心して手、握っててね」
「……うむ」
オレはグゥの手を握り、遊園地の絵が描かれたパネルに手を触れる。すると瞬時に周囲も、オレ自身も真っ白な光に
包まれて行き、しばらくすると、まるで靄が晴れるように周囲にまた色が戻っていく。完全に靄が晴れた時には既に、
オレとグゥは遊園地の中に足を踏み入れていた。
この時ばかりは、こんな感覚ゲームの中じゃないと味わえないよな、なんてソコソコこの世界を楽しんでいる自分が居たりする。
「さて、と。最初はどれに乗ろっかな?」
****[[戻る<<>070321]] [5] [[>>進む>070331]]
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: