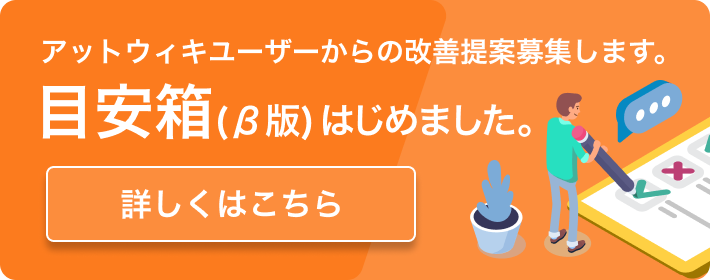「070901_7」(2007/09/13 (木) 01:37:44) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
****小麦色の白雪姫(二:272-278)
<<8>>
「あー、なんかドッと疲れたなー」
部屋に戻るやいなや、ベッドに備え付けられた大きなソファに持たれかかる。
グゥもオレの隣にちょこんと座り、オレの肩に体重をかけた。
「グゥ───」
何を言う間も与えられず、唇が奪われる。
すぐにパッと離れ、グゥは頬を染めてくすりと笑った。
もう一度、今度はオレからグゥの頬に手を添え、唇を重ねる。
深く密着させず、舌も使わず、唇だけを味わうように優しく吸い付き、離れる。
そうして何度も、グゥと見詰め合いながらキスを交わした───
「───なあ、ハレ」
「……ん」
「そろそろ、風呂に行った方が良いんじゃないか」
「……んー」
グゥの髪を撫でながら曖昧な返事を返す。
今、グゥはオレの股の間にお尻を収め、その背中をオレの胸に預けて座っている。
「もうちょっと、このままでいない?」
「……ウェダが風呂で待ってる」
「ん~……。もうちょっとだけ……」
グゥの髪に鼻を埋め、頭を揺する。後ろから肩に腕を回し抱き締めるとグゥは一瞬、身体を
弛緩させたがすぐに頭をぐりぐりと捻りオレの顔を押し戻した。
「遅くなればなるほどウェダの想像力に火がつくと思うのだが?」
オレの腕を解き、肩越しに睨みつけてくる。
……確かに、あまり遅れてはまたいらぬ詮索をされてしまいそうだ。
どうせ風呂から上がって、イベントとやらが終わればここに二人で戻ってくるのだ。焦る必要も
時間を惜しむ必要も無いか。
しかし、一つだけ今やっておかなければならない事がある。
「グゥ。水着跡、ちょっとだけ見せて?」
「……ケダモノ」
「違うっての!」
冷やかな目線をオレに送りながら、グゥは自分の胸をガードするように抱いた。
「手触りは違うのかな? 味も見てみよう、とか言ってまたグゥを慰みものにするつもりなんだろう」
「するかッ!! ってか、"また"ってなんだよ、"また"って」
「だいたい、日焼けの跡など別に今見なくてもいいだろ。もうちょっとマシな口実を考えろ」
「……今じゃなきゃ、ダメなんだよ」
「ほう、その心は?」
グゥは腕を組んだまま肩越しにオレを見上げ、次の言を待つ。
ああ、もう。最初の言い方が不味かったか。自業自得ってやつか……。くそう、また恥ずかしい事を
告白せにゃならんのか。
「……母さんに先に見られるの、悔しかったんだよ」
「…………」
「オレが最初に見たかったのッ!」
顔中が熱い。グゥの顔をまともに見る事も出来ず、中空に目を泳がせる。
しばし無言の時が過ぎるが、不意に大きな溜息がその沈黙を遮った。
「ハレは意気地があるのかないのか……」
「……へ?」
「…………なんでもない」
グゥは何度も小さく溜息を付き、ぴょんとソファから降りると落ち着き無くオレの前をうろうろと
うろつく。最後にもう一度大きく息を吐くと目の前でぐっと屈み込みオレに顔を突き出した。
「……一瞬だけだからな」
「…………」
グゥは怒ったような困ったような顔で口を尖らせるとすっくと身体を起こし、ドアの前まで
歩きくるんとこちらに向き直る。
「……ちょっと待ってろ」
そしてそう言うと、グゥは突然後ろ手にスカートを捲り、ごそごそと何かを弄りはじめた。
こちらからはスカートの内部は見えないが、オレはその光景をただ呆然と見守るしかなかった。
「……よし。いいか、一瞬だけだぞ?」
「な、なんだよ……?」
何かの仕度を整え終えたのか、グゥはパンパンとスカートの皺を伸ばすようにお尻をはたくと、
少し前傾姿勢になり足を開く。
そしておもむろに勢い良く上半身を捻り、反動をつけて回転するようにクイッとお尻を前に
突き出した。
「ブ…………ッ!!」
ヒラリと傘を開くように展開するスカートの奥で、純白の膨らみがぷるんと揺れた。
最初は下着かと思った。だけど、褐色の肌とその白い双丘との間には何の段差も無く、
ただくっきりと色の境界線があるのみだった。
先ほどのグゥの怪しい動きはこれだったのだろう、下着はグゥのお尻の谷間に食い込み、
その根元にのみ逆三角形に布地が見えるのみだった。無理に食い込ませているためか、
布地の圧迫で尻肉がむっちりと持ち上がり、より豊満で柔らかそうに盛り上がっていた。
見えたのはほんの一瞬だったが、しっかりと目に焼きついた。小麦色の脚とのコントラスト
にくっきりと映える色白な双丘の、官能的とすら思えるようなふくよかな肉感。
グゥのスカートはとっくに膝元まで降り、更に上からガードするように前も後ろもグゥの
手で押さえられていたが、オレの目の前にはまだ先ほどの光景がそこにあるかのように
チラチラと浮かぶ。
「……満足したか?」
「…………」
「どうした、何か言え」
「………あ……」
「あ?」
「アンコール……」
「……馬鹿」
「アンコール! アンコール!!」
「黙れ!!」
オレの精一杯の掛け声にもグゥは応えてくれず、むしろ益々スカートを守りに入る。
くそう、ああなっては真下から竜巻が発生しても捲れはすまい。
「まったく。すぐ調子に乗りおって。これはサービスだ、サービス。別に、ハレがちゃんと言えば
グゥだってこれくらいの事はしてやっても良いんだからな」
「…………」
言ってから恥ずかしくなったのか、グゥは頬をほんのりと染めてぷい、とそっぽを向いた。
そこまでは、オレも期待してなかったってのに。こいつのやる事はまったく、ホントに……。
「じゃ、グゥは風呂に行くからな」
早口にそれだけを言うとグゥは後ろ手にドアを開け、オレを置いてそそくさと部屋を出て行った。
一人、取り残されたオレの意識と肉体が正常に戻ったのは、それから数分後の事だった。
風呂場に行くと、ロバートが物凄く良い顔で出迎えてくれた。脱衣所の前で随分と長い間
待ってくれていたようだ。「先に入ってくれて良かったのに」と言うオレの言葉にロバートは
ブンブンと首を振った。オレより先に入る事はロバート的に許されないのだそうだ。なんだか、
申し訳無い事をしてしまった。少し、反省する。
さっさと服を脱ぎ、中に入るとロバートも追って入ってきた。腰に巻いたタオルから覗く、
黒と白のコントラストに先ほどの絶景が上書きされそうになり慌てて顔を背ける。
どうやらロバートもアシオも海で本当にトランクス一丁にされたらしく、上半身はもとより
太ももの中ごろから下までもしっかり焼けていた。普通の水着の跡とまるで変わらない。
しかし男の日焼け跡はどこか間が抜けているように思えるのはオレが同性だからだろうか。
身体を洗い、ゆっくり湯船につかりながら部屋でのグゥを思い出す。……途端に、湯船から
上がる事が困難な状態になる。
自分で呼んでおいてなんだが、今ほどロバートが邪魔者に思えた瞬間は無かった。
「いやぁ、いいお湯ですねえ」
「…………ほんとにねえ」
「今日は疲れたでしょう。脚を伸ばした方が楽ですよ?」
「…………いや、オレはいいや」
「男同士なんですから、ほら、お気にならさずに」
「…………いいっつーの……」
最初に待たせてしまった手前、先に出ていてくれとも言えず、その理由を聞かれた際の言い訳も
思い浮かばず、オレは心地良いはずの広い湯船の中でひたすら窮屈な思いに悶々とするのだった。
<<9>>
───これは、あるストーカーの被害に悩まされとった一人の女性の身に起こった出来事です。
仕事の行き帰りに妙な視線を感じる。夜中に窓の外を覗いたら不気味な人影が立ってる。
毎日のように無言電話がかかってくる。
彼女はいつも背筋が凍る思いで過ごしてました。ドアは勿論、家中の窓をいつも閉めっぱなしに
していても不安は募るばかり。
今日も、いつもと同じ時間に電話の無機質な音が部屋に鳴り響いた。
もしもし? もしもし、どなたですか?
何度聞いても相手は無言。返ってくるのは不気味な沈黙だけや。
彼女はもともと気の強い方や無い、どちらかと言えば控えめな子やったけど、ここまでされては
黙ってもおれへん。今回ばかりはさすがに我慢の限界が来た。
「いい加減にしてよこの変態! アンタみたいに誰の心も理解できない人間サイテーだ!いっぱしの
つもりなんだろうけど傍から見ればちゃんちゃらおかしいだけ! なんもなし! 空っぽ! そーゆー
人間はね、結局死ぬまで今に見てろとホントのオレはこんなもんじゃないと、誰も解ってくれないで
誤魔化して! 根拠の無い自信と自己憐憫に溺れ生きていくんだわ! 大迷惑!! ッ死ね!!」
よっぽど腹が立っとったんやろう、彼女は饒舌にそこまで一気に捲くし立てると受話器を叩き付けた。
せやけどな、彼女の心は全く晴れへんかった。受話器を耳から放す瞬間、彼女は聞いてもうたんや。
いつも何を言うても無言やった受話器の向こう側から聞こえてきた、カスレた男の声。
「────死ぬのはお前だ」
彼女は途端に恐ろしくなり、警察に相談した。
幸いな事に、警察も最近はストーカーの被害者対策に力を入れとったから、彼女の相談に
すぐに対応してくれた。
「今度電話がかかってきたときには逆探知を行ってから携帯電話にかけるので、なるべくストーカーとの
電話を切らないようにして下さい」
そう警官に言われた彼女は、百万の味方を手に入れた気分やった。もう怖くない。
むしろ、電話がかかってくるのが楽しみにすら思えた。
そして、その夜も律儀に同じ時間に電話はかかってきた。
……しかし今日はいつもとは様子が違ったんや。
ククククク……ククククク……ククククク……
ストーカーの男はただ電話口で延々と不気味な笑い声を響かせとった。
恐ろしくなった彼女は電話を切ろうと思ったけど、警察が逆探知をしてくれることになっとるから
そうもいかん。我慢して受話器を持って、ただ男の笑い声を聞いてるしかなかった。
そして、ついに彼女の携帯電話が鳴った。警察からや。
彼女は急いで電話を取った。
「逆探知の結果が出ました!今すぐ外へ出てください!」
電話が繋がった途端、警官のテンパった声が聞こえた。
「ど、どう言う事ですか?」
彼女は慌てて聞いた。そやけど警官は、焦れたような声で「とにかく、早く家を出ろ」と
言うばかりや。
何が何だかわからへん。そやけど警官の声にただならぬ雰囲気を感じて彼女は靴も穿かずに
急いで外に飛び出した。
外に出た途端、一台の黒塗りの車が走ってきて自分の前で止まった。そこから二人の私服の男が
出てきて彼女を見てほっとした顔を見せた。その二人は彼女の相談を聞いてくれた警官やったんです。
こうして彼女は無事に保護されました。せやけど、警察署に向かう途中の車の中で聞いた警官の一言に、
彼女は最後の最後で、これ以上ないくらいの戦慄を覚えた。
────犯人は、あなたの家にいたんですよ。
「うぇぇぇええええええええいゃあああああぁぁぁぁぁぁあああああ!!!!!」
───談話室に、これで何度目とも知れぬ絶叫が木霊する。
しかし響く声はこの部屋に集まった人間のうちのほんの一握り……って言うか、ぶっちゃけ
オレ一人の声だけだった。
「いやー、坊ちゃんはホンマええ反応見せてくれるわ。話し甲斐があるっちゅうもんやで!」
言いながら、本当に愉快そうにアシオがカラカラと笑う。
……こちとらもう、叫びすぎて喉がカラカラに枯れる寸前なんですけどね。
「いやぁ、夏はやっぱり怪談に限るわ。昼は海で遊んで、夜は怖い話で盛り上がる……これぞ夏の風物詩!」
いや、限らないだろ。スイカ食べながら花火大会とか、普通にほんわか癒し系の夜を楽しんでも
罰は当たるまいよ。
「これで、78本目ね。次は誰?」
「俺、まだまだおもろい話残ってますよ?」
「続けて話すのはダメって決めたでしょう? 私だってまだまだ残ってるわよ」
「あらベル、私もメリーちゃんと体験した不思議なお話がいっぱいあるのよ?」
わいわいと子供のようにはしゃぐ三人をよそにオレは先ほどつい消えた七十八本目の蝋燭のように
燃え尽きる寸前だった。
薄暗い部屋を心許なく照らしている蝋燭の数は残り二十二本。その全てが消えるまで、この悪夢は
覚めることを許さないらしい。
一体、なんでこんな恐ろしい会合に参加してしまったのか。
ベルとアシオの企画した「納涼、百物語 -全ての蝋燭が消えた時、何かが起る-」
……もう既にオレの心中に甚大な何かが起っているのだが、それはともかく。
蒸し暑い夜を少しでも涼しくするため、入念に準備をしてくれたものらしい。確かに、その
気合の入れようはこの部屋に足を踏み入れた瞬間から十二分に伝わってきた。
足下が隠れるほどに厚く立ち込めるスモーク。部屋の中央に置かれた円形テーブルの上には
小さな透明の花瓶のようなものに入った蝋燭が整然と並ぶ。それを取り囲むように置かれた
ソファに円座を組んで座る皆の姿が蝋燭の灯りに下から照らし出され、否応無く不安感を煽られる。
確かに、今オレの身体を襲っている寒気を考えれば企画は大成功と言えるかもしれないが
オレは一言いってやりたい。お前ら、怪談話したいだけちゃうんか、と。
参加メンバーはオレ、グゥ、母さん、おばあちゃん、ベル、アシオ、ロバート、そしてアメ。
母さんとアメは既にソファでぐっすり快眠中。定期的に聞こえる絶叫をものともせずにぐっすり
お休み中だ。オレとグゥは聞き役に徹している。グゥはオレの腕にしがみ付き……いや、逆だ。
オレはグゥの腕にしっかりとしがみ付き、寄り添って座っている。グゥがいなければ、正直オレの
精神は今頃どうなっていたか。考えるだに恐ろしい。
語り部は勿論、都市伝説大好きベル、アシオ、おばあちゃん。……そして。
「ベルさん、アシオさん! 次は俺の番って、さっきクジで決めたじゃないですか!」
……そう、ロバートだ。コイツまでこの手の属性を持っていたとは。ホントに何なんだ
このお屋敷の連中は……。
「あら、あなたはもう話し終わったんじゃなかったかしら?」
「そ、そんな……さっきからそう言って飛ばされてばっかじゃないですか俺!! 俺だって
いっぱいネタ持ってるんですよ? なんたって日本は怪談大国なんですから!!」
オレは二度と日本へは行かない。今決めた。もう絶対決めた。
「しょうがないわねえ。じゃあ次はロバートで……その次はまたクジで決めましょう」
「よっしゃ、残り21本やから……一人あと5話ずつですね」
「もうそれだけなの? 物足りないわねえ」
「メリーちゃん以外のお友達のお話もいっぱいあるのに……残念ねぇ」
四人からあと五話ずつ……考えるだけで眩暈がしてきた。しかしここまで耐えたんだ。
ようやくゴールが見えてきた所じゃないか。諦めるな、オレ!!
……って、なんでそこまでして耐えにゃならんのだ……。何の試練だよ、これは。
「グゥ~……失神したら部屋まで送ってくれな?」
「んー?」
かすれた鼻声で、グゥに弱々しく声をかける。
グゥは相変わらずのポーカーフェイスで気のない声を返した。こいつは基本的に物事に動じると
言う事を知らない。特に怪談やらの「お話」に関しては鉄壁の耐性を誇っている。オレの耐性が
紙のようにペライせいで余計にそう見えるのかもしれないが……。とにかく、グゥのこの毅然と
した態度がオレの精神を紙一重で繋ぎ止めてくれている要因の一つとなっている事は間違いない。
「なんだ、そんなに怖いのか」
「うう……恥を承知で言うけど、普通に怖いよ……」
「ふむ。少しは和らぐかもしれん方法が一つ、あるが。試してみるか?」
「な、なになに? どんな方法!?」
「ようは、他の事に意識を向ければよいのだろう?」
グゥの言葉にオレは目を輝かせ、藁にもすがる思いでグゥを見る。
グゥは一瞬、ベルたちの方に目をやり、すぐにこちらに向き直ると、
ほんの一瞬、唇を寄せてすぐに離れた。
「……どうだ」
「…………」
ロバートの話はもう始まっているようだった。だけど、キンキンと頭の奥に響く耳鳴りに
かき消され、すぐ傍にいるグゥの声しか聞こえない。
心に蟠っていた不安感も消し飛んだ。ただ、この会合の唯一の成果であった寒気も消え、
身体中がほこほこと火照り出す。でも、その暑さに嫌な感じはしなかった。
「うん。ホントに効果あった」
「ん。それはよかったな」
「……また、効果が切れたらしてくれる?」
「よ、よかろう……」
「もうそろそろ、切れそうな気がするんだけど……」
「……お前と言うやつは……」
一つ口実を見つけたら、もう止まれない。
なおも勝手に盛り上がっている四人の目を盗み、オレは何度もグゥと唇を交わした。
たった二十ちょいの小話を聞くくらいしか時間が残っていないと思うと、ちょっと残念だった。
「────うふふ。これでこのお話はおしまい。ついに、残り1本になっちゃったわね」
「あれ、坊ちゃんそう言えばさっきから、全然怖がってないみたいですやん」
「え? あ、あはは。さすがにこれだけ聞かされたら、慣れるって」
「そうよね、男の子ですものね。それに私の話は、怖い話じゃなくてちょっと不思議な
ファンタジックなお話なんだから。怖がる必要なんて、無いわよね」
「そ、そうですねぇ……ははは」
いや、むしろアンタの話が……ってか、アンタの語り口が一番怖かったよ……。
でも、グゥのおかげで、なんとかここまで耐える事が出来た。最後の一話も軽く聞き流して
終わりだな。ありがとう、グゥ。ありがとう、オレの理性。
「よっしゃ、ついに100本あった蝋燭の火も最後の1本が残されるのみとなったワケやけど、
さぁて次の語り部は誰や?」
誰でもいいから、さっさとやっちゃって下さいよ。
「ふっふっふ。実はそれはもう決まっとる。最初から、決まっとった事なんやで……」
テーブルの上に置かれた最後の蝋燭の前で、アシオがおどろおどろしい声を出す。元々からして
怖い目が蝋燭の火に照らされもはや凶器と呼べるレベルのキモさになっている。
「それは……坊ちゃん、グゥさん、あんたらやでぇ~~~~!!!!!」
これ以上無いくらいに精一杯演技がかった声を上げ、アシオがオレたちに震える指を突きつける。
怪談話は苦手だが、この手の演出はさすがにオレも素直に怖がってやれる年齢は過ぎてしまった。
逆に、一生懸命なアシオの姿に少し心がホッとする。
「……なんや、ホンマに怖がらんようなってもうたなあ……」
オレの平静ぶりにアシオの熱も少し冷めたのだろう。つまらなそうに口を尖らせた。
「……てかさ、オレ、怖い話なんて全然知らないよ? 最後の語り部って言われてもさあ……」
「いや、それは今語らんでええんです。坊ちゃんは普段どおりにしているだけで、ええんです……」
「……ど、どう言う事だよ……?」
アシオはまだ諦めずに演技を止めようとしない。しかしその不気味な語り口に、少しずつオレの中にも
また不穏な気配が漂いはじめていく。
「一晩で九十九話もの恐ろしい話を聞いた人間は、夜が明けるまでに自分も恐ろしい体験をしてしまうんです。
それが、百話目の話として追加されて、この百物語は完成するんですわ……」
「…………」
ゴクリと、喉が鳴った。
アシオの力技の成果があったか。オレは背筋にゾクリと冷たいものを感じ思わずグゥの手を強く握った。
迷わずに握り返される手の温かい感触に、少し悪寒が和らぐ。しかしそれも、今度ばかりは完全に晴れては
くれなかった。
「この蝋燭は、坊ちゃんが持っといて下さい」
そう言って、蝋燭の入った小さな瓶を手渡された。煌々と揺らめく小さな灯は少し離れた所からでも
ジリジリとその熱を感じる。しかし指から伝わるガラスの硬質な感触は、氷のように冷たかった。
「この蝋燭はいわばセンサーです。怪異が起こる前に、この火がその予兆を知らせてくれるんです」
「…………」
「不自然な揺れ。火が突然燃え上がる。そーゆー変化があれば、すぐそこまで何かが迫ってる証拠です……」
「…………や……」
「この火が前触れなくふっと消えた瞬間……その時こそ、何かが起る瞬間ですから。……気をつけて下さいね……」
「…………いや……」
「あ、これだけは言っときますけど、自分で火、消さんといて下さいね? もしそんな事してもうたら、
今この屋敷に集まってる大量の霊の怒りをかって、何が起こるやわかりませんから…………」
「───いやぁぁぁぁぁぁあああああああああああああああああああ!!!!!!!!!」
最後の最後、本日最大級の大絶叫が談話室を震わせる。
それは歓呼の調べか慟哭か。まるでこの会合の成功を祝うかのような最大最後の断末魔が
静まり返ったお屋敷にどこまでも、どこまでも高らかに響き渡るのだった。
****[[戻る<<>070901_6]] [7] [[>>進む>070901_8]]
****小麦色の白雪姫_7(二:272-278)
<<8>>
「あー、なんかドッと疲れたなー」
部屋に戻るやいなや、ベッドに備え付けられた大きなソファに持たれかかる。
グゥもオレの隣にちょこんと座り、オレの肩に体重をかけた。
「グゥ───」
何を言う間も与えられず、唇が奪われる。
すぐにパッと離れ、グゥは頬を染めてくすりと笑った。
もう一度、今度はオレからグゥの頬に手を添え、唇を重ねる。
深く密着させず、舌も使わず、唇だけを味わうように優しく吸い付き、離れる。
そうして何度も、グゥと見詰め合いながらキスを交わした───
「───なあ、ハレ」
「……ん」
「そろそろ、風呂に行った方が良いんじゃないか」
「……んー」
グゥの髪を撫でながら曖昧な返事を返す。
今、グゥはオレの股の間にお尻を収め、その背中をオレの胸に預けて座っている。
「もうちょっと、このままでいない?」
「……ウェダが風呂で待ってる」
「ん~……。もうちょっとだけ……」
グゥの髪に鼻を埋め、頭を揺する。後ろから肩に腕を回し抱き締めるとグゥは一瞬、身体を
弛緩させたがすぐに頭をぐりぐりと捻りオレの顔を押し戻した。
「遅くなればなるほどウェダの想像力に火がつくと思うのだが?」
オレの腕を解き、肩越しに睨みつけてくる。
……確かに、あまり遅れてはまたいらぬ詮索をされてしまいそうだ。
どうせ風呂から上がって、イベントとやらが終わればここに二人で戻ってくるのだ。焦る必要も
時間を惜しむ必要も無いか。
しかし、一つだけ今やっておかなければならない事がある。
「グゥ。水着跡、ちょっとだけ見せて?」
「……ケダモノ」
「違うっての!」
冷やかな目線をオレに送りながら、グゥは自分の胸をガードするように抱いた。
「手触りは違うのかな? 味も見てみよう、とか言ってまたグゥを慰みものにするつもりなんだろう」
「するかッ!! ってか、"また"ってなんだよ、"また"って」
「だいたい、日焼けの跡など別に今見なくてもいいだろ。もうちょっとマシな口実を考えろ」
「……今じゃなきゃ、ダメなんだよ」
「ほう、その心は?」
グゥは腕を組んだまま肩越しにオレを見上げ、次の言を待つ。
ああ、もう。最初の言い方が不味かったか。自業自得ってやつか……。くそう、また恥ずかしい事を
告白せにゃならんのか。
「……母さんに先に見られるの、悔しかったんだよ」
「…………」
「オレが最初に見たかったのッ!」
顔中が熱い。グゥの顔をまともに見る事も出来ず、中空に目を泳がせる。
しばし無言の時が過ぎるが、不意に大きな溜息がその沈黙を遮った。
「ハレは意気地があるのかないのか……」
「……へ?」
「…………なんでもない」
グゥは何度も小さく溜息を付き、ぴょんとソファから降りると落ち着き無くオレの前をうろうろと
うろつく。最後にもう一度大きく息を吐くと目の前でぐっと屈み込みオレに顔を突き出した。
「……一瞬だけだからな」
「…………」
グゥは怒ったような困ったような顔で口を尖らせるとすっくと身体を起こし、ドアの前まで
歩きくるんとこちらに向き直る。
「……ちょっと待ってろ」
そしてそう言うと、グゥは突然後ろ手にスカートを捲り、ごそごそと何かを弄りはじめた。
こちらからはスカートの内部は見えないが、オレはその光景をただ呆然と見守るしかなかった。
「……よし。いいか、一瞬だけだぞ?」
「な、なんだよ……?」
何かの仕度を整え終えたのか、グゥはパンパンとスカートの皺を伸ばすようにお尻をはたくと、
少し前傾姿勢になり足を開く。
そしておもむろに勢い良く上半身を捻り、反動をつけて回転するようにクイッとお尻を前に
突き出した。
「ブ…………ッ!!」
ヒラリと傘を開くように展開するスカートの奥で、純白の膨らみがぷるんと揺れた。
最初は下着かと思った。だけど、褐色の肌とその白い双丘との間には何の段差も無く、
ただくっきりと色の境界線があるのみだった。
先ほどのグゥの怪しい動きはこれだったのだろう、下着はグゥのお尻の谷間に食い込み、
その根元にのみ逆三角形に布地が見えるのみだった。無理に食い込ませているためか、
布地の圧迫で尻肉がむっちりと持ち上がり、より豊満で柔らかそうに盛り上がっていた。
見えたのはほんの一瞬だったが、しっかりと目に焼きついた。小麦色の脚とのコントラスト
にくっきりと映える色白な双丘の、官能的とすら思えるようなふくよかな肉感。
グゥのスカートはとっくに膝元まで降り、更に上からガードするように前も後ろもグゥの
手で押さえられていたが、オレの目の前にはまだ先ほどの光景がそこにあるかのように
チラチラと浮かぶ。
「……満足したか?」
「…………」
「どうした、何か言え」
「………あ……」
「あ?」
「アンコール……」
「……馬鹿」
「アンコール! アンコール!!」
「黙れ!!」
オレの精一杯の掛け声にもグゥは応えてくれず、むしろ益々スカートを守りに入る。
くそう、ああなっては真下から竜巻が発生しても捲れはすまい。
「まったく。すぐ調子に乗りおって。これはサービスだ、サービス。別に、ハレがちゃんと言えば
グゥだってこれくらいの事はしてやっても良いんだからな」
「…………」
言ってから恥ずかしくなったのか、グゥは頬をほんのりと染めてぷい、とそっぽを向いた。
そこまでは、オレも期待してなかったってのに。こいつのやる事はまったく、ホントに……。
「じゃ、グゥは風呂に行くからな」
早口にそれだけを言うとグゥは後ろ手にドアを開け、オレを置いてそそくさと部屋を出て行った。
一人、取り残されたオレの意識と肉体が正常に戻ったのは、それから数分後の事だった。
風呂場に行くと、ロバートが物凄く良い顔で出迎えてくれた。脱衣所の前で随分と長い間
待ってくれていたようだ。「先に入ってくれて良かったのに」と言うオレの言葉にロバートは
ブンブンと首を振った。オレより先に入る事はロバート的に許されないのだそうだ。なんだか、
申し訳無い事をしてしまった。少し、反省する。
さっさと服を脱ぎ、中に入るとロバートも追って入ってきた。腰に巻いたタオルから覗く、
黒と白のコントラストに先ほどの絶景が上書きされそうになり慌てて顔を背ける。
どうやらロバートもアシオも海で本当にトランクス一丁にされたらしく、上半身はもとより
太ももの中ごろから下までもしっかり焼けていた。普通の水着の跡とまるで変わらない。
しかし男の日焼け跡はどこか間が抜けているように思えるのはオレが同性だからだろうか。
身体を洗い、ゆっくり湯船につかりながら部屋でのグゥを思い出す。……途端に、湯船から
上がる事が困難な状態になる。
自分で呼んでおいてなんだが、今ほどロバートが邪魔者に思えた瞬間は無かった。
「いやぁ、いいお湯ですねえ」
「…………ほんとにねえ」
「今日は疲れたでしょう。脚を伸ばした方が楽ですよ?」
「…………いや、オレはいいや」
「男同士なんですから、ほら、お気にならさずに」
「…………いいっつーの……」
最初に待たせてしまった手前、先に出ていてくれとも言えず、その理由を聞かれた際の言い訳も
思い浮かばず、オレは心地良いはずの広い湯船の中でひたすら窮屈な思いに悶々とするのだった。
<<9>>
───これは、あるストーカーの被害に悩まされとった一人の女性の身に起こった出来事です。
仕事の行き帰りに妙な視線を感じる。夜中に窓の外を覗いたら不気味な人影が立ってる。
毎日のように無言電話がかかってくる。
彼女はいつも背筋が凍る思いで過ごしてました。ドアは勿論、家中の窓をいつも閉めっぱなしに
していても不安は募るばかり。
今日も、いつもと同じ時間に電話の無機質な音が部屋に鳴り響いた。
もしもし? もしもし、どなたですか?
何度聞いても相手は無言。返ってくるのは不気味な沈黙だけや。
彼女はもともと気の強い方や無い、どちらかと言えば控えめな子やったけど、ここまでされては
黙ってもおれへん。今回ばかりはさすがに我慢の限界が来た。
「いい加減にしてよこの変態! アンタみたいに誰の心も理解できない人間サイテーだ!いっぱしの
つもりなんだろうけど傍から見ればちゃんちゃらおかしいだけ! なんもなし! 空っぽ! そーゆー
人間はね、結局死ぬまで今に見てろとホントのオレはこんなもんじゃないと、誰も解ってくれないで
誤魔化して! 根拠の無い自信と自己憐憫に溺れ生きていくんだわ! 大迷惑!! ッ死ね!!」
よっぽど腹が立っとったんやろう、彼女は饒舌にそこまで一気に捲くし立てると受話器を叩き付けた。
せやけどな、彼女の心は全く晴れへんかった。受話器を耳から放す瞬間、彼女は聞いてもうたんや。
いつも何を言うても無言やった受話器の向こう側から聞こえてきた、カスレた男の声。
「────死ぬのはお前だ」
彼女は途端に恐ろしくなり、警察に相談した。
幸いな事に、警察も最近はストーカーの被害者対策に力を入れとったから、彼女の相談に
すぐに対応してくれた。
「今度電話がかかってきたときには逆探知を行ってから携帯電話にかけるので、なるべくストーカーとの
電話を切らないようにして下さい」
そう警官に言われた彼女は、百万の味方を手に入れた気分やった。もう怖くない。
むしろ、電話がかかってくるのが楽しみにすら思えた。
そして、その夜も律儀に同じ時間に電話はかかってきた。
……しかし今日はいつもとは様子が違ったんや。
ククククク……ククククク……ククククク……
ストーカーの男はただ電話口で延々と不気味な笑い声を響かせとった。
恐ろしくなった彼女は電話を切ろうと思ったけど、警察が逆探知をしてくれることになっとるから
そうもいかん。我慢して受話器を持って、ただ男の笑い声を聞いてるしかなかった。
そして、ついに彼女の携帯電話が鳴った。警察からや。
彼女は急いで電話を取った。
「逆探知の結果が出ました!今すぐ外へ出てください!」
電話が繋がった途端、警官のテンパった声が聞こえた。
「ど、どう言う事ですか?」
彼女は慌てて聞いた。そやけど警官は、焦れたような声で「とにかく、早く家を出ろ」と
言うばかりや。
何が何だかわからへん。そやけど警官の声にただならぬ雰囲気を感じて彼女は靴も穿かずに
急いで外に飛び出した。
外に出た途端、一台の黒塗りの車が走ってきて自分の前で止まった。そこから二人の私服の男が
出てきて彼女を見てほっとした顔を見せた。その二人は彼女の相談を聞いてくれた警官やったんです。
こうして彼女は無事に保護されました。せやけど、警察署に向かう途中の車の中で聞いた警官の一言に、
彼女は最後の最後で、これ以上ないくらいの戦慄を覚えた。
────犯人は、あなたの家にいたんですよ。
「うぇぇぇええええええええいゃあああああぁぁぁぁぁぁあああああ!!!!!」
───談話室に、これで何度目とも知れぬ絶叫が木霊する。
しかし響く声はこの部屋に集まった人間のうちのほんの一握り……って言うか、ぶっちゃけ
オレ一人の声だけだった。
「いやー、坊ちゃんはホンマええ反応見せてくれるわ。話し甲斐があるっちゅうもんやで!」
言いながら、本当に愉快そうにアシオがカラカラと笑う。
……こちとらもう、叫びすぎて喉がカラカラに枯れる寸前なんですけどね。
「いやぁ、夏はやっぱり怪談に限るわ。昼は海で遊んで、夜は怖い話で盛り上がる……これぞ夏の風物詩!」
いや、限らないだろ。スイカ食べながら花火大会とか、普通にほんわか癒し系の夜を楽しんでも
罰は当たるまいよ。
「これで、78本目ね。次は誰?」
「俺、まだまだおもろい話残ってますよ?」
「続けて話すのはダメって決めたでしょう? 私だってまだまだ残ってるわよ」
「あらベル、私もメリーちゃんと体験した不思議なお話がいっぱいあるのよ?」
わいわいと子供のようにはしゃぐ三人をよそにオレは先ほどつい消えた七十八本目の蝋燭のように
燃え尽きる寸前だった。
薄暗い部屋を心許なく照らしている蝋燭の数は残り二十二本。その全てが消えるまで、この悪夢は
覚めることを許さないらしい。
一体、なんでこんな恐ろしい会合に参加してしまったのか。
ベルとアシオの企画した「納涼、百物語 -全ての蝋燭が消えた時、何かが起る-」
……もう既にオレの心中に甚大な何かが起っているのだが、それはともかく。
蒸し暑い夜を少しでも涼しくするため、入念に準備をしてくれたものらしい。確かに、その
気合の入れようはこの部屋に足を踏み入れた瞬間から十二分に伝わってきた。
足下が隠れるほどに厚く立ち込めるスモーク。部屋の中央に置かれた円形テーブルの上には
小さな透明の花瓶のようなものに入った蝋燭が整然と並ぶ。それを取り囲むように置かれた
ソファに円座を組んで座る皆の姿が蝋燭の灯りに下から照らし出され、否応無く不安感を煽られる。
確かに、今オレの身体を襲っている寒気を考えれば企画は大成功と言えるかもしれないが
オレは一言いってやりたい。お前ら、怪談話したいだけちゃうんか、と。
参加メンバーはオレ、グゥ、母さん、おばあちゃん、ベル、アシオ、ロバート、そしてアメ。
母さんとアメは既にソファでぐっすり快眠中。定期的に聞こえる絶叫をものともせずにぐっすり
お休み中だ。オレとグゥは聞き役に徹している。グゥはオレの腕にしがみ付き……いや、逆だ。
オレはグゥの腕にしっかりとしがみ付き、寄り添って座っている。グゥがいなければ、正直オレの
精神は今頃どうなっていたか。考えるだに恐ろしい。
語り部は勿論、都市伝説大好きベル、アシオ、おばあちゃん。……そして。
「ベルさん、アシオさん! 次は俺の番って、さっきクジで決めたじゃないですか!」
……そう、ロバートだ。コイツまでこの手の属性を持っていたとは。ホントに何なんだ
このお屋敷の連中は……。
「あら、あなたはもう話し終わったんじゃなかったかしら?」
「そ、そんな……さっきからそう言って飛ばされてばっかじゃないですか俺!! 俺だって
いっぱいネタ持ってるんですよ? なんたって日本は怪談大国なんですから!!」
オレは二度と日本へは行かない。今決めた。もう絶対決めた。
「しょうがないわねえ。じゃあ次はロバートで……その次はまたクジで決めましょう」
「よっしゃ、残り21本やから……一人あと5話ずつですね」
「もうそれだけなの? 物足りないわねえ」
「メリーちゃん以外のお友達のお話もいっぱいあるのに……残念ねぇ」
四人からあと五話ずつ……考えるだけで眩暈がしてきた。しかしここまで耐えたんだ。
ようやくゴールが見えてきた所じゃないか。諦めるな、オレ!!
……って、なんでそこまでして耐えにゃならんのだ……。何の試練だよ、これは。
「グゥ~……失神したら部屋まで送ってくれな?」
「んー?」
かすれた鼻声で、グゥに弱々しく声をかける。
グゥは相変わらずのポーカーフェイスで気のない声を返した。こいつは基本的に物事に動じると
言う事を知らない。特に怪談やらの「お話」に関しては鉄壁の耐性を誇っている。オレの耐性が
紙のようにペライせいで余計にそう見えるのかもしれないが……。とにかく、グゥのこの毅然と
した態度がオレの精神を紙一重で繋ぎ止めてくれている要因の一つとなっている事は間違いない。
「なんだ、そんなに怖いのか」
「うう……恥を承知で言うけど、普通に怖いよ……」
「ふむ。少しは和らぐかもしれん方法が一つ、あるが。試してみるか?」
「な、なになに? どんな方法!?」
「ようは、他の事に意識を向ければよいのだろう?」
グゥの言葉にオレは目を輝かせ、藁にもすがる思いでグゥを見る。
グゥは一瞬、ベルたちの方に目をやり、すぐにこちらに向き直ると、
ほんの一瞬、唇を寄せてすぐに離れた。
「……どうだ」
「…………」
ロバートの話はもう始まっているようだった。だけど、キンキンと頭の奥に響く耳鳴りに
かき消され、すぐ傍にいるグゥの声しか聞こえない。
心に蟠っていた不安感も消し飛んだ。ただ、この会合の唯一の成果であった寒気も消え、
身体中がほこほこと火照り出す。でも、その暑さに嫌な感じはしなかった。
「うん。ホントに効果あった」
「ん。それはよかったな」
「……また、効果が切れたらしてくれる?」
「よ、よかろう……」
「もうそろそろ、切れそうな気がするんだけど……」
「……お前と言うやつは……」
一つ口実を見つけたら、もう止まれない。
なおも勝手に盛り上がっている四人の目を盗み、オレは何度もグゥと唇を交わした。
たった二十ちょいの小話を聞くくらいしか時間が残っていないと思うと、ちょっと残念だった。
「────うふふ。これでこのお話はおしまい。ついに、残り1本になっちゃったわね」
「あれ、坊ちゃんそう言えばさっきから、全然怖がってないみたいですやん」
「え? あ、あはは。さすがにこれだけ聞かされたら、慣れるって」
「そうよね、男の子ですものね。それに私の話は、怖い話じゃなくてちょっと不思議な
ファンタジックなお話なんだから。怖がる必要なんて、無いわよね」
「そ、そうですねぇ……ははは」
いや、むしろアンタの話が……ってか、アンタの語り口が一番怖かったよ……。
でも、グゥのおかげで、なんとかここまで耐える事が出来た。最後の一話も軽く聞き流して
終わりだな。ありがとう、グゥ。ありがとう、オレの理性。
「よっしゃ、ついに100本あった蝋燭の火も最後の1本が残されるのみとなったワケやけど、
さぁて次の語り部は誰や?」
誰でもいいから、さっさとやっちゃって下さいよ。
「ふっふっふ。実はそれはもう決まっとる。最初から、決まっとった事なんやで……」
テーブルの上に置かれた最後の蝋燭の前で、アシオがおどろおどろしい声を出す。元々からして
怖い目が蝋燭の火に照らされもはや凶器と呼べるレベルのキモさになっている。
「それは……坊ちゃん、グゥさん、あんたらやでぇ~~~~!!!!!」
これ以上無いくらいに精一杯演技がかった声を上げ、アシオがオレたちに震える指を突きつける。
怪談話は苦手だが、この手の演出はさすがにオレも素直に怖がってやれる年齢は過ぎてしまった。
逆に、一生懸命なアシオの姿に少し心がホッとする。
「……なんや、ホンマに怖がらんようなってもうたなあ……」
オレの平静ぶりにアシオの熱も少し冷めたのだろう。つまらなそうに口を尖らせた。
「……てかさ、オレ、怖い話なんて全然知らないよ? 最後の語り部って言われてもさあ……」
「いや、それは今語らんでええんです。坊ちゃんは普段どおりにしているだけで、ええんです……」
「……ど、どう言う事だよ……?」
アシオはまだ諦めずに演技を止めようとしない。しかしその不気味な語り口に、少しずつオレの中にも
また不穏な気配が漂いはじめていく。
「一晩で九十九話もの恐ろしい話を聞いた人間は、夜が明けるまでに自分も恐ろしい体験をしてしまうんです。
それが、百話目の話として追加されて、この百物語は完成するんですわ……」
「…………」
ゴクリと、喉が鳴った。
アシオの力技の成果があったか。オレは背筋にゾクリと冷たいものを感じ思わずグゥの手を強く握った。
迷わずに握り返される手の温かい感触に、少し悪寒が和らぐ。しかしそれも、今度ばかりは完全に晴れては
くれなかった。
「この蝋燭は、坊ちゃんが持っといて下さい」
そう言って、蝋燭の入った小さな瓶を手渡された。煌々と揺らめく小さな灯は少し離れた所からでも
ジリジリとその熱を感じる。しかし指から伝わるガラスの硬質な感触は、氷のように冷たかった。
「この蝋燭はいわばセンサーです。怪異が起こる前に、この火がその予兆を知らせてくれるんです」
「…………」
「不自然な揺れ。火が突然燃え上がる。そーゆー変化があれば、すぐそこまで何かが迫ってる証拠です……」
「…………や……」
「この火が前触れなくふっと消えた瞬間……その時こそ、何かが起る瞬間ですから。……気をつけて下さいね……」
「…………いや……」
「あ、これだけは言っときますけど、自分で火、消さんといて下さいね? もしそんな事してもうたら、
今この屋敷に集まってる大量の霊の怒りをかって、何が起こるやわかりませんから…………」
「───いやぁぁぁぁぁぁあああああああああああああああああああ!!!!!!!!!」
最後の最後、本日最大級の大絶叫が談話室を震わせる。
それは歓呼の調べか慟哭か。まるでこの会合の成功を祝うかのような最大最後の断末魔が
静まり返ったお屋敷にどこまでも、どこまでも高らかに響き渡るのだった。
****[[戻る<<>070901_6]] [7] [[>>進む>070901_8]]
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: